2012年9月10日
独立行政法人理化学研究所
米国コーネル大学
国立大学法人名古屋大学
物理学史上、最も精密な理論計算値
-電子の磁気能率の大きさを1.3兆分の1の精度で決定-
ポイント
- 電子とミュー粒子の磁気能率を量子電気力学(QED)により理論的に計算
- 基礎物理定数の1つ微細構造定数αを40億分の1の最高精度で決定
- 素粒子の標準理論に対して最も厳密な検証を可能に
要旨
理化学研究所(野依良治理事長)とコーネル大学(Cornell University、D. J. スコルトン学長)、名古屋大学(濵口道成総長)は、電子およびミュー粒子※1の持つ磁気能率※2の大きさ(g因子※2)を量子電気力学(QED)※3に基づき理論的に計算し、微細構造定数α※4の5乗までの全寄与をスーパーコンピュータを用いて求めることに成功しました。これにより、電子の磁気能率の大きさを1.3兆分の1の精度で理論的に決定し、3.6兆分の1の精度で求められている実験値と不確かさ※5の範囲内で一致することを確認、この精度までQEDが正しいことを検証しました。同時に、この計算によって、基礎物理定数の1つである微細構造定数αの値を、40億分の1という現在知られている値の中では最も良い精度で決定しました。これは、コーネル大学素粒子研究所の木下東一郎 G・スミス名誉教授、理研仁科加速器研究センターの仁尾真紀子 仁科センター研究員、名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構の青山龍美 特任准教授、同学理学研究科の早川雅司 准教授らの共同研究による成果です。
物質を構成する基本粒子である素粒子とその間に働く力は、標準模型※6の形にまとめられ、これまで数多くの実験による検証に耐えてきました。しかし、この模型が自然を記述する究極の理論であるかどうかについてはさまざまな意見があり、より正しい理解への手がかりを得ることが、理論においても実験においても、現代物理学の重要な課題の1つとなっています。この問題へは2通りのアプローチがあり、非常に高いエネルギー領域での物理現象を探索する手法と、実験と理論の精度を高め、双方の間の矛盾を探すという手法があります。本研究は、後者に拠っています。
電子およびミュー粒子の磁気能率は、数ある物理量のなかでも、実験により最も精密に測定されている量の1つです。理論的には、その値は量子電気力学(QED)によって、微細構造定数αのベキ級数※7として表すことができます。今回、5個の光子を含んだ過程を意味するαの5乗の係数を、電子とミュー粒子双方について確定しました。これは、理研のスパコン(RSCCとRICC)を使用した9年間にわたる計算の成果です。この計算結果により得た電子のg因子の値とそこから導いた微細構造定数αは、現時点における人類の科学の到達度を最も端的に示す数字です。今回の結果により、物理学の精密検証は新たな段階に進んだことになります。
本研究成果は、電子の磁気能率に関する論文とミュー粒子の磁気能率に関する論文として、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』のオンライン版に、近日、2本同時に掲載される予定です。
背景
私たちが日常生活で目にする現象のほとんどは、電磁気力によって引き起こされています。現在の素粒子物理学では、この電磁気的な相互作用を量子電気力学(Quantum Electrodynamics:QED)として定式化しています。QEDは、電気と磁気の力を特殊相対性理論と量子論を調和させながら記述するものです。電磁気的な力の強さを示す数である微細構造定数αは、自然界における基礎物理定数の1つであり、その値は精密な測定が可能で理論的にも計算できる量から逆算して決定されます。電磁気力が関与する自然現象は幅広く、さまざまな物理現象、例えば、量子ホール効果でのホール電圧、セシウム原子やルビジウム原子の反跳測定、原子のエネルギー準位の測定、素粒子の磁気能率の大きさなどから決まる物理量を組み合わせて、αの値を求めることができます(図1)。
特に、電子の磁気能率の大きさ(g因子)は、電子が磁場の中に単独で置かれるという非常に単純な電子の運動から測定できる量であるため、理論的にも実験的にも究めて高い精度で決定することが可能です。実験では、2008年に、米国ハーバード大学のグループが3.6兆分の1の精度で測定しています。一方、理論では共同研究グループらがQEDに基づいて同程度の精度まで計算しています。そのため、あらゆる方法のなかでも電子のg因子からは最も精度の良いαの値が得られます。
このように、さまざまな方法で得られたαの値の相互の整合性を見て、個々の物理現象そのものに関する理解、電磁気に関する理解、さらには、不確定性原理を含めた量子論の理解が本当に正しいかどうかを検証します。
ミュー粒子と呼ばれる素粒子のg因子もまた、理論的にも実験的にも、16億分の1程度の精度で決定されています。この量に関しては、実験値と標準模型による理論値が99.9%の信頼度で異なっており、標準模型の破綻を示す候補として強い関心を集めています。最近、発見の兆候が見えてきたヒッグス粒子※8の存在は、現在の素粒子の標準模型に欠けていた最後の一片を埋めるもので、それ自体は実験と理論の間の矛盾を示唆するものではありません。これに対してミュー粒子のg因子は、標準模型を超える物理を探る重要な手がかりの1つとなっています。
研究手法と成果
共同研究グループは、電子のg因子におけるQEDの寄与を求める理論計算を長く推進してきました。QEDの理論計算では、摂動計算※9という手法を用います。そこでは、電子が仮想的な光子を放出したり吸収したりすると考えることができ、仮想光子の交換による効果を大きいものから順次、計算に取り入れていきます。この様子は、電子の間の仮想光子の交換の仕方を示すファインマン図※10によって表現することができます。交換される光子1個あたり微細構造定数α倍の寄与が生じるため、結局、g因子はαのベキ級数として表されます。αそのものは約137分の1という小さい値ですが、実験と同程度の精度に到達するためには、交換される光子の数が多い、複雑なファインマン図の計算を行う必要があります。
共同研究グループは、2007年までに光子4個を含むαの4乗の寄与を数値的な手法で計算し、当時の最高精度の電子のg因子の値と微細構造定数αの値を提示しました(2007年8月22日プレスリリース)。より精度を上げるためには、光子5個、つまり、αの5乗に寄与する12,672個のファインマン図を計算する必要があります(図2)。考慮すべきファインマン図の多さに加え、αの4乗の場合に比べて計算式の総計は約千倍程度の長さになります。しかも複雑なくりこみ項※11を構成しなくてはならず、結果の正しさを保証しながら計算を進めるには大きな困難を伴います。
そこで共同研究グループは、複雑な構造を持つファインマン図に対しては、その図の数値計算プログラムを自動的に制作するコンピュータプログラムを構成しました。これによって計算プログラムを正確かつ迅速に制作することが可能になりました。
このように制作した数値計算プログラムを、理研のスーパーコンピュータシステムRSCC(2004年~2009年)とRICC(2009年~2012年現在)で実行し、ファインマン図からの寄与を計算しました。特にRICCの導入により、最も数値計算の難しいファインマン図の計算が可能となり、ようやくαの5乗の寄与を確定することができました。同時に、ミュー粒子のg因子への寄与も、電子用のプログラムのパラメータを変更して計算を進めました。αの5乗の寄与が求められたのは、初めてのことです。
このQED計算の結果とこれまで知られていたQEDのαの4乗までの結果に、2011年にビラベンらがルビジウム原子実験から決めた微細構造定数αの値を代入して、電子のg因子の値を
g/2(理論)=1.001 159 652 181 78±0.000 000 000 000 77 と1.3兆分の1の精度で決定しました。3.6兆分の1の精度を持つ米国ハーバード大学での実験値
g/2(実験)=1.001 159 652 180 73±0.000 000 000 000 28 と不確かさの範囲内で一致し、この精度までQEDが正しいことを検証しました。電子のg 因子の理論値は、物理の基本原理から導かれた理論から直接計算し観測量を再現するものとしては、物理学史上、最も精密な値です。
また、逆にαを未知数として、電子g因子の理論値と実験値からその値を導くと
1/α(電子g)=137.035 999 173±0.000 000 035 と40億分の1の精度で決定することができました。この10年間に、理論と実験の進歩によりαの精度は20倍以上も向上しています。これは、物理学の精密検証がより高い段階へと進化したことを示しています。
一方、ミュー粒子のg因子に関しては、QEDによる寄与を1.2兆分の1の高精度で確定し、現在の実験値と標準模型による理論値との差がQED計算に起因するものではないことを明確にしました。今後は、実験値と理論値との差を明らかにする上で、標準模型による理論値の中で不確かさの一番大きい“強い相互作用”による寄与の精度を高めることが、最も重要な課題となります。
今後の期待
米国ハーバード大学の実験グループは、2008年の電子のg因子測定に引き続き、陽電子のg因子を測定する実験を進行中です。この実験値とQED計算の進展を考慮すると、αの精度は100億分の1程度にまで改善できる見込みです。
また、フランス・パリ大学のグループは、2011年のルビジウム原子を用いた反跳測定を改良して、現在のαの精度(15億分の1)をさらに数倍程度改良しようとしています。2012年時点では、今回得た電子g因子からのαとルビジウム原子から決めたαの間には明らかな差はありませんが、それぞれの誤差が改良された先に何が起こるかは興味深いものがあります。このαによる精密検証の実現のためにも、さらなる大規模計算によるQED理論値の精度向上が不可欠です。
一方、ミュー粒子のg因子は、未知の素粒子や力の存在を探査する上で、現在、強い関心を集めている物理量です。そのため、日本にある大強度陽子加速器施設(J-PARC)と米国シカゴにあるフェルミ国立加速器研究所(Fermilab)で2つの独立な国際共同実験が同時進行しており、さらに良い精度での測定を目指しています。共同研究グループが今回決定したQEDの寄与は、これらの将来の測定精度に比べても十分に高い精度で理論的予言を与えるものであり、新しい物理現象の探索を支えています。
原論文情報
- Tatsumi Aoyama, Masashi Hayakawa, Toichiro Kinoshita, and Makiko Nio,
“Tenth-Order QED Contribution to the Electron g-2 and an Improved Value of the Fine Structure Constant”, Physical Review Letters, 109巻、2012年9月14日号, DOI:10.1103/PhysRevLett.109.111807
“Complete tenth-order QED contribution to the muon g-2”, Physical Review Letters, 109巻、2012年9月14日号, DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.111808
発表者
理化学研究所
仁科加速器研究センター 初田量子ハドロン物理学研究室
仁科センター研究員 仁尾 真紀子(にお まきこ)
国立大学法人名古屋大学
理学研究科物理学教室
准教授 早川 雅司 (はやかわ まさし)
国立大学法人名古屋大学
素粒子宇宙起源研究機構基礎理論研究センター
特任准教授 青山 龍美 (あおやま たつみ)
報道担当
独立行政法人理化学研究所 広報室 報道担当
Tel:048-467-9272 / Fax:048-462-4715
国立大学法人名古屋大学 広報室 報道担当
Tel: 052-789-2016 / Fax: 052-788-6272
補足説明
- 1.ミュー粒子
電子と同じ性質(同じ電荷、同じスピン)を持つが、電子の約200倍の質量を持つ素粒子。電子と同じく磁気能率を持っているが、この質量の違いのため、ミュー粒子のg因子の値は電子のg因子の値よりも0.0006%程度大きな値となる。 - 2.磁気能率、g因子
素粒子の持つ磁石としての性質を、磁気能率と呼ぶ。その大きさはg因子という無次元の数で示される。 - 3.量子電気力学(QED)
QEDはQuantum Electrodynamicsの略。特殊相対性理論と量子論の双方を満たし、電気的および磁気的な力を記述する素粒子の理論を量子電気力学と呼ぶ。朝永振一郎、ファインマン、シュウィンガー、ダイソンをはじめとする多くの理論物理学者の貢献によって1948年頃に完成した。くりこみ理論の適用を受けて初めて、実際の物理量を正確に計算できるようになった。 - 4.微細構造定数 α
自然における基本物理定数の1つで、電気的および磁気的な力の大きさを示す数。歴史的には、水素原子のエネルギー準位がさらに細かく分離している微細構造が発見されたとき、その分離の大きさがαに比例する相対論的量子効果として理論的に説明されたことが最初である。これにちなんで、αは微細構造定数と呼ばれている。ルビジウム原子を用いた実験から決めた値は
1/α(Rb) = 137.035 999 049±0.000 000 090
である。一方、今回電子g 因子から決めた値は、
1/α(電子g)=137.035 999 173±0.000 000 035
となった。 - 5.不確かさ
測定結果の疑わしさを数値で表わしたもの。「誤差」とは、測定しようとするものについての、測定された値と「真の値」との差をいう。しかし、「真の値」は分からない場合がほとんどであるため、測定値から推定することが必要となる。この場合、「真の値」が測定結果からどの程度のばらつきの間にあるかを示す目安として「不確かさ」が用いられる。 - 6.標準模型
さまざまな素粒子とその間に働く力をまとめあげた理論。電磁相互作用以外に、中性子を崩壊させる弱い相互作用、原子核を構成する強い相互作用を記述する。1970年頃までに完成し、ニュートリノの質量の発見で若干修正されたことを除けば、現時点までさまざまな実験による検証に耐えてきた。 - 7.ベキ級数
一般には、関数f(x)の変数xを小さな数だと仮定し、
f(x)=a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 + …
とxの累乗の和で表すこと。ここで、a0, a1, a2,… は定数。
QEDの摂動計算では、磁気能率の大きさ g を微細構造定数αのベキ級数
g/2 = 1 + A(1)α + A(2)α2 + A(3)α3 + A(4)α4 + A(5)α5 +…
として表す。今回、本共同研究グループが係数A(5)を決定した。 - 8.ヒッグス粒子
素粒子標準模型のなかで、自発的対称性の破れを引き起こす役割を担う素粒子。その存在は1960年代にヒッグスにより提唱され、標準模型の完成に不可欠となった。2012年7月に、スイス・欧州原子核研究機構(CERN)におけるLHC実験で、その存在の兆候が報告された。 - 9.摂動計算
主体となる大きな寄与が近似としてよく分かっている場合に、影響の小さな部分の効果を後から取り入れ、系統的に近似を改良する計算方法の1つ。物理や工学で用いられる。例えば、天王星の摂動計算で求めた軌道が、観測からわずかにずれていたことが、海王星の発見(1846年)につながった。 - 10.ファインマン図
QEDなどの摂動計算に現れる粒子間の相互作用の過程を視覚的に表現したもの。R.P.ファインマンにより考案された。QEDのファインマン図は、各頂点をそこから出る2本の電子の線と1本の光子の線をつないで構成される1つのグラフである。線分は電子あるいは光子が時空間中を伝播することを表し、頂点は、光子が電子より放出、又は吸収されることを表している。各過程からの寄与は、ファインマン則と呼ばれるルールに従ってファインマン図に対応する計算式を書き下すことにより計算できる。計算式は相互作用頂点と粒子の伝播関数から構成され、一般には無限大の発散を含む多重積分の形になる。 - 11.くりこみ項
朝永振一郎らが考案した、摂動計算で物理量を得るための方法。ファインマン図に従って計算すると、ある条件のもとに量子ゆらぎが無限大の大きさになり、答えが無限大に発散して物理的な意味を持たなくなってしまう。量子ゆらぎのほとんどは観測される物理量にすでに取り込まれていると考え、そこから観測されるべき有限の量子ゆらぎだけを取り出す手法。計算式の中でくりこみ操作に相当する項を、特にくりこみ項と呼ぶ。
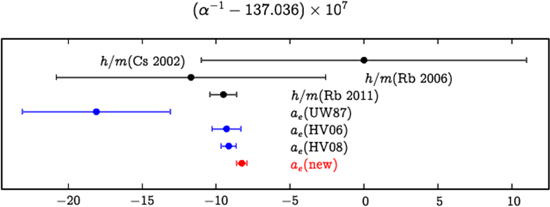
図1 さまざまな方法で決めた微細構造定数αの値
さまざまな方法で決めた微細構定数αの逆数値から、完全に一致をみている最初の6桁分137.036を差し引いたもの。h/mは原子の反跳測定を示し、Cs2002はセシウム原子を用いたチューらの2002年の結果から、Rb2006とRb2011はそれぞれルビジウム原子を用いたビラベンらの2006年と2011年の実験結果から導かれたαの値を示している。aeは電子の磁気能率によるもので、UW87は1987年のデーメルトらの実験と2007年のQED計算、HV06, HV08はそれぞれガブリエルスらによる実験と2007年のQED計算によるもので、newはHV08の実験と今回のQED計算に基づくものである。
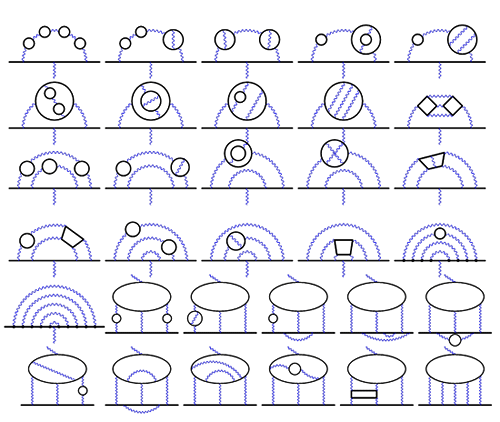
図2 電子のg因子に寄与する光子5個を含むファインマン図の代表例
電子の磁気能率に寄与する光子5個を含む量子電気力学(QED)の効果を表すファインマン図は全部で12,672個ある。構造の似たもの同士を集めると32個のセットにまとめることができる。青の波線が時空間を伝搬する仮想光子を表し、黒の線は弱い磁場の中を運動している電子を表す。特に、黒の閉じた曲線や四角は、仮想的に生成し光子へと消滅する電子と陽電子のペアを表す。
