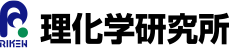知的財産情報
61-89件表示 / 89件中
![]() 左右にスクロールできます
左右にスクロールできます
| 理研番号 | 発明の名称 |
|---|---|
| 08418 | 300ギガから10テラヘルツ波の吸収材料
鉄を主成分とするフェライト材料においてテラヘルツ波とスピンの磁気モーメントゆらぎが結合し、エレクトロマグノン励起が起こることを発見しました。 |
| 08404 | ペンタセン誘導体を用いたNMRの高感度化技術 -光励起三重項電子を用いた動的核偏極-
ラジカル分子の代わりにレーザー照射によって生ずる光励起三重項電子を用いたDNP(トリプレットDNP)を発展させる技術を開発しました。 |
| 08435 | 色調が二段階に大きく変化するロイコ色素の新技術
ロイコ色素の骨格を二つ繋げた新規パイ電子系化合物のアミノベンゾピラノキサンテン系色素(iso-ABPX)を開発しました。無色のiso-ABPXは、酸やフェノール性化合物によって桃色から青緑色までの色を示し、その濃度や周囲の温度によって無色・桃色・青緑色の三つの色調をコントロールできます。 |
| 07948 08201 |
テラヘルツ量子カスケードレーザ
小型、高出力、高効率、狭線幅、連続動作可能、安価なテラヘルツ光源として実用利用が期待される「テラヘルツ量子カスケードレーザ(THz-QCL)」の開発を行っています。 |
| 08028 08093 |
粘菌から着想した解探索コンピュータ
アメーバ状単細胞生物・粘菌の変形行動を光刺激により制御する事で、様々な組合せ最適化問題の解を探索できる粘菌コンピュータの研究開発を進め、SAT解探索モデルを定式化しました。 |
| 08731 | 内部流路を有する手の平サイズのガラス製ツール
微細な流路に複数種類の機能物質や生体材料を区画定着させた後に、2枚のガラスを貼り合わせることで1枚のマイクロ流体チップに複数の化学、生化学機能を集積することに成功しました。 |
| 08289 | 細胞内1分子スクリーニングシステム
日本が世界に先駆けて実現した、細胞内で1分子の振る舞いを分析する手法(細胞内1分子動態解析)を応用し、分子動態の変化に基づく新しい指標による、薬剤や疾病因子の『細胞内1分子スクリーニングシステム』を実現する為の基本技術です。1分子技術は、創薬や医療など生命科学分野の強力な手法となり得るため、懸案である計測・解析の効率を自動化やプロセスの統合によって大幅に向上させる事で、網羅的分析が可能なハイスループットシステムの構築が可能になります。 |
| 07785 | 慢性疲労症候群の血液バイオマーカーの発見
慢性疲労症候群患者と健常人の血漿を対象に代謝物質の変動を網羅的に解析することにより、慢性疲労のメカニズムに基づいた客観的な疲労バイオマーカーを探索しました。 |
| 07873 | ガラスキャピラリによるX線偏向技術
様々な曲率をもつキャピラリ束を用いることにより照射方向を制御する方法、および、程よい堅さのハウジングを施した長いキャピラリを用いる方法を提案し、その実証を行いました。 |
| 08361 | 暗視野X線タイコグラフィによる高分解能・高感度イメージング
X線タイコグラフィは、試料にコヒーレントX線を照射した際に観測される回折強度パターンに位相回復計算を実行し、試料像を取得するレンズレスイメージング技術です。暗視野X線タイコグラフィは、従来のX線タイコグラフィ技術と比べて、暗視野X線タイコグラフィでは、目的の空間分解能・感度を達成するために必要な回折強度のダイナミックレンジが大幅に圧縮されるため、空間分解能・感度を飛躍的に向上させることが可能です。 |
| 07754 07917 |
生物機能分子探索テクノロジーの新規開発
疾病関連タンパク質・金属材料・ポリマーなどの標的分子・材料に対して特異的に結合し、特定の生物機能を制御、賦与する新規ペプチドを独自に創出することに成功しました。 |
| 07843 | 植物由来ブラシノステロイドを用いた免疫賦活剤
ブラシノステロイドは微量で動物の免疫賦活化作用を有することを見出しました。 |
| 08187 | 中赤外レーザーを用いたガス成分分析システム
呼気中に含まれるガスの吸収スペクトルに波長同調させた狭帯域中赤外レーザーとマルチパスセルを用いた赤外吸収分光計測により、ガス成分の定量分析が可能です。 |
| 08413 | 生体内に埋植可能なウェアラブル光プローブ
本発明の微小な光プローブは、目的とする生体組織内に低侵襲的に埋植し長期間留置することが可能であり、被検体には大きな負荷が無く、自由に行動できます。 |
| 07114 07716 08283 |
薬剤や食品成分の生体イメージングを可能とするPET標識化学技術
本技術は、わずか5分の反応時間で最小の炭素置換基である[11C]メチル基を目的の炭素骨格上に導入できる革新的標識法です。また、生体分子の標識化に関して、核酸に対するクリック化学型化学量論的18F-標識法の開発を行ってきました。現在、生体高分子化合物(タンパク質、抗体など)に対する新しい標識法となる[11C]アセチル化法の開発にも取り組んでいます。 |
| 08461 | 再利用可能で汚れに強い電子線バイプリズム
回転型電子線バイプリズムのフィラメントホルダーを二電極構造とし、一方の電極にホルダー本体へ結線(接地)される回転角度を設けることで、フィラメント電極への通電を可能とします。また、金属フィラメントを採用することにより、フィラメント電極の「繰り返し使用」が可能となります。 |
| 08352 | 波面歪み測定技術と補償技術
波面補償光学装置が波面歪み測定にも使用され、光学顕微鏡などの測定装置自身によって、観察している試料位置における波面歪みを測定します。そのため、追加の波面センサーを用いる必要がなく、装置を簡易化できます。また、明るい点光源も必要ないため、あらゆる試料の観察に適用可能な手法となっています。 |
| 08388 | 実験動物の微細振動検出方法および検出システム
本態性振戦のモデルと考えられるネトリンG2遺伝子ノックアウトマウスの微細な振戦を客観的に検出するために、振戦検出装置ならびに検出アルゴリズムを開発しました。 |
| 08118 | 蛍光タンパク質UnaGを利用した臨床検査蛍光試薬
大腸菌で作らせたUnaG(アポ蛋白質)にビリルビンを結合させることで蛍光を発することを発見、その現象を応用し、血清中のビリルビンの濃度を測定するキットを開発しました。 |
| 08004 | 小型中性子源用の金属Beターゲット
小型中性子源で使われる低エネルギーの陽子ビームや重陽子ビームは中性子発生ターゲットである金属Be中で停止すると水素脆化により金属板を破壊してしまいます。そこで、荷電粒子の金属中侵入距離を正確に計算し、Be金属の下流側で陽子ビームが止まるようにBe金属箔の厚さを調整しました。また、バッキング板には水素の拡散性が高く、熱伝導率の良い金属を選択する事で除熱と水素脆化の2つの問題を同時に解決する事に成功しました。 |
| 08049 | 超薄板ガラスを用いた全ガラス製マイクロチップ内電動バルブ
全ガラス製マイクロチップ内電動バルブの開発に成功しました。 |
| 07752 | 新規ヘテロアセン類化合物
5員環の形成と同時に所望する原子を導入する足場となるハロゲン対を形成する反応を新たに見出し、様々なヘテロ元素の導入が可能となる一般的合成法を開発しました。 |
| 07366 | 無細胞タンパク質合成系を活用した膜タンパク質合成方法
脂質二重膜に組み込んだ状態の活性体膜タンパク質を大量に合成する新技術の開発に成功しました。膜タンパク質の結晶構造解析によるドラッグデザインやGPCRなどの抗原調整等、創薬において非常に有用な技術として応用可能と考えられます。 |
| 07787 | 軽元素分析装置及び分析方法
全固体リチウムイオン電池の充放電中のリチウム分布状況を、実時間・実空間で、動的にその場分析することができます。 |
| 07819 | 熱膨張の影響を受けにくい検出器などの固定方法
室温の範囲から外れた温度で動作する装置に使用する目的で、熱膨張による影響を受けにくい固定方法を開発しました。 |
| 08607 | 超広帯域において光吸収を呈するメタマテリアルフィルム
メタマテリアルを用いた可視から赤外域にかけての超広帯域光吸収体です。メタマテリアルを用いているため、吸収体の厚さは1ミクロンを切り、入射角依存性や偏光依存性を有せず、大面積吸収体の作製を安価で容易に行うことが可能です。また、本吸収体は可視から赤外域にかけての3オクターブに達する超広帯域を有します。 |
| 07801 | 酵素結晶固定化電極並びにそれを備えるセンサー及び電池
酵素結晶を電極表面に固定化することによって、高密度かつ一定の配向性で酵素を固定化でき、これにより触媒機能を円滑に発揮して従来技術より高い電流応答を示す電極を構築できることを見出しました。 |
| 08014 | 10~20色マルチカラー蛍光イメージング
細胞内生体分子の解析に有効な蛍光顕微鏡法の多色化の研究。 |
| 07772 | 広範囲分析をマネジメントする新規アルゴリズム
大規模な検出対象を標的としたワイドターゲット解析を可能にする革新的なマネジメントアルゴリズムを開発しました。これにより、従来法では数か月以上かかっていた条件検討が瞬時に行えるようになりました。 |