2015年8月5日
生体外での臓器育成を目指す研究者
生体外での臓器育成、つまり細胞から臓器をつくり出すことができる装置の開発を目指している研究者が、多細胞システム形成研究センター(CDB)にいる。器官誘導研究チームの石川 潤リサーチアソシエイト(RA)だ。目標達成への大きな一歩として、摘出した臓器の血管にチューブをつなぎポンプで培養液を流しながら培養する「臓器灌かん流りゅう培養システム」を開発し、ラットの肝臓の長時間保存と蘇生に成功した(図)。移植医療の現場では、ドナー(臓器提供者)数が不足している。今回の成果は、ドナー臓器の保存時間の延長と、機能障害によって移植不適応だった心停止ドナーの臓器の利用を可能にし、臓器移植の課題解決につながると期待される。「途中、研究が嫌になりかけたときもありましたが、ラットの肝臓を初めて機能障害を起こさずに培養できたときと肝臓の移植に成功したときは、本当にうれしかった。日付まで覚えています」。そう語る石川RAの素顔に迫る。
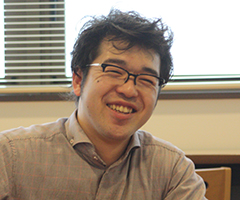
石川 潤 リサーチアソシエイト
多細胞システム形成研究センター 器官誘導研究チーム
1984年、埼玉県生まれ。修士(工学)。東京理科大学基礎工学部生物工学科卒業。同大学大学院基礎工学科生物工学博士課程単位取得後退学。2014年より理研 発生・再生科学総合研究センター(CDB)器官誘導研究グループ研修生。2015年4月より現職。
 図 臓器灌流培養システム
図 臓器灌流培養システム培養容器(右)に入れた肝臓の血管にチューブを接続し、酸素を運ぶ赤血球と栄養を含んだ培養液をポンプで流す。培養液の温度やpH、酸素濃度などを制御できる。
「昆虫が大好きだった」と石川RA。小学生のとき、自由研究でセミの羽化を観察し、表彰された。「教師だった母の貢献も大きかった」と笑う。ピアノ、トランペット、習字、水泳と多くの習い事をし、将来は医者か研究者になりたいと思っていた。しかし、県内トップクラスの高校に入学すると、状況が一変。「自分は勉強ができると思っていたのに、周りははるかに優秀な人ばかり。伸び切っていた天狗の鼻がポキッと折れてしまいました。勉強も嫌になり、ぐれてしまいました」
高校卒業後、予備校にも通わずアルバイトをして過ごしていた。そんなある日、母と久しぶりに話をした。「父は製薬会社の研究員でしたが、私が小さいころに転職しています。それは、私との時間を大切にしたいからだったと言うのです。そういえば、小学生のころは父が勉強を教えてくれていました。このままでは両親にも申し訳ないと、真剣に受験勉強を始めました。結局、大学入学まで3年かかってしまいました。でも、あの3年があるからこそ、今の自分がいるのだと思います」
東京理科大学基礎工学部生物工学科に進学し、4年からは辻 孝 教授の研究室に所属。「研究室見学で、ラットの肝臓を培養しているシャーレを見せてもらいました。肝臓を見るのも初めてでしたし、肝臓の育成を目指していると聞き、これは面白い!と思ったのです」。しかし、肝臓は培養すら難しかった。「培養液に浸すだけでは、機能が低下していきます。私たちは生体の仕組みに学ぶべきだと考え、血管に培養液を流しながら培養するシステムをつくりました。酸素を運ぶために、培養液に赤血球を加える工夫もしました」。それでも機能は落ちてしまう。「酸素や栄養が足りていないのだと考えました。培養温度を下げると細胞の活性が下がり、必要な酸素や栄養が少なくて済みます。さまざまな温度を試した結果、22℃の場合48時間培養しても機能障害が起きないことが分かりました」。現在の移植医療で行われている低温保存より状態が良く、22℃で24時間灌流培養した肝臓を移植したラットの生存率が100%であること、心停止によって血流が途絶えて障害が起きた肝臓を摘出して灌流培養すると機能が回復し移植が可能になることも確認し、2015年4月に発表した。
「辻先生がこの研究に着手して9年、私が加わってからだけでも6年かかっています」。途中、企業への就職を考えたこともあった。2014年には辻 教授が理研CDBで研究チームを立ち上げ、石川RAもCDBへ。特に苦労した点は?「移植です。医師に血管の縫合技術を教えてもらい、必死に修得しました。教えられたことができない自分が許せないんです。そんな性格が幸いしました」。朝、移植したラットの様子を見るのが日課だ。「鼻の動きや体毛の様子から体調が分かるようになり、先輩から『ラットと話せる男』と呼ばれたことも(笑)」
今回の成果をヒトへ応用するため、ヒトと臓器の大きさが近いブタの臓器の培養を計画している。最終目標は臓器の育成だ。人工的につくった血管網を灌流培養システムにつなぎ、その血管網の上にiPS細胞(人工多能性幹細胞)などからつくった肝臓の前駆細胞を置けば自己組織化によって立体的な肝臓ができると考え、研究を着々と進めている。石川RAは力強く言う。「臓器培養・育成の父と呼ばれるような研究者になりたい」と。
(取材・執筆:鈴木志乃/フォトンクリエイト)
『RIKEN NEWS』2015年8月号より転載
