2019年3月5日
植物遺伝子を社会に役立てる研究者
地球温暖化によって将来、植物が高温ストレスにさらされる頻度が高まり、成長が阻害されることが危惧されている。そうした中、環境資源科学研究センター(CSRS)統合メタボロミクス研究グループの東 泰弘 研究員は、高温ストレスの緩和に必須である脂質分解酵素リパーゼの遺伝子を発見。その遺伝子の機能を強化するなどの改良を行うことで、高温ストレスに強い作物の創出につながると期待されている。「植物の遺伝子を使って社会のためになることをしたい」そう語る東研究員の素顔に迫る。
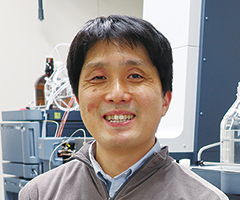
東泰弘 研究員
環境資源科学研究センター 統合メタボロミクス研究グループ
1979年、千葉県生まれ。博士(薬学)。千葉大学薬学部総合薬品科学科卒業。薬剤師免許取得。千葉大学大学院医学薬学府創薬生命科学専攻博士課程修了。米国ドナルド・ダンフォース植物科学研究所ポストドクトラルフェローを経て、2012年より現職。2018年度理研桜舞賞受賞。
 図 hil1変異体の高温ストレスに対する応答
図 hil1変異体の高温ストレスに対する応答
高校時代、「人と話すのは苦手だから、1人で黙々と実験をする研究者が自分には合っている」と思っていた東研究員。ある日、友人から「研究所の見学に行こう」と誘われた。それが、地元の千葉県木更津市にある、かずさDNA研究所だった。「DNAシーケンサーがずらっと並び、読み取った塩基配列が次々と出力されていました。なんて格好いいんだ、遺伝子の研究をしよう、と決めました」
千葉大学薬学部に進学。4年生からの所属は、遺伝子資源応用研究室と入学時から決めていた。「実験が面白くて、毎日遅くまでやっていました」と東研究員。大学院では、種子に貯蔵されるタンパク質の生合成機構を研究。当時注目され始めていたトランスクリプトーム解析とプロテオーム解析を駆使して、環境ストレスで変化するRNAとタンパク質の発現量を調べた。「貯蔵タンパク質の生合成に重要な遺伝子を突き止めるまでには至らず、悔しさを残して博士課程を終えました」
研究室には留学生や外国人研究員も多く、刺激を受けたことや、旅行好きだったことから、「海外で研究してみたい」と米国のドナルド・ダンフォース植物科学研究所へ。ケシから得られる化合物モルヒネの生合成酵素の立体構造解析プロジェクトに加わった。X線による構造解析に必要なタンパク質の結晶化を担当。「添加物などを少しずつ変えて大きく高品質な結晶ができる条件を地道に探るのは、性に合っていました。でも、今日こそはと顕微鏡をのぞいても小さな結晶ばかり。実験が大好きとはいえ、つらい日々でした」と振り返る。1年ほどして、ようやく解析に使える結晶ができた。「同僚から『baby’s luckだね』と言われました」と頬が緩む。直前に子どもが生まれていたのだ。その結晶を使って共同研究者が立体構造の解析に成功した。ほかにもバイオ燃料への応用を目指し、遺伝子組み換えによって植物にテルペンという脂質をたくさんつくらせる研究も行った。気が付けば、米国に来て5年がたっていた。2012年に帰国し、理研へ。
現在の研究テーマの一つは、植物の高温ストレス応答である。植物を通常より高い温度で栽培すると葉緑体の膜を構成する脂質の分子組成が変わることから、脂質組成の変化が高温ストレスの緩和に関わっていると考えられている。東研究員は、高温ストレスによって発現が誘導される遺伝子をトランスクリプトーム解析で調べ、その中で脂質分解酵素リパーゼの遺伝子に注目した。その遺伝子をHIL1と名付け、機能を調べ始めたが難航。しばらくして東研究員の勤務地が神奈川の横浜から埼玉の和光へ変わった。CSRS内の連携推進を目的としたものだったが、これが幸いした。「通勤時間が短くなり、実験に使える時間が増えたのです。しかも、3人目の子どもが生まれたばかりだったので、妻の負担を少しは減らせたかも」。およそ2年かけ、HIL1遺伝子は葉緑体膜の脂質組成の変化に重要な役割を果たしていて、高温ストレスの緩和に必須であることを明らかにした。HIL1遺伝子の機能を欠損させた変異体は高温ストレスを受けると枯れてしまう(図)。「脂質組成の変化はわずかなので、高性能の質量分析計とその性能を発揮できる技術を持つ研究グループのメンバーあってこその成果」と東研究員。それまでの一見無関係に思える研究で得た知識や技術も役立った。
「研究者は、いろいろな人と協力し合い、大勢の前で発表もする。昔抱いていた研究者のイメージとは違っていました」と笑う。「遺伝子を研究しているからには、新しい遺伝子を見つけたいと思い続けてきました。それがようやく実現できた。HIL1遺伝子の機能をさらに理解し、社会に役立てること。それが次の目標です」
(取材・執筆:鈴木志乃/フォトンクリエイト)
『RIKEN NEWS』2019年3月号より転載
