驚異のカラダ
ウイルスやテクノロジーを通じて見ると改めて気づく私たちのカラダの不思議。骨格系、消化器系、呼吸器系、免疫系……さまざまなシステムから成り立つ人体の精巧さ、賢さ、ヘンテコさに驚く18冊。
2020
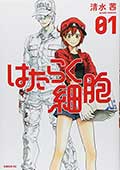
『はたらく細胞(1)~(6)』
- 清水 茜(著)
- 講談社 2015年
細胞たちのキャラ祭り マンガで学ぶ免疫系
舞台は体内、主人公は体中に酸素を届けるおっちょこちょいの赤血球。白血球(好中球)、キラーT細胞、マクロファージなどの免疫細胞が、それぞれの得意技を生かして、体内に侵入した細菌やウイルスと戦いまくる!休みなく働いてくれる自分の体に感謝の念が湧いてくる。
2020
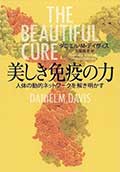
『美しき免疫の力─人体の動的ネットワークを解き明かす』
- ダニエル・M・デイヴィス(著)久保 尚子(訳)
- NHK出版 2018年
急速に研究が進む免疫学 科学者たちのを奮闘を追う
驚くほど精密な免疫システムの全体像に迫る。免疫はどうやって敵と味方を区別しているのか?自分の体を攻撃してしまう「自己免疫疾患」とは何か?注目のがんの免疫療法とは?近年の革命的ともいえる免疫学の進歩と、その最前線に立つ科学者たちの挑戦を追う。
2020
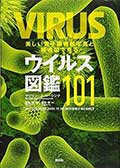
『美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑101』
- マリリン・J・ルーシンク(著)布施 晃(監)北川 玲(訳)
- 創元社 2018年
色とりどり形さまざま ウイルス図鑑の決定版
肉眼では見えないウイルス。電子顕微鏡写真で見ると、ミクロの世界の姿かたちにビックリ。ヒトに病気をもたらすウイルスのほか、動物ウイルス、植物ウイルス、細菌につくウイルスまで。形の特徴や、宿主、感染経路、分布、ワクチンの有無など、この1冊でウイルスの種類と仕組みがまるっとわかる。
2020

『生物はウイルスが進化させた─巨大ウイルスが語る新たな生命像』
- 武村 政春(著)
- 講談社 2017年
巨大ウイルスから導かれる 生命進化の新たなシナリオ
2003年に発見された「巨大ウイルス」はそれまでのウイルス観を大きく覆した。ウイルスは本当に非生物なのか?生物の進化において想像以上に重要な役割を担っているのではないか?日本初の巨大ウイルス「トーキョーウイルス」の発見者がスリリングに導く、生物進化の新たな仮説。
2020

『感染症の世界史』
- 石 弘之(著)
- KADOKAWA 2018年
地球を舞台に描かれる 人類と感染症の長大なる戦記
感染症の原因は、ずばり過密社会。人類が農耕を発明し、定住集落ができたころから、感染症は始まった。産業革命による都市の不衛生がもたらしたコレラ、熱帯林の破壊に端を発するエボラ出血熱、交通網の発達で拡大したSARS。環境史の立場から論じる感染症。パンデミックは人災とも言える。
2020
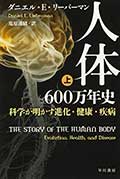
『人体600万年史(上)(下)─科学が明かす進化・健康・疾病』
- ダニエル・E・リーバーマン(著)塩原 通緒(訳)
- 早川書房 2017年
二足歩行を始めて600万年 人体の驚異的な進化プロセス
人間の身体は何に適応し、どう進化してきたのか?人類が二足歩行を始めてから現在まで600万年のあいだに起こった身体的・文化的変化を追う。肥満、腰痛、糖尿病など現代の慢性病の原因も歴史の中で明らかに。健康とは何なのか、体と暮らしを見つめ直す1冊。
2020
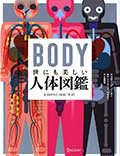
『BODY 世にも美しい人体図鑑』
- スティーブン・パーカー(著)アンドリュー・ベイカー(絵)千葉 啓恵(訳)
- ディスカヴァー・トゥエンティワン 2018年
トリビア満載のビジュアル図鑑 目で見てわかる人体の不思議
人体にまつわる細かな知識を、数字とインフォグラフィックで紹介。人の骨の総数は?関節はどこまで動く?体重に占める皮膚の割合は?脳とコンピュータの記憶容量は?ページをめくるたびに、鮮やかな図解に引き込まれる!友達に教えたくなる知識が100個は見つかる。
2020

『生まれながらのサイボーグ─心・テクノロジー・知能の未来』
- アンディ・クラーク(著)呉羽 真、久木田 水生、西尾 香苗(訳)丹治 信春(監)
- 春秋社 2015年
人間はすでにサイボーグ!?テクノロジー時代の身体観
テクノロジーと人間の融合が加速しているといわれる昨今。しかし、人間はずっと昔からサイボーグなのだと著者は言う。例えばペンと紙を使うことによって思考や計算ができるのなら、その道具はもはや人間の機能の一部ではないか?これからの身体観を問う。
2020

『人体、なんでそうなった?─余分な骨、使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳』
- ネイサン・レンツ(著)久保 美代子(訳)
- 化学同人 2019年
人体は妥協の産物だらけ!?ハチャメチャな進化の軌跡
ヒトの身体の素晴らしさ…ではなく「イケてなさ」を追究する。小さな骨がやたら多い足首、後ろ向きの網膜、不要な遺伝子をため込み続けるDNA、誤解しやすい脳、なぜか心臓をぐるりと迂回している声帯の神経…。出来損ないのデザインから、進化の過程を解き明かす。
2020

『人体はこうしてつくられる─ひとつの細胞から始まったわたしたち』
- ジェイミー・A.デイヴィス(著)橘 明美(訳)
- 紀伊國屋書店 2018年
設計図もなく現場監督もいない 奇跡のようなヒトの発生過程
たった一つの受精卵から数十兆の細胞で組織された人体になるまで、母の胎内で9ヶ月。コントロールする者がいなくても、細胞同士が創発し、自己組織化して、人体という精密なシステムをつくり上げる。記憶にはないけれど、私たち一人一人が経験してきたそのプロセスは感動モノだ。
2020
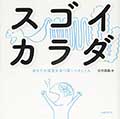
『スゴイカラダ─あなたの健康を保つ驚くべきしくみ』
- 北村 昌陽(著)江田 ななえ(絵)
- 日経BP社 2014年
カラダの中の連携プレー 思慮深い人体の仕組み
緊張するとドキドキするのはなぜ?ダイエットに筋トレが有効な理由は?新陳代謝のメカニズムとは?カラダに関する疑問のあれこれを、46人の医学研究者に聞く。ユーモラスな図解で内臓、神経、ホルモンなどの働きぶりが明快に。各器官は互いのことを考えて賢く連携プレーをしているのだ。
2020
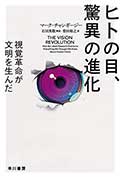
『ヒトの目、驚異の進化─視覚革命が文明を生んだ』
- マーク・チャンギージー(著)柴田 裕之(訳)
- 早川書房 2020年
視覚を超進化させることで 人類は文明を作りあげた
視覚にまつわる四つの謎。なぜ人間は色を判別できるのか?なぜ人の目は前向きについているのか?「目の錯覚」が起きるのはどうして?文字はなぜ現在の形をしているのか?これらの疑問を追いながら、人類がどう進化し、サバイブしてきたかを仮説する大胆な1冊。なるほど、人間の視覚は超人的だ。
2020

『いのちを呼びさますもの─ひとのこころとからだ』
- 稲葉 俊郎(著)
- アノニマ・スタジオ 2017年
いのちとは何なのか?臨床医による人間讃歌
病や心身の不調は、体や心からの大切なメッセージなのだ。医療現場で働きながら「いのち」の根源を問い続ける臨床医による、瑞々しいエッセイ。東洋的な心身論や、芸術が人に与える力を、小説や詩の一編を引用しながら解いていく。「今生きている自分」に立ち返る1冊。

推薦コメント
著者の稲葉 俊郎氏は西洋医学の医師ですが、科学の客観性だけでは捉えきれない一人ひとりのこころや主観の重要性を説いています。自然や芸術と対峙するなかで、自分の内と外を結ぶ身体感覚を育むこと。その大切さを伝える1冊です。
檜山 敦(革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術グループ 医用機械知能チーム 客員研究員)
2020
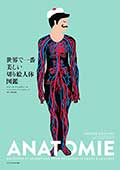
『世界で一番美しい切り絵人体図鑑』
- エレーヌ・ドゥルヴェール、ジャン=クロード・ドゥルヴェール(著)奈良 信雄(監訳)
- エクスナレッジ 2017
人体の構造が感覚でわかる アートな仕掛け絵本
フランス発、デザイナーの娘と医師の父がつくった世にも美しい人体図鑑。筋肉系、骨格系、消化器系、循環器系などのシステムを繊細な切り絵で表現。重ねて見ると、人体の多層さが感覚的にわかる。脳や五感の仕組みもめくって楽しめる、アート作品のような1冊。
2020
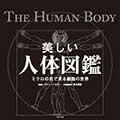
『美しい人体図鑑─ミクロの目で見る細胞の世界』
- コリン・ソルター(総編集)奈良 信雄(監)三村 明子(訳)
- ポプラ社 2014年
私たちの中にある宇宙 十人十色の働く細胞たち
ジェリービーンズのような大腸菌、まるで宇宙人に見えるT4バクテリオファージ、牡丹の花にそっくりの樹状細胞。血液、脳、眼や耳、内臓など各器官の細胞152点を最新鋭の顕微鏡で撮影。役割ごとにプロフェッショナルな仕事をする細胞たちは、こんな形をしてる!?人間の内なるミクロコスモスに驚嘆する。
2020

『アスリートの科学─身体に秘められた能力』
- 小田 伸午(著)
- 角川学芸出版 2013年
一流アスリートはいかにして身体感覚を研ぎ澄ますのか
スポーツは「頭」で検討して、「感じ」で実践する。練習では考えながら動きを調整し、いざ試合になれば、思考は削ぎ落し感覚を研ぎ澄ます。速く走るには?遠くに投げるには?走りながらパスするには?イラストや写真で具体例をあげながら、合理的な身体の動かし方を解き明かす実践の書。
2020

『カーボン・アスリート─美しい義足に描く夢』
- 山中 俊治(著)
- 白水社 2012年
新しいシルエットを求めて 試行錯誤の義足プロジェクト
プロダクトデザイナーの山中 俊治氏は、テレビで見た競技用義足の機能美に釘付けになった。大学内でプロジェクトを立ち上げ、義足のデザインでパラリンピックへの入賞貢献を目指すことに。学生や義足アスリートと打ち込んだ、2008年から3年間の記録。

推薦コメント
私には論文で研究を終わらせるのではなく、成果を何かしら形にして人に届けたい、社会の必要に応えたい、という思いがあります。その意味でも、スポーツ用義足のデザインプロジェクトを描いた『カーボン・アスリート』はお薦めです。著者の山中 俊治先生はプロダクトデザイナー。選手たちとの対話や、失敗を繰り返した3年間の研究現場の様子はリアルで、ものづくりに興味がある高校生にぜひ読んでほしい。
檜山 敦(革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術グループ 医用機械知能チーム 客員研究員)
2020
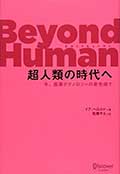
『Beyond Human(ビヨンドヒューマン)超人類の時代へ』
- イブ・ヘロルド(著)佐藤 やえ(訳)
- ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017年
見た目は30歳、実は250歳。不老無病はもうすぐ現実に
「生きている限りみな健康で若々しい」という未来はそこまで来ている??人工臓器、脳機能の強化、細胞に入り込んで病気や老化を防ぐナノボット技術など、衝撃の医療テクノロジーが次々に登場。しかし、死ねない人間になっていいのだろうか。待ったなしの生命倫理の難題を、しっかりと考えたい。
