脳とココロ
脳が分かれば人が分かる?多方から脳とココロの謎に迫る17冊。
2021
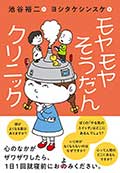
『モヤモヤそうだんクリニック』
- 池谷 裕二(文)ヨシタケ シンスケ(絵)
- NHK出版 2020年
脳研究者・池谷 裕二 先生が小学生のふしぎにズバリ回答
僕の「やる気スイッチ」はどこにある?ゲームが頭に良くないって本当?いじめがなくならないのはなぜ?256人の小学生から寄せられたモヤモヤに、脳研究者の池谷 裕二 先生が愛とユーモアたっぷりにヒントをくれる。子どもから大人まで「なるほど!」な脳科学の超入門書。
2021

『脳はバカ、腸はかしこい』
- 藤田 紘一郎(著)
- 三笠書房 2019年
脳と腸はこんなに密接!脳だけで人間は語れない
うつ病や少子化の原因も、脳で考えすぎることにある?寄生虫博士こと藤田 紘一郎 先生は、脳偏重の世に警鐘を鳴らし「腸を可愛がれば、頭が良くなる!」と断言する。実は、幸せ物質のセロトニン、ドーパミンも腸で合成されるのだ。脳科学の世界でも注目される「脳と腸の関係性」をわかりやすく解説。

推薦コメント
脳と腸は体内の離れた部位にあり異なる働きを担っていますが、お互い密接に関係しています。本書で「かしこい」とされる腸の役割を知れば、人体の仕組みにますます興味を持つはずです。
上口 裕之(脳神経科学研究センター 副センター長)

推薦コメント
私が子供の頃には花粉症で悩む人は周りにいませんでした。花粉症が増えてきたのはどうやら暮らしの変化と腸が関係しているらしい。そんな身近な話から興味を持って読みました。腸に関する本は最近ブームですが、藤田 紘一郎さんはその先駆者と言える方です。脳にも勝る腸の大切な働きを、中高生でも読みやすく解説してくれています。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
2021
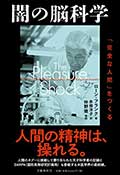
『闇の脳科学─「完全な人間」をつくる』
- ローン・フランク(著)赤根 洋子(訳)仲野 徹(解説)
- 文藝春秋 2020年
精神の操作は許されるのか?脳治療で問われる倫理
1950~70年のアメリカで活躍した天才医師ヒース。彼が行っていた脳に電極を埋め込む「脳深部刺激療法」は、非人道的として当時非難された。それが現在、最前線の治療法として再び注目を浴びている。脳治療で犯罪者や同性愛者の精神を「矯正」できるとして、それは倫理において許されるのか?
2021

『私はすでに死んでいる─ゆがんだ<自己>を生みだす脳』
- アニル・アナンサスワーミー(著)藤井 留美(訳)春日 武彦(解説)
- 紀伊國屋書店 2018年
私とは誰なのか?「自己意識」の難問に挑む
「自分は死んでいる」と思いこむコタール症候群。身体の一部を切断したくてたまらない身体完全同一性障害。ゆがんだ自己感覚を持つ患者たちへの取材を通じて「私とは何なのか?」を問う。神経科学の知見をベースに、精神医学や哲学の視点からも考察する。
2021

『意識はいつ生まれるのか─脳の謎に挑む統合情報理論』
- マルチェッロ・マッスィミーニ、ジュリオ・トノーニ(著)花本 知子(訳)
- 亜紀書房 2015年
脳の最大の謎「意識」はどのように生まれるのか?
解剖実験中、手のひらに脳を載せ、数時間前までその中に、知識、記憶、夢など全てが宿っていたことに愕然とした。著者・精神科医トノーニの学生時代の思い出から本書は始まる。ただの物質である脳に、どうして意識が宿るのか?革新的な統合情報理論「Φ理論」によってその正体に迫っていく。

推薦コメント
この本がすごいのは、「人間の意識という捉えどころのないものを、科学がどう扱うのか?」という枠組みを最初に提唱したところです。意識の解明という難題に著者、ジュリオ・トノーニがどうアプローチしたのか、発想の仕方や試行錯誤のプロセスに注目して楽しんでもらいたいです。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)

推薦コメント
脳科学の最先端で、意識のメカニズムに迫ろうとする研究者の迫力と興奮が伝わってきました。研究は一人ではできません。こうした自身の研究のワクワク感を周囲に伝え広めていくことは、研究者としてとても大切なことだと思います。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
2021
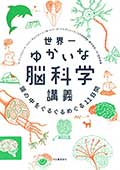
『世界一ゆかいな脳科学講義─頭の中をぐるぐるめぐる11日間』
- アンジェリーク・ファン・オムベルヘン(文)ルイーゼ・ペルディユース(絵)藤井 直敬(日本語版監修)塩崎 香織(訳)
- 河出書房新社 2020年
脳の全体像がわかる目で見て楽しい11講義
ユーモラスなイラストを交えて書かれた中高生向けの脳科学入門書。脳内の見取り図、各部のはたらき、五感に関係する神経とのつながり、喜怒哀楽といった情動、記憶など。脳内をぐるぐるめぐって、謎を解き明かしてゆく。眠っている間も休まない脳は、私たち専用のスーパーコンピュータだ。
2021

『歴史を変えた100の大発見 脳─心の謎に迫った偉人たち』
- トム・ジャクソン(著)石浦 章一(監訳)大森 充香(訳)
- 丸善出版 2017年
先史の頭蓋骨からMRIまでキーワードで読む脳研究の歴史
人類の歴史の中で、脳の働きはどのように解明されてきたのだろう?石器時代の頭蓋骨に残る手術痕に始まり、ルネサンス期の脳解剖、フロイトの精神分析、シナプスの解明、MRIなど、100のキーワードで神経科学の歴史を一覧するビジュアル図鑑。巻末の年表や神経学の偉人一覧も明快。
2021
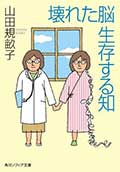
『壊れた脳 生存する知』
- 山田 規畝子(著)
- KADOKAWA 2009年
脳出血に倒れた女性医師が壊れた脳の回復を描く
整形外科医の著者は、37歳までに3回の脳出血を起こし、重い高次脳機能障害を発症した。時計が読めない、漢字が書けない、身体の左半分があることを忘れてしまう。脳出血時の状況から、治療、リハビリ、家族との関係、仕事復帰まで。医師の冷静な分析と患者の切ない想いの両方をユーモラスに伝える。
2021
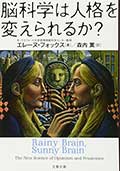
『脳科学は人格を変えられるか?』
- エレーヌ・フォックス(著)森内 薫(訳)
- 文藝春秋 2017年
あなたは楽観的?悲観的?脳が変われば性格は変わる?
がんだと誤診された人が恐怖に押し潰されて死んでしまった!?陽気で明るい修道女はネガディブな同僚より平均10歳も長生きだった!?楽観脳と悲観脳はどう違うのか。心理学、神経科学の専門家が、分子遺伝子学を交えながら人格形成のプロセスを探る。性格は変えられる?
2021

『孤独の科学─人はなぜ寂しくなるのか』
- ジョン・T・カシオポ、ウィリアム・パトリック(著)柴田 祐之(訳)
- 河出書房新社 2018年
なぜ人はつながりたいのか 孤独とは何なのか
孤独の辛さはどこからくるのか?物理的に独りでいることよりも、社会と断絶していると感じることにその原因がある。孤独と健康の因果関係、人間にとっての孤独の意味、社会的つながりの中でよく生きる方法を探求する1冊。心理学、生理学から経済学まで、多領域の見方を重ねて「孤独感」の理由をさぐる。

推薦コメント
コロナ禍の今、「孤独」は最も注目の集まるテーマです。著者は心理学と脳科学の研究者。心理学と脳科学は基本的に個人個人の内面を扱う学問ですが、この本でカシオポは長年にわたる研究経験から「社会的つながりの重要性」を指摘していました。学問分野の枠組みにとらわれない提言に感銘を受けました。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)
2021

『脳を司る「脳」─最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき』
- 毛内 拡(著)
- 講談社 2020年
ニューロンだけじゃない 今注目はグリア細胞
脳の正体はニューロンのはたらきにあると考えられてきた。だが近年、ニューロン以外の脳の構成要素に注目が集まっている。脳の中にある「すきま」が気分を決めている、脳細胞の半分を占めるグリア細胞が知性や心を司っている、など次々と仮説が登場。新しい脳科学がここに。
2021
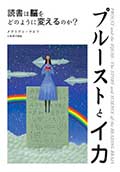
『プルーストとイカ─読書は脳をどのように変えるのか?』
- メアリアン・ウルフ(著)小松 淳子(訳)
- インターシフト 2008年
読むという行為が脳を思いっきり進化させた
文字の発明は、人間の脳をどのように変えたのか?子どもが読み方を学ぶとき、脳では何が起こっているのか?読書の達人の脳はどうなっている?「ディスレクシア(読字障害)」の研究を通して、脳科学、心理学、教育学などを横断しながら、「読む」脳の秘密を解き明かす。現代メディアの課題と可能性を展望する。
2021
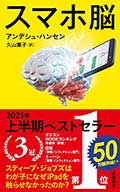
『スマホ脳』
- アンデシュ・ハンセン(著)久山 葉子(訳)
- 新潮社 2020年
睡眠障害、うつ、学力低下…スマホは最強ドラッグ!?
手放せないスマホ、チェックしないではいられないSNS。それもそのはず、これらは人間の脳をハッキングするように巧妙に設計されているのだ。集中力を奪い尽くされないように、相手の手の内を知り、スマホに支配されない自分でいよう。スウェーデンの精神科医による提言は、世界的なベストセラーになった。

推薦コメント
スマホやデジタル技術が脳に与える影響は社会的に非常に関心の高いテーマですが、その影響がポジティブかネガティブかは科学的に決着がついていません。実は読書もかつては「危険な行為」と恐れられていた時代がありました。この本ではスマホのネガディブな部分を取り上げていますが、今の子どもたちにとってすでに環境の一部。現時点での評価を絶対とせず、広い視野を持ちながらひとつの視点として読むといいと思います。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)
2021

『パラリンピックブレイン』
- 中澤 公孝(著)
- 東京大学出版会 2021年
身体に合わせておこる脳のカスタマイズ
身体のどこかに障害が発生すると、それを補うために脳は自ら変化する。この代償的変化に、競技トレーニングによる変化が加わって、パラリンピアンの脳には目覚ましい再編が起きていた!そのプロセスを見出し、リハビリテーションのモデルにしようとする試み。再生医療への希望が見える。
2021

『メカ屋のための脳科学入門─脳をリバースエンジニアリングする』
- 高橋 宏知(著)
- 日刊工業新聞社 2016年
機械工学出身の脳研究者が脳をエンジニアリング
東大工学部の熱血講義が1冊になった。脳をハードウェアと見立て、リバースエンジニアリングすることで脳のメカニズムを解き明かす。情報処理システムとしての脳、細胞膜のはたらきはRC回路、学習メカニズムや省エネ戦略と、エンジニアの視点と言葉で脳科学を語る。医学・生物学と機械工学を橋渡しする。

推薦コメント
脳をリバースエンジニアリングするという観点で書かれた本書は、理工系の感性にマッチしていて非常にしっくりきます。脳に興味がある数学・物理が好きな学生に是非読んでほしい1冊です。
磯村 拓哉(脳神経科学研究センター 脳型知能理論研究ユニット ユニットリーダー)
2021

『行動経済学まんが ヘンテコノミクス』
- 佐藤 雅彦、菅 俊一(作)高橋 秀明(画)
- マガジンハウス 2017年
人間は合理的じゃない!?皆やっちゃうヘンテコな行動
人間は合理的に行動している?いや、そうでもない。仲間の判断があきらかに間違っていても、つい同調してしまう。安いから、質がいいから、人はそんな真っ当な理由だけで買い物をしていない。みんなが身に覚えのあるヘンテコな行動を23のエピソードで紹介。漫画で楽しく学べる行動経済学の入門書。

推薦コメント
人間がついしてしまう非合理な行動を研究してきた行動経済学。この漫画は、そんな「矛盾」や「非合理」がなぜ起きるのか?を正確に、かつ身近なエピソードで描いています。『実践 行動経済学─健康、富、幸福への聡明な選択』と合わせて読むと理解が深まります。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)
2021

『実践行動経済学─健康、富、幸福への聡明な選択』
- リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン(著)遠藤 真美(訳)
- 日経BP 2009年
ナッジとは、人々を賢い選択に導く小さな工夫
カフェテリアで目立つ所に野菜を置くか、フライドポテトを置くかで、消費は劇的に変わる。店員は小さな工夫で私たちの健康をサポートできるのだ。著者はこのように人々を賢い選択に導く工夫を「Nudge (ナッジ) 」と名づけ、生活や社会制度への応用アイデアを挙げる。ノーベル経済学者による、使える経済学。

推薦コメント
人間がついしてしまう非合理な行動を研究してきた行動経済学。欧米では近年、政策決定にも取り入れられています。この本でリチャード・セイラーは「Nudge」(ナッジ:強制や報酬に頼らず、人を賢い選択へ導くちょっとした工夫)という言葉を世に送り出し、のちにノーベル経済学賞を受賞しました。私が研究している意思決定の脳科学にも関連する、興味深い分野です。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)
