科学史タイムトラベル
人類は科学で進化してきた。7万年の歴史を楽しむ18冊。
2022

『漫画 サピエンス全史(人類の誕生編)(文明の正体編)』
- ユヴァル・ノア・ハラリ(原著・脚本)ダヴィッド・ヴァンデルムーレン(脚本)ダニエル・カザナヴ(画)ほか
- 河出書房新社 2020年
7万年前、すべてはサピエンスの認知革命から始まった
人類の歴史は認知革命から始まった。数種類いたヒト属の中で、なぜホモ・サピエンスだけが生き延びたのか?1万2000年前の農業革命は何をもたらしたのか?人類史に新たな視点を提示した世界的ベストセラーが、公式漫画化でパワーアップ。

推薦コメント
歴史学者・哲学者であるユヴァル・ノア・ハラリの著書の漫画バージョン。大きくもない、強くもない、走るのが速いわけでもないホモ・サピエンスが、どうして唯一の人類として生き延び、永らえたのか。これを可能にした「革命」的な出来事を大胆に語る。
仲 真紀子(理化学研究所 理事)
2022

『サイエンス 大図鑑【コンパクト版】』
- アダム・ハート=デイヴィス(総監修)日暮 雅通(監訳)日暮 雅通、藤原 多伽夫、山田 和子(訳)
- 河出書房新社 2014年
紀元前1万4000年から現代まで科学の重要トピックを網羅
先史時代の火の利用に始まり、古代ギリシアの世界観、印刷革命、重力の発見、蒸気機関の発明、ゲノム解読、気候変動対策まで。500ページにわたる歴史の旅で、科学の発展の流れがまる分かり。人物解説、重要データの付録もあり、一家に1冊の保存版。
2022

『チ。─地球の運動について─(1)~(8)』
- 魚 豊(著)
- 小学館 2020年
地動説が「真実」になるまで宗教との激しい戦いがあった
「僕は、地動説を信じています」、そう宣言し、処刑されることを選んだ神童・ラファウ。キリスト教世界において異端だった地動説の思想は、連綿と続いていたのだ。コペルニクスが地動説を発表する以前の15世紀ヨーロッパを描いた、残忍かつ深淵な漫画。
2022

『〈どんでん返し〉の科学史』
- 小山 慶太(著)
- 中央公論新社 2018年
古代からの錬金術は20世紀に復活した
20世紀、原子核物理の研究が進んだことにより、夢から現実になった「錬金術」。最初の生命体は物質から生じたという説から、新たな展開を見せる「自然発生説」。一度は否定されたものの、別の視点から復活した科学に注目し、その展開を追った1冊。次のパラダイムシフトは何だ?

推薦コメント
科学の歴史は、考え方の枠組みが変わっていく歴史といえます。ただ、「人間が何をやりたいのか」は変わらないんですね。本書を読めばそれがよくわかります。例えば錬金術は、物質が「元素」からできていることがわかって以降、否定されました。しかし、現代では原子核物理の実験で元素を変えることが可能になり、再び錬金術が蘇っています。
櫻井 博儀(仁科加速器科学研究センター センター長)
2022
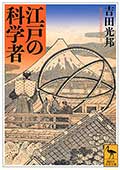
『江戸の科学者』
- 吉田 光邦(著)
- 講談社 2021年
300年間の鎖国中に開花した和のサイエンス
和算家の関 孝和、日本を測量した伊能 忠敬、日本独自の暦をつくった渋川 春海、『解体新書』の杉田 玄白、異端の発明家・平賀 源内など、江戸を発展させた30人の伝記集。西欧のスタンダードがなかったからこそ花開いたジャパンサイエンスを、いまこそ見返したい。

推薦コメント
江戸時代は300年も鎖国をしましたが、中国やオランダから書物が入ってきたし、自由に学問する気風が満ちていました。この科学精神が今の日本の科学の礎になっています。特にすごいと思ったのは、日本独自の数学『和算』。各地に塾があり、皆が競って問題をつくり解き合う。江戸の人々は数学を楽しんでいたんですね。
中野 明彦(光量子工学研究センター 特別顧問)
2022

『図説 科学史入門』
- 橋本 毅彦(著)
- 筑摩書房 2016年
天空図、気象図、解剖図 科学を物語るのは「図」だ!
科学者たちは何を調べ、考え、明らかにしてきたのか?その足跡はさまざまに工夫された図像という形で残されている。ガリレオの月面図、ヴェゲナーの大陸移動の図、ダ・ヴィンチの人体解剖図、ボーアの原子構造モデルなど、100枚に及ぶ図で科学の発展を追う。
2022

『かけらが語る地球と人類138億年の大図鑑』
- ミニ・ミュージアム、ジェミー・グローブ、マックス・グローブ(著)縣 秀彦、小林 玲子(訳)
- 河出書房新社 2022年
小さく圧縮された地球の歴史 かけらは壮大なタイムカプセル
1969年オーストラリアに落下した隕石から、70億年前の微粒子と地球外アミノ酸が発見された。生命の起源に迫るかけらだ。本書は、133のかけらから138億年の歴史を紐解くビジュアル図鑑。雷の化石、ネアンデルタール人の手斧、ベルリンの壁の破片など、想像力を刺激するかけらがズラリ。
2022

『世界を変えた150の科学の本』
- ブライアン・クレッグ(著)石黒 千秋(訳)
- 創元社 2020年
科学書はこれまでもこれからも人類の進歩を照らす灯火だ
科学の知識は、本に記述され、人々に伝わってこそ大きな進歩を遂げる。古代エジプトのパピルスに始まり、ダ・ヴィンチの手稿、ガリレオの『星界の報告』、ダーウィンの『種の起源』、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』など、2500年の科学書の歴史を、カラー写真で振り返る。印刷の発展や本のデザインも見どころ。

推薦コメント
Study nature, not books. ールイ・アガシー(スイス・1807-1873)科学者たるもの、何かを追究するなら、まずは「本物の実物」を無心に眺めることから始めるべきだ。この本では「世界を変えた科学」の原典を見ることができる。抽出された結果の情報のみからでは得られない、科学のパイオニア達の情念・息吹・葛藤・逡巡など、その時代の心の内面に思い馳せる入口となる。Bookでありながら、ただのBooksでは無い。
入來 篤史(生命機能科学研究センター 象徴概念発達研究チーム チームリーダー)
2022

『パラダイムと科学革命の歴史』
- 中山 茂(著)
- 講談社 2013年
時代によって変化する科学。その転換点を辿る
科学という学問は、いかにして発展してきたのか?古代アジアとヨーロッパの学問的伝統の比較から、近代科学成立後に生まれた学術雑誌や大学アカデミズム、明治日本の西洋科学の移植、学問のデジタル化まで。パラダイム論を日本に紹介した科学史家が俯瞰的に描く、学問の歴史。

推薦コメント
トーマス・クーンの「パラダイム論」を日本に紹介した中山 茂 先生が、科学史のパラダイムシフトの過程を書いています。パラダイムを簡単にいうと、「考え方の枠組み」のようなもの。普段研究をしていると、自分の考えに囚われがちですが、思考の外側を注意深く点検することが大事。枠を出ることから新しいパラダイムが生まれる可能性がある、それを教えてくれる本です。
櫻井 博儀(仁科加速器科学研究センター センター長)
2022
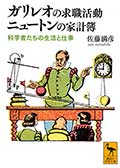
『ガリレオの求職活動 ニュートンの家計簿─科学者たちの生活と仕事』
- 佐藤 満彦(著)
- 講談社 2020年
偉大な科学者たちも日々の暮らしは楽ではなかった
長い間、科学者たちは、研究だけでは食べていけなかった。コペルニクスは聖職を本業にし、ガリレオはパトロンに生活を支えてもらい、ニュートンは錬金術の研究をしていた。どんなに偉大な科学者も生身の人間。科学の発展に貢献した科学者たちの性格や私生活、人間関係に光を当てたユニークな1冊。

推薦コメント
大科学者の生い立ちや、暮らしぶり、人間関係などが描かれていて、文句なしに面白い。売り込む力が大事だとか、大学教授だけやる人は少ないとか、今も昔も変わらず研究者って苦労していたんですね。お気に入りはロバート・フックのエピソード。17世紀に自作の顕微鏡でコルクの切片から細胞を発見した人ですが、バネの法則でも有名な物理学者です。彼とニュートンの対比に、引き込まれました。
中野 明彦(光量子工学研究センター 特別顧問)
2022
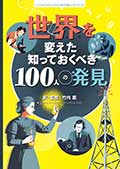
『世界を変えた 知っておくべき100人の発見─インフォグラフィックで学ぶ楽しいサイエンス』
- アビゲイル・ウィートリー(著)レオナール・デュポン(画)竹内 薫(訳)
- 小学館 2020年
エジソンやホーキングだけが偉大な科学者ではない!
自然淘汰による進化を唱えたダーウィン、有人動力飛行に成功したライト兄弟、X線を発見したマリー・キュリー、地動説を発表したコペルニクス……。歴史に名を残す、偉大な科学者ベスト100を、楽しいイラストで一挙公開。あまり有名でない偉人も取り上げていて、科学のトリビアが満載。
2022

『進化論の進化史─アリストテレスからDNAまで』
- ジョン・グリビン、メアリー・グリビン(著)水谷 淳(訳)
- 早川書房 2022年
生命進化を考え続けた有名無名の科学者たち
進化論を唱えたのは、ダーウィンだけじゃない。アリストテレスの時代から現代まで、進化論は千数百年をかけて進化し、2020年代も発展を続けている。遺伝英国の科学ジャーナリスト夫妻が、生命進化のメカニズムを考え続けた科学者たちの生涯を取り上げながら、進化論の歴史を紹介する。

推薦コメント
進化論といえば、誰もがダーウィンを思い浮かべるでしょう。しかし進化についての考察は、古代ギリシャの時代から始まっていました。さらにダーウイン以降に進化論がどこま進展したかも、この本を読めば分かります。化石からゲノムが読み取れるようになった今、生物の進化の解明は、実験科学へと変貌しました。進化論の進化をじっくりたどれる1冊です。
中野 明彦(光量子工学研究センター 特別顧問)
2022

『ケミストリー世界史─その時、化学が時代を変えた!』
- 大宮 理(著)
- PHP研究所 2022年
酒、スパイス、ワクチン、原爆 化学反応が文明を発展させた
先史時代の幕開けは140万年前、加熱調理の開始から。紀元前4000年には金・銅製品や、パン・ビールが誕生。13世紀には火薬が世界に広がり、17世紀には石炭が世界の動力になった。「物質」の視点から見ると、世界史の奥の因果関係が見えてくる。人類を進化させた「化学反応」に目を見張る。
2022

『まんが 医学の歴史』
- 茨木 保(著)
- 医学書院 2008年
「人生は短く術の道は長い」病気と人間の闘いのドラマ
紀元前に医療倫理を説いたヒポクラテス、母と妻を実験台に全身麻酔を行った華岡 青洲、細菌とワクチンをめぐって競ったパスツールとコッホ、X線を発見しながら無一文だったレントゲン…。『Dr.コトー診療所』の監修も務めた著者が、医学の発展に貢献した人々のドラマを漫画で分かりやすく紹介する。
2022

『ビジュアル 数学全史─人類誕生前から多次元宇宙まで』
- クリフォード・ピックオーバー(著)根上 生也、水原 文(訳)
- 岩波書店 2017年
250のトピックがまる分かり世界は数学でできている
紀元前に公式化されたピタゴラスの定理、650年ごろのゼロの発見、1611年のケプラー予想、1852年の四色定理、1936年のチューリングマシン、そして2007年の数学的宇宙仮説まで。あらゆる数学の発見を年代順に紹介する。オールカラーの写真付きで、数式ギライも読み物として楽しめる1冊。
2022

『日本近代科学史』
- 村上 陽一郎(著)
- 講談社 2018年
近代科学は西欧生まれ。日本人はどのように受け入れた?
私たちが信頼しきっている「科学」。しかし150年ほど前まで日本に今のような科学はなかった。すっかりユニバーサルになった西欧科学を通して、日本文化を考察する野心的な書。伊野尾 忠敬、杉田 玄白、北里 柴三郎、長岡 半太郎。江戸から明治、昭和にかけて、日本の西欧科学との関わりの歴史をたどる。

推薦コメント
村上 陽一郎 先生の科学の捉え方は、とても信頼がおけます。この本では、西欧と比べて相対的に日本を見ていて、おすすめです。「和魂洋才」という言葉がありますが、私たちには私たちなりに西欧とは異なる文化や「和才」があります。
櫻井 博儀(仁科加速器科学研究センター センター長)
2022

『食の歴史』
- ジャック・アタリ(著)林 昌宏(訳)
- プレジデント社 2020年
2050年の主食は昆虫になる?人類と食の過去と未来
食べ物を求めて移動していた猿人時代から、食料を確保するための農耕の普及、人口爆発によって起きた飢餓、食料不足を解消するための昆虫食まで。フランスの思想家ジャック・アタリが古今東西の数百万年に及ぶ食の歴史を辿りつつ、食がもたらす喜びが失われつつある現状に警鐘を鳴らす。
2022
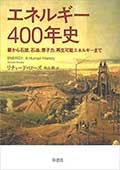
『エネルギー400年史─薪から石炭、石油、原子力、再生可能エネルギーまで』
- リチャード・ローズ(著)秋山 勝(訳)
- 草思社 2019年
エネルギーはどこから来たの?400年に及ぶ開発の歴史
私たちの生活になくてはならないエネルギーは、どのようにしてここまで発展してきたのか?薪から石炭、石油、原子力、そして再生可能エネルギーへ。蒸気機関から内燃機関、発電機へ。400年の試行錯誤の歴史をたどりつつ、エネルギー発展の副産物である環境問題にも目を向ける。
