情報の世紀
すべてがデータで処理される時代。情報の見方を新たにする16冊。
2022
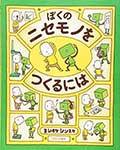
『ぼくのニセモノをつくるには』
- ヨシタケ シンスケ(著)
- ブロンズ新社 2014年
「ぼくのすべて」を伝えるにはどう説明したらいい?
「ロボットにぼくのニセモノとして、宿題やお手伝いをやってもらおう!」。ロボットに自分のことを教え始めるけんた君。でもいくら説明してもしきれない。学校や家での役目は違うし、日によっても気分が変わる。「情報としての自分」の複雑さに気付く発想絵本。

推薦コメント
自分が好きなこと、得意なこと、苦手なこと……。大人になっても繰り返し自問自答します。人生は選択の連続と言いますが、その都度、自分に何ができるか、何がしたいかを決定し、人生を歩んでいきます。選択しなかった方に後悔が残らないよう、そして選択した方に自信を持って進んでいけるように、この本のけんたくんをお手本にして自分をとことん見つめてみよう。
長壁 早弥子(革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 遺伝統計学チーム テクニカルスタッフⅡ)
2022
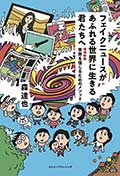
『フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ─増補新版 世界を信じるためのメソッド』
- 森 達也(著)
- ミツイパブリッシング 2019年
そのニュース、信じていい?情報に振り回されないために。
テレビやインターネットで触れるニュースは、全て編集されている。フェイクニュースの時代、受け取り手にも注意深く背景まで想像するリテラシーが必要だ。ニュース現場で働きながら、メディアの在り方に疑問を持った著者が描く「正しい情報の選び方」。
2022

『情報と秩序─原子から経済までを動かす根本原理を求めて』
- セザー・ヒダルゴ(著)千葉 敏生(訳)
- 早川書房 2017年
経済成長は、情報成長の表われにほかならない
情報とは何か?情報はどこからやってくるのか?情報の視点で世の中を見ると?米国のMITメディアラボで先端科学に従事する著者が、「情報」で社会や経済を読み解いた。経済成長とは情報成長である、と言いきる、話題の1冊。
2022

『大図鑑 コードの秘密─世界に隠されたメッセージを読み解く』
- ポール・ルンダ(編著)浜口 稔(訳)
- 明石書店 2021年
私たちは完全にコード化された世界に暮らしている
コード=暗号だけではない。文字、紋章、楽譜、ファッション、身振り、DNAまで、情報を運ぶさまざまなコードがある。インターネットの台頭とともにますます重要性が増すコード。130種類を網羅したビジュアル図鑑から、人類の情報史が見えてくる。
2022

『コード・ガールズ─日独の暗号を解き明かした女性たち』
- ライザ・マンディ(著)小野木 明恵(訳)小谷 賢(解説)
- みすず書房 2021年
第二次世界大戦中、暗号解読を担った女性たちがいた
情報技術を発展させてきたのは戦争だ。第二次世界大戦中、日独の暗号解読に従事した1万人以上の米国女性たちがいた。これまで口を閉ざしてきた当事者らへのインタビューや手紙を元に、彼女たちの日々を鮮明に描き出すノンフィクション。

推薦コメント
暗号解読という場に限定されてはいますが、アメリカ版の『戦争は女の顔をしていない』とも言える1冊。従来知られていなかったアメリカの女性暗号解読者たちの貢献をオーラルヒストリーとして掘り起こし、個々人が語るエピソードの集合体として第二次世界大戦の暗号解読の裏側を描き出しています。
柚木 克之(生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー)
2022

『生物の中の悪魔─「情報」で生命の謎を解く』
- ポール・デイヴィス(著)水谷 淳(訳)
- SBクリエイティブ 2019年
「情報」のレンズで見えてきた新たな生命の姿とは?
生命の誕生や進化、意識の発生などの謎を、「情報」という視点から読みとくスリリングな1冊。非生命である分子が、いかにして秩序だった生命になりえたのか?著名な米国の物理学者である著者が、量子生物学の最先端分野で解明されつつある生命の仕組みを紹介する。

推薦コメント
生命科学では生物のハードウェアを「化学」の言葉で明らかにする研究が盛んに行われています。これに対して本書ではさまざまな生命現象を一貫して「情報」のメガネで見直します。その結果見えてきたのは、流れ込んでくるビットを計算処理する、ソフトウェアとしての生命像でした。情報熱力学やシステム生物学など、複数分野の交点で芽生える新たな生命像を伝える1冊です。
柚木 克之(生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー)
2022

『遺伝子図鑑』
- 国立遺伝学研究所「遺伝子図鑑」編集委員会(編)
- 悠書館 2013年
生物が多様なのは遺伝子が多様であるからだ
地球上のあらゆる生物がもつ「遺伝情報」。遺伝子はどのように世代を超えて性質を伝え、どのように生命の働きをつかさどっているのか?生物多様性の謎から、分子レベルでの進化のメカニズム、品種改良や犯罪捜査の実用現場まで。目には見えない遺伝子の世界を描いた、貴重なビジュアル図鑑。
2022

『世界を一枚の紙の上に─歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生』
- 大田 暁雄(著)
- オーム社 2021年
全ては一枚の紙に表されている世界を視覚化したダイアグラム
19世紀初頭の西欧。市民社会拡大の中で、人々は「世界の可視化」を必要とした。生態系をダイアグラム(図表)に表現したドイツの科学者フンボルト。以降150年間に描かれた、人口や貿易収支などの統計図表、世界地図や地球儀、統計に絵文字を用いたアイソタイプまで、科学のグラフィズムの歴史を解説する。
2022
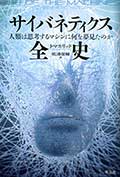
『サイバネティクス全史─人類は思考するマシンに何を夢見たのか』
- トマス・リッド(著)松浦 俊輔(訳)
- 作品社 2017年
世界を制覇したサイバー。その思想や文化の系譜を辿る
サイバー空間、サイバー戦争、サイボーグ。これらの元になった「サイバネティクス」という言葉は、第二次世界大戦中に、天才米国人数学者ノーバート・ウィーナーがつくった造語だ。コンピュータが生み出すユートピアの希望とディストピアの不安。最新資料やインタビューで、サイバネティクスの歴史を浮き彫りにする。
2022
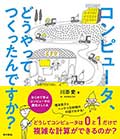
『コンピュータ、どうやってつくったんですか?─はじめて学ぶ、コンピュータの歴史としくみ』
- 川添 愛(著)
- 東京書籍 2018年
毎日使うコンピュータ。でも中身は、まるで知らない。
コンピュータは、なぜ0と1だけで、複雑な計算ができるのだろう。理系男子とヘンテコな妖精が、問答形式で紐解く入門書。そもそも数字って?電気で計算するってどういうこと?プログラミングの考え方とは?コンピュータを生み出した過去を振り返り、未来を考える。

推薦コメント
数や位取りの概念から始まり、論理回路やリレー、半導体を経て、最後にプログラム内蔵型コンピュータのしくみを解き明かします。登場人物である理系男子と、コンピュータの作り方を学びに来たヘンな妖精との対話がポイントを突いていて、技術が発展する歴史にも触れられています。基本原理の本質を外すことなく平易な説明に成功している入門書として貴重です。
柚木 克之(生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー)
2022

『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか─脳AI融合の最前線』
- 紺野 大地、池谷 裕二(著)
- 講談社 2021年
現実はすでに想像を超えている人工知能と脳研究の最前線
「目を介さずに世界を見る」「他人が見ている夢を読み取る」「うつ病患者を治療する」…人工知能の研究は、すでにわたしたちが想像する以上のことを実現しつつある。脳とAIを融合させることによって、脳の潜在能力をアップデートする驚異のプロジェクトを、気鋭の脳研究者が自ら紹介する。
2022

『ニューロマンサー』
- ウィリアム・ギブスン(著)黒丸 尚(訳)
- 早川書房 1986年
電脳世界はここから始まった!現代を先取りした古典SF
かつて電脳空間でカウボーイと呼ばれるハッカーだったケイスは、今はその能力を奪われ、千葉シティでくすぶっていた。そこへアーミテジと名乗る男から仕事の依頼が舞い込み、電脳空間で“冬寂”と呼ばれるAIと対峙することになる。映画「マトリックス」の原点となったサイバーパンクの傑作SF。

推薦コメント
昔のスパコンが手のひらに乗るスマホになり、「人工知能」が実現しつつある現在。科学技術イノベーションは、人間の想像を超えるものです。次の時代はメタバース?脳・コンピュータインタフェース?本書は、それらが本当に実現して社会や人々の生活を変えていく未来を、リアルに体験させてくれることでしょう。
佐野 健太郎(計算科学研究センター プロセッサ研究チーム チームリーダー)
2022
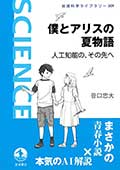
『僕とアリスの夏物語─人工知能の、その先へ』
- 谷口 忠大(著)
- 岩波書店 2022年
人工知能の知能って何だ?アリスと学ぶAIのすべて
不登校の悠翔のもとにやってきた、話すことも歩くこともできない少女アリス。赤ちゃん人工知能のアリスは周りの人から言葉や動作を学び、ついには自分の意思で行動できるようになるが…。青春小説仕立てのストーリーと丁寧なAI解説で、人工知能の仕組みと課題を明らかにする。
2022

『FACTFULNESS─10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』
- ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド(著)上杉 周作、関 美和(訳)
- 日経BP社 2019年
世界はどんどん悪くなっている?それも思い込みの一つ。
低所得国の女子は初等教育を終えられない?世界中の1才児で予防接種を受けているのは何%?大学教授も政治家もジャーナリストも間違える。私たちは「世界の今」を理解しているつもりで、思い込みに囚われているのだ。データに基づいて世界を正しく認識するための方法を教える話題の書。

推薦コメント
「人間には10種類の認知の偏り(バイアス)が備わっており、それによって世界が歪んで見えている」と書いてあります。試しに、この本の最初に載っている現代の世界に関する13問の3択クイズをやってみてください。多くの人は3分の1以下しか正解できないという触れ込みで、私も実際そうでした。単に知識が無いだけなら、3択クイズなので3分の1は正解できるはずです。にもかかわらずそれ以下の結果になるのは、現代の世界についての知識が無いからではなく、バイアスがあるため間違えていることを意味します。バイアスがどのようなものかを知り、事実やデータに即して世界を見る目を養うのに最適な本です。一過性のベストセラーではなく、未来の古典になりうる1冊です。
柚木 克之(生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー)
2022

『統計学が見つけた野球の真理─最先端のセイバーメトリクスが明らかにしたもの』
- 鳥越 規央(著)
- 講談社 2022年
野球の勝敗を握るのはビッグデータの解析だった
野球を統計学の観点から分析する「セイバーメトリクス」。失点を抑える能力から、チームへの貢献度を測る投手の指標、得点創出能力を表す打撃の指標、大谷 翔平がMVPを獲得した数字の裏付けまで。野球のあらゆる側面をセイバーメトリクスで解析し、これまでの野球の定説を覆す。
2022

『QRコードの奇跡─モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ』
- 小川 進(著)
- 東洋経済新報社 2020年
トヨタの工場から始まった世界標準のQRコード誕生秘話
ウェブサイトのアクセスや空港のチェックインなど、日常のあらゆる場面で使われているQRコード。実はその始まりは、日本にあった。トヨタ自動車の工場での源流から、二次元コードと読み取り機の開発、世界に向けた標準化まで、現場の開発者たちが重ねた地道な努力から、ものづくりの本質を学ぶ。

推薦コメント
QRコードが日本の発明ということは、あまり知られていません。現在では搭乗券の読み取りから電子決済まで、至るところに使われている、日本発の稀有なイノベーションの好例です。50年前に開発が始められ、様々な困難や現場の反発を交えながらも、国際標準に至った経緯を知ることができる良書です。
佐野 健太郎(計算科学研究センター プロセッサ研究チーム チームリーダー)
