選書アドバイザー 南後 恵理子

南後 恵理子
放射光科学研究センター 利用技術開拓研究部門 SACLA利用技術開拓グループ 分子動画研究チーム チームリーダー
研究テーマは、X線自由電子レーザーを用いたタンパク質分子動画解析。1999年東京工業大学理学部化学科卒業。2004年同大学理工学研究科化学専攻単位取得満期退学。2004年同大学助手(2007年より助教)。2007年博士号取得(理学博士)。2010年理化学研究所に入所。2019年京都大学医学研究科助教、その後に特定准教授。2020年東北大学多元物質科学研究所計測研究部門教授。2021年より理化学研究所にて現職。
10代の若者へのメッセージ
若いときに先達の知恵や知識にたくさん触れて、自分の頭で考える経験を積むことは、長い人生の基礎となり、必ずやいつか助けてくれるものになるでしょう。科学の扉を開くきっかけに、まずは本を手に取ってみませんか。
科学と読書
- Q. 一番古い本の記憶は?
- A. 幼稚園生の頃、知り合いのお宅で見た「植物図鑑」。色鮮やかで見たことのない植物の写真が印象に残っています。その後両親が買ってくれた教科事典も大好きでした。
- Q. 小学生時代の読書歴は?
- A. 小学校低学年の時に読んでいたのは、学研まんがひみつシリーズ。「地球のひみつ」「宇宙のひみつ」「海のひみつ」など。科学を学ぶ楽しさを教えてくれた本です。その後は、ミヒャエル・エンデの『はてしない物語』『モモ』、日本の児童文学では『霧のむこうの不思議なまち』など、ファンタジーの名作に夢中になりました。
- Q. 中高生時代の読書歴は?
- A. 江戸川 乱歩、アーサー・コナン・ドイルなどのミステリーや宮部 みゆきの小説など。大人になってからも読み返している本は、星 新一のショートショート。いつ読んでも色あせない近未来の話に心躍ります。
担当テーマ
科学道100冊 2022 光を追いかけて
推薦本
2022
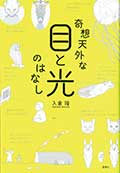
『奇想天外な目と光のはなし』
- 入倉 隆(著)安賀 裕子(画)
- 雷鳥社 2022年
生物の種類によって見える世界はこんなにも違う
視覚心理学の研究者による、目と光の話。白目が見えるようになっているのはヒトの生存戦略、シャコは人間の4倍の色覚を持つ、トンボの目は約2万個あるなど、思わず人に言いたくなるネタが盛りだくさん。生物進化論、視覚心理学、光学をまたいだユニークな1冊。
推薦コメント
人にとって一番身近な光センサーは目。どうして光を捉えると「明るい』と感じるのか、改めて考えるとそれって不思議なことです。この本は、さまざまな生物種の視覚についてイラストつきで解説していて、とてもわかりやすい。私も夢中になって読んでしまいました。
2022

『ふしぎ!光る生きもの大図鑑』
- 近江谷 克裕、小江 克典(著)
- 国土社 2021年
なぜ光る?どうやって光る?暗闇の中の宝石たち
海をプラネタリウムのように照らし出すウミホタル、点滅するサーチライトの使い手ヒカリキンメダイ、日本人にはなじみの深いゲンジボタル、世界で唯一川の中で光る巻貝カサガイ…。威嚇したり、目くらましにしたり、求愛したり。さまざまな目的とメカニズムで光るふしぎな生き物たちの秘密にせまる。
推薦コメント
光る生物ってこんなにたくさんあったのかと、新しい発見があります。写真の美しさに加えて、説明もわかりやすく、小学生でも多くの学びが得られる本です。最後に実験コーナーがあるのも良いところ。イカに付着した微生物を使った発光実験は、私もやってみたいです。
2022

『光と物質のふしぎな理論─私の量子電磁力学』
- R.P.ファインマン(著)釜江 常好、大貫 昌子(訳)
- 岩波書店 2007年
ファインマンさんが挑戦!量子電磁力学を平易に語る
「あなたは何を研究しているの?」。聞かれて説明に困ったノーベル賞物理学者ファインマンが、自身の研究内容である量子電磁力学について分かりやすく伝えることに本気でチャレンジした。光と電子の相互作用についてユーモアを交えて語った、連続講義の書籍化。
推薦コメント
笑いながら読める物理の本は、ファインマンさんが書いたもの以外はないんじゃないでしょうか。私も授業で量子科学を教えているので、数式を使わず一般向けにこの分野の話をすることがどれほど難しいか、身に染みてわかります。物理学への敷居を下げてくれる本当に楽しい本です。
2022

『カメラとレンズのしくみがわかる光学入門』
- 安藤 幸司(著)
- インプレス 2019年
「光」が分からなければカメラは使いこなせません
デジタルカメラのボタンを押すと写真が撮れる。当たり前のことだけど、これってどうやっていう仕組みなの?映像計測技術のエンジニアが、光学の基礎やレンズの歴史とともに、カメラのメカニズムを詳しく説明。レーザー光での光記録、デジタル画像処理の話まで。
推薦コメント
私たちにとって身近なスマートフォンのカメラ、これも「光学」です。この本では、光の話を中心に、カメラの仕組みを解説しています。波動性・粒子性といった光の性質から、カメラの歴史、光学ガラス、画像処理まで。専門的ですが、理解しやすいようにイラスト付きで丁寧に書かれているところがとても良いです。
