選書アドバイザー 長壁 早弥子

長壁 早弥子
革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 遺伝統計学チーム テクニカルスタッフⅡ
オントロジーや医学文献データベースから構築した、疾患類似度ネットワークの研究をしている。理研に入所する前は司書として図書館に勤務。本や文献データを扱いながらプログラミングを学んだ。学生時代得意だった科目は古典。
10代の若者へのメッセージ
笑顔でいよう。
科学と読書
- Q.あなたにとっての「科学道の本」は?
- A. 『方法序説』(デカルト)小さい頃からずっとやってみたかったプログラミング。学ぶチャンスがないまま大人になり、いまさらながらの挑戦を迷っていた時に手に取った本が『方法序説』です。デカルトが自身の今後の生き方について述べ、最後に決意表明するのですが、自分と重なり、背中をそっと押してくれました。
- Q. 無人島に1冊持っていくなら?
- A.『ムーミンパパ海へいく』(トーベ・ヤンソン)ムーミン一家が孤島でそれぞれの生き方を模索するものがたり。その苦悩する姿はまるで人間のようで、不気味なくらいリアル。この本があれば心強い。
担当テーマ
科学道100冊 2022 情報の世紀
推薦本
2022
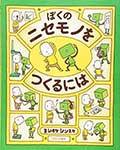
『ぼくのニセモノをつくるには』
- ヨシタケ シンスケ(著)
- ブロンズ新社 2014年
「ぼくのすべて」を伝えるにはどう説明したらいい?
「ロボットにぼくのニセモノとして、宿題やお手伝いをやってもらおう!」。ロボットに自分のことを教え始めるけんた君。でもいくら説明してもしきれない。学校や家での役目は違うし、日によっても気分が変わる。「情報としての自分」の複雑さに気付く発想絵本。
推薦コメント
自分が好きなこと、得意なこと、苦手なこと……。大人になっても繰り返し自問自答します。人生は選択の連続と言いますが、その都度、自分に何ができるか、何がしたいかを決定し、人生を歩んでいきます。選択しなかった方に後悔が残らないよう、そして選択した方に自信を持って進んでいけるように、この本のけんたくんをお手本にして自分をとことん見つめてみよう。
