選書アドバイザー 柚木 克之

柚木 克之
生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー
慶應義塾大学環境情報学部で、細胞内の生化学反応をコンピューター上でシミュレーションする、多分野が融合する生命科学と出会う。2005年博士(学術)取得。2013年東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻助教。2017年理研に入所し、2020年より現職。細胞内の代謝と制御機構をシステムとして明らかにすることを目指している。哲学、歴史ものから小説、ビジネス書、マンガも読む、大の読書家。
10代の若者へのメッセージ
本をきっかけにして自分の中で“何かに夢中になるスイッチ”がONになることが大事ではないでしょうか。好奇心を太らせるため、いつもと違うジャンルに触れるのも一つの方法だと思います。
科学と読書
- Q. 幼少期の印象深い読書は?
- A. ディック・ブルーナの「子どもがはじめてであう絵本」などの絵本が今でも印象に残っています。小学生の頃はナポレオン、徳川 家康、ベーブ・ルースといった偉人伝や「学習まんが 日本の歴史」など、家や学校に置いてあった本でビビッと来たものは手当たり次第に読んできました。
- Q. 学生時代の読書遍歴は?
- A. 電車通学の合間に読んだ遠藤 周作『沈黙』、塩野 七生『ローマ人の物語IIハンニバル戦記』、ドストエフスキー『罪と罰』、ゲーテ『ファウスト』といったあたりが印象に残っています。科学の本は、矢野 健太郎『すばらしい数学者たち』、藤原 正彦『天才の栄光と挫折』、サイモン・シン『フェルマーの最終定理』など、数学者たちの人間像を描いたものから入りました。
- Q. 科学以外で推薦したい本は?
- A. ショーペンハウアー『読書について』。「読書とは、他人にものを考えてもらうことだ」と作者は書いています。知識を得る喜びにおぼれて、本から教わったことをそのまま鵜呑みにしていると、自分で考える力を失ってしまう危険があります。春先になると、「大学生に薦める100冊」のようなブックリストの企画を目にしますが、こういったブックリストの最初か最後にはこの本を置くべきだと常々考えています。
担当テーマ
科学道100冊 2022 情報の世紀
推薦本
2022

『生物の中の悪魔─「情報」で生命の謎を解く』
- ポール・デイヴィス(著)水谷 淳(訳)
- SBクリエイティブ 2019年
「情報」のレンズで見えてきた 新たな生命の姿とは?
生命の誕生や進化、意識の発生などの謎を、「情報」という視点から読みとくスリリングな1冊。非生命である分子が、いかにして秩序だった生命になりえたのか?著名な米国の物理学者である著者が、量子生物学の最先端分野で解明されつつある生命の仕組みを紹介する。
推薦コメント
生命科学では生物のハードウェアを「化学」の言葉で明らかにする研究が盛んに行われています。これに対して本書ではさまざまな生命現象を一貫して「情報」のメガネで見直します。その結果見えてきたのは、流れ込んでくるビットを計算処理する、ソフトウェアとしての生命像でした。情報熱力学やシステム生物学など、複数分野の交点で芽生える新たな生命像を伝える1冊です。
2022

『コード・ガールズ─日独の暗号を解き明かした女性たち』
- ライザ・マンディ(著)小野木 明恵(訳)小谷 賢(解説)
- みすず書房 2021年
第二次世界大戦中、暗号解読を担った女性たちがいた
情報技術を発展させてきたのは戦争だ。第二次世界大戦中、日独の暗号解読に従事した1万人以上の米国女性たちがいた。これまで口を閉ざしてきた当事者らへのインタビューや手紙を元に、彼女たちの日々を鮮明に描き出すノンフィクション。
推薦コメント
暗号解読という場に限定されてはいますが、アメリカ版の『戦争は女の顔をしていない』とも言える1冊。従来知られていなかったアメリカの女性暗号解読者たちの貢献をオーラルヒストリーとして掘り起こし、個々人が語るエピソードの集合体として第二次世界大戦の暗号解読の裏側を描き出しています。
2022

『FACTFULNESS─10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』
- ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド(著)上杉 周作、関 美和(訳)
- 日経BP社 2019年
世界はどんどん悪くなっている?それも思い込みの一つ。
低所得国の女子は初等教育を終えられない?世界中の1才児で予防接種を受けているのは何%?大学教授も政治家もジャーナリストも間違える。私たちは「世界の今」を理解しているつもりで、思い込みに囚われているのだ。データに基づいて世界を正しく認識するための方法を教える話題の書。
推薦コメント
「人間には10種類の認知の偏り(バイアス)が備わっており、それによって世界が歪んで見えている」と書いてあります。試しに、この本の最初に載っている現代の世界に関する13問の3択クイズをやってみてください。多くの人は3分の1以下しか正解できないという触れ込みで、私も実際そうでした。単に知識が無いだけなら、3択クイズなので3分の1は正解できるはずです。にもかかわらずそれ以下の結果になるのは、現代の世界についての知識が無いからではなく、バイアスがあるため間違えていることを意味します。バイアスがどのようなものかを知り、事実やデータに即して世界を見る目を養うのに最適な本です。一過性のベストセラーではなく、未来の古典になりうる1冊です。
2022
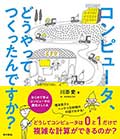
『コンピュータ、どうやってつくったんですか?─はじめて学ぶ、コンピュータの歴史としくみ』
- 川添 愛(著)
- 東京書籍 2018年
毎日使うコンピュータ。でも中身は、まるで知らない。
コンピュータは、なぜ0と1だけで、複雑な計算ができるのだろう。理系男子とヘンテコな妖精が、問答形式で紐解く入門書。そもそも数字って?電気で計算するってどういうこと?プログラミングの考え方とは?コンピュータを生み出した過去を振り返り、未来を考える。
推薦コメント
数や位取りの概念から始まり、論理回路やリレー、半導体を経て、最後にプログラム内蔵型コンピュータのしくみを解き明かします。登場人物である理系男子と、コンピュータの作り方を学びに来たヘンな妖精との対話がポイントを突いていて、技術が発展する歴史にも触れられています。基本原理の本質を外すことなく平易な説明に成功している入門書として貴重です。
