選書アドバイザー 赤石 れい

赤石 れい
脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー
脳の意思決定の研究から、社会における人間のウェルビーイング促進を目指す。学生時代は図書館でひと棚まるごと読みあさっていたというツワモノ。本を通して宇宙や生きものの不思議と出会い、一方でシャーロック・ホームズや江戸川 乱歩に親しんだ。読書は今も生活の一部。
コメント
身近な問題についても大きな社会問題に関しても、これからは多様な分野の視点を持つことが力になります。読書も幅広いジャンルに触れてみてください。
担当テーマ
科学道100冊 2021 脳とココロ
推薦本
2021

『意識はいつ生まれるのか─脳の謎に挑む統合情報理論』
- マルチェッロ・マッスィミーニ、ジュリオ・トノーニ(著)花本 知子(訳)
- 亜紀書房 2015年
脳の最大の謎「意識」はどのように生まれるのか?
解剖実験中、手のひらに脳を載せ、数時間前までその中に、知識、記憶、夢など全てが宿っていたことに愕然とした。著者・精神科医トノーニの学生時代の思い出から本書は始まる。ただの物質である脳に、どうして意識が宿るのか?革新的な統合情報理論「Φ理論」によってその正体に迫っていく。
推薦コメント
この本がすごいのは、「人間の意識という捉えどころのないものを、科学がどう扱うのか?」という枠組みを最初に提唱したところです。意識の解明という難題に著者、ジュリオ・トノーニがどうアプローチしたのか、発想の仕方や試行錯誤のプロセスに注目して楽しんでもらいたいです。
2021

『孤独の科学─人はなぜ寂しくなるのか』
- ジョン・T・カシオポ、ウィリアム・パトリック(著)柴田 祐之(訳)
- 河出書房新社 2018年
なぜ人はつながりたいのか 孤独とは何なのか
孤独の辛さはどこからくるのか?物理的に独りでいることよりも、社会と断絶していると感じることにその原因がある。孤独と健康の因果関係、人間にとっての孤独の意味、社会的つながりの中でよく生きる方法を探求する1冊。心理学、生理学から経済学まで、多領域の見方を重ねて「孤独感」の理由をさぐる。
推薦コメント
コロナ禍の今、「孤独」は最も注目の集まるテーマです。著者は心理学と脳科学の研究者。心理学と脳科学は基本的に個人個人の内面を扱う学問ですが、この本でカシオポは長年にわたる研究経験から「社会的つながりの重要性」を指摘していました。学問分野の枠組みにとらわれない提言に感銘を受けました。
2021
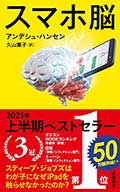
『スマホ脳』
- アンデシュ・ハンセン(著)久山 葉子(訳)
- 新潮社 2020年
睡眠障害、うつ、学力低下…スマホは最強ドラッグ!?
手放せないスマホ、チェックしないではいられないSNS。それもそのはず、これらは人間の脳をハッキングするように巧妙に設計されているのだ。集中力を奪い尽くされないように、相手の手の内を知り、スマホに支配されない自分でいよう。スウェーデンの精神科医による提言は、世界的なベストセラーになった。
推薦コメント
スマホやデジタル技術が脳に与える影響は社会的に非常に関心の高いテーマですが、その影響がポジティブかネガティブかは科学的に決着がついていません。実は読書もかつては「危険な行為」と恐れられていた時代がありました。この本ではスマホのネガディブな部分を取り上げていますが、今の子どもたちにとってすでに環境の一部。現時点での評価を絶対とせず、広い視野を持ちながらひとつの視点として読むといいと思います。
2021

『行動経済学まんが ヘンテコノミクス』
- 佐藤 雅彦、菅 俊一(作)高橋 秀明(画)
- マガジンハウス 2017年
人間は合理的じゃない!?皆やっちゃうヘンテコな行動
人間は合理的に行動している?いや、そうでもない。仲間の判断があきらかに間違っていても、つい同調してしまう。安いから、質がいいから、人はそんな真っ当な理由だけで買い物をしていない。みんなが身に覚えのあるヘンテコな行動を23のエピソードで紹介。漫画で楽しく学べる行動経済学の入門書。
推薦コメント
人間がついしてしまう非合理な行動を研究してきた行動経済学。この漫画は、そんな「矛盾」や「非合理」がなぜ起きるのか?を正確に、かつ身近なエピソードで描いています。『実践 行動経済学─健康、富、幸福への聡明な選択』と合わせて読むと理解が深まります。
2021

『実践行動経済学─健康、富、幸福への聡明な選択』
- リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン(著)遠藤 真美(訳)
- 日経BP 2009年
ナッジとは、人々を賢い選択に導く小さな工夫
カフェテリアで目立つ所に野菜を置くか、フライドポテトを置くかで、消費は劇的に変わる。店員は小さな工夫で私たちの健康をサポートできるのだ。著者はこのように人々を賢い選択に導く工夫を「Nudge (ナッジ) 」と名づけ、生活や社会制度への応用アイデアを挙げる。ノーベル経済学者による、使える経済学。
推薦コメント
人間がついしてしまう非合理な行動を研究してきた行動経済学。欧米では近年、政策決定にも取り入れられています。この本でリチャード・セイラーは「Nudge」(ナッジ:強制や報酬に頼らず、人を賢い選択へ導くちょっとした工夫)という言葉を世に送り出し、のちにノーベル経済学賞を受賞しました。私が研究している意思決定の脳科学にも関連する、興味深い分野です。
