科学道クラシックス 1から25
時代を経ても古びない良書として選んだ「オールタイム・ベスト50」。2019年に選出し、2022年まで引き続き、同じ本をお薦めしました。
クラシックス

『科学と科学者のはなし─寺田 寅彦エッセイ集』
- 池内 了(編)
- 岩波書店 2000年
花鳥風月の中にも科学の原理、法則がある
茶碗の湯、電車の混雑、宙に舞う埃、線香花火に金平糖……。ごく身近なありふれた物の中には、さまざまな科学の原理や法則が潜んでいる。夏目 漱石の弟子であり『吾輩は猫である』にも登場した寺田 寅彦による科学エッセイ。「津浪と日本人」という一編では、繰り返される三陸沿岸の被災を描いている。
クラシックス
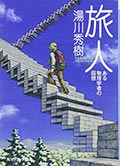
『旅人─ある物理学者の回想』
- 湯川 秀樹(著)
- KADOKAWA 2011年
原子物理学を開拓した科学者・湯川 秀樹の道程
「中間子の着想を得たときに思い出したのは、少年時代に見た真昼の星のような木漏れ日だった―」。はにかみ屋だった幼少期から、数学に夢中になった少年時代、理論物理学と出会った大学時代、そして中間子という新理論を得るまで。日本人初のノーベル賞受賞者・湯川 秀樹が、自らの半生を振り返る。

推薦コメント
日本人初のノーベル賞受賞者、湯川 秀樹が自身の半生を綴った本です。小学校高学年の時に読み、一つのことを突き詰める姿勢に感銘を受けました。「科学者になりたい」と思ったきっかけであり、僕の最初のヒーローです。湯川さんが提唱した原子核の「核力」の謎に没頭し、今もその解明に取り組んでいます。
初田 哲男(数理創造プログラム プログラムディレクター)
クラシックス

『ご冗談でしょう、ファインマンさん(上)(下)』
- R.P.ファインマン(著)大貫 昌子(訳)
- 岩波書店 2000年
ファインマンさんは冗談抜きで好奇心のかたまりです
アメリカの物理学者、リチャード・P・ファインマンの回想記。小さな頃からラジオが大好きな知りたがりで、12歳の頃には実験室を持っていた。真っ正直で、つい遊び心を発揮してしまうから事件が起こる。ノーベル賞を取っても変わらない。原爆開発のマンハッタン計画を内側から見た章は、科学秘史としても貴重だ。

推薦コメント
ファインマンさんの人柄と研究愛を感じる自伝です。彼は学者でも特別おもしろい人だと思います。
豊泉 太郎(脳神経科学研究センター 数理脳科学研究チーム チームリーダー)

推薦コメント
いたずら好きで好奇心のままに突進するファインマンの姿は人間味に溢れていて、「ノーベル賞受賞者はどこか遠い存在のすごい人」というイメージが崩れます(笑)。「そう構えずに研究者になってもいいんだ」と勇気をくれるので、若い人にぜひ読んでほしいです。
原山 優子(理化学研究所 理事)
クラシックス

『「科学者の楽園」をつくった男─大河内 正敏と理化学研究所』
- 宮田 親平(著)
- 河出書房新社 2014年
日本の科学はここから始まった!傑物が集った理化学研究所
日本を科学立国にすべく、大正期に設立された理化学研究所。科学者たちに自由を与えた大河内 正敏 所長のもと、鈴木 梅太郎、湯川 秀樹、朝永 振一郎ら、傑出した才能が集った。この「科学者たちの楽園」にもやがて戦争が影を落とす―。日本の科学史に多くの功績を残した理研の栄光と苦難の歴史を生き生きと描く。

推薦コメント
「社会の課題解決のために、徹底的に基礎研究を行う」という“理研精神”が溢れた本。理化学研究所の研究員だった私の祖父、桜田 一郎も登場します。
桜田 一洋(医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクター)

推薦コメント
戦前戦中の理研を支えた大河内 正敏さんに興味があります。彼は科学者の可能性を信じた人だったと思います。
長瀧 重博(開拓研究本部 長瀧天体ビッグバン研究室 主任研究員)
クラシックス

『学問の発見─数学者が語る「考えること・学ぶこと」』
- 広中 平祐(著)
- 講談社 2018年
生きるということはたえず何かを学ぶこと
生きていくことは、何かを創造すること。創造するためには、まず学ばなければならない。では学ぶとはどういうことなのか?「特異点解消の定理」の発見によって、数学界のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞した数学者・広中 平祐が、自らの半生を振り返りながら、学ぶことの大切さを語る。
クラシックス

『いかにして問題をとくか』
- G.ポリア(著)柿内 賢信(訳)
- 丸善出版 1975年
答えを考える前に問題の解き方を考えよ
スタンフォード大学の数学教授G・ポリアによる「問題解決」のロングセラー。1945年に出版されて以来、広く読み継がれる。「未知のものは何か、与えられているものは何か、条件は何か、という3つの問いから出発する」「問題を解くには決意と情緒が重要」など。数学書だがその方法は普遍的、ビジネスにも効く一冊だ。
クラシックス

『科学と仮説』
- ポアンカレ(著)河野 伊三郎(訳)
- 岩波書店 1938年
真実を探究するためには仮説が重要である
科学はいかにして真理を発見していくのか?近代随一の数学者、物理学者であるポアンカレは、真理探究の方法に着目。幾何学、力学、光学、電気学など、あらゆる科学において仮説がいかに重要な役割を占めるかを解いた。原文の初版が1902年発行、以来読み継がれる科学思想書の古典。
クラシックス
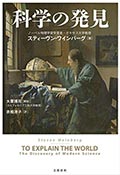
『科学の発見』
- スティーヴン・ワインバーグ(著)赤根 洋子(訳)
- 文藝春秋 2016年
ノーベル賞科学者が斬る 科学の歴史
古代ギリシアの「科学」はポエムだった?プラトン、アリストテレス、ガリレオらが犯したミスは?ノーベル物理学賞受賞のスティーブン・ワインバーグが現代の基準で過去のヒーローたちを裁く。ウィットたっぷりの痛快な科学史。
クラシックス
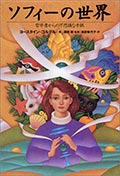
『ソフィーの世界─哲学者からの不思議な手紙』
- ヨースタイン・ゴルデル(著)須田 朗(監修)池田 香代子(訳)
- NHK出版 1995年
あなたはだれ?1通の手紙から始まる哲学の冒険
ある日、14歳のソフィーのもとに届いた手紙。「あなたはだれ?」わたしはソフィー。でもそれってどんな人…?次々と届く不思議な手紙に導かれて、少女は哲学者たちに出会っていく。「ソフィーの世界」がいつしか「あなたの世界」になる、不思議な哲学ファンタジー。
推薦コメント
脳の研究をしている人は哲学から入る人も多い。私も『ソフィーの世界』を読み、世の中はどのようにできているのか、自我とは何か、と考えるきっかけになりました。
田中 和正(脳神経科学研究センター 神経回路・行動生理学研究チーム 訪問研究員)
クラシックス
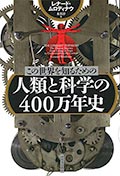
『この世界を知るための人類と科学の400万年史』
- レナード・ムロディナウ(著)水谷 淳(訳)
- 河出書房新社 2016年
人類誕生から量子論まで高速で駆けぬける科学発展史
科学はどのように進歩してきたのか?その歴史を、知識を探求する動物・人類の誕生から、科学革命をへて、見えない量子の世界をも理解するようになった現代まで、3部構成で描く科学発展史。アリストテレス、ニュートン、アインシュタインなどの偉人が当時の時代背景の中で生き生きと描かれている。
クラシックス

『New Scientist 起源図鑑─ビッグバンからへそのゴマまで、ほとんどあらゆることの歴史』
- グレアム・ロートン(著)ジェニファー・ダニエル(絵)佐藤 やえ(訳)
- ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017年
科学で読み解く あらゆるものの始まりの物語
星や銀河は宇宙の「ゆらぎ」から生まれた、お酒の起源は1億3000万年前のある種子植物の登場による、世界初のトイレットペーパー会社は14世紀中国で設立された。思わず人に話したくなる、あらゆるものの「始まりの物語」を集めたビジュアル図鑑。睡眠、所有、友情、性行動、へそのゴマの起源は?
クラシックス
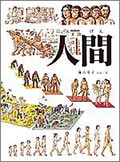
『人間』
- 加古 里子(文・絵)
- 福音館書店 1995年
150億年前の宇宙誕生にはじまる人間の物語
科学絵本の巨匠・加古 里子が17年の構想を経て描いた「人間」とは。人類の誕生をビックバンに始まる流れの中で語り、臓器の仕組みなど人体の不思議を大胆な絵で描き、人間が発明した道具や学問から社会的な動物としての側面をあぶり出す。自分が壮大な物語の一部であることに気付かされる絵本。

推薦コメント
幼い頃から、絵本作家・加古 里子さんの本が大好きでしたが、彼が東京大学出身の工学博士だとは最近まで知りませんでした。科学の基礎知識があった上での精緻かつ親しみやすい絵柄、人体の構造だけでなく人類の歴史まで描いており、専門家が読んでも素晴らしい内容ではないかと思います。
鈴木 千歳(バトンゾーン研究推進プログラム 人工ワクチン研究チーム テクニカルスタッフ)
クラシックス
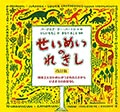
『せいめいのれきし 改訂版』
- バージニア・リー・バートン(文・絵)いしい ももこ(訳)まなべ まこと(監修)
- 岩波書店 2015年
三葉虫や恐竜から人間へ 受け継がれる生命のバトン
物語の幕開けは46億年前、地球誕生のシーンから。三葉虫が大繁殖したカンブリア紀、恐竜が巨大化し鳥類も登場したジュラ紀、地球温暖化で哺乳類が台頭した中新世、そして氷河期を経て、人間の時代へ。35の場面で私たちに流れ込む壮大な命のリレーを描く科学絵本。絵の細部を読み解くのも面白い。

推薦コメント
銀河系の始まりから現在まで、今の歴史を網羅した内容の濃い絵本です。3歳と5歳の子も見入っています。
栗原 恵美子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 研究員)
クラシックス

『完訳 ファーブル昆虫記 第1巻(上)(下)』
- ジャン=アンリ・ファーブル(著)奥本 大三郎(訳)
- 集英社 2005年
ファーブルが30年かけて書いた愛情たっぷりの昆虫観察記
ファーブルが55歳から83歳まで後半生をかけて書いた全10巻の昆虫記。南フランスの美しい景色を背景に、ファーブルの日常も交えながら描かれる仔細な昆虫のドラマは、ヴィクトール・ユゴーに「昆虫のホメーロス」と評された。第1巻はフンコロガシと蜂の物語。ふんだんな挿絵も楽しめる。

推薦コメント
ファーブル昆虫記は、科学精神に満ちています。「標本に突き刺しただけでは虫を知ったとは言えない。生活の仕方や本能を知りたい」というのがファーブルです。非常に成熟した視点ですね。僕としては少し大人になってから寝転がって読むのが最高だと思います。この本は奥本 大三郎さんによる新訳と、ふんだんにちりばめられた挿絵が素晴らしい。この版で初めて読める人は恵まれていますね。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
クラシックス

『シートン動物記 オオカミ王 ロボ』
- アーネスト・T・シートン(文・絵)今泉 吉晴(訳・解説)
- 童心社 2010年
シートン直筆の絵と味わう オオカミ王の愛と死の物語
人間を出し抜いて牧場を襲い、そのあまりの賢さから「ルー・ガルー(オオカミ人間)」と呼ばれたオオカミ王、ロボ。シートンは、その伴侶であるブランカを罠にかけるが。オオカミを賢く愛情深い動物として世に知らしめた名作。画家でもあったシートン直筆の挿画が物語を彩る。

推薦コメント
小学生の頃に『シートン動物記』に出会い、ロボの物語にとても感動しました。その後、シートンは生物学者であり、画家であり、探検家であり、自然保護運動の創始者であり、マルチな才能を持つ人だと知りました。ロボの話はシートンが実際に牧場でオオカミ対策をした時の体験であり、彼はまさに実践知を持つ人なんです。私は現場の知を持つ人に惹かれるので「シートンのように生きたい」と思います。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
クラシックス
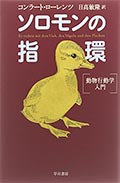
『ソロモンの指環─動物行動学入門』
- コンラート・ローレンツ(著)日高 敏隆(訳)
- 早川書房 1998年
一緒に暮らして書いたノーベル賞学者の生き物観察記
29日間温めてきたガンの卵から、ついにヒナが顔を出した。目と目を合わせ、言葉を交わしたその時から、ヒナは著者ローレンツを母親と認め、離れなくなった。食事の世話に寝かしつけ、川べりへの散歩、忙しくものどかな子育ての日々。ガン語が話せ、カラス語がわかるノーベル賞学者の動物観察記。

推薦コメント
ソロモンの指輪を身につけると動物と話ができる?行動学者であるコンラート・ローレンツが、動物の行動のメカニズムを紐解く。生涯にわたる行動に影響を及ぼす初期学習など、遺伝と環境の問題を考える上でも有用な1冊です。
仲 真紀子(理化学研究所 理事)
クラシックス
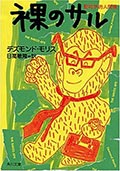
『裸のサル─動物学的人間像』
- デズモンド・モリス(著)日高 敏隆(訳)
- 角川書店 1999年
サルの中で唯一毛がないのは?答えは「人間」です。
性行動のために長期間に渡って求愛する裸のサル。なわばり確保のために闘う裸のサル。多大な労力をかけて子育てをする裸のサル。裸のサル=人間は所詮、1個の動物にすぎない!?他の霊長類の行動を観察・比較しながら、人間がいかに動物的な行動に支配されているのか、大胆に仮説する。

推薦コメント
大学1年の英語教材でした。人類は海辺に住んだから体毛が減ったんじゃないかなど、大胆な仮説が刺激的でした。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
クラシックス

『種の起源(上)(下)』
- ダーウィン(著)渡辺 政隆(訳)
- 光文社 2009年
生物学の根幹をなすダーウィンの進化論
なぜ生物にはこれほど多様な種が存在するのか?生物は神が個別に創造したものだと考えられていた時代に、生物は共通の祖先から進化したと唱えたダーウィン。自然淘汰、生存闘争、突然変異、地理的分布など、様々な疑問点を進化論で説明し、世界の価値観を一変させた驚異の書。1859年初版。

推薦コメント
ダーウィンの進化論は機械的な因果律によって生命現象を説明する端緒を開きました。その意味を本書から読み解いてみてください。
桜田 一洋(医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクター)

推薦コメント
渡辺 政隆さんの新訳が読みやすいです。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
クラシックス
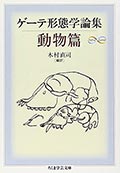
『ゲーテ形態学論集 動物篇』
- ゲーテ(著)木村 直司(編訳)
- 筑摩書房 2009年
偉大な科学者でもあるゲーテが論じる動物の形
詩劇『ファウスト』などで知られる、ドイツの文豪ゲーテ。彼は詩人でありながら自然科学者でもあった。人間と動物の骨格に同じ原型を見出そうとする「比較解剖学」をはじめ、外見から内面を推しはかる「観相学」など、その形態学的思想の一端に触れる論文を多数の図版とともに収録する。

推薦コメント
僕の専門である形態学という言葉をつくったのがゲーテ。動植物の形に対する見方を最初に提示した人です。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
クラシックス
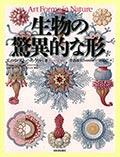
『生物の驚異的な形』
- エルンスト・ヘッケル(著)小畠 郁生(監修)戸田 裕之(訳)
- 河出書房新社 2014年
まるでアート作品。ヘッケルが描く多様な形
生物学者ヘッケルはデッサンの天才だった。ウミユリもクラゲも放散虫も精巧なアート作品に早変わり。芸術界も驚いた自然界のかたちの魅力が次々と溢れ出す。100点もの貴重な博物画は、虫めがね片手に覗き込んでほしい。
クラシックス
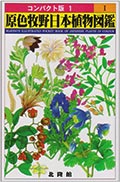
『コンパクト版1 原色牧野日本植物図鑑I』
- 牧野 富太郎(著)
- 北隆館 1985年
日本植物学の父 牧野 富太郎のスケッチ図鑑
94歳で亡くなる直前まで日本全国をまわり、生涯で40万の植物標本を作製した。牧野 富太郎は、1500種もの植物を命名した日本植物学の父。本書は牧野が描いた1216種のスケッチを堪能できる図鑑。「雑草という名前の植物はない」という言葉どおり、優しい眼差しに溢れている。
クラシックス

『微生物の狩人(上)(下)』
- ポール・ド・クライフ(著)秋元 寿恵夫(訳)
- 岩波書店 1980年
目に見えない微生物を追う13人の個性豊かな科学者たち
手製の顕微鏡を使い、世界で初めて微生物を発見したレーウェンフック。近代細菌学の開祖と言われるパスツールとコッホ。梅毒の特効薬を発見したエールリヒ。病原菌の研究を通して社会に貢献した科学者13名の列伝記。研究の偉大さとは裏腹に彼らの人間らしい部分も読みどころだ。
推薦コメント
微生物研究で社会を救った13名の列伝期です。医学史研究者の間では「悪名高き古典」らしいのですが、学問は人類が切磋琢磨してつくりあげるものだと感じられる良書です。
山崎 展樹(開拓研究本部 上野核分光研究室 専任研究員)
クラシックス
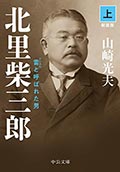
『北里 柴三郎(上)(下)─雷と呼ばれた男 新装版』
- 山崎 光夫(著)
- 中央公論新社 2019年
細菌研究にも教育にも全力を注いだ北里の生き様
1894年にペスト菌を発見し、伝染病から人類を救った北里 柴三郎。血気盛んな医学生時代から、細菌学の祖・コッホに師事し破傷風菌の血清療法を確立したドイツ留学、伝染病研究所を創立し門下生を育てた晩年まで。日本近代医学に多大な貢献をしながらも、雷おやじと慕われた北里をいきいきと描く伝記小説。
クラシックス
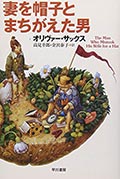
『妻を帽子とまちがえた男』
- オリヴァー・サックス(著)高見 幸郎、金沢 泰子(訳)
- 早川書房 2009年
サックス先生が出会った患者たちの豊かな世界
妻の頭を帽子と間違えてかぶろうとする音楽家、30年間の記憶を喪失した元船乗り、突然ひょうきん者に性格が変わった科学研究員の夫人。脳神経科医のオリヴァー・サックスが奇妙な症状を抱える患者たちについて愛情を込めて描いた24篇の医学エッセイ。

推薦コメント
脳神経内科医オリヴァー・サックスが、奇妙な症状を抱える患者24人を愛情豊かに描いています。大学の授業で読み、神経科学を学ぼうと決めたきっかけの本です。何が人間を人間たらしめているのかを考えさせる、哲学的なところも魅力です。
アダム・フィリップス(国際部)
クラシックス
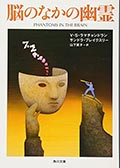
『脳のなかの幽霊』
- V. S.ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスリー(著)山下 篤子(訳)
- 角川書店 2011年
私の身体感覚は脳がつくった幻なのか?
事故で失った腕をまだあると感じ続けるスポーツ選手、麻痺した腕を兄の腕だと答える教師、自分の両親は偽物だと主張する青年。神経科学者の著者は、患者の得体の知れない症状から脳の仕組みや働きを推論。一人ひとりに対峙し、治療法を模索していく。1998年に刊行し脳ブームに火をつけた本。

推薦コメント
腕を切ったのにない腕が痛む「幻肢痛」から脳の不思議を描いています。先端技術なしに患者さんとのやりとりだけで解明するのが素晴らしい。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
