科学道100冊 傑作選 1から25
科学道100冊傑作選は、理研が選ぶ「時代を経ても古びない良書100冊」です。理研の研究者や職員にアンケートをして選出した、決定版のラインナップです。
- ※2019年に選定した科学道100冊クラシックス(50冊)をベースに選びなおしました。
- ※推薦コメント、推薦者の所属は、過去のシリーズでの選書時のものです。
傑作選

『科学と科学者のはなし─寺田 寅彦エッセイ集』
- 池内 了(編)
- 岩波書店 2000年
花鳥風月の中にも科学の原理、法則がある
茶碗の湯、電車の混雑、宙に舞う埃、線香花火に金平糖…。ごく身近なありふれた物の中には、さまざまな科学の原理や法則が潜んでいる。夏目 漱石の弟子であり『吾輩は猫である』にも登場した寺田 寅彦による科学エッセイ。「津浪と日本人」という一編では、繰り返される三陸沿岸の被災を描いている。
傑作選

『銀河の片隅で科学夜話─物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世界の小さな驚異』
- 全 卓樹(著)
- 朝日出版社 2020年
眠れない夜。物理学者の見ている宇宙を旅しよう
潮の満ち引きは永遠に続くのか?「三人寄れば文殊の知恵」は確率論的に正しいか?思い出せない夢を人はなぜ見るのか?言語によって世界の見え方は変わるか?天空編・原子編・数理社会編・倫理編・生命編の5部構成で、物理学者がやさしく語る、眠れぬ夜にぴったりの科学奇譚集。

推薦コメント
肩の力を抜いて楽しめる科学談話の数々。少し、イナガキ・タルホ(小説家)の世界にも似ている。文学と科学の狭間を楽しみたい人にお勧めです。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選
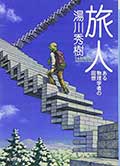
『旅人─ある物理学者の回想』
- 湯川 秀樹(著)
- KADOKAWA 2011年
原子物理学を開拓した科学者・湯川 秀樹の道程
「中間子の着想を得たときに思い出したのは、少年時代に見た真昼の星のような木漏れ日だった―」。はにかみ屋だった幼少期から、数学に夢中になった少年時代、理論物理学と出会った大学時代、そして中間子という新理論を得るまで。日本人初のノーベル賞受賞者・湯川 秀樹が、自らの半生を振り返る。

推薦コメント
日本人初のノーベル賞受賞者、湯川 秀樹が自身の半生を綴った本です。小学校高学年の時に読み、一つのことを突き詰める姿勢に感銘を受けました。「科学者になりたい」と思ったきっかけであり、僕の最初のヒーローです。湯川さんが提唱した原子核の「核力」の謎に没頭し、今もその解明に取り組んでいます。
初田 哲男(数理創造プログラム プログラムディレクター)
傑作選

『ご冗談でしょう、ファインマンさん(上)(下)』
- R.P.ファインマン(著)
- 大貫 昌子(訳) 岩波書店 2000年
ファインマンさんは冗談抜きで好奇心のかたまりです
アメリカの物理学者、リチャード・P・ファインマンの回想記。小さな頃からラジオが大好きな知りたがりで、12歳の頃には実験室を持っていた。真っ正直で、つい遊び心を発揮してしまうから事件が起こる。ノーベル賞を取っても変わらない。原爆開発のマンハッタン計画を内側から見た章は、科学秘史としても貴重だ。

推薦コメント
ファインマンさんの人柄と研究愛を感じる自伝です。彼は学者でも特別おもしろい人だと思います。
豊泉 太郎(脳神経科学研究センター 数理脳科学研究チーム チームリーダー)

推薦コメント
ファインマンの分野にとらわれない好奇心のあり方が素敵です。この本に影響を受けた科学者の人たちが世界中にたくさんいると思います。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)
傑作選

『「科学者の楽園」をつくった男─大河内 正敏と理化学研究所』
- 宮田 親平(著)
- 河出書房新社 2014年
日本の科学はここから始まった!傑物が集った理化学研究所
日本を科学立国にすべく、大正期に設立された理化学研究所。科学者たちに自由を与えた大河内 正敏 所長のもと、鈴木 梅太郎、湯川 秀樹、朝永 振一郎ら、傑出した才能が集った。この「科学者たちの楽園」にもやがて戦争が影を落とす―。日本の科学史に多くの功績を残した理研の栄光と苦難の歴史を生き生きと描く。

推薦コメント
「社会の課題解決のために、徹底的に基礎研究を行う」という“理研精神”が溢れた本。理化学研究所の研究員だった私の祖父、桜田 一郎も登場します。
桜田 一洋(医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクター)

推薦コメント
戦前戦中の理研を支えた大河内 正敏さんに興味があります。彼は科学者の可能性を信じた人だったと思います。
長瀧 重博(開拓研究本部 長瀧天体ビッグバン研究室 主任研究員)
傑作選
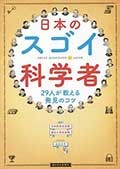
『日本のスゴイ科学者─29人が教える発見のコツ』
- 日本科学未来館、朝日小学生新聞(編著)池田 圭吾(イラスト)
- 朝日学生新聞社 2019年
日本発、最先端研究のポイントがまるわかり
人類の発展につながるスゴイ発見をした29人に取材!部品みたいなタンパク質、世界一正確な時計、地球の底の再現など、驚くような研究も。イラストで解説する研究内容に目を見張り、博士の小・中学生時代のエピソードに勇気をもらう。朝日小学生新聞連載の書籍化。
傑作選

『世界を変えた50人の女性科学者たち』
- レイチェル・イグノトフスキー(著)野中 モモ(訳)
- 創元社 2018年
女だって研究がしたい!情熱で道を切り拓いた50人
マリー・キュリーだけじゃない!科学や技術、工学、数学の分野で活躍しながらも歴史の陰に隠れがちだった女性科学者。世界を変えた古今東西の女性たち、その夢と冒険に満ちた足跡を追う。

推薦コメント
今や数多くの女性科学者が活躍し、男女を問う意味もない欧米であるが、このような状況にいたるまでの女性科学者ならではの苦労と活躍を、見開き1ページでポップなイラストとともに50人を紹介。漢字にはルビがふってあり、小学生高学年から読め、リケジョのロールモデル満載。
伊藤 嘉浩(開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室 主任研究員)

推薦コメント
自分の専門分野で活躍した女性研究者を確認する一方、教科書に出てくる有名な研究者が女性だと初めて知ることができました。科学は男女、人種等を超えて平等でなければならない、と改めて思います。
櫻井 博儀(仁科加速器科学研究センター センター長)
傑作選

『科学史ひらめき図鑑 世界を変えた科学者70人のブレイクスルー』
- 株式会社スペースタイム(著)杉山 滋郎(監)
- ナツメ社 2019年
未来を切り拓くためのひらめきのエンジニアリング
70もの歴史的な発見・発明の奥にあるひらめきの方法を紐解いて図解。グーテンベルクは「既存の方法を組み合わせる」ことで活版印刷を発明。ガリレオは「わかりやすいものに置き換える」ことで落体の法則を発見した。4ページ1テーマで読みやすく、どこを開いてもヒントがいっぱい!

推薦コメント
過去の科学技術イノベーションが起きた背景を丹念に調べ、科学者たちの「ひらめきの技」をリストアップ&図解した、ユニークな本。ピタゴラスから山中 伸弥 先生まで、分野も時代も幅広い。人生で困ることがあっても、これだけ技があれば突破できるはず!
園田 翔(革新知能統合研究センター 汎用基盤技術研究グループ 深層学習理論チーム 研究員)

推薦コメント
科学者は「ひらめき」を追い求める生き物です。ユーモアあふれるイラストと、科学技術についての簡潔かつ的確な説明で飽きさせません。どこから読んでも楽しめます。
伊藤 嘉浩(開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室 主任研究員)
傑作選

『科学と仮説』
- ポアンカレ(著) 河野 伊三郎(訳)
- 岩波書店 1938年
真実を探究するためには仮説が重要である
科学はいかにして真理を発見していくのか?近代随一の数学者、物理学者であるポアンカレは、真理探究の方法に着目。幾何学、力学、光学、電気学など、あらゆる科学において仮説がいかに重要な役割を占めるかを解いた。原文の初版が1902年発行、以来読み継がれる科学思想書の古典。
傑作選

『いかにして問題をとくか』
- G. ポリア(著) 柿内 賢信(訳)
- 丸善出版 1975年
答えを考える前に問題の解き方を考えよ
スタンフォード大学の数学教授G・ポリアによる「問題解決」のロングセラー。1945年に出版されて以来、広く読み継がれる。「未知のものは何か、与えられているものは何か、条件は何か、という3つの問いから出発する」「問題を解くには決意と情緒が重要」など。数学書だがその方法は普遍的、ビジネスにも効く一冊だ。
傑作選

『精神と自然─生きた世界の認識論』
- グレゴリー・ベイトソン(著)佐藤 良明(訳)
- 岩波書店 2022年
命あるものには共通するパターンがある?
紙袋からとりだした、ゆでたてのカニ。「この物体が生物の死骸であるということを、私が納得のいくように説明しなさい」。難問で学生を戸惑わせるのは、知の巨人グレゴリー・ベイトソンだ。アメーバからサイバネティクスまでを一緒くたに考える、世界の認識論。

推薦コメント
世界の見方を一変させるような力を持った本は、たしかに時々存在する。ある人にとっては本書もそのうちのひとつに数えられるでしょう。ちなみに、この著者の父親は、ホメオティック突然変異の概念の生みの親、ウィリアム・ベイトソンです。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選

『遊びと人間』
- ロジェ・カイヨワ(著)多田 道太郎(訳)塚崎 幹夫(訳)
- 講談社 1990年
遊びこそ、人間の本質?遊びを4種に分類した名著。
遊びは楽しい。でも所詮、遊びは遊び。財産や作品を産み出すわけではない。そんな考えがある一方で、遊びこそが文化をつくってきたと評価する見方もある。果たして人間にとって遊びとは何なのか?科学も遊びから始まった?人間の遊びを4つに分類した、古びない1冊。

推薦コメント
ヨハン・ホイジンガが『ホモ・ルーデンス』(1938年)を問うて以来、遊びと社会の関係は興味深い考察の対象となっています。カイヨワにとって、遊びの概念はホイジンガのそれよりも拡張・精緻化されており、理論化のための興味深い分類が示されています。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選

『ソフィーの世界─哲学者からの不思議な手紙』
- ヨースタイン・ゴルデル(著)須田 朗(監修)池田 香代子(訳)
- NHK出版 1995年
あなたはだれ?1通の手紙から始まる哲学の冒険
ある日、14歳のソフィーのもとに届いた手紙。「あなたはだれ?」わたしはソフィー。でもそれってどんな人…?次々と届く不思議な手紙に導かれて、少女は哲学者たちに出会っていく。「ソフィーの世界」がいつしか「あなたの世界」になる、不思議な哲学ファンタジー。
推薦コメント
脳の研究をしている人は哲学から入る人も多い。私も『ソフィーの世界』を読み、世の中はどのようにできているのか、自我とは何か、と考えるきっかけになりました。
田中 和正(脳神経科学研究センター 神経回路・行動生理学研究チーム 訪問研究員)
傑作選

『サイエンス 大図鑑【コンパクト版】』
- アダム・ハート=デイヴィス(総監修)日暮 雅通(監訳)日暮 雅通、藤原 多伽夫、山田 和子(訳)
- 河出書房新社 2014年
紀元前1万4000年から現代まで科学の重要トピックを網羅
先史時代の火の利用に始まり、古代ギリシアの世界観、印刷革命、重力の発見、蒸気機関の発明、ゲノム解読、気候変動対策まで。500ページにわたる歴史の旅で、科学の発展の流れがまる分かり。人物解説、重要データの付録もあり、一家に1冊の保存版。
傑作選

『Dr.STONE』
- 稲垣 理一郎(原作)Boichi(作画)
- 集英社 2017年
ゼロから文明を作り出す!科学少年と仲間達の熱き挑戦
集めまくって、試し続けろ。科学とは未知のルールを探す「クッソ地道な努力」のことだ!文明が失われた3700年後の世界に目覚めた高校生・千空が、仲間とともに大自然と石化の謎に真っ向勝負し、未来をこじあけていくサバイバルSF漫画。ラーメン、コーラ、鉄づくり、真似して実験したくなる。

推薦コメント
生きていく上で必ず必要なものからあると便利なものまで、実際の生活の中で生まれる科学を楽しく理解できる1冊。最初はこのようなマンガを通して楽しく学びながら、サイエンスの世界に足を踏み入れるのはいかがでしょうか。
清成 寛(生命機能科学研究センター 生体モデル開発チーム チームリーダー)

推薦コメント
ゼロから文明を作ろうとする、スケールの大きなSFサバイバル冒険譚です。僕たち研究者も、これまでに無い理論をゼロから自分たちでつくることがあるので、「必要なものが無ければつくればいい」という不屈の精神に共感します。研究の根本にある大切なことを、改めて気づかせてくれます。
園田 翔(革新知能統合研究センター 汎用基盤技術研究グループ 深層学習理論チーム 研究員)
傑作選

『この世界を知るための人類と科学の400万年史』
- レナード・ムロディナウ(著)水谷 淳(訳)
- 河出書房新社 2016年
人類誕生から量子論まで高速で駆けぬける科学発展史
科学はどのように進歩してきたのか?その歴史を、知識を探求する動物・人類の誕生から、科学革命をへて、見えない量子の世界をも理解するようになった現代まで、3部構成で描く科学発展史。アリストテレス、ニュートン、アインシュタインなどの偉人が当時の時代背景の中で生き生きと描かれている。
傑作選

『数量化革命』
- アルフレッド・W・クロスビー(著)小沢 千重子(訳)
- 紀伊国屋書店 2003年
ヨーロッパ覇権のヒミツは数量化と視覚化にあった
中世ヨーロッパが世界で覇権をとれたのは、科学やテクノロジーのおかげではない。物の見方の変化によるものである。機械時計や暦、地図・海図などの「数量化」と、楽譜や遠近法、複式簿記といった「視覚化」によって、ヨーロッパ人の世界観がいかに変容を遂げ、社会の発展につながったのかを詳説する。
傑作選

『パラダイムと科学革命の歴史』
- 中山 茂(著)
- 講談社 2013年
時代によって変化する科学。その転換点を辿る
科学という学問は、いかにして発展してきたのか?古代アジアとヨーロッパの学問的伝統の比較から、近代科学成立後に生まれた学術雑誌や大学アカデミズム、明治日本の西洋科学の移植、学問のデジタル化まで。パラダイム論を日本に紹介した科学史家が俯瞰的に描く、学問の歴史。

推薦コメント
トーマス・クーンの「パラダイム論」を日本に紹介した中山 茂 先生が、科学史のパラダイムシフトの過程を書いています。パラダイムを簡単にいうと、「考え方の枠組み」のようなもの。普段研究をしていると、自分の考えに囚われがちですが、思考の外側を注意深く点検することが大事。枠を出ることから新しいパラダイムが生まれる可能性がある、それを教えてくれる本です。
櫻井 博儀(仁科加速器科学研究センター センター長)
傑作選

『世界を変えた150の科学の本』
- ブライアン・クレッグ(著)石黒 千秋(訳)
- 創元社 2020年
科学書はこれまでもこれからも人類の進歩を照らす灯火だ
科学の知識は、本に記述され、人々に伝わってこそ大きな進歩を遂げる。古代エジプトのパピルスに始まり、ダ・ヴィンチの手稿、ガリレオの『星界の報告』、ダーウィンの『種の起源』、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』など、2500年の科学書の歴史を、カラー写真で振り返る。印刷の発展や本のデザインも見どころ。

推薦コメント
Study nature, not books. ールイ・アガシー(スイス・1807-1873)科学者たるもの、何かを追究するなら、まずは「本物の実物」を無心に眺めることから始めるべきだ。この本では「世界を変えた科学」の原典を見ることができる。抽出された結果の情報のみからでは得られない、科学のパイオニア達の情念・息吹・葛藤・逡巡など、その時代の心の内面に思い馳せる入口となる。Bookでありながら、ただのBooksでは無い。
入來 篤史(生命機能科学研究センター 象徴概念発達研究チーム チームリーダー)
傑作選

『New Scientist 起源図鑑─ビッグバンからへそのゴマまで、ほとんどあらゆることの歴史』
- グレアム・ロートン(著)ジェニファー・ダニエル(絵)佐藤 やえ(訳)
- ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017年
科学で読み解くあらゆるものの始まりの物語
星や銀河は宇宙の「ゆらぎ」から生まれた、お酒の起源は1億3000万年前のある種子植物の登場による、世界初のトイレットペーパー会社は14世紀中国で設立された。思わず人に話したくなる、あらゆるものの「始まりの物語」を集めたビジュアル図鑑。睡眠、所有、友情、性行動、へそのゴマの起源は?
傑作選
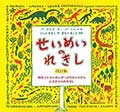
『せいめいのれきし 改訂版』
- バージニア・リー・バートン(文・絵)いしい ももこ(訳)まなべ まこと(監修)
- 岩波書店 2015年
三葉虫や恐竜から人間へ受け継がれる生命のバトン
物語の幕開けは46億年前、地球誕生のシーンから。三葉虫が大繁殖したカンブリア紀、恐竜が巨大化し鳥類も登場したジュラ紀、地球温暖化で哺乳類が台頭した中新世、そして氷河期を経て、人間の時代へ。35の場面で私たちに流れ込む壮大な命のリレーを描く科学絵本。絵の細部を読み解くのも面白い。

推薦コメント
銀河系の始まりから現在まで、今の歴史を網羅した内容の濃い絵本です。3歳と5歳の子も見入っています。
栗原 恵美子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 研究員)
傑作選
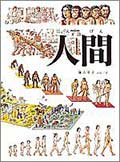
『人間』
- 加古 里子(文・絵)
- 福音館書店 1995年
150億年前の宇宙誕生にはじまる人間の物語
科学絵本の巨匠・加古 里子が17年の構想を経て描いた「人間」とは。人類の誕生をビックバンに始まる流れの中で語り、臓器の仕組みなど人体の不思議を大胆な絵で描き、人間が発明した道具や学問から社会的な動物としての側面をあぶり出す。自分が壮大な物語の一部であることに気付かされる絵本。

推薦コメント
幼い頃から、絵本作家・加古 里子さんの本が大好きでしたが、彼が東京大学出身の工学博士だとは最近まで知りませんでした。科学の基礎知識があった上での精緻かつ親しみやすい絵柄、人体の構造だけでなく人類の歴史まで描いており、専門家が読んでも素晴らしい内容ではないかと思います。
鈴木 千歳(バトンゾーン研究推進プログラム 人工ワクチン研究チーム テクニカルスタッフ)
傑作選

『漫画 サピエンス全史(人類の誕生編)(文明の正体編)』
- ユヴァル・ノア・ハラリ(原著・脚本)ダヴィッド・ヴァンデルムーレン(脚本)ダニエル・カザナヴ(画)ほか
- 河出書房新社 2020年
7万年前、すべてはサピエンスの認知革命から始まった
人類の歴史は認知革命から始まった。数種類いたヒト属の中で、なぜホモ・サピエンスだけが生き延びたのか?1万2000年前の農業革命は何をもたらしたのか?人類史に新たな視点を提示した世界的ベストセラーが、公式漫画化でパワーアップ。

推薦コメント
歴史学者・哲学者であるユヴァル・ノア・ハラリの著書の漫画バージョン。大きくもない、強くもない、走るのが速いわけでもないホモ・サピエンスが、どうして唯一の人類として生き延び、永らえたのか。これを可能にした「革命」的な出来事を大胆に語る。
仲 真紀子(理化学研究所 理事)

推薦コメント
人類の誕生と文明の発展、そして私たちの社会のあり方が、すっと1本の線でつながるような印象を受けました。「文明の正体」を見極めることは、これからの世界をどのようによくしていけるかを考えるために重要です。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
傑作選

『種の起源(上)(下)』
- ダーウィン(著)渡辺 政隆(訳)
- 光文社 2009年
生物学の根幹をなすダーウィンの進化論
なぜ生物にはこれほど多様な種が存在するのか?生物は神が個別に創造したものだと考えられていた時代に、生物は共通の祖先から進化したと唱えたダーウィン。自然淘汰、生存闘争、突然変異、地理的分布など、様々な疑問点を進化論で説明し、世界の価値観を一変させた驚異の書。1859年初版。

推薦コメント
ダーウィンの進化論は機械的な因果律によって生命現象を説明する端緒を開きました。その意味を本書から読み解いてみてください。
桜田 一洋(医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクター)

推薦コメント
渡辺 政隆さんの新訳が読みやすいです。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選

『創造的進化』
- アンリ・ベルクソン(著)合田 正人、松井 久(訳)
- 筑摩書房 2010年
生命の進化はなぜ起きたか?哲学的視点による大胆な解釈
生命の進化は、特定の目的のためにあるのではない。それは「生命の弾み(エラン・ヴィタル)」によって起こされる。生命は意識と同じく、創造的な衝動によって絶えず変化していくものなのだ―。ダーウィンの進化論とは異なった、生命と意識のアナロジーによって導かれる、哲学者ベルクソンの独自の進化論。
推薦コメント
生物の進化の問題を新しい視点から捉えようとしたベルクソンの主著の一つです。生物に関する具体的な例は、今の科学では正しくない箇所もありますが、「時間」の意味を問い直して科学と哲学を融合しようとした試みは、これからの科学の可能性を示しているように思えます。
山崎 展樹(開拓研究本部 上野核分光研究室 専任研究員)
