科学道100冊 傑作選 26から50
科学道100冊傑作選は、理研が選ぶ「時代を経ても古びない良書100冊」です。理研の研究者や職員にアンケートをして選出した、決定版のラインナップです。
- ※2019年に選定した科学道100冊クラシックス(50冊)をベースに選びなおしました。
- ※推薦コメント、推薦者の所属は、過去のシリーズでの選書時のものです。
傑作選
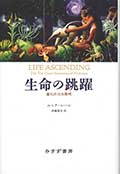
『生命の跳躍ー進化の10大発明』
- ニック・レーン(著)斉藤 隆央(訳)
- みすず書房 2010年
生命の歴史における10の大きな「発明」とは!?
深海の熱水噴出孔での生命の誕生、生命の暗号であるDNA、酸素を発生させる光合成、眼による視覚の獲得、人間の心のルーツとなる意識の芽生え、そしてすべての生命に待ち受けている死まで。進化において重大な転機となった10の革命を、自然界の「発明」と称して解説する。

推薦コメント
生物の進化に関して、10の革命的な「発明」を記載することで生命進化に迫るユニークな本です。生命の誕生、DNA、光合成、細胞、有性生殖、運動、視覚、温血、意識、死を取り上げ、生物の進化と多様性に関して深く考察しています。
篠崎 一雄(環境資源科学研究センター 機能開発研究グループ グループディレクター)
傑作選

『WHAT IS LIFE?─(ホワット・イズ・ライフ?)生命とは何か』
- ポール・ナース(著)竹内 薫(訳)
- ダイヤモンド社 2021年
「生きている」とはどういうことだろう?
What is life?ノーベル賞生物学者が、細胞、遺伝子、進化など、5つの見方を通じて生命を定義する「統一原理」を導いていく。研究が明かしたのは、地球上の全生命の始まりは同時多発ではなく「たった1回」の契機に起因するということ。我々はこの星の家族であり、すべての命とつながっている。

推薦コメント
細胞分裂の制御でノーベル生理学・医学賞を受賞した著者が、「生命とは何か?」というビッグクエッションに挑んだ、現代生命科学の入門書。一般の読者にも理解できるように書かれています。研究者の生活に関しても書かれていて親しみやすいです。
篠崎 一雄(環境資源科学研究センター 機能開発研究グループ グループディレクター)
傑作選
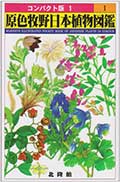
『コンパクト版1 原色牧野日本植物図鑑I』
- 牧野 富太郎(著)
- 北隆館 1985年
日本植物学の父 牧野 富太郎のスケッチ図鑑
94歳で亡くなる直前まで日本全国をまわり、生涯で40万の植物標本を作製した。牧野 富太郎は、1500種もの植物を命名した日本植物学の父。本書は牧野が描いた1216種のスケッチを堪能できる図鑑。「雑草という名前の植物はない」という言葉どおり、優しい眼差しに溢れている。
傑作選
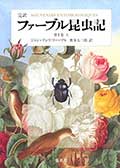
『完訳 ファーブル昆虫記 第1巻(上)』
- ジャン=アンリ・ファーブル(著)奥本 大三郎(訳)
- 集英社 2005年
ファーブルが30年かけて書いた愛情たっぷりの昆虫観察記
ファーブルが55歳から83歳まで後半生をかけて書いた全10巻の昆虫記。南フランスの美しい景色を背景に、ファーブルの日常も交えながら描かれる仔細な昆虫のドラマは、ヴィクトール・ユゴーに「昆虫のホメーロス」と評された。第1巻はフンコロガシと蜂の物語。ふんだんな挿絵も楽しめる。

推薦コメント
ファーブル昆虫記は、科学精神に満ちています。「標本に突き刺しただけでは虫を知ったとは言えない。生活の仕方や本能を知りたい」というのがファーブルです。非常に成熟した視点ですね。僕としては少し大人になってから寝転がって読むのが最高だと思います。この本は奥本 大三郎さんによる新訳と、ふんだんにちりばめられた挿絵が素晴らしい。この版で初めて読める人は恵まれていますね。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選

『世界一うつくしい昆虫図鑑』
- クリストファー・マーレー(著)熊谷 玲美(訳)
- 宝島社 2014年
昆虫は、自然が生み出した最上級のデザインだ!
宝石のような節足動物、繊細な芸術作品のような蝶。美しい虫を求めて世界を旅する昆虫ハンターが集めた、自然の造形美。見れば見るほど、機能的かつゴージャスなデザインに感動する。虫ぎらいが思わず虫マニアになってしまう、カラーパレットのような昆虫写真集。
傑作選
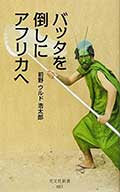
『バッタを倒しにアフリカへ』
- 前野 ウルド 浩太郎(著)
- 光文社 2017年
「バッタに食べられたい!」過剰なバッタ愛の果てに
ファーブルに憧れ、子どもの頃からの「バッタに食べられたい」という夢を叶えるべく、単身モーリタニアへと向かった著者。だがバッタの大発生に苦しんでいるはずの現地で、バッタには出会えぬまま。人生をかけたバッタ研究はどうなるのか。バッタ愛溢れるバッタ博士のドタバッタ奮闘記。
傑作選

『絵とき ゾウの時間とネズミの時間』
- 本川 達雄(著)あべ 弘士(絵)
- 福音館書店 1994年
小さいものはせかせか、大きいものはゆったり?
ネズミの鼓動は1分間に約600回、人間は60~70回、ゾウは30回。体重が増えるにつれて、時間はゆっくりになる。寿命の長さも全然違う。でもじつは、一生の鼓動の回数は、みんな同じ15億回なんだ。スケールが違えど、生きものはみなそれぞれの時間を生きている。
傑作選

『生物から見た世界』
- ユクスキュル、クリサート(著)日高 敏隆、羽田 節子(訳)
- 岩波書店 2005年
世界はひとつ?いいえ。世界は生物の数だけある。
私が認識する世界と、ハエが認識する世界は一緒だろうか?いや、そんなずはない。同じ1本のカシワの樹でも、カミキリムシにとっては巨大な食物市場であり、キツネにとっては巣穴だ。ユクスキュルは生き物それぞれが見る世界をUmwelt(環世界)と名付けた。新しい生物行動学の道を拓いた先駆的な書。
傑作選

『シートン動物記 オオカミ王 ロボ』
- アーネスト・T・シートン(文・絵)今泉 吉晴(訳・解説)
- 童心社 2010年
シートン直筆の絵と味わうオオカミ王の愛と死の物語
人間を出し抜いて牧場を襲い、そのあまりの賢さから「ルー・ガルー(オオカミ人間)」と呼ばれたオオカミ王、ロボ。シートンは、その伴侶であるブランカを罠にかけるが。オオカミを賢く愛情深い動物として世に知らしめた名作。画家でもあったシートン直筆の挿画が物語を彩る。

推薦コメント
小学生の頃に『シートン動物記』に出会い、ロボの物語にとても感動しました。その後、シートンは生物学者であり、画家であり、探検家であり、自然保護運動の創始者であり、マルチな才能を持つ人だと知りました。ロボの話はシートンが実際に牧場でオオカミ対策をした時の体験であり、彼はまさに実践知を持つ人なんです。私は現場の知を持つ人に惹かれるので「シートンのように生きたい」と思います。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
傑作選
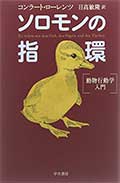
『ソロモンの指環─動物行動学入門』
- コンラート・ローレンツ(著)日高 敏隆(訳)
- 早川書房 1998年
一緒に暮らして書いたノーベル賞学者の生き物観察記
29日間温めてきたガンの卵から、ついにヒナが顔を出した。目と目を合わせ、言葉を交わしたその時から、ヒナは著者ローレンツを母親と認め、離れなくなった。食事の世話に寝かしつけ、川べりへの散歩、忙しくものどかな子育ての日々。ガン語が話せ、カラス語がわかるノーベル賞学者の動物観察記。

推薦コメント
ソロモンの指輪を身につけると動物と話ができる?行動学者であるコンラート・ローレンツが、動物の行動のメカニズムを紐解く。生涯にわたる行動に影響を及ぼす初期学習など、遺伝と環境の問題を考える上でも有用な1冊です。
仲 真紀子(理化学研究所 理事)
傑作選

『鼻行類─新しく発見された哺乳類の構造と生活』
- ハラルト・シュテュンプケ(著)日高 敏隆、羽田 節子(訳)
- 平凡社 1999年
20世紀に発見された新種!?鼻で歩く「鼻行類」の正体とは
1941年にハイアイアイ群島で初めて発見され、核実験によって絶滅した新種の哺乳類「鼻行類」。鼻で体を支え耳を使って飛行するダンボハナアルキ、鼻を釣り糸にして水中の獲物を捕るハナススリハナアルキ…。鼻が独自の進化を遂げた鼻行類の全貌を多くの図版で明かし、世界中で物議を醸した奇書。

推薦コメント
1961年に発見されたという設定の偽書、もしくは奇書。非現実でありながらも、正統派生物学の基礎を踏まえて考察が展開するところが興味深いです。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選

『古生物のサイズが実感できる!リアルサイズ古生物図鑑 古生代編』
- 土屋 健(著)群馬県立自然史博物館(監修)
- 技術評論社 2018年
マカロンと思ったら古生物!?リアルな質感で現代に蘇る図鑑
さまざまな時代の古生物を、現代の身近な風景の中に配置してみました!魚屋の店頭にならぶ海洋動物アノマロカリス、虫取り網で狙われる巨大トンボのメガネウラ、駐車場で休憩中の大きな帆を持つディメトロドン。普通の復元イラストではわからない、古生物たちのリアルなサイズ感が実感できるユニークな図鑑。
傑作選
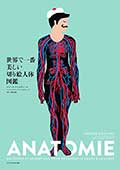
『世界で一番美しい切り絵人体図鑑』
- エレーヌ・ドゥルヴェール、ジャン=クロード・ドゥルヴェール(著)奈良 信雄(監訳)
- エクスナレッジ 2017年
人体の構造が感覚でわかるアートな仕掛け絵本
フランス発、デザイナーの娘と医師の父がつくった世にも美しい人体図鑑。筋肉系、骨格系、消化器系、循環器系などのシステムを繊細な切り絵で表現。重ねて見ると、人体の多層さが感覚的にわかる。脳や五感の仕組みもめくって楽しめる、アート作品のような1冊。
傑作選

『はたらく細胞(1)~(6)』
- 清水 茜(著)
- 講談社 2015年
細胞たちのキャラ祭りマンガで学ぶ免疫系
舞台は体内、主人公は体中に酸素を届けるおっちょこちょいの赤血球。白血球(好中球)、キラーT細胞、マクロファージなどの免疫細胞が、それぞれの得意技を生かして、体内に侵入した細菌やウイルスと戦いまくる!休みなく働いてくれる自分の体に感謝の念が湧いてくる。
傑作選

『解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯』
- ウェンディ・ムーア(著)矢野 真千子(訳)
- 河出書房新社 2013年
研究のために遺体を盗掘??天才医師の、伝説の数々
近代外科医学の父、ジョン・ハンター。『ドリトル先生』『ジキル博士とハイド氏』のモデルといわれた男は、筋金入りの変人だった!?実験のために墓から死体を掘り起こし、動物や人間の標本を集める日々。解剖学への執念に、科学者の生きざまを見る。
傑作選
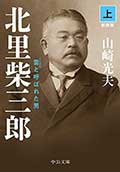
『北里 柴三郎(上)(下)─雷と呼ばれた男 新装版』
- 山崎 光夫(著)
- 中央公論新社 2019年
細菌研究にも教育にも全力を注いだ北里の生き様
1894年にペスト菌を発見し、伝染病から人類を救った北里 柴三郎。血気盛んな医学生時代から、細菌学の祖・コッホに師事し破傷風菌の血清療法を確立したドイツ留学、伝染病研究所を創立し門下生を育てた晩年まで。日本近代医学に多大な貢献をしながらも、雷おやじと慕われた北里をいきいきと描く伝記小説。
傑作選

『感染症の世界史』
- 石 弘之(著)
- KADOKAWA 2018年
地球を舞台に描かれる人類と感染症の長大なる戦記
感染症の原因は、ずばり過密社会。人類が農耕を発明し、定住集落ができたころから、感染症は始まった。産業革命による都市の不衛生がもたらしたコレラ、熱帯林の破壊に端を発するエボラ出血熱、交通網の発達で拡大したSARS。環境史の立場から論じる感染症。パンデミックは人災とも言える。
傑作選

『アルジャーノンに花束を〔新版〕』
- ダニエル・キイス(著)小尾 芙佐(訳)
- 早川書房 2015年
もししじつがうまくいたらもっとりこーになれるんだ
幼児なみの知能しかない32歳のチャーリィ・ゴードン。ある手術を受けたことで、天才的な頭脳を手に入れるが、自身と周囲の急激な変化に苦しむことに。さらに、同じ被検体のネズミのアルジャーノンに異変が起こり始め……。純朴な青年の皮肉な運命を描き、世界中にブームを巻き起こしたSF小説。
傑作選
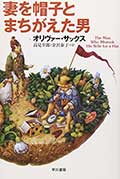
『妻を帽子とまちがえた男』
- オリヴァー・サックス(著)高見 幸郎、金沢 泰子(訳)
- 早川書房 2009年
サックス先生が出会った患者たちの豊かな世界
妻の頭を帽子と間違えてかぶろうとする音楽家、30年間の記憶を喪失した元船乗り、突然ひょうきん者に性格が変わった科学研究員の夫人。脳神経科医のオリヴァー・サックスが奇妙な症状を抱える患者たちについて愛情を込めて描いた24篇の医学エッセイ。

推薦コメント
脳神経内科医オリヴァー・サックスが、奇妙な症状を抱える患者24人を愛情豊かに描いています。大学の授業で読み、神経科学を学ぼうと決めたきっかけの本です。何が人間を人間たらしめているのかを考えさせる、哲学的なところも魅力です。
アダム・フィリップス(国際部)

推薦コメント
脳の失われた機能から人間の本質に迫るサックスの代表的な著作です。「人間とは何か」を考えさせれます。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット(ユニットリーダー)
傑作選
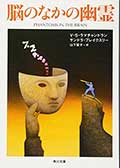
『脳のなかの幽霊』
- V. S.ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスリー(著)山下 篤子(訳)
- 角川書店 2011年
私の身体感覚は脳がつくった幻なのか?
事故で失った腕をまだあると感じ続けるスポーツ選手、麻痺した腕を兄の腕だと答える教師、自分の両親は偽物だと主張する青年。神経科学者の著者は、患者の得体の知れない症状から脳の仕組みや働きを推論。一人ひとりに対峙し、治療法を模索していく。1998年に刊行し脳ブームに火をつけた本。

推薦コメント
腕を切ったのにない腕が痛む「幻肢痛」から脳の不思議を描いています。先端技術なしに患者さんとのやりとりだけで解明するのが素晴らしい。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
傑作選

『意識はいつ生まれるのか─脳の謎に挑む統合情報理論』
- マルチェッロ・マッスィミーニ、ジュリオ・トノーニ(著)花本 知子(訳)
- 亜紀書房 2015年
脳の最大の謎「意識」はどのように生まれるのか?
解剖実験中、手のひらに脳を載せ、数時間前までその中に、知識、記憶、夢など全てが宿っていたことに愕然とした。著者・精神科医トノーニの学生時代の思い出から本書は始まる。ただの物質である脳に、どうして意識が宿るのか?革新的な統合情報理論「Φ理論」によってその正体に迫っていく。

推薦コメント
この本がすごいのは、「人間の意識という捉えどころのないものを、科学がどう扱うのか?」という枠組みを最初に提唱したところです。意識の解明という難題に著者、ジュリオ・トノーニがどうアプローチしたのか、発想の仕方や試行錯誤のプロセスに注目して楽しんでもらいたいです。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)

推薦コメント
脳科学の最先端で、意識のメカニズムに迫ろうとする研究者の迫力と興奮が伝わってきました。研究は一人ではできません。こうした自身の研究のワクワク感を周囲に伝え広めていくことは、研究者としてとても大切なことだと思います。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
傑作選

『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか─脳AI融合の最前線』
- 紺野 大地、池谷 裕二(著)
- 講談社 2021年
現実はすでに想像を超えている人工知能と脳研究の最前線
「目を介さずに世界を見る」「他人が見ている夢を読み取る」「うつ病患者を治療する」…人工知能の研究は、すでにわたしたちが想像する以上のことを実現しつつある。脳とAIを融合させることによって、脳の潜在能力をアップデートする驚異のプロジェクトを、気鋭の脳研究者が自ら紹介する。
傑作選

『二重らせん』
- ジェームス・D・ワトソン(著)江上 不二夫、中村 桂子(訳)
- 講談社 2012年
DNAの構造解明にいたる熱い研究生活を、本人が描く
DNAは二重らせん構造をしている。生物学の常識を覆す大発見を果たしたジェームス・D・ワトソンが明かす、研究の日常やライバル研究者との競争のやり取り。この本をきっかけに科学を志したという科学者も少なくない、生々しく刺激に満ちた研究者のリアル。

推薦コメント
生物学研究に新しい地平を開いたDNAの二重らせん構造の発見は、バイオテクノロジーへ発展し、数々の恩恵を人類にもたらしています。本書は、教科書に記されない裏側を科学者自身が語った人間味あふれる生々しい体験の物語として描き出されています。
伊藤 嘉浩(開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室 主任研究員)
傑作選

『利己的な遺伝子 40周年記念版』
- リチャード・ドーキンス(著)日高 敏隆、岸 由二、羽田 節子、垂水 雄二(訳)
- 紀伊國屋書店 2018年
恋をするのも、争うのもすべては遺伝子の思惑通り?
生物は、遺伝子に利用される「乗り物」に過ぎない-。進化生物学者ドーキンスが「ダーウィンの進化論」を、遺伝子を主語に捉え直した。自らのコピーを増やそうとする遺伝子は、いかに生物を操るのか?親子間の愛や、縄張り闘争も遺伝子のせい?新たな生命観を提示し、大論争を巻き起こした書。

推薦コメント
本書は進化生物学の説明書というより、進化生物学の見方に基づき、生物の行動様式や心理を理解するヒントを与える教養書です。私は生物学の非専門家ですが、この本を通して人間社会で起こるさまざまな現象を、斬新な視点で覗くことができて楽しかったです。
金 有洙(開拓研究本部 Kim表面界面科学研究室 主任研究員)

推薦コメント
いうまでもない生物学の名著です。科学をする上での重要な考え方や、論理の使い方、アナロジーの正確さ、構想の広さと深さなど、学ぶべきことがぎっしりと詰まっています。
赤石 れい(脳神経科学研究センター 理研CBS-トヨタ連携センター 社会価値意思決定連携ユニット ユニットリーダー)
傑作選
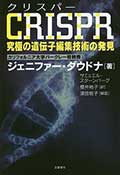
『CRISPR(クリスパー)─究極の遺伝子編集技術の発見』
- ジェニファー・ダウドナ、サミュエル・スターンバーグ(著)櫻井 祐子(訳)須田 桃子(解説)
- 文藝春秋 2017年
遺伝子編集技術を開発したダウドナ博士による手記
ヒトゲノムを構成する約32億文字から、たった一字の誤りを探し出し修正する技術、CRISPR-Cas9。著者のダウドナ博士は自分の開発した技術が病の治療に限らず、遺伝子操作技術として広がっていく様におののく。臨場感溢れる生命倫理の「いま」。
