科学道100冊 傑作選 51から75
科学道100冊傑作選は、理研が選ぶ「時代を経ても古びない良書100冊」です。理研の研究者や職員にアンケートをして選出した、決定版のラインナップです。
- ※2019年に選定した科学道100冊クラシックス(50冊)をベースに選びなおしました。
- ※推薦コメント、推薦者の所属は、過去のシリーズでの選書時のものです。
傑作選

『センス・オブ・ワンダー』
- レイチェル・カーソン(著)上遠 恵子(訳)
- 新潮社 1996年
自然の神秘に感動する力それは全ての子どもへの贈り物
子どもたちの世界はいつも新鮮で美しく、驚きと感激にあふれている。地球の声に耳を傾けるべき今こそ、神秘さや不思議さに目を見はる感性=センス・オブ・ワンダーを取り戻そう。『沈黙の春』で環境汚染に警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンが最後に残したメッセージ。
傑作選

『ウォールデン 森の生活(上)(下)』
- ヘンリー・D・ソロー(著)今泉 吉晴(訳)
- 小学館 2016年
森で暮らして見えてきた社会と人間のあるべきすがた
モノにあふれた現代社会で、人間らしい生き方がわからなくなったら、ソローを読んでみるといい。28歳からの2年2カ月、ひとり文明社会に背を向けて、森に囲まれた小屋で思索を紡いだ。トルストイやガンジーにも影響を与えた異色の思想家が、自然への愛や社会と人間の本質を説く。
傑作選

『中谷 宇吉郎─雪を作る話』
- 中谷 宇吉郎(著)
- 平凡社 2016年
雪の結晶に魅せられた雪博士のきらめくエッセイ
「雪は天からの手紙である」という名言を残した中谷 宇吉郎(1900-1962)。雪の結晶の形を分類し、世界で初めて人工雪の結晶の作製に成功した雪博士だ。雪を作る話から、線香花火、茶碗の曲線についてまで、科学と芸術のあいだをなめらかに行き来するエッセイ。
傑作選
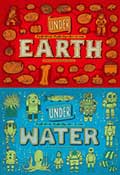
『アンダーアース・アンダーウォーター─地中・水中図絵』
- アレクサンドラ・ミジェリンスカ、ダニエル・ミジェリンスキ(作・絵)徳間書店児童書編集部(訳)
- 徳間書店 2016年
謎だらけの地球の内部探検 ツアーへようこそ!
赤い表紙の「アンダーアース」をめくると、地面の下の世界。青い表紙の「アンダーウォーター」をめくると、水の中の世界。足元から地球の中心まで、どんどん深く、見えない場所を探索する大型絵本。洞窟に住む生き物、深く根を張る大樹、むかしの潜水服、深海の生き物……どのページもオドロキに満ちている。
傑作選

『川はどうしてできるのか』
- 藤岡 換太郎(著)
- 講談社 2014年
地形探偵と解き明かす川をめぐる13の謎
ヒマラヤ山脈を乗り越える川がある?タクラマカン砂漠で洪水が発生?海底にも川が流れている?天竜川の源流はロシアにあった?本人にとってなじみの深い川にも、知られていないたくさんの謎があった。名探偵と一緒に、地形の謎解きミステリーツアーに出かけよう。

推薦コメント
ヒマラヤ山脈を越える川があるなんて、不思議じゃないですか?おもしろいので、とにかく読んでみてください。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選
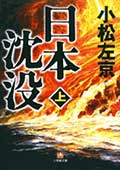
『日本沈没(上)(下)』
- 小松 左京(著)
- 小学館 2005年
地震大国・日本の危機!国民に衝撃を与えたSF大作。
「この国が…本当にこの巨大な島が沈むのか?」。鳥島南東の無人島が突如消失した。原因を探っていた小野寺は、日本海溝全体の異常に気付く。それを裏付けるかのように、日本各地を大地震が襲い始める。地球物理学の知識に裏づけされた大胆なアイディアで、日本のメディアに多大な影響を与えた衝撃のSF大作。
推薦コメント
孤高の地球物理学者・田所 博士、彼の洞察力による日本沈没の予知とそれを受けた国家規模での日本からの退避計画が、小松 左京氏の筆によりイキイキと描写されています。小学生の頃に読み、私も地球物理学者になりたいと真剣に思いました。
山崎 展樹(開拓研究本部 上野核分光研究室 専任研究員)
傑作選
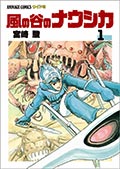
『風の谷のナウシカ 全7巻箱入りセット』
- 宮崎 駿(著)
- 徳間書店 2003年
人類は滅びるべきなのか?宮崎 駿が描く科学文明のその後
映画は序章にすぎなかった!現在の科学文明が戦争で滅びた1000年後。死の森・腐海に覆われた大地で、人と自然の歩むべき道を求めて孤軍奮闘するナウシカは、驚くべき真実にたどりつく。宮崎 駿が10年以上書き紡いだ大作漫画。環境問題への強烈なメッセージ。

推薦コメント
子どもの頃から夏休みごとに10回は映画を見返すくらいナウシカが好きでした。漫画は映画の後の物語も描いているので、ぜひ読んでもらいたいです。研究者にもよく読まれていて、ナウシカを起点に議論をすると、止まらなくなりそうです。私も読み返す度、「腐海はどうしてできたのか?」と考えます。さまざまな視点で読める名作です。
蒔田 由布子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 上級研究員)

推薦コメント
私は1968年生まれなので、今よりは社会に残る戦争の記憶が近かった世代です。ナウシカを読むと、宮崎 駿さんの反戦の思いを強く感じます。人類と文明のあり方について考えさせられる名作だと思います。映画版よりもはるかに奥深いです。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
傑作選
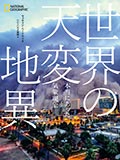
『世界の天変地異─本当にあった気象現象』
- マッティン・ヘードベリ(著)ヘレンハルメ 美穂(訳)
- 日経ナショナル ジオグラフィック 2021年
自然の底力は、人間の手に負えない。気候変動のリアル
街なかに突如現れる巨大砂嵐、一瞬で燃え広がる山火事、銃弾のような雨、見たこともない不思議な雲……。自然を資源としてどんどん利用してきた人類。しかし私たちは自然の「管理者」ではなく、巨大な生命システムの「一部」にすぎない。気候のバランスが大きく変わりつつあるいま、私たちには何ができる?
傑作選

『セレンゲティ・ルール─生命はいかに調節されるか』
- ショーン・B. キャロル(著)高橋 洋(訳)
- 紀伊國屋書店 2017年
生態系が健康であるために自然が作ったルールがある
この50年間で、世界のライオンの総数は45万頭から3万頭に減った。分子生物学者の著者は「ある区域における、生息可能な動植物の種類や個体数を調整する自然の摂理」をセレンゲティ・ルールと名づけ、その絶妙なバランスを紐解いていく。壊れた生態系の再生プロジェクトに希望をもらう。

推薦コメント
生物の数はピラミッド型に調整されています。この本では、通常は調整されている生態系が崩れる時に、何が起きているのかを「多すぎ」「少なすぎ」「やりすぎ」というカテゴリーに分類して分析します。すると、ほとんどが人間の「やりすぎ」に起因することが分かるんです。人間の活動がどう生態系のバランスに影響してしまうかを教えてくれます。
栗原 恵美子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 研究員)

推薦コメント
ヌーなどの大型哺乳類が多数生息する「セレンゲティ国立公園」における生態系の調節について論じた良書です。生命がいかに調節されているかを、生物学や医学の発展に多大な貢献をした人物の科学的発見に至るエピソードを紹介しながら、わかりやすく解説しています。
関 原明(環境資源科学研究センター 植物ゲノム発現研究チーム チームリーダー)
傑作選

『土と内臓』
- デイビッド・モントゴメリー、アン・ビクレー(著)片岡 夏実(訳)
- 築地書館 2016年
嫌われ者?それとも味方?土と人体をつなぐ微生物
著者は、地質学者の夫と生物学者の妻。2人は荒野だった新居の庭に有機物を与えて、生命溢れる庭に変えた。しかし、妻がある日がんになる。これらの経験から、土壌の中と腸の中に棲む微生物に注目し、研究にどっぷりハマった。微生物の重要な働きを知り、食物や人体への見方も変わる。

推薦コメント
土と内臓。一見関係なさそうに思えますが、実は人間の「内側」の腸の中と、植物の「外側」の根の周りが非常に類似した環境にあるということが書かれています。環境やからだへの見方が変わる一冊です。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
傑作選

『日本の酒』
- 坂口 謹一郎(著)
- 岩波書店 2007年
古い文明はかならずうるわしい酒を持つ
日本人が大昔から育てあげてきた一大芸術的創作である日本酒。その歴史から、基本の味わいである辛口と甘口、品評会の功罪、酒造業及び酒売店としての酒屋、繊細かつ重労働である酒造り、高峰 譲吉による醸造法の輸出、「火入れ」という日本酒独自の智慧まで、醗酵学者がその魅力を存分に語りつくす。
傑作選

『世界からバナナがなくなるまえに─食糧危機に立ち向かう科学者たち』
- ロブ・ダン(著)高橋 洋(訳)
- 青土社 2017年
バナナ、米、小麦、砂糖…農作物をめぐる危険な事情
効率的に作物を収穫するには、画一化するのがいい。みんな大好きなバナナやチョコレートでも、小麦やトウモロコシでも同じこと。でもそれは、病原菌や虫の被害で全滅するリスクを増やすことになる。行きすぎたアグリビジネス(農業に関連する経済活動)がもたらす危機と、そこに立ち向かう科学者たちを追う。

推薦コメント
私は、乾燥・高温などの環境ストレス下でも安定的に生産できる植物の開発を目指して、研究を進めています。この本では、米や小麦などの主要作物が、病原菌・害虫や気候変動によって、なくなってしまう可能性を伝えています。食料危機に備えるために、私たちは何をすべきかを考えさせてくれる良書です。
関 原明(環境資源科学研究センター 植物ゲノム発現研究チーム チームリーダー)
傑作選

『宇宙への秘密の鍵』
- スティーヴン・ホーキング、ルーシー・ホーキング(著)佐藤 勝彦(監)さくま ゆみこ(訳)
- 岩崎書店 2008年
ホーキング 博士が娘と書いた宇宙を旅するものがたり
ホーキング 博士と愛娘の作家ルーシーによる子どものための宇宙ファンタジー。小学生ジョージがスーパーコンピュータ・コスモスの力で宇宙を大冒険!夢中になって読むうちに、太陽系やブラックホールなど、宇宙に関する知識が自然と身につく。
傑作選

『ホーキング、宇宙を語る─ビッグバンからブラックホールまで』
- スティーヴン・W・ホーキング(著)林 一(訳)
- 早川書房 1995年
宇宙の謎を明かす統一理論へホーキング 博士の思考の軌跡
宇宙はどのように始まり、どう終わるのだろうか?車椅子の物理学者・ホーキング 博士が、数式を使わずに宇宙理論を紐解く。宇宙の膨張、素粒子の力、ブラックホールの構造、時間の本性などを語り、一般相対性理論と量子力学を統合する統一理論を探究する。天才の思考の軌跡を体感できる1冊。

推薦コメント
大学時代、進路を模索し、読み漁った中で出会った一冊です。ホーキング 博士は、宇宙の始まりやブラックホールの謎は、数学と物理を使えばスッキリ理解できるはずと語っています。その明快さと壮大さにロマンを感じ、宇宙物理学専攻を決めました。今でもたまに読み返し、真理を追求し続ける気持ちを再認識します。
長瀧 重博(開拓研究本部 長瀧天体ビッグバン研究室 主任研究員)
傑作選

『COSMOS(上)(下)』
- カール・セーガン(著)木村 繁(訳)
- 朝日新聞出版 2013年
セーガン 博士が語る人類の故郷・コスモス
宇宙という広大な海の浜辺にある地球。探査衛星で明らかになりつつある太陽系の惑星。はるか彼方で輝く星々や銀河。どこかにいるかもしれない宇宙人。カール・セーガン 博士が縦横に語るベストセラー。奇跡のように誕生した地球が、核兵器の危機にさらされる現実に警鐘を鳴らす。
推薦コメント
「秩序ある全体としての宇宙」をこれほどおもしろく語る本はありません。高校時代に読んで以来ずっと宇宙や人生と向き合う時の精神的な拠り所になっています。
山崎 展樹(開拓研究本部 上野核分光研究室 専任研究員)
傑作選

『宇宙からの帰還─新版』
- 立花 隆(著)
- 中央公論社 (中公文庫) 2020年
地球の外に出るという体験は宇宙飛行士をどう変えるのか?
170万年も慣れ親しんできた地球の外に出るという、人類史上最も特異な体験をした宇宙飛行士たちは、その内面にどんな変化を起こしたのか。伝道者になった者、ビジネスの世界へ飛び込んだ者、精神に異常を来した者……。元宇宙飛行士たちの内面に鋭く切り込むインタビューによって、宇宙体験の核心に迫る。
傑作選

『人類、宇宙に住む─実現への3つのステップ』
- ミチオ・カク(著)斉藤 隆央(訳)
- NHK出版 2019年
まず月や火星に入植。同時に人体改造。人類生き残り計画
人類はいずれ、地球を後にしなければならないー。自然の脅威や小惑星衝突の危険性、太陽にも寿命がある。さあ、宇宙に移り住む準備をしよう。まずは月と火星に入植し、並行して人体改造……。理論物理学の第一人者が、最新の技術や理論をもとに、宇宙移住の実現に向けて3ステップで解説する。
傑作選

『普及版 数の悪魔─算数・数学が楽しくなる12夜』
- エンツェンスベルガー(著)ベルナー(絵)丘沢 静也(訳)
- 晶文社 2000年
10歳から100歳まで楽しめる数学のワンダーランド
ある夜、数学嫌いの少年・ロバートの夢に小柄な老紳士「数の悪魔」が現れ、12夜のレッスンが始まった。洞窟の中で明かされる素数の秘密、うさぎの数で導かれるフィボナッチ数、サイコロを積み上げて学ぶパスカルの三角形……2人と共に冒険するうちに、数学の創造性に魅了される不思議な物語。

推薦コメント
数の悪魔が毎晩夢の中に現れ、少年に数学の魅力を教えるストーリーです。素数やフィボナッチ数、パスカルの三角形、黄金比などをテーマに、小難しくなく、数と遊ぶ楽しさと不思議さを教えてくれます。小学校高学年の頃に読んで、「問題が解けて嬉しい」という以上の数学の奥深さに目覚めました。
杉浦 拓也(数理創造プログラム 特別研究員)
傑作選
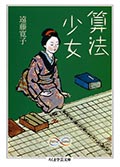
『算法少女』
- 遠藤 寛子(著)
- 筑摩書房 2006年
女の子だって算数が好き!江戸に実在した算法書の物語
安永4年の江戸、父に算法を教わってきた少女あきは、観音さまに奉納されていた算額に誤りを見つけてしまう。それがきっかけで、久留米藩主の姫の算法指南役の声がかかるのだが…。実在する江戸時代の和算書「算法少女」を題材に、一人の少女の姿を通して、日本独自に発展してきた和算の魅力を描き出す。
傑作選

『春宵十話』
- 岡 潔(著)
- 光文社 2006年
明治の数学者・岡 潔が語る「情緒の数学」
数学っておかたい。むずかしい。私たちはそう感じている。しかし、明治の数学者・岡 潔は、情緒の数学を志した。「人の中心は情緒である」と語り、数学は情緒を表現する学問だと考えた。数学は人間の心からくるものであり、体温があるのだ。クールな数学観が反転する名作。

推薦コメント
大きすぎる主語や、思い込みとすら受け取れる強い断定など、現在であれば物議をかもしそうな箇所も散見されます。しかしそれ以上に、異様な熱量と気迫に惹きつけられる文章です。特に、数学の難問を解決したときの心象風景について語るくだりは、まさしく「科学道」にふさわしい内容と言えます。
柚木 克之(生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー)
傑作選

『学問の発見─数学者が語る「考えること・学ぶこと」』
- 広中 平祐(著)
- 講談社 2018年
生きるということはたえず何かを学ぶこと
生きていくことは、何かを創造すること。創造するためには、まず学ばなければならない。では学ぶとはどういうことなのか?「特異点解消の定理」の発見によって、数学界のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞した数学者・広中 平祐が、自らの半生を振り返りながら、学ぶことの大切さを語る。
傑作選
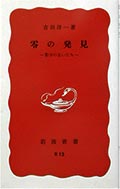
『零の発見─数学の生い立ち』
- 吉田 洋一(著)
- 岩波書店 1979年
もしも「0」がなかったら今の文明は存在しない?
無名のインド人数学者が発見した「0」のおかげで、数学は飛躍的に進歩し、人類の文明にも多大な貢献をもたらした。アラビア数字の誕生から、ピュタゴラスによる三平方の定理、ソロバンやコンピュータなどの計算機の歴史まで。数学嫌いにもなじみの深いトピックに沿って描かれる数学発展史。

推薦コメント
普通は0という数字がイノベーションだと気付きません。それを発見して驚くのが、研究者に必要な力だと思います。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
傑作選

『フラットランド』
- エドウィン・アボット・アボット(著)竹内 薫(訳)アイドゥン・ブユクタシ(写真)
- 講談社 2017年
二次元?四次元?異なる次元はいかにして捉えられるのか
さまざまな図形が平面の中で生活する二次元の国フラットランド。ある日、正方形の「私」のもとに「球」が訪れ三次元の国の存在を告げる―。アインシュタインが四次元を語る30年以上前の1884年に刊行された、次元の本質を捉えた名作物語。

推薦コメント
3次元空間を超えた、多次元空間への想像を掻き立てられます。物理学では我々の住む世界は3次元空間+1次元時間の4次元時空と考えられています。この本を読んでいれば、大学2年生向きの相対論の講義で自分の語り口がだいぶ変わっていただろう、と悔やまれます。
櫻井 博儀(仁科加速器科学研究センター センター長)
傑作選

『フェルマーの最終定理』
- サイモン・シン(著)青木 薫(訳)
- 新潮社 2006年
数学界最大の難問に隠された数学者たちの熱いドラマ
360年間誰も解くことができなかった「フェルマーの最終定理」。町の図書館で数式に出会った少年ワイルズは、人生を数学に捧げ、1995年、ついに完全証明を成し遂げた。サイモン・シンがワイルズへの取材をもとに、3世紀に及ぶ数学者たちの苦闘を描いたノンフィクション。数学はこんなにアツかった。

推薦コメント
360年解けなかった超難問をめぐるノンフィクションです。私のような研究者にも、時に「わかった!」という瞬間が訪れ、幸福感に包まれることがあります。この本では天才数学者ワイルズがフェルマーの最終定理を証明したその瞬間を「言葉にならない美しい瞬間」と振り返ります。そのリアリティは圧巻です。
花栗 哲郎(創発物性科学研究センター 創発物性計測研究チーム チームリーダー)

推薦コメント
研究の過程にはさまざまなドラマがあります。一つの問題にも世界中に競合する研究グループがいて、時々刻々と状況が変わります。科学者は「誰か他の人が先に解決してしまうのではないか」というヒリヒリとした感覚を持ちつつ、楽しみながら研究に没頭しています。このスピード感を一般人に伝えるのはとても難しいことですが、本書は変に脚色することなく、現場の科学者が感じているヒリヒリを伝えてくれます。
園田 翔(革新知能統合研究センター 汎用基盤技術研究グループ 深層学習理論チーム 研究員)
傑作選

『新装版 オイラーの贈物─人類の至宝eiπ=-1を学ぶ』
- 吉田 武(著)
- 東海大学出版会 2010年
目的はただ一つオイラーの公式を理解すること
ファインマンをして「人類の至宝」と言わしめたオイラー公式。その公式を理解することを唯一の目的に、本書はつくられた。パスカルの三角形に始まり、微分積分から三角関数、行列にいたる流れを俯瞰し、数式を解き進める。数学の美の頂点に、ぜひチャレンジしてみて欲しい。

推薦コメント
高校生の頃、大学数学にチャレンジしようと手に取りました。一冊かけてオイラーの公式を理解するために、丁寧に順を追って数式を解説しています。表紙の数式eiπ=-1を初めて見た時、一見関係のない3つの値が並んでシンプルな解になることに驚きました。初めて数学の美しさを学んだ印象的な本です。
磯部 忠明(仁科加速器科学研究センター RI物理研究室 専任研究員)
