科学道100冊 傑作選 76から100
科学道100冊傑作選は、理研が選ぶ「時代を経ても古びない良書100冊」です。理研の研究者や職員にアンケートをして選出した、決定版のラインナップです。
- ※2019年に選定した科学道100冊クラシックス(50冊)をベースに選びなおしました。
- ※推薦コメント、推薦者の所属は、過去のシリーズでの選書時のものです。
傑作選
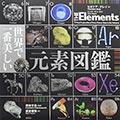
『世界で一番美しい元素図鑑』
- セオドア・グレイ(著)ニック・マン(写真)若林 文高(監修)武井 摩利(訳)
- 創元社 2010年
周期表まるわかり!元素の最強ビジュアル図鑑
水素、ヘリウム、炭素、酸素……なじみある元素でも、その姿かたちは未知の世界だ。自称元素コレクターの著者が、118元素の純粋状態や使用例を集めて写真に収めた博物館のような1冊。きっと身の回りの物質が気になり始める。

推薦コメント
手に取るとズシリと重い。机の上でゆっくりとページをめくり始めると、地球はさまざまな元素で彩られていることが実感できます。「ニホニウムは何色なの?」と園児から質問されたことがあります。この図鑑にニホニウムの写真が掲載されるのは、何年後になるでしょう。
櫻井 博儀(仁科加速器科学研究センター センター長)
傑作選
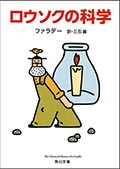
『ロウソクの科学』
- ファラデー(著)三石 巌(訳)
- 角川書店 2012年
1本のロウソクに始まるファラデーの伝説の講演
炎、大気、水、物質。たった一本のロウソクに宇宙の法則がすべてある。19世紀イギリスの大科学者ファラデーが、ロウソクの実験を通して子どもたちに伝える科学と自然と人間との深い関わり。少年少女の心で耳を澄ませたい、クリスマスの夜の特別講演。

推薦コメント
「電磁誘導の法則」を発見した物理学者、マイケル・ファラデー(1791ー1867)が子ども向けのクリスマス・レクチャーで語った内容を本にしたもの。「ロウソクが燃える」ということに関わる深淵な物理現象を説明しています。
仲 真紀子(理化学研究所 理事)
傑作選

『物理学とは何だろうか(上)』
- 朝永 振一郎(著)
- 岩波書店 1979年
星を見つめることから物理学の歴史は始まった
近代物理学は占星術や錬金術などから生まれた。占星術を天文学に発展させたケプラー、「実験」という方法を導入したガリレオ、錬金術から化学を育てたボイル、万有引力を発見したニュートン……。ノーベル賞受賞者の朝永 振一郎が、物理学の歴史を振り返りながら、科学が進むべき未来を展望する。

推薦コメント
湯川さんの終生のライバルである朝永 振一郎さんが物理学の歴史を解いたのがこの本。名著です。
初田 哲男(数理創造プログラム プログラムディレクター)
傑作選

『だれが原子をみたか』
- 江沢 洋(著)
- 岩波書店 2013年
古代から想像されてきた「原子」が発見されるまで
「原子」は存在するのか?アリストテレスの時代から、アインシュタインが登場するまで、原子の存在をめぐる論争は長い間続いてきた。科学者たちによる仮説と実験の繰り返しの歴史を辿り、実験を再現。その苦難の道を追体験する。
傑作選

『光と電磁気─ファラデーとマクスウェルが考えたこと─電場とは何か?磁場とは何か?』
- 小山 慶太(著)
- 講談社 2016年
苦労人の実験家と天才の理論家対照的な二人の連携プレー
鍛冶職人の家に生まれ、独学による実験を続けて科学者として大成したファラデー。有産階級出身で、ケンブリッジ大学を卒業し天賦の才に恵まれたマクスウェル。実験家と理論家という、19世紀を代表する対照的な二人の科学者の連携によって、電磁気学が大きく発展していく過程を追う。
傑作選

『量子革命:アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突』
- マンジット・クマール(著)青木 薫(訳)
- 新潮社 2017年
「量子」の解釈をめぐる直接対決物理学を進展させた巨人たち
スマホから核兵器まで、現代のテクノロジーの源にある量子力学。20世紀初頭、この新しい物理学の解釈をめぐり、アインシュタインとボーアは論争を繰り広げた。ふたりを軸にハイゼンベルク、シュレーディンガーなど天才たちが織りなすドラマ。量子論の100年を追うノンフィクション。

推薦コメント
2025年に誕生100周年を迎える量子力学。量子力学の発見は、それ以前の物理学と人間の日常感覚を大きく覆すような出来事でした。本書からは、その基礎理論がまさに革命的に打ち立てられていく様子が、熱く伝わってきます。科学の発展に人々の対話とその背景となる社会が重要であることは今も昔も変わりません。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)

推薦コメント
近年、量子コンピューターへの期待が高まっています。2023年のノーベル化学賞「量子ドット」など「量子」を冠する先端技術が、社会に浸透してきました。本書は、ニュートン力学を覆す「量子」という概念が100年以上前に生まれ、発展してきた歴史を物理学者らの人間ドラマとして描き出しています。
伊藤 嘉浩(開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室 主任研究員)
傑作選

『不思議の国のトムキンス〈復刻版〉』
- ジョージ・ガモフ(著)伏見 康治(訳)
- 白揚社 2016年
トムキンス氏と旅する相対性理論のヘンテコな世界
銀行員トムキンス氏は、相対性理論の講演を聞きながらウトウト…。すると世界は一変していた。速度を上げると体が平べったくなる「のろい町」、1匹の動物が何十匹にも広がって見える「量子ジャングル」。ロシアの物理学者ガモフが相対性理論と量子論を物語に仕立てた。アインシュタインも読んだ不思議の国のお話。
傑作選

『部分と全体 新装版─私の生涯の偉大な出会いと対話』
- W.ハイゼンベルク(著)山崎 和夫(訳)
- みすず書房 1999年
ハイゼンベルク本人が描く量子力学を生んだ対話の数々
「科学は対話の中でこそ生まれる」とハイゼンベルクは言う。対話の相手は、アインシュタイン、ボーア、シュレティンガーなど、科学界の巨星たち。2度の大戦を経験しながら、著者がいかに暮らし、どんな討論によって思索を深めたのか。量子力学の生みの親が若き日々を振り返る。

推薦コメント
量子物理学に「不確定性原理」を提唱した20世紀の代表的物理学者ハイデンベルグの自伝著作です。数々の物理学者との交流を通じ、その思索を深めるとともに、日常を含め当時の社会状況などが語られています。
伊藤 嘉浩(開拓研究本部 伊藤ナノ医工学研究室 主任研究員)

推薦コメント
著者ハイゼンベルクによる序文が特に素晴らしいです。「科学は人間によってつくられるものであります」という一文で始まり、「科学は討論の中から生まれるもの」と、科学の核心には討論(対話)があることを強調しています。本編中でも、実験結果の解釈をめぐって討論する量子力学建設期の物理学者たちの様子が、イキイキと描かれています。
柚木 克之(生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー)
傑作選

『新版─自然界における左と右(上)(下)』
- マーティン・ガードナー(著)坪井 忠二、藤井 昭彦、小島 弘(訳)
- 筑摩書房 2021年
鏡はなぜ上下ではなく左右が逆?宇宙人に左右を教えられるか?
宇宙は根本的に対称性があるのか。鏡に映った像の左右の反転から説き起こし、右利きと左利き、カノンや回文といった芸術における対称性、分子の世界や銀河系、物理学における対称性の破れ、さらには時間の流れまで、自然界のありとあらゆるテーマを取り上げながら、対称性と非対称性の不思議に迫る。
傑作選

『ねじとねじ回し─この千年で最高の発明をめぐる物語』
- ヴィトルト・リプチンスキ(著)春日井 晶子(訳)
- 早川書房 2010年
ねじとねじ回しがなかったら科学も経済も遅れていた!?
この1000年で最大の発明はねじであると著者は言う。蛇口から携帯電話、ペットボトルのふたまで、ねじがなければ生まれなかった。古代ギリシアから用いられていた回転と螺旋の工学。日用品を見る目がガラリと変わる物語。
傑作選
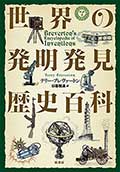
『世界の発明発見歴史百科』
- テリー・ブレヴァートン(著)日暮 雅通(訳)
- 原書房 2015年
先史時代から21世紀まで人類史の重要発見&発明300
260万年前の石のナイフから、原子論、印刷術、蒸気機関、クローン化技術、ウィキペディアまで。生活を一変させ常識を覆した重要な発明・発見300項目を年代順に紹介した事典。ボタンホールや絆創膏、水洗トイレ、鉛筆、歯磨き粉など、身近なものの発明秘話も楽しい。
傑作選
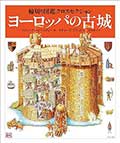
『輪切り図鑑クロスセクション(1)~(5)』
- スティーブン・ビースティー(画)リチャード・プラット(文)赤尾 秀子、宮坂 宏美(訳)
- あすなろ書房 2021年
構造が知りたい!なら、輪切りにしちゃおう。
中はどうなっているのかな?宇宙ステーションから、グランドキャオン、ヨーロッパの古城、帆船軍艦、人体、さらには入れ歯やかつらまで。なんでも輪切りにしたら、構造がまるわかり!細かく書き込まれたイラストに見入るうちに、工学センスが磨かれる。大人も子供もハマる大判図鑑。
傑作選
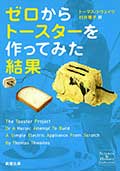
『ゼロからトースターを作ってみた結果』
- トーマス・トウェイツ(著)村井 理子(訳)
- 新潮社 2015年
毎朝パンを焼くトースターは一体どこから来たのか?
トースターをゼロから、すなわち原材料から作ろうと決意した著者。鉄を入手するために鉱山へ行き、ミネラル・ウォーターから銅を抽出し、ニッケルを作るために硬貨を溶かす……。苦闘ののちに完成したものは?ありふれた電化製品が多大な労力と歴史の上にあることを、ユーモアたっぷりに教えてくれる本。
傑作選

『眼の冒険─デザインの道具箱』
- 松田 行正(著)
- 筑摩書房 2021年
「なんとなく似ている」が大発見のきっかけになる!
つむじ、星雲、素粒子の飛跡、ヒナギクの配列図……これらの共通点は?写真を並べると一目瞭然、ぐるぐる渦巻きの形がそっくりだ。「似ている」は科学や物理の発見のきっかけにも大きく作用している。大量の図版から「かたち」と「視線」を探索し、私たちの図像的思考を大胆に開いてくれる1冊。

推薦コメント
点や線、図形、色彩、陰影など、視覚を刺激するさまざまなアイテムがどのように人間を人間たらしめ我々の思考やイメージを左右するのか、縦横無尽に語った痛快な1冊。話はとどまるところを知らず、視覚論、デザイン論から歴史、政治、映画、小説、アニメやオタク文化に至ります。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
傑作選

『ニコラ・テスラ 秘密の告白─世界システム=私の履歴書 フリーエネルギー=真空中の宇宙』
- ニコラ・テスラ(著)宮本 寿代(訳)
- 成甲書房 2013年
エジソンのライバル天才発明家の自伝的告白
電気の交流誘導モーターを発明し、エジソンのライバルと呼ばれたニコラ・テスラ。天才を形成したのは、幼少期の奇妙な体験や病との戦いだった。やがて探究は地球や人類自体のエネルギー利用へと発展する。彼はどのように発想し、未来を予想したのか。本人の回顧録から脳内を覗き見る。
傑作選

『ウィーナー サイバネティックス─動物と機械における制御と通信』
- ノーバート・ウィーナー(著)池原 止戈夫、彌永 昌
- 岩波書店 2011年
サイバネティックスという新しい学問領域を生み出した書
足を動かす、コップに手を伸ばして水を飲む。数学者ウィーナーは、こんな単純な動作にも、複雑な制御の仕組みが働いているのだと考えた。心の動きや、社会までをダイナミックな制御システムとして捉え、20世紀後半の科学技術に多大な影響を与えた書。人工知能や認知科学、非線形科学の研究の基礎になった。1948年初版刊行。
傑作選

『システムの科学 第3版』
- ハーバート・A・サイモン(著)稲葉 元吉、吉原 英樹(訳)
- パーソナルメディア 1999年
ノーベル経済学賞受賞者が探る人工物の本質と可能性
自然や社会といった複雑な外部環境のなかで、自らの目的を達成するために、人間はさまざまな人工物をつくってきた。本書では、飛行機やコンピュータのようなモノから、経済や企業のような社会組織までを、人間が設計した「人工システム」として捉え、その本質を探る。
傑作選
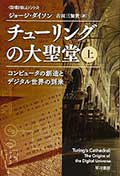
『チューリングの大聖堂─コンピュータの創造とデジタル世界の到来(上)(下)』
- ジョージ・ダイソン(著)吉田 三知世(訳)
- 早川書房 2013年
チューリングが生み出したデジタル宇宙の創造神話
1936年にチューリングによって構想された万能の電子計算機。フォン・ノイマンはどのようにしてそれを実現したのか。数学者が研究に没頭できる楽園として設立されたプリンストンの高等研究所で、理論上の存在だったコンピュータが生み出され、現在に連なるデジタル宇宙が創造されていく歴史を克明に辿る。
傑作選

『暗号解読(上)(下)』
- サイモン・シン(著)青木 薫(訳)
- 新潮社 2007年
作成者と解読者の生存競争暗号をめぐる知のバトル
スコットランド女王の暗号手紙は読み解かれ、彼女は処刑された。最強と言われたドイツ軍の暗号は天才の努力の末に破られた。情報ネットワーク時代、さらに強力な暗号技術が必要とされている。『フェルマーの最終定理』のサイモン・シンが取材した暗号の歴史と未来。実際の暗号を多数掲載、解読に挑戦してみよう。

推薦コメント
腕利きのサイエンスライター、サイモン・シンが描く暗号技術の歴史。暗号は一見地味な分野ですが、実は情報科学の最先端で、インターネットの安全も支えている重要なテクノロジーです。最後の章は、来たる量子コンピュータ時代の暗号について。自身の研究とも関わりが深く夢中で読みました。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
傑作選

『レンブラントの身震い』
- マーカス・デュ・ソートイ(著)冨永 星(訳)
- 新潮社 2020年
アルゴリズムの進化でAIは芸術家や数学者になるのか?
2016年にお披露目されたレンブラントの新作絵画。AIが18ヶ月間データを食らい、500時間かけて描いた作品だ。深層学習によりアートや音楽、数学などでも創造性を発揮しだしたAI。危機感をもった数学者が、研究の最前線を探訪する。AI進化の鍵を握るアルゴリズムのいろはがわかる1冊。

推薦コメント
AIは本格的に創造性を発揮できるようになってきました。著者は数学者ですが、数学の研究もAIに取って代わられるようになるのではないかと危機感を覚え、AIと人間の創造性についての探究を綴った本です。AIの部品となる技術には実は100年以上の歴史があります。そこにしっかりと踏み込みながら、現代のAI開発者にもたくさん取材をして書かれているので、AIの研究者としても読み応えを感じました。
園田 翔(革新知能統合研究センター 汎用基盤技術研究グループ 深層学習理論チーム 研究員)
傑作選
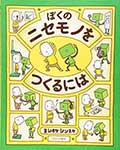
『ぼくのニセモノをつくるには』
- ヨシタケ シンスケ(著)
- ブロンズ新社 2014年
「ぼくのすべて」を伝えるにはどう説明したらいい?
「ロボットにぼくのニセモノとして、宿題やお手伝いをやってもらおう!」。ロボットに自分のことを教え始めるけんた君。でもいくら説明してもしきれない。学校や家での役目は違うし、日によっても気分が変わる。「情報としての自分」の複雑さに気付く発想絵本。

推薦コメント
自分が好きなこと、得意なこと、苦手なこと……。大人になっても繰り返し自問自答します。人生は選択の連続と言いますが、その都度、自分に何ができるか、何がしたいかを決定し、人生を歩んでいきます。選択しなかった方に後悔が残らないよう、そして選択した方に自信を持って進んでいけるように、この本のけんたくんをお手本にして自分をとことん見つめてみよう。
長壁 早弥子(革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 遺伝統計学チーム テクニカルスタッフⅡ)
傑作選

『FACTFULNESS─10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』
- ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド(著)上杉 周作、関 美和(訳)
- 日経BP社 2019年
世界はどんどん悪くなっている?それも思い込みの一つ。
低所得国の女子は初等教育を終えられない?世界中の1才児で予防接種を受けているのは何%?大学教授も政治家もジャーナリストも間違える。私たちは「世界の今」を理解しているつもりで、思い込みに囚われているのだ。データに基づいて世界を正しく認識するための方法を教える話題の書。

推薦コメント
「人間には10種類の認知の偏り(バイアス)が備わっており、それによって世界が歪んで見えている」と書いてあります。試しに、この本の最初に載っている現代の世界に関する13問の3択クイズをやってみてください。多くの人は3分の1以下しか正解できないという触れ込みで、私も実際そうでした。単に知識が無いだけなら、3択クイズなので3分の1は正解できるはずです。にもかかわらずそれ以下の結果になるのは、現代の世界についての知識が無いからではなく、バイアスがあるため間違えていることを意味します。バイアスがどのようなものかを知り、事実やデータに即して世界を見る目を養うのに最適な本です。一過性のベストセラーではなく、未来の古典になりうる1冊です。
柚木 克之(生命医科学研究センター 統合細胞システム研究チーム チームリーダー)
傑作選

『ほしのはじまり─決定版 星 新一ショートショート』
- 星 新一(著)新井 素子(編)
- 角川書店 2007年
星新一の描く未来は50年以上経っても古びない
科学者の幼い頃の愛読書としてよく名が挙がる星 新一。SFを中心に1000編を超える作品を執筆した、ショートショートの神様だ。バーで働く美人ロボットを描いた「ボッコちゃん」、平和な休日に突然恐竜が出現する「午後の恐竜」など、星チルドレンの作家・新井 素子が選び抜いた54篇を収録した保存版。

推薦コメント
小学生の頃、星 新一のショートショートに夢中になりました。今読んでも古くならないおもしろさがありますね。
鈴木 千歳(バトンゾーン研究推進プログラム 人工ワクチン研究チーム テクニカルスタッフ)
傑作選
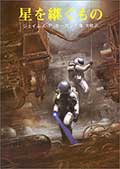
『星を継ぐもの』
- ジェイムズ・P・ホーガン(著)池央 耿(訳)
- 東京創元社 1980年
5万年前の月面に人が?宇宙と人類の謎に迫るSF
月面で宇宙服を着た死体が発見された。調査の結果、彼は5万年前に死亡していたことが分かる。地球が旧石器時代だった頃、月面を闊歩していた人間とは一体何者か?月や地球との関係は?突如現れた巨大な謎に、研究者たちが果敢に挑む。宇宙スケールで人類の起源を冒険する、ハードSF。

推薦コメント
月で5万年前の人の遺体が発見されたという所から始まるSFです。大胆な謎解きに引き込まれました。
杉浦 拓也(数理創造プログラム 特別研究員)
傑作選

『空想科学読本(1)~(3)』
- 柳田 理科雄(著)
- KADOKAWA 2022年
ドラえもんのタケコプターで実際に空を飛べるのか?
漫画やアニメの世界で普通に起こっていることを、科学で真面目に解釈してみよう!宇宙戦艦ヤマトの29万6千光年の旅を相対性理論で考えると?ウルトラマンはなぜ最初からスペシウム光線を撃たないのか?小さなモンスターボールにポケモンが入れるのはなぜ?楽しみながら科学への好奇心が芽生える本。

推薦コメント
小学生の頃にゲラゲラ笑いながら読んでいました。誰もがよく知るSFを題材として、真面目に定式化・考察し、笑える結論を導くというのが面白かったわけですが、今思えば現象を定式化するという科学の基本姿勢をこの本から学んだような気がします。
園田 翔(革新知能統合研究センター 汎用基盤技術研究グループ 深層学習理論チーム 研究員)
