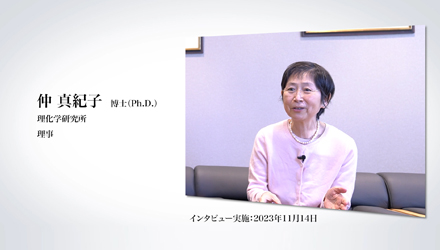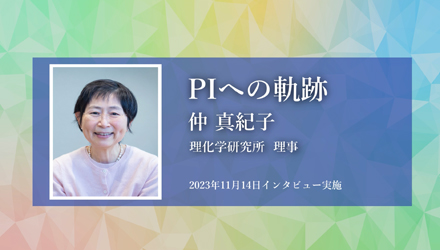準備と出会いで紡いだキャリアと研究室運営
仲 真紀子 理化学研究所 理事(Ph.D.)
(インタビュー当時)
略歴
| 1979年 | お茶の水女子大学 教育学部 教育学科心理学専攻 卒業 |
| 1981年 | お茶の水女子大学 大学院人文科学研究科 心理学専攻 修士課程 修了 |
| 1984年 | お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 人間発達学専攻 博士課程 退学 |
| 1984年 | お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 助手 |
| 1987年 | 学術博士(お茶の水女子大学)取得 |
| 1987年 | 千葉大学 教育学部 講師 |
| 1989年 | 千葉大学 教育学部 助教授 |
| 1990年 | Duke大学(アメリカ合衆国)客員教員 |
| 1999年 | 東京都立大学人文学部 助教授 |
| 2003年 | 北海道大学大学院 文学研究科 人間システム科学専攻 教授 |
| 2017年 | 立命館大学 総合心理学部 教授 |
| 2017年―現在 | 北海道大学 名誉教授 |
| 2021年 | 立命館大学 OIC総合研究機構 教授 |
| 2022年―現在 | 立命館大学 OIC総合研究機構 招聘研究教員(教授) |
| 2022年―2024年 | 理化学研究所 理事 |
| 2025年― | 人間環境大学 教授 |
| 2025年― | 理化学研究所 理事長特別補佐 |
プロジェクト説明
足立:このプロジェクトは前理事の原山先生のご縁があって、Elsevier Foundationに声をかけていただいて、理研に縁のある先生方にお話を伺っていくプロジェクトです。主に研究の内容ではなくて、研究室のマネージメントですとか、若手の方に参考になるようなリーダーシップの取り方などを伺えればと思いますので、よろしくお願いします。
仲:よろしくお願いします。
博士後期課程修了時のキャリアビジョン
足立:仲先生は、1984年にお茶の水女子大学の博士後期課程を修了されて、すぐにお茶の水女子大学の助手になられたのですか。
仲:その通りです。
足立:博士号の取得は1987年ということなので、博士論文を書きながら助手をされていた形でしょうか。
仲:そうです。
足立:その時に、仲先生ご自身はご自分のキャリアをどのように考えていらっしゃいましたか。
仲:私は人文社会の心理学が専門なので、当時はあまり博士号を取るということもなかったんですよね。そもそも大学院の博士課程ができたのも、私が修士を出る少し前ぐらいだったんです。なので、先行きがよく分からないような状態でした。修士課程の時は本当に自分がどういうふうになるのか、みんな他の人達は仕事をして働いているのに、自分だけなんかこうお勉強みたいなのをしていていいんだろうか、と少し鬱々としていました。博士課程に入ってからはもういいや、自分でミニ博士になったという気持ちになろうと切り替えて、科学者への道と自分で勝手に決めて思っていました。就職できるかできないかも全然関係なく、もう自分はミニ科学者だと思っていた。そういう意味では未来への見通しもなく、そう思い込んでいた感じかなと思います。博士課程を修了して、その時はまだ博士論文を書いてないんですけれど、助手のポストをいただいた。ちょうどその年に子どもが生まれたので、なんというか、新しい研究ができるような環境ではなかったです。ちょっと後ろ向きの仕事かなぁなんて思いながら、子育てをしながら、助手の仕事をしながら、学位論文をまとめました。まとめるのはちょっと過去の研究をまとめるみたいな形になるでしょう。なので、過去向きの仕事をしていたという感じでした。
足立:助手の時代は、博士論文のスーパーバイザー(指導教員)の研究室でお手伝いをしながら、ご自分の論文も書いていたという形ですか。
仲:そこがですね、人文社会系の少し特殊なところかもしれないんですけど、比較的みんな1人ひとりがやっていくという感じなんです。そして、時々指導教員の研究室を訪ねて、「こんなふうなことを考えているんですけど」とか、「ちょっとここ悩んじゃってるんですけど」とかって言って話し合いをしてもらって、なんかすっきりして、また続きをやるみたいな感じだったんですよね。だからラボに属して、そこにずっと籠ってとかではなくて、自分の家が研究室のようでした。前住んでいた所も、勝手に自分のアパートを「仲ラボ」とつけて、自分の研究室みたいに思っていました。指導教員の指導を受けながら自分で進めていた、そんな感じです。はい。
博士号を取得して、千葉大学へ
足立:1987年の3月にドクターを取られて、千葉大学に就職されたということですね。
仲:そうです、そうです。就職して、その年くらいに学位が出たという感じ。だから、ちょっとみんな(順番が)逆ですね。
足立:関東周辺で就職活動をされたのですか。
仲:ああ、そうでもない。まあそうね、結果的にはそうなってしまったんですけど。確かに夫も関東にいて、親もその頃は千葉にいたので、なんとなく関東周辺の所の公募に応募してました。
足立:並行していくつかの所にアプライ(応募)しながら千葉大に?
仲:千葉大に決まったという感じですね。そう。先輩が、「出すもんだ」と教えてくれたので、何件かあたって、ダメダメ、ダメみたいな(いくつか不合格になった)状況で、でも千葉大で採ってくれました。
足立:最初の2年間は講師で、その後助教授になられて、合計12年千葉大にいらっしゃったことをCV(履歴書)から拝見してるんですが、その時はどのような形で研究を進められていたんですか。
仲:学位論文を出して、学位を取って、千葉大に行ったら学生さんがいて、卒論指導などをしなくてはいけない、ゼミ運営が始まったところかなと思います。理科系・自然科学系とは違って、みんな学生さん個人個人で研究するので、週に1回とか2回とかゼミを持って、それぞれの進行状況を聞いたりアドバイスしたりとか、そういう感じのゼミ運営だったです。それをずっと12年間続けてきて、その中でなんとなく私の研究の関心も、自然文脈の中での記憶というような(方向になりました)。例えば、手を動かして書いて覚えるとよく記憶に残るのかとか、あるいは普通に行う会話の記憶ってどんな記憶なのかとか。子どもが過去の体験を親御さんとかに話したりしますが、その話す内容はどんなものなのかとか、どんな会話が行われるのかとか。まあ本当に好きなことをテーマに自分でも研究しながら、学生さんと一緒にやれるところはやって、という感じだったですかね。
自分の研究室を構えて
足立:そうすると、理研で言ういわゆるPIの立場、千葉大の講師の時はもう独立して研究室を持たれたというイメージでしたか?
仲:まあそういうことになりますね。当時はPIとは思ってなかったけれども、そういうことになりますね。
足立:博士号を取得されて、プロの研究者として独立されて、その時に何かギャップなどを感じたことはありますか。
仲:そもそも大体研究が自分単位の、1人でやっていかなくちゃいけない、1人でやることが主だったので、学生さんと一緒にやっていくのは初めてでした。また、教育もしなくてはいけないわけで、当然ながら。教えるというのも、教え方を教わってきたわけではなかったので、1つひとつ新しいことだったなと思いますね。
足立:その新しいことに挑戦する時に、仲先生はどのようなことを準備されましたか。
仲:もう行き当たりばったりで、必要なことをやってきたっていう感じです。面白いことは、やっぱりすごく面白いので、寝ても覚めてもみたいなところがあります。そうね、楽しんでいろんな(ことをしました)。学生さんがまた新しいアイデアとかも持ってくるものだから、それにこっちものめり込んだりしながら進めてきたように思います。特段見通しがあってこれをやっていくのではなくて、たまたまぶち当たった面白いこととか、たまたまぶち当たった大変難しいことなどをなんとなく乗り越えてきたみたい。乗り越えてもないかもね。なんとかやってきたという感じだと思います。
足立:千葉大時代、先生のゼミの人数、学生さんはどのくらいいらっしゃったんですか。
仲:学生の数が決まっていて、それを教員の数で割るので、大体10人くらいだったかなと思います。教育学部だったので、ほとんどが教員志望の方達でした。さっき言ったような、書いて覚えると覚えられるかとか、会話の記憶とか、例えば自分が卒業した中学校のキャンパスをどれくらい後で思い出すことができるかとか、いろいろ学生さんは素朴に考えて持ってくるんだけれども、先行研究などを調べてみると、結構いろいろ面白い研究が周辺にあって、楽しんでやっていました。
足立:ゼミの構成は、学部の学生さんがメインでしたか。
仲:そう。学部と、修士課程ができて修士の学生さんも少しいたけれども、大体は教員を目指すとか、公務員を目指すとか。もちろん企業に行った方もいます。ドクターの学生は(千葉大時代の)最後の方で(指導しました)。千葉大は総合大学院という自然科学系の工学部とかと一緒になって大学院ができて、そこの教員に私はなりました。だから千葉大にいる間の終わりの方までは博士の学生はいなかったんです。
足立:ポスドクや研究員の方を、先生の研究室で採られたことはありましたか。
仲:いや、それも。その自然科学系の大学院ができて、私もそこの教員になって、その頃には何人か博士の学生もできました。あとは研究員となる方とか、海外から(私の)研究室にサバティカル(研究専念期間)で行きたいと仰る方がいらしたりして、なんとなく自然科学系のような感じの研究室になってきました。それは最後の4~5年くらいだったかなと思います。
足立:1990年前後の教育学部教育心理学教室の1つの研究室ということでお話を伺っていたんですけれども、学部の学生さんが主体ですと、先生の論文として出す時は学部学生さんから刺激を受けながら、先生の興味で論文を書く感じでしょうか。
仲:ほぼほぼそうですね。学生さんが行った研究をそのまま研究として報告するのは、学会発表で彼女や彼が主になって私が副になって学会報告することはあったのですが、論文を書くことはほぼなかったです。私が再度データを取って書くとか、そんな感じだったと思います。
足立:学部だけでは時間が足りないとか、そういう形になってしまうので、先生が興味のある部分を深めて、論文にされたのでしょうか。
仲:そうですね。自分がやっている研究の一部の、こういうのでちょっと応用して、ここのこの条件でやってみたら、みたいなのがあったかなと思います。
在外研究でデューク大学に
足立:そして、千葉大学にいらっしゃる間に、1年間デューク大学に在外研究という形で行かれたのですか。
仲:そうです、そうです。
足立:それのきっかけを教えていただけますか。
仲:87年に千葉大に行って、2年くらい経ったところでその案内が来て、応募できると知ったわけです。若手在外と言います。なんかむらむらっと行ってみたいなと思って応募しました。同じその教室、教室とその頃は言っていたのですが、研究講座の他の先生に「きっと通らないと思うから、出させてもらってもいいかな」と言ったら、周りが「え~、本当に通らないんだったらいいよ」とか言われる、という感じで出させてもらいました。そしたら通っちゃったんですよね。周りの人からは「まだ2年目、3年目なのにちょっと早すぎない?」とも言われましたが、もう「せっかくのチャンスだから」とか言って出かけたんです、1年間。自分にとってはとても刺激になったし、大きな新しいテーマに出会うチャンスになったなっていうふうに思います。
足立:以前から海外に挑戦したいと思われていたのですか。
仲:いや、そういうわけではなかったです。高校の時に1年留学していたことがあって、そこでもうどっぷり浸かりすぎてて、もう海外はいいかなという感じで日本に帰ってきていたので、あまり行く気もなかったんです。それからかれこれ10、20年ぐらい経っていたと思うんですね、帰ってきてから。そこまでは経ってないか。17~18年。なんかちょっとまた行ってみたいかなとその時は思ったんですよね。でも、子どもがいるからどうしようかなとか、アメリカも結構治安が悪いかもしれないしなあとも思った。どうしようかと悩み、父にアメリカの話もしないで、「何もしないで後悔するよりは、何かして後悔した方がいいよね」と言ったら、父が「う~ん、そうだよね」と言ったから、もうそれで行くことに決めたんですよね。どっちに転んでも後悔するかもとか思いながら行ってみたら、本当に楽しかったです。
足立:いろいろ周りにも配慮をされながら、でも最後はご自分の希望を通されたように伺ったのですが、周りに配慮しすぎて諦めてしまう人もいたりする中、どのように調整しましたか。
仲:いや、本当は配慮してなかった。「通らないと思うけど出させてね」と言って、通っちゃったでしょ。そしたら周りからも「通らないって言ってたじゃない」、「ちょっと早すぎるんじゃない?」など言われたのに、もうね、なんかね、「行くもんね!」みたいな気持ちになった。双子の子どもがいるので、夫も、「じゃあ、1人自分の所に置いて、1人だけ連れて行くか。2人共連れて行くんだったら、離婚は覚悟だな」と言われて、う~んとか思ったんだけど、まぁ気も変わるかもと思って出かけたんですよね。日本でも保育園に入れていたのですが、その時のアメリカのシステムは大変簡単で、連れて行ったその日から学校に子どもも行ける感じになっていて、ありがたかった。夫も最初はそんなこと言っていたんですが、1年の間に3~4回遊びに来たりして、まんざらでもなかったのかなと思いました。もうなんかドボンって行けそうな時は、後からきっといろいろついてくると思って、行った方がいいですよ、と周りには言いたいですね。
足立:海外でそのまま職を見つけようとは思いませんでしたか。
仲:それはなかったです。本当に1年の留学基金と言いますか、滞在基金をもらって行ったので、(期間が終われば)帰ってくる。その時のビザは、行って帰って、(行く前の職場に戻って)少し(の期間は以前の立場で)仕事をしなくてはいけなかった。何かちょっと思い違いかもしれないんですけれども。いずれにしても、向こうで就職とか留まるとかいうことは全く考えないで、戻ってきて続きをやるつもりでした。向こうで本当にいろいろな自然文脈の中での記憶という研究に触れることもできて、帰ってきたらすぐに目撃証言の研究に出会うことができて、その後の20年、30年、自分にとっての研究の方向性を大きく変えたなっていうふうに思います。
新しい研究テーマとの出会い
足立:今、目撃証言の研究に出会われたということでしたけれども、その出会いは仲先生から自ら取りに行ったものか、たまたま来たものなのか、どうでしょう?
仲:そこはやっぱり両方とも。いろいろな目撃研究も面白いなと思って、いっぱい(論文を読んでいました)。当時は電子ジャーナルがほぼない時代で、いっぱいデュークの図書館で論文をコピーして、もうこんなに持って帰ってきて、すごい楽しみに読んでから、また(やりたい)って思っていました。たまたまある弁護士さんからお手紙が来て、「これこれこういうような事案で、目撃証言は正確なのか知りたい。ついてはこういう研究に協力してもらえないか。」というような、皆に多分出したお手紙が(私の所にも)来ました。それを見て私はたまたま、自分もこうやって論文を集めてきていたので、「こういう研究もある、ああいう研究もある」と送って差し上げたんですよね。この弁護士さんから見ると、いっぱいお手紙を出したけど、そういう返事をくれた人は本当に少なかったようです。それで、研究協力の依頼をいただいたことがありました。本当にリアルな目撃証言なので、私ものめり込んだみたいな感じなんです。だから、準備もあったけど、声をかけてくださったのは向こうっていう感じですかね。
足立:お手紙で本当に初めて知った方と、その後もう何十年にも渡る協力をされたのですか。
仲:そうですね。本当そう。2000年にはみんなで、そこら辺の仲間と一緒に学会を立ち上げて、それが法と心理学会になっていったので、いろいろな所に出会いとかあるもんだと思います。
東京都立大へ
足立:デューク大から帰られても引き続き千葉大で助教授をされて、1999年に首都大※転出されましたが、何かきっかけがありましたか。
仲:だんだん教育学部も、より教育実践的なことを教えなくちゃいけないみたいになり、私もプロパー(心理学専攻の学生対象の)心理学というよりは教育相談とか、そういう科目が当たるようになってきていました。ちょっと今までやってきたことと違うなと思っていたところ、たまたま都立大で自然環境での認知のようなことを研究されていた方が呼んでくださったんだったかな。お声をかけていただいて、異動しました。
足立:そうすると、ご自分であちこちにアプライされていたわけではなく?
仲:なく。そうなんです。
足立:首都大学では千葉大と似たような感じで、ゼミを学部生中心に行われていたのですか。
仲:都立大は以前から博士課程があって、個人個人の研究室があって、理科系的な感じでした。千葉大はさっき言ったような総合大学院でしたが、そうではなくて心理学(部)の中に研究室があった。だから私も前任の教員の学生だった(博士課程の)大学院生2名と、修士課程の学生を引き継いだりして、研究してきた。4年だったんですけどね。そこでも、また新たないろいろな体験をして面白かったです。
足立:研究者の卵である大学院生を、そこで本格的に指導をするような経験を積まれたのですか。
仲:そうですね。学生と一緒に論文を書くのは、そこからだったと思います。うん。
足立:ご自身だけで書くのではなく、学生さんを巻き込みつつ書くという面ではいかがでしたか。
仲:そういうスタイルになっていく。
足立:そこに難しさとか工夫をした点とかありましたか。
仲:そうですね。都立大(にいた期間は)短くて、都立大から北大に移った時も何人か、都立大から北大に来てくださいました。その辺りから大学院生指導が始まったんですけれども、私も最初はちゃんと分かってない部分もあった。どこまで口出しをしていいものかとか、言ってたことを後でちょっと思い違いというか、その思いを変えたり。「やっぱりこうやった方がいいんじゃない?ああやった方がいいんじゃない?」とかいろいろ言って混乱させたりしました。1人でやればそういう問題はないと思うんですが、やはり共同で院生を指導しながらやっていくのは難しいなと思いつつ、でした。でも楽しいこともね、いっぱいあったっという感じです。
- ※東京都立大学は2005年に「首都大学東京」の名称にて再編・統合。2020年に「東京都立大学」に名称変更。
北海道大学へ
足立:都立大で4年間過ごされた後、北大に転出されましたが、そのきっかけはなんでしょうか。
仲:都立大に移って2年目か3年目に、私に声をかけてくださって「北大に来ませんか」と言われたんだけど、まだその時は、都立大に慣れている最中ぐらいのところで行けなかったんです。そうこうしているうちに、夫が関東から九州の九産大という大学に移って、なんかもう離れ離れになっちゃったなと思いました。それだったら、もうどこに住んでもいいな、となった。都立大も大変楽しくて良かったんですが、北大もちょっと行ってみたいかなと思って行ってみました。
足立:北大で教授になられましたが、助教授から教授になった時に何か変わったことはありましたか。
仲:確かにそうですね、都立大の時は助教授でした。私はその時までは講師も助教授も教授も、なんと言うか、違いを感じない、全然こだわらなかったです。教授になるのは結構大変だったりもするんだとか思っていた頃、北大では教授としてのポストだったから、ちょっと行ってみてもいいかなと思ったんです。何が違ったかと言うと、あまり違わなかったです。でも教授会に行ったら、北大は100人ぐらい教員がいる中で女性の教授は多分、私ともう1人の先生だけでした。大変女性比率が低かった。都立大は、もっともっとたくさん女性教員がいて、同じ学科の中にも3人、半分はいないけど4割ぐらいは女性だったので、なんと言うか、おおっ!てちょっと思いましたね。
足立:北大までは、本当にバリバリ文系の学部の中で過ごされていて、千葉大の最後の方に、ちょっと理系、工学と混じったようなご経験をされていたと伺いましたが、そこで何か違いがありましたか。大学ごとの心理学の位置づけ、教育学部の中にあったり、文学部の中にあったり、工学系とか学際領域にあったりとか。
仲:ああ、そこはね、あんまり感じなくて。千葉大の時は本当に学部生と一緒にゼミという感じで、最後は自然科学系の組織に入った。都立大は人文科学部って言ったかな、あの時は。研究実験室と個人の研究室があって、そういう意味では少し理科系的な感じだったかなと思います。北大に移ったら、私の前にいた方が生理学的な研究をされる方で、私が実験室としてあてがわれた部屋は、「前は動物が飼われていて、ちょっとまだ匂うんですよ。」と言われて、匂いをなくすところから始めるような感じでした。より自然科学的な環境になったように思います。でも、やっている研究自体が変わったわけではないです。複数実験室もいただいて、そこで実験して、論文を書く、そんな体制でした。
足立:北大の研究室はどのような構成で、何人くらいいらっしゃいましたか。
仲:年度によって違うのですが、大学院大学になっていたので、博士の学生が何人かと、修士の学生が何人かで、そんなに多くないです。2~3人ずつとか、3~4人ずつとかで、学部の学生も大変少なくて、2人か3人くらい。だから7~8人、多い時は10人ぐらいの研究室でした。学位をどれくらい出してきたかをさっき数えてみたら、16人でした。その方達の大半は北大の大学院ですね。最後に行った立命の人もいます。そういう方達が学部から入ってくるか、修士から入ってくるか、ドクターから入ってきて、毎年10人くらいでずっと行く感じでした。
足立:心理学系ですと、博士号の取得を無事にできる確率は結構高いのでしょうか。
仲:ああー、本当にやっぱり様変わりして、1980年代は本当に少なかったです。私が学位を取るのも6年かかりました。北大に入ってからは、3年は無理でも4年目くらいで出るような感じになってきたし、ちょうどその頃、文科省の大学院重点化プログラムの代表をさせてもらっていて、3年で学位を出しましょうと進めていました。そんなことで、皆さん(学位を)取らないで満期退学した方はずっと少ないですね。
足立:学生さんに無事学位を取ってもらうために、工夫されていた点はありますか。
仲:心理ですと、最初は文献研究をやって、実験計画を立てて、実験をやって、論文を書くという感じです。かつては100人くらい参加者のいる研究、例えば2~30人の研究を3つとか、50人のを2つとか、そのような形でできれば書けるかな、という感じでした。まあどうにかね、皆さん頑張られて書かれました。中には少し時間がかかった方もいるんですけど。もう本当に素晴らしい。
立命館大学へ
足立:北大に14年間いらっしゃった後に、立命館へ2017年に転出されたのは何かきっかけがあるのですか。
仲:北大の定年が63なのですが、転出した時、私は61でした。立命の方に「仲さん、こちらは私学だから、来ればもうちょっと長くできるかもよ」と言われました。確かにもう少し研究のできる時間が長い方がいい。もうあっという間に60とかなっちゃうんですよ。もう本当。面白いな、面白いなとやっているとね。だから、2年残して移ったんですかね。61の時かな。そして、4年間、立命にいました。
足立:立命のゼミ構成は、どのような形でしたか。
仲:立命は、また少し違って学部生が多かったです。北大の時は4年生が例えば2~3人でした。立命は3年生からゼミ配属になるのですが、各学年10人くらいでした。3年生、4年生、それぞれ10人、10人で、20人。院生は1~2人いますが、教室で授業をやるみたいな感じのゼミになった。
足立:少人数のゼミと大人数のゼミだとかなり違うのではと思いますが、いかがでしたか。
仲:やり方は随分違うと思いますね、まあ本当に。少ないゼミだと、研究領域を分かち合いながら同じような研究を進めていく感じですが、やはり10人とかいるとそれぞれみんな思っていることが違うので、むしろ学生さん主体でした。千葉大とも近いかもしれないですね。それぞれがテーマを持って、こちらがアドバイスする。ゼミの時間も、北大では夕方何時間もかけてやって、後みんなでご飯を食べに行く感じでした。立命だとゼミの時間というコマがあるので、そこでやります。授業をやっている感じでした。それもそれで面白いけれども、やり方は随分違っていたなと思います。
理研へ
足立:引き続き立命館のポジションを持ちながら、理研にも理事としていらっしゃったきっかけはなんでしょう?
仲:ちょうど私は立命を65で終わって、後5年ぐらいは特任でいられるよと言われていたのですが、特任は学部から離れるので。だからなんか、ワイワイやる方が楽しいかなと思って、こっちに来てみようと決めたのでした。
足立:理研には心理学の先生が非常に少ない所に飛び込もうと思った決意と言いますか、その時思われていたことはありますか。
仲:それはね、冒険が好きだし多動みたいな面があるので、面白そうな所は行ってみたいなということで、来ました。理研に馬塚(れい子)先生がいらっしゃる。馬塚さんと私はデュークで出会って、1年一緒にお付き合いがあったんですよね。あと、夫も理研の研究者と共同研究をしていたことがあり、理研の話は聞いていたので、お~とか思ってちょっと行ってみようかなとあまり深い考えもなく来てしまった、みたいな感じです。
足立:今も立命館では研究をされているのですか。
仲:立命館は今年の7月に、最後のドクター学生の学位審査まで終わりました。今年の3月に、彼は(学位論文を)書き終えて提出して、審査が7月で終わった。あと2人くらいいたのですが、その学生さん達は他の先生方に引き継ぎました。今はもうドクターの学生は残ってないです。やっていることは、司法面接という被害を受けたとされる可能性のある子どもさんへの面接法で、記憶に基づいて話してもらわなくてはいけないので、心理学、発達心理学の成果が役に立つのです。そういう研修活動や、それに関する研究活動は立命でもさせてもらっています。特段、今、授業があるわけではないです。だから、ほぼほぼこっちにズッポリいるかなという感じです。はい。
研究者として嬉しかったこと
足立:今までの研究者のキャリアを振り返られて、一番嬉しかったことは何でしょうか。理系の先生方にはPIとして一番嬉しかったことを伺っています。
仲:そうね、一番かどうか分からないですけど、少しずつ積み重ねるようにしてきました。例えばRISTEX(JST社会技術研究開発センター)の研究費を得て、4年にわたってプロジェクトをやって、その後、新学術領域の代表としてまた4-5年間やった。同じような司法面接です。その後またRISTEXの研究のPIになって、5年間続ける。だから、15年くらいは、大変大きな研究費をいただいて、(学述研究)領域をみんなで一緒に形成してきたという感じがあるんですよね。最近、例えばその面接法に関しては法律が変わって、そういった形の面接を行った場合、その録音・録画は法廷での証拠として使用できるように、刑事訴訟法の改正がありました。そのような形で、まあ社会実装とか言ったら言葉が大げさすぎるけど、社会と繋がりを持ちながら心理学の研究が活かされていくのは、本当に嬉しいなあと思いますね。
足立:その大型研究資金のグループは何人くらいで構成されていたんですか。
仲:RISTEXは最初自分達のグループだけで、文科省の新学術は私が代表班になって、それ以外に10くらい研究班があって、それぞれが4~5人ずついて、プラス公募班があったから、総勢50人くらいだったと思います。10個くらいあるグループの代表に集まってもらって、総括班としてのガバナンスのようなことをしました。
足立:50人くらいの方を巻き込む方法は?全員最初から知り合いではないですよね?
仲:(知り合いでは)ないよね。それが立ち上がった時は、ちょうど法と心理学会もできていたので、関心のある人に声をかけたりしました。もちろん公募になるから、誰でも知っているのですが。そうそう、その時にもやはり難しさはありました。私は誰でも関心ある人は(どうぞ)と思っていたけれども、中には自分には声がかからなかったと思われた方もいたような反応も後でいただいたりしました。思いが至らなかったな、と思ったりしました。法と人間科学ということで、事件に関するところ、捜査に関するところ、裁判に関するところ、そしてその後の被害者支援や立ち直り、そのような4つに下位領域を分けて、それに関連するような研究をされている方に声をかけたか、集まってきたかで、構成する感じにしました。
足立:仲先生が代表を務められていたのは、ご自身から手を挙げたのでしょうか。
仲:知り合いが「出したらいいと思うのだけど、仲さん代表やってよ」というふうに言われました。え?私が?などと思ったのですが、やってもいいかなと思ってやってみた、という感じです。1回目はダメで落ちて、2回目は通って5年間(研究が)できたわ、みたいな感じでした。
足立:50人をまとめる難しさはありましたか?
仲:調書を最後に出したり、あるいは申請する時にも出さなくちゃいけないんだけど、それぞれ書きぶりも違っていたりするので、相当トップダウン的にいろいろさせてもらったのはあるかなと思います。あと良かったのは、毎年1回、どこかの大学でホストになってもらって模擬裁判をやりました。それぞれの研究者が関心のある、例えば学校でのいじめの問題とか、子どもが被害者になった事案とか、そういったことで模擬裁判をやって、そこにみんなが集まってわいわい議論したり、そこでデータを取ったりとかしました。それは1つ、求心力になっていたかなと思います。
足立:学会も仲先生が始めたのでしょうか。
仲:そうではなくて、さっき言ったように目撃証言などの研究をしていた人達が集まって(始まりました)。考えてみたら、本当に女性の数は比率としてはすごく少なかったです。立ち上げて、20年くらいやってきました。今は別の理事長ですが、その前の2期は私が理事長をさせてもらいました。それもやってみたらと言われて、ちょっとやってみようかな、みたいな感じでしました。なんか面白そうだなと思ったら、もう本当に「いや、ちょっとこれこれのことが、、、」、「家族のことがあるからできないかも」、「研究が忙しいし、できないかも」などとあまり悩まないで、引き受けてみると新しい世界が広がるかなと思います。
足立:学生さんの指導など、大きな研究グループをまとめている時に、辛かったことはありますか。
仲:わざと以前言ったことと、少し変わったことを言ってしまうわけではないのに、「この間は仲先生はこんなふうに言っていたのに、今回はこのように言っておられて、もう本当やってられません」みたいな感じで言われることもあるわけですよね。「ごめん、ごめん、ごめん」となるんだけど。申し訳ないなあ、みたいなことがあったりしました。学生さん同士で少しいさかいがあったり、まあなんかいろいろなことが細々とあるんです、ありますよね。でも、まあなんと言うか、人生、ありがとうとごめんなさいしかもうないかなと思っています。だから何かあったら、ごめんなさいだし。上手くいったことがあったら、みんなに本当にできるだけありがとうと言う。そう、もう、全部こう、ね。削ぎ落としていったら、もうその2つかな、と思うところです。
キャリアの岐路を振り返って
足立:研究者人生を振り返られて、一番のターニングポイント、ここでかなりキャリアが変わったなみたいなことはありますか。
仲:1個ではなくて、1つひとつが今に繋がってきてるかな、という感じです。千葉大、都立大、北大に行かなかったらまた違う人生になっていたと思うし、途中でアメリカに出させてもらわなかったらまた違う人生になってたかなと思う。帰ってきて、目撃証言のところでやってみようと思わなかったら、また全然違う形になってたかなと思います。1個1個が、ちょっと面白そうとか、やってみようかな、みたいなことの繋がりかなと思います。RISTEXの時も、最初「アドバイザリーボード(運営評価委員会)に入ってもらえませんか?」と依頼されて、そういう領域があるんだとその時知りました。それだったらアドバイザリーボードに入るよりは、自分がプレーヤーになりたいなと思って申請することにしたのです。だから、きっかけと何を選ぶかみたいな感じの連続だったと思います。失敗ばっかりというところもあるんだけど。そうそう、こうじゃなければ、みたいなこともあるのかもしれないけど、ね。
足立:あの時、あちらの選択肢を取れば良かったな、ということはありますか。
仲:大学から声をかけてもらって、いや、今、これこれこうだから、ちょっと行けません、みたいな形で何度かお断りしたことがあります。その時に行っていたら、また違うことはあったかなと思う時がないわけではない。でも、まあ、今がやっぱりきっと一番いいんですよと思うことにしています。はい。
足立:お話を伺っている中で、ライフイベントやご家族の話が出てきましたが、ワークライフバランスの取り方はいかがでしたか。
仲:よくよく考えてみると、ワークと言うとなんか仕事な感じでしょう。ライフは家族のためとか、生活という感じでしょう。でもね、ワークも仕事だし、ライフも仕事なんだと思うんですよ。ワークは会議に出たり、何か書類を書いたり。ライフの方もご飯を作ったり、お風呂を洗ったりする。何が一番本当の自分なのかと考えると、1人になって好きなことをやるみたいなことになるのかなと思うんですよね。だから、どっちもどっちもで両方仕事。バランス取るも取らないも、全部仕事、ほとんど仕事かなと思ったりもします。家族もないがしろ、仕事もないがしろみたいなところもあるかなって思うんだけど。まあでも、どっちも面白い。公のことばっかりやっているとなんとなく行き詰まるから、ライフの仕事もして。ライフの仕事ばっかりで、ちょっと飽きてくると、こっちもやるみたいな感じなので、常に2つ持っているのがいいんじゃないかなと思います。あまり答えになってなくてすみません。
足立:ご家族が全員一緒に住まれることが、なかなかなかったように伺ったんですが、いかがでしたか。
仲:そうですね。学生結婚で、学生の頃は1年か2年、筑波の寮に一緒に住んでいたんですけど、夫と一緒に住めたのはそれぐらいでした。夫も勤務地が遠かったので、週に何回ぐらいしか帰ってこないのは続いていました。挙げ句の果てには2000年くらいに九州の方の大学へ行っちゃったから、今もずっと、月に1回会えればいい感じ。まあZOOMで朝ご飯というのはやっているんですけど。大体ずっと離れています。子どもも中学生までは一緒にいましたが、それから留学して、その後は大学に行ったから一緒に住めてない。本当にバラバラに住んでいるなあと思います。でもこれもまた、どうにかなるんですよねって、なってないかもしれないんですけど。いろいろな形があっていいかなと思います。
足立:ありがとうございます。そうしましたら、まず私の質問はここまでです。
仲:ありがとうございました。
足立:松尾さん、お願いします。
ワークライフバランス
松尾:仲理事のお話を伺っていると、あまり両立のご苦労みたいなニュアンスは伝わってこないんですけど、あえてエピソードとして伺えることがあればと思います。最初に、お茶大から就職活動をされていた時は、ミニ博士として行こうと決意をされ、双子の育児も始まりという一番大変な時期だったかなと思うのですが、その頃はどんなふうに両立というか、ワークライフバランスを過ごしていましたか?
仲:保育所に育ててもらったような感じなんです。でも保育所も夜6時とか7時には迎えに行かなくちゃいけなくて。だから本当、時間がなかったなと思います。夫もその頃は総研みたいな所にいて、夜遅いんです。もう夜中に帰ってくるような。だけど、(週)1日だけ、夜何時まででも大学に残って研究して良いという日を、私は月曜日だったんだけど、もらっていた。その日にもう思いっきりやるみたいな感じで、あとは6時、7時になったら帰ってというふうにしていましたね。なので、本当にその頃は新しいことが何もできなくて、今までやってきた研究論文とかまとめて、学位論文にするみたいな感じだったかなと思います。その後、千葉大に就職した時に子どもが2歳くらいだったんですが、保育所はやっぱり7時までで、私が一番遅く行って2人共もう帰る支度をして玄関で靴履いて待っているみたいな感じなんですよね。それでもいろいろ終わらなかった。千葉大から歩いて15分ぐらいでしたが、2人を連れて歩いて、ビデオ屋さんが途中にあったんですよ。そこでビデオを借りて、また大学に行って、会議室みたいな所でビデオを見させていた。ドラえもんとか。そして、私は残りの仕事や研究をするとか、そんなふうにしていました。朝、保育所に送るのが8時半くらいなので、朝1回、5時とか6時に起きて大学へ行ってちょっと仕事をやって戻ってきて、(保育所に)連れて行くとかですね。だから、元気だった、体力がまだ若くてあったっていうのはあると思うのですが、やはり時間を作ることがすごい大変でしたね。そう、思い出しました。ずっと後になって、父の介護とか、もう亡くなってしまったんですけど、時々家族で集まっているのを誰かが動画で、写メで撮っているのがありました。そういうのが(クラウド)アルバムに入っていて、時々(タイムラインに)上ってきて見えたりするんですけど。父がいて、もう本当衰えているのに、家族が集まっているのに、私は横でパソコンとかやってるんですよね。もうなんかね、本当にみんなの時間を、自分がやりたいことのために使っちゃったなあってね、思うことがあります。ほんとね、ウルウルってなっちゃうんですけども。
松尾:それがあってこそ、今がある。
仲:いや、もうなんかね、本当にもう。
松尾:今、お父様のお話が出ましたが、デュークに行こうと決意をされた時に、お父様にアドバイスを伺ったという話なんですけど、それはなぜ?
仲:夫だったらきっと、無理だよとか言うだろうと思うし、同僚とかも全然ダメだし、行くのはちょっと早すぎるとか言われると思うし。まあそんなことで、父だったら、何て言うかなと。まあ結局、背中を押してもらいたいんですよね。なので、何をするかは言わないで、さっき言ったような形で聞いてみたら、「うん、それはそうだよなあ」とか言ったから、もういいやと思ってですね。という感じですね。
松尾:ご主人は離婚というキーワード。
仲:そうそう。もう言ってた。
松尾:それでも行く決意っていうのは揺らがない。
仲:まあ、そこまではしないかなって思って、行ってみたんです。最初に行く時に2人連れて行かなくちゃいけないので、旦那も一緒に来てくれたんですよね。4人で行った。そして、旦那もまんざらではないような、なんか楽しいみたいな感じでやっていたので、まあいいかなとなりました。
女性研究者を取り巻く環境
松尾:北大に移られた時に、それまでの都立大は女性が割と多かったけれど、女性が少なくなったというお話でした。仲理事が働きやすさで違いをお感じになるところはありましたか。
仲:それはね、あまりなかったです。その頃までは、いつもいつも自分自分って考えているもんだから、あまり女性が少ないとか、周りはどうかを気にしなかったんですよね。女性が少ないと思うようになったのは、ほんと60代くらいになってから。改めて見たら、なんか男性多いなという感じでした。その時はあまり気にしてなかったと思います。でも委員会などがあると、いろいろな学部から来る女性の顔ぶれは同じだなと思っていました。さっき言ったRISTEXの前に、文科省のGood Practiceで大学院の充実を目指してお金がドーンと来るプログラムがありました。それも「仲さん、代表やって」と言われたのですが、どちらかというと教育に関わるような内容は女性がやるみたいな感じがあったかと、今となってみれば少し思うところがあります。でも、そのプロジェクトをやれたおかげで次のRISTEXとかに繋がっていったので、何事も結構いいように運ぶものだなと思ったりします。
松尾:研究者としてのご経験の中で、周りに両立に悩む女性も結構いたんじゃないかなと思うのですが、背中を押したとか、アドバイスをしたとか、そういうご記憶はありますか。
仲:少しずつ気が付くようになってきたのもあります。私は長いこと常務理事を日本心理学会でしていましたが、そこも女性の理事がずっと1人でした。委員や委員長を選ぶような時には、女性に声をかけるようにしてきました。先ほどのRISTEXもそうですし、女性のチームリーダーを招き入れるというような形で声をかけることは、比較的積極的にやってきました。先ほど学位を出したのが16人と言いましたが、その中の女性の人数を数えたら、6人でした。ということは37%だなとさっき計算して思いました。通常の学位取得比率から見ると、女性割合が多かったかなと思います。困っているなという人の助けができたかどうか分からないけど、引き入れることは一緒にやってきたかなと思います。あまりちゃんとお答えになってないかもしれません。
松尾:ありがとうございます。
研究者としての試練
足立:研究者のキャリアの中で一番の危機は何でしたか。
仲:40年もやっているといろいろなことがありました。それはもうなんと言うか、その時その時、1つひとつ対応していかなくてはいけなくて、あまりそれが危機になるという感じではないと思うんですよね。どこかで、でも対決しなくちゃいけない時というのはありました。例えば、自分がやった仕事をその人がやった仕事のように報告されている時とか。自分の所の研究費が少し違うように使われているとか、そういうことがあった時には、「もしもし、これは私の仕事だからちゃんと引用してね」とか言うのは、少し対決みたいな感じでした。私は対決が一番苦手なので、人に何か「もしもし」と言うのはすごい苦手なんだけど、3-4回くらいは、「あの、ちょっとお話があるんですけど」というように言いに行ったりはしたかな。あとは例えばその方がきっと悪いつもりではないと思うんだけど、連日呼び出されてお説教されるみたいなこととかも人生の中であったりするわけですよ。帰ってきてうーって泣いちゃうんだけど、そういうふうにして泣いていてもしょうがないなと思うから、ある時ちょっと意を決して、「あの、なんと言うか、お話しいただくのはありがたいんですけど、ちょっとそれは辛いんですけど」みたいなことを言ったら、「あ、そうだったか」みたいな感じでやめてくださったりしました。だから、多分されている方はそんな気にしてないみたいな。何度か、そういう少し勇気を奮って言いに行くみたいなことはあったなと思います、うん。
足立:対学生さんで苦労されたことはありますか。
仲:対学生さんも、一緒にやった研究なのに、なんで私の名前入ってないの?みたいなことも、あるわけですよ、たまにはね。だけど、長い人生を見てみたら、自分だって自分でやってきたみたいな感じがあるかもしれないけど、周りから見たら、「いやいや、私が助けてあげたから仲さんできたんだよ」というのはいっぱいきっとあると思うんです。それを自分ではポジティブシンキングで、全部私が何か考えてやってきたみたいに思い込んでいたりする部分もきっとあるだろうなと思う。ないがしろにされたと思うようなことがあっても、あんまりそれはもうね、気にしない。何か良いことがあったら若手のため、何か困ったことあったらじゃあもう私が被るよ、くらいでいくのがいいかなと思っています。なかなか思い通りにはいかないんですけど。
キャリアの岐路に立っている若手研究者へ
足立:ご経歴を伺っていて、全国あちこちに行かれているように思いましたけれども、若手の方もポジションを探す時に、ご家族の状況やいろいろな制約がある中で、選択を悩まれる場面もあると思います。そういった若手の方に、何かメッセージをいただけますか。
仲:大体においてどうにかなるっていうことがあると思います。孤軍奮闘と思っても、見かねて手を差し伸べてくださる方もあったりもする。ここはね、もう勇気を奮うところと思って、ドボンって飛び込んでみるっていうのがいい場合もあるかなと思います。ダメだったら、あ、ダメだったと思ってちょっと戻ってくればいいとか、方向を変えればいいので。そういう意味ではなんて言うか、人生は勇気と冒険の部分があるかなっていうふうに思うところですね。
足立:どうもありがとうございました。
インタビュー実施:2023年11月14日
インタビュー場所:本部棟 3階 特別会議室
RIKEN Elsevier Foundation Partnership Project
撮影・編集 西山 朋子・小野田 愛子(脳神経科学研究センター)
撮影支援・編集支援 雀部 正毅(広報部)
インタビュアー・製作支援 松尾 寛子(ダイバーシティ推進課)
インタビュアー・製作 足立 枝実子(ダイバーシティ推進課)