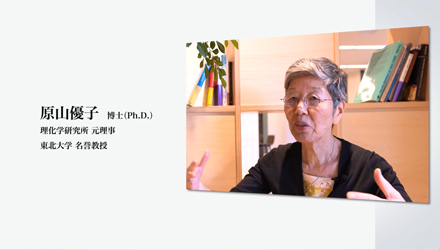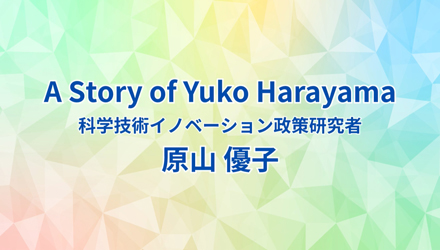分野も国境も跨いだキャリアと研究室運営
原山 優子 理化学研究所 元理事
(東北大学 名誉教授(Ph.D.))
略歴
| 1973年 | ブザンソン大学 理学部 数学科卒業 |
| 1988年 | ジュネーブ大学 教育学部 卒業 |
| 1996年 | ジュネーブ大学大学院 教育学研究科 博士課程修了 |
| 1997年 | ジュネーブ大学大学院 経済学研究科 博士課程修了 |
| 1998年 | ジュネーブ大学 経済学研究科 Assistant Professor |
| 2001年 | 独立行政法人経済産業研究所 研究員 |
| 2002年 | 東北大学 工学研究科 技術社会システム専攻 教授 |
| 2006年 | 内閣府総合科学技術会議(現総合科学技術・イノベーション会議)非常勤議員 |
| 2007年 | (仏)Companie de Saint Gobain 社外取締役 |
| 2010年 | 経済協力開発機構(OECD)科学技術産業局 次長 |
| 2013年 | 内閣府総合科学技術会議(現総合科学技術・イノベーション会議)常勤議員 |
| 2020年 | 国立研究開発法人理化学研究所 理事 |
| 2022年 | 特定非営利活動法人日本科学振興協会 代表理事 |
| 2023年-現在 | 東レ株式会社 社外取締役 |
| 2024年-現在 | 山口大学 非常勤理事(研究戦略担当) |
学部卒業時のキャリアビジョン
足立:原山先生のCVを拝見しました。1973年に、フランスのブザンソン大学の理学部数学科を卒業された時、将来の展望はどんなことを考えていらっしゃいましたか。
原山:昔の話で、ちょっと思い起こさなくちゃいけないんですけれども。そもそもブザンソン大学の数学科に行ったのは、本当にピュアに「数学おもしろそう」っていうので選びました。ご存知のように、フランスの場合には高校卒業資格というより、大学の入学資格としてバカロレアというシステムがあり、バカロレアを取りました。セクションがあって、私は「C」という理数系でした。国立大学だからどこでも行けるというので、自分の判断でパリ大学の数学科にアプライしましたが、ブザンソン大学に配属となりました。すごく楽しかったです。日本のように教養部みたいなのがないので、3年間で学士を取得しますが、ブザンソン大学の理学部がある山の上で、どっぷり3年間数学に浸かっていました。そこに寮もあったので、そこでの生活範囲が全てでした。修士に続けて行きたいと思い、申請したところ給費留学生のお金をもらうことができました。でも、運命のアレで結婚することを決めてしまい、日本に帰ってきました。なので、初めの質問ですが、当時、将来の展望は数学を続けたいというのがありましたが、結婚するためにフランスから日本に戻ってきちゃったんです。日本の環境で何ができるか、しかも、その先なかなかどうなるか分からない状況でした。
足立:そうすると、ご家庭に入られた?
原山:家庭に入ったというか、何と言うか、結婚したんです。でも自分は自分なので、日本の大学で数学を続けたいと思って、いろいろと見て回っていた。一つは早稲田大学の研究生みたいな形で、さしあたり修士に入るまでの準備をして良いということになり、大学に出入りできるようになったんです。そこで、日本の数学の教授のもとで勉強を始めたんですが、なんと妊娠してしまって。妊娠した後に大きなお腹で早稲田のキャンパス内にいると、何か居心地悪かったっていうのがありました。最終的にその次のステップに行く前に、子どもが生まれて、さっき足立さんが仰ったように、家庭に入ったというか、子育てがプライオリティになりました。なので、そこで一旦、私自身は休止っていうんですかね。終わりじゃないけれど、そこでストップしたというのがその時点のことでした。
育児中心の生活から社会復帰へ
足立:そうしましたら、育児に力を注がれていて。次の経歴を見ますと、1988年にスイスジュネーブ大学の教育学部卒業とありますが、また学部で?
原山:完全に数年間経歴が飛んでるんですよね。日本で、例えば、勤めるとか何とかっていう時に、履歴書を書きますが、この間は何をしてたんですかって聞かれる対象になります。まさに最初の子どもが生まれて育児していて、2人目が生まれて、などなどで、結局3人子どもがいます。その間にできる仕事は、フルタイムじゃなくて大学で教えたりとか、細切れのことをやっていました。自分自身本当にフルで何かやるという活動は、どちらかというと子育て中心だったので、可能な範囲でというところがありました。その時うちの夫は日本の大学で助手をしていたんですが、「僕は海外にやっぱり飛び出したい」と言い出して、私もウェルカムだったんで、「じゃあ行こう行こう」と言って、家族全員でジュネーブに移りました。夫はジュネーブ大学で教職の仕事を得て、私は家族を連れて一緒に行ったんです。そこで周りを見回すと、子どもを預ける環境もあったし、住んでいる所も安全だったので、「じゃあここでもう一回社会復帰するぞ」と思い立ちました。フルタイムの仕事はなかなか子育て中で難しいので、「じゃあ大学で、もう一度学生をやろう」という形で再度入学したんですね。その時に最初は「数学を続けたいな」という思いがありましたが、ちょっと大学に潜り込んでみて講義などを聞いてみると、10年ブランクがあると、ほぼキャッチアップするのが不可能と自分で認識したんです。「じゃあ方向を変えるか」と思って、子育ての体験とか、これまで自分が感じてきたことを生かしたいと考えた時に、浮かび上がった問題意識が教育の在り方だったのです。教育学という学部がありますが、他の学部に比べるとすごくフレキシブルでした。仕事を持っている人も入りやすいし、自分のスピードで講義を取ることができるというので、そういう意味で自分にとってすごくやりやすいところだったので、教育学部に入り、もろ1年生から始めました。だから私にとっては2つ目の学部の学生で、それをやっているうちにどっぷりは大学にはまってしまった。そして学部が終わった時に、その後も博士まで行きたいと思うようになったんですね。そこで、実質的に博士論文をどうするか、私と議論がすごく合っていた先生がいたので、議論しながら結局その道に行くことになった。途中いろいろとあったんですが、教育学という学問そのものにはいろいろな切り口がありますが、個人的には「教育する効果とは何か」、という問いに興味を持ち、経済学的アプローチにも少しずつ引き込まれていきました。その中で教育のシステム、特に私は高等教育システムの価値みたいなことに興味を持ち、経済学、経済的価値という視点を入れたいと考えるようになりましたが、指導教員から、経済学もしっかり学ばないと理論武装ができない、と突っ込まれました。「じゃあ経済学もやるぞ」と、3つ目の学部(に行きました)。そちらも1年生から入って、結局学部を3つやったことになります。そして、博士課程は、教育学と経済学を並行してやっていました。まず教育学の方で博士課程を修了し、その次の年に経済学の博士課程を修了したという、ちょっとメチャクチャな経緯です(笑)。
2つの博士号取得を目指して
足立:博士課程のコースを並行して2つやるというのは、非常に大変だと思うんですが?
原山:日本のコンテクスト(状況)で考えると大変。現在、ジュネーブ大学のシステムも変わりましたが、私がいた当時、博士課程に入るというのは、博士論文の指導教員が誰かいて、かつその人と合意したテーマがあるということが前提でした。そして、研究テーマを基に、準備段階の資料としてしっかりとした研究プロポーザルを準備し、教授会に提出し、それが承認されると、博士課程の学生として認められるんですね。その後は、ほぼ何にもなくて、博士論文を提出して、論文審査をしておしまいという形だったんです。だから自分自身でタイミングを図ることができるし、こういうルーズな所があるので、途中で辞めていく人もいっぱいいるわけなんです。登録して最後までいくというのは、本当に何%かという状況でした。良い点はフレキシブルなんだけども、マイナスの点はよっぽど自分で自分のことをハンドリングしないと到着点までいかないという感じでした。逆を言えば、自分のリズムでやれたし、その間に経済学部の助手のポジションもいただいたので、給料も入るようになったし、平日はそちらの仕事をしながら、経済学の論文書きに注力し、土曜、日曜は教育学の論文書きという、そういう生活でした。
足立:教育学と経済学ということで、ディシプリン(専門分野)それぞれの流儀を身につけて、それなりの分厚い博士論文を?
原山:まさに仰るようにね、学問分野によって論文の書き方も違うし、課題設定の仕方も違うし、というところなんだけども。私がなぜ経済学に興味を持ったかを考えると、教育経済学という分野があるんですね。その中身にすごく興味を持ち、ある種、教育学と経済学の接点であり、そこから視野が開けたという感じですね。(教育学と経済学では)対象とするテーマの設定の仕方もまるっきり違うし、ツールの使い方も違うし、検証の仕方も違うし、という2つの分野なんだけども。私自身の興味の出発点は、日本の大学システムをどうやったらもっと良くできるだろうかという個人的な問題意識でした。だから大学システムのあるべき姿を現場で調査しながら検証していったのです。それと同時に、今度は経済学の方では、ちょうどその当時経済成長をどのように促すかいろいろな議論が流行っていて、マクロレベルもミクロレベルもあったんですけれども、その中に公共の投資が経済全体の成長に貢献するという理論があるんですね。公共の投資は、公的な橋を作ったり、学校作ったりとなるんだけれど、その中にも高等教育への投資もあるし、研究開発への投資もある。特に私が興味を持ったのは、政府がなぜに研究開発へ投資しなくちゃいけないのか。そもそも科学を進歩させるために投資していることもあるんだけども、最終的に行き着くところは周り回って、桶屋が…じゃないけれども経済成長に結びつくというロジックがある。その道筋を、どういう因果関係でいくのかなということにすごく興味を持っていて、それを分析対象にしてきました。
博士号取得後のキャリアの展望
足立:そうすると1996年に教育学博士、1997年に経済学博士、2つ取られて、その時はどういう分野で今後自分のキャリアを進めていきたいとお考えでしたか。
原山:その時もそうだし、今もそうなんですけど、キャリアがどうなるかあんまり意識してなかったです。なぜかというと、子どもも3人いたし、しっちゃかめっちゃかな毎日をしながらやってきたので、先のことを見るよりは、明日、明後日のことで精一杯だった。大学もそうだったし、まずは一歩一歩進んでいくやり方でした。博士号を取ったからって、それが着地点では私自身なかったし、まあ一つの証明書みたいなものなわけですよ。私の昔の指導教員に言われたのは、「博士論文というのは君の名刺みたいなもんだから」。それを人に見せることによって、どういうことをしてきたかと同時に、これから何をしたいか説明する時の一つの名刺になるという話。そこで終わったんじゃなくて、これからだっていうことです。したいことはいっぱいあったし、その時点では研究という道が、自分自身にフィットしていたと思っていました。でも、どの分野でとか、どの大学でとかはそれ以前の問題で、自分がその当時いたのがジュネーブ大学だったので、ジュネーブ大学の中で(研究を)やるとどうなるかな、とは想定しながらやっていた。
足立:研究分野的には国連の機関ですとか、パブリックセクター(公的組織)の職も考えられたのかなと思いましたが。
原山:ああそうかそうか。ある程度自分自身でこの分野でやっていけそうだなという感触を持ったのはどの時点かを言いましょう。ジュネーブ大学の経済学の指導教員が、ある日突然、「1年分の研究資金を取ってきたから、1年間好きな所へ行ってもいいよ」と言ってくれました。それは教育学の博士論文を終えた年でした。私自身はそれまでにヨーロッパは結構経験があるんですけども、アメリカへ1回も行ったことがなかったので、「じゃあその1年間の資金でアメリカに行って、違う研究環境で違うアプローチを見てきたい」。「どこにしようか」と思った時に、私のことを応援してくれていた他の教授からいろいろとアドバイスを受け、結論として「優子はスタンフォード大学が向いている」となりました。スタンフォード大学の経済学にどういう人がいるかをリストアップしたところ、青木 昌彦にたどりつきました。そこで彼に、研究テーマを説明した上で、「教育学の博士号を取ったのでポスドクの立場ですが、経済学はまだ準備中です。微妙なところで、ポスドクとも呼べるし、ドクターの学生とも呼べるんですけれども、こういう状況で1年間受け入れてくださいますか」とお願いしました。なかなか始めは大変だったんですけれど、最終的に受け入れてくれました。それで、アメリカのスタンフォード大学に1年間研究生として行くことができました。そこでですね、本当に目から鱗じゃないんですけども、いわゆるシリコンバレーのど真ん中で、大学っていうものがいかに産業界と繋がっていて、それも旧来型のやり方ではなくて、同時並行的にいろいろなことが起こって、大学と企業のインタラクションがあって、そのことによりシリコンバレーそのものも活性化されてるし、大学そのものも活性化されてるという、その現象を論文とか書籍ではなく、自分で目の当たりにしたんですよ。すごく私にとってはフレッシュだったし。「どうしてこういうことが起こったのか、起こる土壌がどこにあって、やっぱり歴史的に見た時に今日の状況に至ったのは、昨今の話だけでなくて、ルーツがあるはずだ」と思った。スタンフォード大学へ行って何をやったかと言うと、アーカイブがすごく整っていたので図書館に通い、今日に至るまでの経緯というのを資料で遡っていった。「ああ、こういう大学のあり方というのもあるんだ」というのを研究テーマとしてそこでやったんですね。研究テーマだけじゃなくて、実際に仕掛けた人がまだご健在だったので、インタビューをしたりしました。スタンフォードがスタンフォードたるやにスイッチングを入れた何人かの人と、今日、今やっているみたいにインタビューして、その話を聞きながら、昔の資料を見ながら、「ああ、大学っていうのはこういう進め方もあるんだ」ということを何か実感したんですね。研究テーマとしてすごく興味深いし、あともう一つ、実践的なことがすごく大事だと思った。単純に研究だけじゃなくて、アクションリサーチというんですけれども、実際に世の中を変えるようなアクションを自ら促しながら、かつそれを研究テーマにしてやってみたいなと思ったのがその当時でした。もう一つ、青木 昌彦の研究生として滞在しましたが、彼の周りにいる同僚とも接点を作ってもらいました。滞在中にまとめたペーパーを彼の同僚のネイサン・ローゼンバーグに、「君、これ多分興味を持ちそうだから」と言って見せてくれて、すごくその方が反応してくれ、一回会いたいと言われました。私はすでにジュネーブに戻っていたけれど、「実は僕、ロンドンに行くことがあるからロンドンまで来ませんか?」ということになりました。初対面でしたが、意気投合しちゃったんです。その時ですね、この分野でやっぱり深堀りしたいと思った。玉突き方式でいろいろな人とのことがあって、何かストンと落ちるものが予期せぬところで多分にあった。ローゼンバーグが言ったのは、「君が今対象としている高等教育のあり方とイノベーションの関係は、あまりみんなが着目しているものではなかったけれども、僕もすごく今、興味を持っている。いわゆるランキングの高いジャーナルに論文を投稿することを目指すには、あまり効率が良くないかもしれないけど、でもやることはすごく価値がある」と。すごく有名な先生だけど、「当初、僕が、イノベーションがどのように起こるかというメカニズムをペーパーにした時は、興味を持ってくれるジャーナルは多くなかった。だから論文より、自分で本を書いたんだよ。君もそうすればいいんだ」と言ってくれたんです。いろいろと何かそういうほっとする会話があって、その結果として「じゃあやっぱりやろう」となりました。でもそれは必ずしもキャリアとして考えたわけではなく、自分の興味を持つ分野を一歩進めるか、諦めるか、他に行くかという時に、何か一押ししてくれる人がいて、そっちに行った。結果からするとそうですね。その時はよく分からなかったけれど。
帰国後のキャリアの展開
足立:興味を持った分野をさらに深堀りしていきたいということで、ジュネーブ大学の経済学部の助教授に?
原山:はい。教えながらとか(研究を)やっていたんですけども、たまたまその時青木 昌彦が日本の経済産業省の中で独立行政法人化された経済産業研究所の所長になることが決まった。そして「来ないか」と言われたんです。私自身、日本で仕事をする想定はほとんどなかったし、「多分日本の社会で誰も受け入れてくれないだろう」と勝手に思い込んでいたところがあったので、全然想定外でした。でも「来ないか」と言われて、彼が所長でやるなら、多分面白そうな研究所になるから、そこで新たなスタートを切る時に一緒にやりたいなと思って、「はい、行きます」と言って、ジュネーブ大学を辞めちゃって、日本の経済産業研究所の研究員になったんです。日本でキャリアを積みたいから帰ってきたというよりか、何か楽しそうなものに一緒に相乗りしたいと帰ってきた。ジュネーブ大学の同僚は、「たぶん日本は女性にとって息苦しい所だから、お前は数年経ったらジュネーブに戻ってくるよね」と言っていて、「うん、そうだよね」と話をした。でも実際戻ることなくずっとそれ以降日本にいて、今日に至る感じです。
足立:2002年の4月に東北大の教授になられたきっかけは?
原山:それも全く想定外でした。今お話ししたように、私にとって、日本の大学は研究の対象でした。日本の大学システムがどうあるべきかということを議論するから、具体的な事例は日本の大学だったんだけども、それまで実際自分が学生になった経験もないし、先生として教える側の経験もないし、完全に第三者の目から見る研究対象でしかなかったんですよ。だから、まさか自分が教員になるなんてことは全く想定外でした。本当にぐるっと回ってなんですけれど、私が興味を持っていた研究の対象は大学の在り方みたいなところと、もう一つは科学技術への投資として成長に最終的には行き着くところの関係性とかがある。その長い道のりの一つが、大学で研究開発した成果が、企業によって製品化されたり、サービスになって、それが世の中に出回って、消費者が受け入れて、というストーリーがありますよね。この一連のプロセスをイノベーションと今では語られていますが、これが本当に自然にそうなるのか、あるいは誰かが意図的に行動を取らなくちゃいけないのか。その辺もすごく興味を持っていて、事例を研究したいと思いました。さっきの話も同じです。スタンフォードに行った時、スタンフォードの研究者と学生が起業をいっぱいしているじゃないですか、スタートアップの。そのプロセスも研究対象として見ていた。全部ひっくるめた時に、日本でも当時「そういうことが重要だね」と言われるようになっていた頃なんですよ。2000年の初めの頃ね。今あちこちでイノベーションの話を耳にしますが、当時はまだフレッシュだった。そういうことを東北大学では工学研究科の学生に教えることを試みた。工学研究科の学生が、自分達がこれから作るであろう技術が、どのような形で世の中の役に立っていくのだろうということを学部、大学にいる時から勉強する。そういう仕組みがあると認識することが大事だという視点から、100年ぐらい歴史のある工学研究科の中に新しい専攻を作った。その名前が技術社会システム専攻です。「技術と社会との関係性をそこで学びましょう、研究しましょう」という専攻ができた。その新しい専攻を作る時に、東北大学として半分は工学系の先生を入れた。残りの半分は経済学とか経営学とかマネジメントしたりとか、政策を教えたりする、いわゆる工学外の先生を入れる構想で作ったんです。工学系の先生は東北大学にいっぱいいらっしゃるんですよ。しかし、もう片方がなかなか、どこに誰がいるかという土地勘が少なかった。たまたま経済学部の先生といろいろなイベントを一緒にやった経緯があって、その方が「あそこに原山っていうのがいる」と仰ってくださった。その当時はスイスから日本に帰ってきていて、経済産業研究所にいましたが、突然彼から電話があって、「今こういう構想があるんだけども、原山さん来ませんか」という話だったんですよ。その時も中身そのものが私としては、研究対象としていたんだけども、実践したいと思っていた時だし、まさに実践の場として最適な状況に思えたんですね。工学の学生が来るし。彼らが自分達の手で何か加工して起業などに繋がるであろう研究科を作るというのであれば、乗らないわけにはいかないと思って、「ぜひ」という形で東北大学に入った。日本の大学でポジションを取りたいとか、キャリアを積むという想定0だった。でも、こういう機会があった時にはやっぱりやりたいなと思って「お願いします」という形で入っていったのがきっかけです。今、博士号を取った後になかなかポジション取れなくて苦労してらっしゃる方がいっぱいいらっしゃることは確かなんですよ。私は全くそういう道を経験せずにして、こういうふうに入ってしまったんですけども。機会はいろんなところで出てくるから、やっぱりそれを掴むか掴まないか。そのためにある種の心の準備が必要だし、やっぱり自分の興味がすごく大事だなと、後から思い浮かべると思います。
研究室の運営スタイル
足立:このインタビューシリーズは、マネジメントについて皆さんに伺っています。原山先生の分野、経済学ですと、多分、共著者数もそこまで理系に比べては多くないし、ご本人と共同研究相手でやるみたいな感じで、学生さんも1人ずつテーマを持つと思います。ご自身で独立された、PIになったのは、やはりスイスのジュネーブ大学助教授で、1人前のPIになったというイメージでしょうか。
原山:PIという認識はほとんど自分にはなくて、どちらかというと一匹狼的な道のりだったんですね。だから、一緒に議論する人はいるけれども、ペーパーは自分で書いていたというのが過去の経緯です。それから一緒に共同研究しましょうという人達がいて、何人かで共著もあるんだけども、必ずしも私がPIとして旗振りして、資金を取ってきて何とかやったというのではなく、もっとラフな関係性でやっていた。私自身、PI、PIっていう認識はあんまりないです。東北大学に移った時も、今仰ったように、学生も個別に「こういうことがしたい」と言うと、「こういうテーマがあるよ」って(アドバイスしました)。ざくっとしたものを提示しながらも、本人がこれをしたいと言うのを、私はどちらかというと待つタイプでした。だから学生同士で何か一緒に共同でというより、全て個別にいろんなことをやらせていたのが東北大にいた時のやり方です。博士の学生もそうだったし、修士の学生もそうだったという意味で、まあみんな個別です。東北大学に入った時には、研究室があって、私ともう1人助教授、今は准教授ですか、の人とペアでやるんだけど、それぞれ自分の立場でいながらも、学生同士の交流とか研究者の交流は非常に促すようにしながらやってきました。これまでのシリーズでは、理研の女性研究者がPIになる前と後について、皆さん議論できたじゃないですか。私の場合はそれがなくていろんなことをやってきたという経緯があります。いろいろな組織でいろんなプロジェクトを立ち上げて、そのヘッドをしたことはあるけれど、必ずしもここまで、これまで議論してきたPIというステータスがあってというのではないのが、ちょっと例外的なのかなと思っています。
足立:学生さんがいても、スタッフの研究員がいたことはないですか?
原山:ポスドクみたいな形で私の所に来て、それぞれが皆自分でテーマを抱えていて、ペーパーを書いて、いろいろな議論したり、アドバイスしたりとか。そういう意味での共著はあるんだけれども、やっぱり個別対応をしてきた感じです。でもお互いに、「何やってる?これ、僕、違う所でやっていて」という刺激や、何て言うのかな、ケミストリみたいなものは存在していて、彼らがまだいろいろな所で繋がっているのがすごく嬉しいです。
足立:研究室のマネジメント面でいうと、例えば文献講読とか、あとは学生の発表を皆で議論するみたいな形のスタイルでされていたのですか。
原山:そういうのはやりますよ。それぞれが持つテーマで発表しながら、インタラクションもあることは確かなんだけども、いわゆる組織立った研究室というものをマネージすることは意図的にしてなかった。私自身そういう固まりを作るのがあんまり好きじゃない人間なので。別に他の先生もいっぱいいるわけだから、「いろいろな所に行って話しを聞いてらっしゃい」。他の研究室の学生もウェルカムで、「一緒に来て議論しましょうね」という、ある種のオープンスペースみたいのを作っていたことは確かです。私にとって東北大学が初めての日本の大学でしたが、これまで日本の大学で育った学生が私の所に来て、「僕、何とか研究室の、何とか先生のことに興味あるんですけれども、彼に、聞きに行っていいですか」って聞かれたんですよ。それがすごくカルチャーショックで、「行きゃあいいじゃん」って。「なんで私にそんな許可を取る必要があるの?」というのが私の反応で、すごくびっくりしちゃった。人によってはそういうやり方をするところもあるので、「あ、そうか」と(思った)。私自身はなかなかそういうのに馴染めないので、行きたい所があったら勝手に行って議論して、「誰でも来ていいですよ」というスタンスでやってきた感じです。
東北大学工学研究科に研究室を設けて
足立:東北大学工学研究科に研究室を設けられていたということで、工学部のやり方に影響を受けたことはありますか。
原山:工学研究科は歴史のある所で、工学の中にもいろいろな分野があって、それも歴史がある分野なんですね。歴史があるということは、研究の仕方、課題設定の仕方、それからラボの運営の仕方というのは、結構形が整っていて、伝承されている。そういう重みがいっぱいある中で、私が所属した所は、本当に一番新しくできた専攻なんです。だから、他の分野からすると、ちょっと掴みどころがないねという所だったし、自分達とは違うねという目で認識されたし、逆にそっちに合わせる必然性がなかったという面もあった。半分は工学系の先生だったんで、その半分の工学系の先生はどこかにもともとの親元があるわけですよ。親元は本当に伝統のある所で、だから彼らはそれを引き継ぎながら、この新しい所で新しいやり方を一緒に模索していた。悪く言うと寄せ集め状態だったんですね、工学の先生も、いろいろな分野から来ていて。私たちが始めに何したかというと、「自分達のアイデンティティ作らなくちゃいけないね」という認識だったのと同時に、「ここでの教育の仕方、ここでの単位の出し方、ここでの学位の出し方、共通の認識を作らなくてはいけない」というのが初めの一歩だったんですよ。例えば単純なことだけれど、修士の学生に修士論文を書かせるじゃないですか。どういうふうに評価するかっていう時に、分野によって全然違うんですよ。工学の中だって分野によって違うわけです。ましてやこういうヘテロジーニアス(異質)な組織で、でも、同じ専攻から出す修士だから、ある種の品質の均一性というものも担保しなくちゃいけないんで、どこに共通の価値観を見出すかというのが必要で、結構大変な作業だったんです。初めの1年は試行錯誤的な状況で、数年経ってやっと落ち着いたところまで行った。だからそういう意味で他に合わせるというか、私達の基準を作ることが大事だった。その作業が結構大変だったんですが、すごく私も学んだし、工学系の先生たちも違うやり方もアクセプトしてくれた。どこで共通分母とするかという認識を持って、そこまでいくといろいろな議論をするじゃないですか。知らないもの同士だったんだけども、そういう議論をすることによって、「ああ、あの人はこういうふうに考えてるんだ」とか、「この分野ではこうなんだ」という認識を新たにした。そういう意味ですごく学習でした、私にとって。
足立:それぞれ工学と経済学でもしっかりした伝統の下で、分野の中では大体修士はこのくらい、博士はこのぐらいみたいなレベル感を多分お持ちなところ、まったく異質なところを最後統一できたのでしょうか。
原山:統一できたというよりか、ある種ルールみたいなものを作りましょうというところまでいったんですね。例えば、修士であれば、どういう学会があって、比較ができないけれど、「工学系だったらこの学会、経済系だったらこの学会の最低限この辺でちょっと発表するぐらいかな」とか、相場感を作ったんですよ。博士論文であれば、論文投稿でお互い比べると、「この程度のところが我々が目指すところだよね」と。そういうものを目指した。論文審査をする時にも、なるべくクロスで。もちろん指導教員がいるけれど、同時にちょっと分野の違う人も専攻の中から(入った)。工学系であれば経済系の人が中に入るとか。学外からも審査に入るけれど、「専攻の中でも分野の違う人が入る形でやってきましょう」とか、「そういう学生の育て方をしましょう」というやり方を作ったとか、ある種のルール的なものを見出したわけです。完全にこれでOKというわけじゃないけれど、「この辺だよね」という相場感を作りました。それも一回作ったからって、ずっといくわけじゃなくて。私もだいぶ前に卒業しましたが進化しているのかなと思っています。
足立:原山先生の研究室に来られる学生さんのバックグラウンドはどんな感じでしたか。
原山:すごくバラエティに富んでいた。私の所へ来た後も、いろいろな分野に行っている。もう何年後には「あっちに行ってるの!?」など、すごく面白い学生が来ました。もともと工学系でも、技術の開発では無く、技術の活用に興味を持っている学生もいたし、逆に経営学をやっていた学生で工学に興味があり、この専攻では両方見られるからと来た学生もいれば、高専出身の学生ですごく現実的な感覚と体験を持った学生もいるし。いろいろな学生がいました。
足立:研究室の中で理系と文系が入り交じって?
原山:理系、文系ってことはあんまり思ってない。意識せずにそれぞれ違う人が入っていて、でも何か一緒に議論することによって発見があるだろうし。どちらかというとチームでやらせたことはないけれど、興味があればいろいろな話を一緒にする。1つ東北大学でいいなと思ったのが、留学生が来るじゃないですか。私の所にも留学生が来てました。来てすぐの時になかなか溶け込めないので、大学がサポートをしてくれて、同じ研究科の学生1人、日本人の学生を最初アテンドするためにアサイン(指名)してくれるのね。その学生に少しお小遣い程度なんですけども、謝金をくれて。フランス人留学生がいっぱいいたんですが、うちの学部・研究科で、「今度新しく来るから誰かやってくれない?」と話したら、「僕、あんまり英語うまくないですが、自分の勉強のためにやります」と1人言ってくれた。すごく努力してくれたんですよ。もう10年ぐらい経ってるんだけども、「フランスで今一緒に写真を撮ってます」と本当数日前に、送ってきてくれた。「そういう繋がりがあるのかな」と思った。だから人と人の出会いってすごく大事だと思います。すごい余談になっちゃったけれど。
手探り状態から始めた研究室
足立:東北大の研究室はどんな方針で運営しようと心がけていらっしゃいましたか?
原山:そう言われると、どういう方針だったかというのを思い出さなくちゃいけないんですけども。私自身は学生にテーマを与えるのはあまり好きじゃなくて、「こういう可能性があるんだけども、何したい?」というアプローチでした。だから、どちらかというと自主的にやるしかなかった。それこそバックグラウンドの違う学生ばっかりだったし、新しい専攻だったから、これまでの蓄積がなくて、過去の卒業生はこういう論文を書きましたというのも何もない所だったんですよ。だから全て手探りで、学生も一緒に手探りよねという感じで、引き込みながらやっていたのが初めでした。もう1人、准教授がいたんだけれども、彼もどちらかというと原子力の専門だったのが、原子力の様々な問題があって、社会との対話とかにすごくシフトしてきた方でした。バリバリの工学だったんだけども、社会学的なアプローチにも興味を持っていましたが、お互いに独立してやっていたんです。でも、一緒にやるプロジェクトもあったし、一緒に企画をしたりしました。例えば学生を連れて青森県の六ケ所村に行って、あそこはエネルギー関連の壮大なサイト(拠点)があるんだけども、それを見ながら地元の人達と交流するとか、地元の高校生をうちの学生が訪問するとか。向こうからも東北大学に来てくれて、高校生を受け入れたりしました。通常やる講義と並行して、いろいろな活動を学生の教育の枠組の中でやっていました。あと、専攻の中に閉じず、他の研究科とか学生にもオープンにしておいた。なるべくオープンなスペースにして、学生も教員の人達も一緒に議論できるような雰囲気を作ってきた、あえて言うならばそういう感じでした。あともう1つね、ちょうど私が東北大学に行った時が、日本の国立大学が国立大学法人になった時でした。そのちょっと手前で、私は東北大学に入った。2004年に法人化があって、法人化をどういうふうに運営するか変革のすごい時期に東北大学に行ったんですよ。私が研究テーマとしていた大学システムのあり方とか、運営の仕方とか、海外での体験もあるし、そういうところがあったんで、大学そのものに大きな波が来た時にその波をどう受けるかという議論に参画させていただいたという経験があった。自分の研究室の運営だけじゃなく、大学本体の運営にも。東北大学に入って右も左もわかんない時に「東北大学、これからどうするか」という議論を一緒にさせていただいたという、すごい経験をしたんです。
アカデミアの外の世界へ
足立:その後、東北大学の教授を続けながら、いろいろな展開になったということでしょうか。世界銀行の短期コンサルタントとか、総合科学技術会議有識者議員とか。
原山:当時、世界銀行が、地域イノベーションはどのように起こるか、いろいろな国で調査を始めたんです。その枠組みで、日本において地域イノベーションの状況を分析をするためのプロジェクトが立ち上げられた。その時私はたまたま東北大学の教員として仙台にいた。私ごとですが、それまで、日本で東京以外に住んだことが無く、仙台が初めてでした。知らない所に行くんだから、じゃあどっぷりそこに浸かっちゃおうと思った。どっぷり中に浸かるためにはどうしたらいいかっていうと、地元の人といろんなことを仕掛けるのが一番手っ取り早いと思った。私のカードとして持っているのが、さっき申し上げた研究開発した技術を活用していくという話。地域が東北大学の色々な成果を活用できているかできていないのか、できるようにするために何したらいいのかということを、地域の方たちと一緒に議論する仕掛けを作ったんです。地域のためでもあるのですが、私自身が東北地域にどんな人がいるかを知る「ディスカバー東北」でした。中でも「ディスカバー仙台」、「ディスカバー宮城」となりました。ちょうど東北地域で地域のことを考えなくちゃいけないと(活動していた)。先ほどの世界銀行のプロジェクトでは、日本政策投資銀行が日本を担当し、日本政策投資銀行の東北地域支店の方たちが東北地方を調査することになり、そこで、私は、日本全体と東北地方と二つのレベルで参画することになった。具体的には、うちの学生とポスドクの研究者でチームを組んで、そのプロジェクトに張り付けたんです。当時、修士の学生として入って、まだほやほやの学生をそういうプロジェクトに参画させちゃって、彼にとってすごい経験だったと思う。その後もいろいろと役に立ってるんじゃないかなと思う。内閣府(総合科学技術会議)の仕事は、それこそ私の研究テーマだったイノベーションが、政策的に促す対象、要は政策課題になったんです。「政策を作る側の方に来ないか」と言われた。なので研究する側から実際に政策を作る側に身を移した。フルタイムで大学の仕事をしながら非常勤で初めの2年間やりました。やっていることはそんなに違ってなかったけれど、地域にフォーカスしたものであったり、日本の国にフォーカスしたものであったり。その後は東北大学に10年くらいいた後に、パリにあるOECD(経済協力開発機構)の科学技術産業局へ行きました。そこは同じように科学技術政策を作る側です。1つの国ではなくて、いろんなメンバー国が、自分たちの国ではこういう政策をやった、この先どのような政策を取るべきかという議論を促すための組織です。そこでたまたま次長のポジションが空いて、手を挙げて、採用されて、2年間大学を休職して行ってきました。研究テーマを、まさにいろんな国々の人たちと議論した。どちらかというと議論を促す立場にあったんですけれども。あちこちウロウロしてました。
足立:先生のお話を伺っていて、こういう言い方が正しいのかよく分からないですが、アクションリサーチをいろいろな研究の分野で、仙台であったり、国であったり、国を超えてヨーロッパや世界とかでされて、非常に面白いなと思いました。
原山:そうそうそう(笑)。本人は結構楽しんでたんですけど。そんなこと言っちゃ怒られるかもしれない。
キャリアの中での一番のジャンプ
足立:これまでを振り返って、先生の今までのアカデミックもすごく飛び越えてキャリアを送られていた中で、一番のジャンプというのはどこの時点だったと思いますか。
原山:ジャンプですか。いろいろジャンプ、ぴょんぴょこやっていたのを、積み重ねたけれども。どこかな?やっぱり日本に帰って来た時は、結構「帰るぞ」っていうのがあった。それからさっきのOECDの話もやっぱり「どうしようかな」と思いつつだった。自分の性質か分かりませんが、新しい所でやっていって、段々段々状況がよく分かるようになるじゃないですか。そして、いろいろなことがスムーズにできるようになってくると、逆に不安になってくる。「私、このままでいいんだろうか」と。何か「他のことをしてみたいな」と思うことが出てくるんです。大概10年サイクルなんですけども。そういう気持ちになってくると、たまたまですが、「来ません?」、「こういう空きがありますよ」などが耳に入ってきて、「じゃあやってみるか」的にやってきました。「どうしようか」とすごい考えてジャンプしたのではなくて、自分自身でも何か変えなくちゃいけないというふうな、何かこの辺の思いが溜まってきて、そこにきっかけがあるとポンとジャンプしてきたという感じなのかなと思っています。なので、今後も何かあるかなって(笑)。まだ分かんないしね。
足立:きっかけを掴んでジャンプする時の心得、ここまでは自分で準備しないとジャンプ飛びついちゃいけないな、みたいな部分はありますか。
原山:自分自身の体験だから他の方に当てはまるか全然分からないんだけれども。何かコツコツとやっていると、自分自身、新しい学びや発見があって、吸収していくものがあって、かなり栄養が自分自身に満ち足りた状態になったところで、多分ジャンプできると思うんですね。これがある程度ないと、非常に危ういジャンプになっちゃって、落っこっちゃう可能性もある。ジャンプしたからにはそこで何か新しいものを掴みたい。そのためにはやはり栄養素をしっかり蓄えておく必要があると思っています。次に行く時の準備のための栄養というか、自分自身が何かやりたいと思って吸収する。レーダーですかね。いろいろなものに入りながら、取るものは取っておいて、ある程度溜まったところで次にそれを使う。使い切っちゃ困るんだけど、かなりのものを使って、新たな一歩を踏み出して、またそこでもいろいろなことを吸収しながら蓄えていく。それが溜まってくると、さっき申し上げたように、「居心地良すぎて、何か逆に不安だな」と思ったりする。そこでまた次の何か(に挑戦する)という感じかな。私自身はそんな感じです。何となく面白そうだからふわっと行って、こっちに行って、あっちに行ってでは、成り立たないと思います。やはり蓄積がものすごく大事だと思っている。蓄積には必ずしも良い体験ばかりじゃなくて、結構苦労もあったり、その時点ではとてもお先真っ暗になっちゃって、「どうしよう、どうしよう」ということもあるかもしれないです。そこで、どういうあがき方ができるかとか、どういう風に乗り越えることにチャレンジするかはすごい学習で、それが糧になり、似たようなことがあった時にビビらなくなる。そういう蓄積も大事かなと思っています。それは戦略的にできるわけじゃないし、ある種、行き当たりばったりなところがあるけれども、なるべくいろいろな体験を、良い意味で糧にするように心がけることも大事かなと思います。
足立:ジャンプの前に不安になりがちだと思います。その上、国を超えてジャンプするのがすごいなと思うんですが、躊躇いはなかったですか?
原山:自己責任だと思っているから、コケた場合にはなるべく人に迷惑をかけない状況を作ってやってきました。「いつもあいつは迷惑かけて」と、うちの夫なんか思っているかもしれないけれども、私としてはなるべく周りの人たちが、私が勝手なことをすることで悪影響が出ないようにと、それだけは一生懸命心がけてやってきました。結構大変なので自分自身のことを心配するゆとりがたぶんなくて、「行くぞ」という時は「行くぞ」って乗り越えるしかなかったかもしれないです。ある程度、なんとかなると思ってやってきた面もある。大概のことは、1発でうまくいくことはほとんどないじゃないですか。だから、大事なのはうまくいかなかった時に、次の手として何をするかちゃんと考えておく。「これしかない」と自分を追い詰めることは絶対しちゃいけないと思っている。面白そうでやるんだけども、まあやってうまくいけばOKで、うまくいかなかった時に「じゃあこうするか」という、セカンドオプションみたいなのを少し頭の中で考えておくと、ある種の安心感が出るかもしれないと思っています。追い詰めちゃいけないですよね、自分自身をね。それは私はやらない。
足立:ジャンプをする時に、人によっては優先順位をいろいろ考えて、「家族をどうしよう」とかあると思います。先生ご自身もご家族がいらっしゃる時に、特に国を跨いでジャンプや決断をするにあたり、どんなことを考えていましたか。
原山:子どもが小さい時は、親の責任。でも、ある程度大人になって自分の足で立って歩いていたら、ある種、自分の責任。親も切り替える。でも何かあった時には「いつでも言ってきて」だし。何かあった時にはやっぱり一番に何とかしてあげるのが私だと思っているし、そうしてきました。逆にそれ以上何かやる必要があるかというと、必ずしもで、子どももそれぞれだし、というところがある。子ども達だって私のことを一応リスペクトしてくれていると思ってはいるんですけどね。まあ、そんな感じですかね。なるべく私が取った行動によってネガティブなインパクトがないようにと常々心がけている。(子どもは)それぞれ独立しているし、それ以上に必要があるかというと、必ずしもそうじゃないかなと思っています。本人達はそう思ってないかもしれないけど(笑)。聞いてみますね、今度。
足立:ありがとうございます。ひとまず、私からの質問は終わりです。
数学を好きになった理由
松尾:学生の時に数学が面白そうだったと仰っていました。今、日本では特に理数系、数理に行く女子が少ないというお話がありますが、原山先生が数学を好きになった背景が、特に何かあれば教えてください。
原山:私、計算がすごい苦手なんですよ。いっぱい間違うし。今はスマートフォンがあるからいいんだけども。そういう形での数学は、全然だめだったんですね。それから問題を解くこと、何か決められた計算方法にしたがってやることは、あんまり得意じゃないというか、面白いとは思っていなかった。数学の背景にある、ロジックで物を語り、理解して、詰めていき、証明するという、この一連の流れがすごいきれいだなと思っていた。自分でもやってみたいという思いがあった。数学の先生や高校でとかいろいろな人の影響を受けてるんだけれども、何かちょっと日常とは違うものの見方が面白そうだなと思った。人間として年を取ってきて世の中の事象とかいろいろなことを見ていると、ロジックだけで片付けられるのはほんの一部分でしかなくて、そうじゃない部分が山ほどある。そういう二面性を持った上でいろいろなことを判断するんだけども、こういうものの考え方とか理解の仕方が自分の中に一部分あることはすごく大事だなと今でも思っています。
専門分野を跨いで
松尾:アカデミックな専門分野を、数学、教育学、経済学と変えてこられています。専門分野を変えたことが原山先生のキャリアにプラスになっていることが多いかなと思ったんですけど、もしネガティブなところがあるとしたら、どんなところでしょうか。
原山:世の中にはいろいろな現象を見るために、いろいろなアプローチがあるじゃないですか。1つの分野しか持たないと1つのアプローチでしかものが見えない。同じ現象を見ていても別のアプローチを用いることができると、1つの凝り固まった見方を避けることができる。ある種の反射神経みたいなものは自分自身で獲得していると思います。いろいろな見方が、いろいろな場面で役に立っていることは確かです。学問分野として3つをやったことで、キャリアに結びついているかというと、直接的じゃないけれども間接的に、そういうバッググランドがあるということで、頭のトレーニングができているということが、いろんな場面で役に立っていることは確かなんですよ。キャリアという視点からすると、私自身、行き当たりばったり的な、1つの道で何か飽きたらなくなっちゃう。自分自身で何か「もう他のことしたい」と思った時が変わるタイミングで、それがキャリアと呼べるかというと、一般的に言うキャリアとはちょっと違うのかなと思っている。なので、役に立つ、役に立たないという視点からすると、よく分からないというのが答えです。でも、私自身の糧になっていることは確かで、いろいろなものを見る時の考え方を形成する時に、いろいろなことが役に立っているのは確かです。数学のロジックというのは、何かパッと判断しなくちゃいけない時に、現象をクールに見る手段となるので、それは今でも役に立ってるのかなと思っています。
リーダーシップについて
松尾:リーダーの在り方。
原山:きた!(笑)
松尾:ジュネーブ大学の時のボスとか、青木先生とか、恩師にあたる方達に原山先生も背中を押してもらったこともおありだったと思いますし、原山先生もスタイルをお持ちで。リーダーの在り方についてお伺いできますか。
原山:OECDにアプライした時は書類選考があって、その後インタビュー(面接)がありました。OECDのパリのオフィスに6人ぐらい人がいて、私はOECDの東京オフィスにいて、オンラインでやったんです。その時に質問されたのが、「リーダーシップを取った経験を教えてください」と。リーダーシップなんて、自分自身で何か「やった」という実感はあまり持ってなかった。でも、即、答えなくちゃいけなかった。そこで思い出したのが、ジュネーブにいた時のことでした。子どもたち3人は、平日はジュネーブの公立学校で、土曜日に日本語補習校に行かせた。そこは国語とか算数とか数学を学習する。その学校は本当に親の手作りでした。3人お世話になっていたから、恩返しじゃないけれども運営委員をしていた。150人規模の手作り学校の運営を、何年間かやったことがあるんですよ。そう言えば、あれが一番のリーダーシップだと思った。ガチっとした組織があれば、ポジションで誰かがリーダーシップを取っていれば一応形になるじゃないですか。本当に手作りだから、教える先生はいて、一応校長もいて、運営そのものは運営委員会があって、「ああでもない、こうでもない」と皆で言いながら一生懸命やっていたけれど、なかなかまとまらなくて難しいんですよね。しかも予算だって国から来るわけじゃなくて、ファンドレイジング(資金調達)しなくちゃいけない。それをやった時の体験が、何か組織を動かすという私の原点にある。当時大変だったけれども、子ども達のためにという親の集まりをまとめていく作業が、私にとってすごい体験でした。今、いろいろ大学や理研も含めて、リーダーシップ論みたいなのを頼まれて講演したりしますが、体系的に習得したリーダーシップ論というより、私自身がこれまで構築してきたものは、ある種の体験ベースです。その中からと同時に、いろいろな組織の動かし方をいろいろな角度から見てきた体験も踏まえて、こういうやり方が機能するという、ある種の実感が自分の中に蓄積されてきて、それが私のリーダーシップ論の基礎かなと思います。ですので、結構実践型なのと、形がかちっとしていない組織にもリーダーシップは重要との認識を持っています。必ずしも形がなくても、人が何人か集まって何か行動を取る時には、引っ張る人が必要な場面が出てくるんですね。その時に、必要に応じて自分がそういうアクションを取れるか取れないかいうのがすごく大事だなと思っている。役職があるからリーダーシップを取るんじゃなくて、やっぱりその組織の動かし方をどうするかという視点から、アクションを取れるか取れないかというのが大事な点だと思っています。
日本の女性研究者の置かれている状況について
松尾:ジュネーブ大学にいらして、お子さんを育ててこられて、その後日本に帰国されて、アメリカにも行かれた。女性研究者としての働きやすさや、女性を取り巻く環境を日本、欧米、いろいろご覧になってきていると思いますが、今、日本の女性研究者に対してどう分析されていらっしゃいますか。
原山:多分私の世代の研究者と、今、20代、30代の研究者の置かれている環境は全然違うと思うんですね。日本も環境整備という意味ではすごく良くなってきていると思います。研究者として継続的に何かするということも、バリアは昔に比べたらすごく低くなっていると思う。認識している役割分担の話でもある。じゃあ本当に自分でいろいろなことを選べるかというと、選択肢がまだまだ足りないのかなというところもあるし、まだ変えることができる部分というのはいっぱいあると思う。でもやっぱり女性である男性である以前に、研究者の道が面白いと思ったら、誰でもそこに入れるような状況を作っていくことが大事かなと思っている。それが例えば、お子さんがいらっしゃるとか、いろいろな状況があるのは、本当にベースラインとしてサポートできるような体制を作ることが大事です。それ以上のアンコンシャス・バイアス的な話とか、いろいろなことがまだ残っているので、それは徐々にですが意識的に変えていかなくちゃいけないと思っています。
松尾:原山先生はご自身で両立をされてこられたので、両立に今迷い悩んでいるという女性に対して、経験的に言えることはありますか。
原山:両立というか、2つのものを持って何とかというよりか、全部ひっくるめて自分じゃないですか。私自身、子どもがいることは私の一部分だし、私自身が親でない自分もやっぱり存在するわけですよ。自分のための自分というのが欲しくて、そのために私はジュネーブに行った時にもう一度大学に入学した。誰のためでもなくて、自分の時間が欲しかったのと、誰にもディスターブ(妨害)されない自分のエリアが欲しくて大学に行ったという経緯がある。両立というか、全部ひっくるめて、やるしかないという(状況でした)。応援してくれる人がいればウェルカムだし、手伝ってくれる人もウェルカムだけど、それがなかったらやらなかったかというと、やったんじゃないのかなというふうに思います。
松尾:ありがとうございます。
博士号を取得して嬉しかったことと辛かったこと
足立:博士号を取った後で一番嬉しかったことはなんですか。
原山:1つ目の教育学が終わって、経済学部の博士号を取った時に、ジュネーブ大学ではトラディション(伝統)なんだけども、論文審査があるじゃないですか、シビアな。審査会が終わった後に、博士号を取った人が、審査員を含む関係者をアペロ、お酒を飲みながら懇談するというのを、自ら「皆さん来てください」と招待するんですよ。その時に一番嬉しかったのが、うちの娘が当時大学生になっていたので、お母さんのためにそのアペロの準備をしてくれたんですよ。手作りのおつまみやお菓子を作って。あれが一番嬉しかったです。これ(博士号取得)は自分のためにやったところがあるけれど、その喜びを分かち合ってくれる人がいたのが嬉しかったですね。
足立:逆に一番辛かったことはなんでしょうか。
原山:辛かったことはいっぱいある、並行して2つの博士論文を準備していると。平日は経済学部の助手もしていたから、そっちの仕事があるし。土日は、どちらかというと教育学をやっていた。子どももいろんなことがあるし、ほぼ休みはなし。削るのが夜寝る時間ぐらいかなというところで、まあそれで乗り切ってたんだけど、大変だったんですよ、多分。やりきった感みたいなのもあったし、大変と言ったら大変。でも、それだったらやらなきゃいいじゃんってなっちゃうから、と思いますね。
キャリアチェンジのツールとしての博士号取得
足立:若手でキャリアを変えて博士号を取ろうという方に対してのメッセージをいただけますか。
原山:皆さんいろいろな状況のもと、何か1つの仕事に入って、でもそれだけがその人の道かというと、いろいろな可能性をそれぞれ持っていると思うから、その可能性を何かうまく引き出す機会があれば、私はやるべきだなというふうに思っている。その引き出す1つのツールが博士号かもしれないし、そうじゃないやり方もあるかもしれない。もう1つの道として、オプションとして、何か可能性として温めておくことがすごく大事だと思います。博士号を取るという作業は結構重たい作業だし、何年もかかるし、論文を書くだけじゃなくて、自分の学習の仕方とか、それから教え方も学ぶわけですよね。課題設定の仕方や、様々なことを学ぶので、必ずしも最後のゴールまで行き着かなかったとしてもその数年間は絶対無駄にならないと思うし、ある種の自分のトレーニングですし。そういう意味で飛躍に繋がる可能性のある経験だと思っています。なので、チャンスがあったらいろんなことはしてほしいなと思うし、1つだけじゃなくて、欲を持って2つ(笑)、でもいいんじゃないですか。
学際的な研究科の設立に関わって
足立:最後に、本当に個人的な興味からの質問です。東北大学で工学部と経済系とか経営系の議論を先ほど伺いました。当時のことを思い出すと、日本でもMBAをいろいろな大学で作って、MBAだけではなくてマネジメント。Management of Technologyも。
原山:そうそう、MOT。東北大学が導入したのはMOTです。
足立:そういう議論の中で、東北大ならではの特徴をどこに定めるかみたいな議論を少し伺ってよろしいですか。たぶん理研も今、人文社会に広げましょうという議論があります。
原山:当時、工学研究科がMOTを作って、経済学研究科がMBAを作るという構想があったそうです。MOTの方が先にスタートしましたが、MBAは最終的に作るというところまで至らなかったと。東北大学の場合、大学全体を見た時のウエイトというのは、工学研究科がすごく重いんですね。工学の中に経済学的なものを埋め込むことの重要性を皆さん認識していらした。当時の総長だった阿部(博之)先生はもともと工学の方で、今の工学教育の中に欠けているものがあるという認識を持ってらして、この専攻を作ったんですね。そういう意味で、すごく自然な形で東北大学ならではのアプローチでMOTが導入され、実際に学生を採れるようになりました。修士と博士の学位を出すという流れになったのは、日本の国内の大学では、東北大学が一番最初でした。それが今、サイエンスパークが整備され、産学連携とか、様々な活動がありますが、これらの流れのきっかけの一つにMOTの構想があったと思っています。
足立:そうすると、原山先生が、日本の大学の純粋な経済学や教育学など、そういう所にポジションを得ずに、東北大のそういった先進的な、学際的なポジションを得て良かったことは何でしょうか。
原山:いろいろな大学の中にいろいろな研究科とか学部があって、それぞれが独立して教育研究をやっています。けれど、さっきのスタンフォード大学もその一例ですが、それと同時に他の分野から何かを取り入れることにより、あるいは他との接点でいろいろ面白いことが起こっていることを、あちこちで実感してきました。そのやり方を、東北大学でもある程度試みることができたかなと思っています。閉じないことが大事なのと、もちろんその専門の学問の重要性は変わらないわけだから、それと同時にプラスアルファで他との接点で何か新しい仕掛けを作ると、やはりそこに興味もつ学生も来るし新たな出発点になる。新陳代謝の1つにこういうのがあるんじゃないのかなと思っています。理研も同じで、いわゆるセンター方式でやってるじゃないですか。多分もうひと押しチャレンジできるのが、その接点の所とか新しい要素をプラスアルファした所で何か面白いことが生まれる可能性があって、それがちょっと花咲いたところで、1つのセンターとして独立したものになるかもしれない。何かそういう種蒔きやお水をやって、というのが必要かなと思っています。
足立:どうもありがとうございました。
原山:ありがとうございました。
インタビュー実施:2023年7月25日
インタビュー場所:研究本館3階350リラックススペース
RIKEN Elsevier Foundation Partnership Project
撮影・編集 西山 朋子・小野田 愛子(脳神経科学研究センター)
インタビュアー・製作支援 松尾 寛子(ダイバーシティ推進室)
インタビュアー・製作 足立 枝実子(ダイバーシティ推進室)