美しき数学
この世はエレガントな方程式でできている。数学ギライもきっと引き込まれる美しくも不思議な数の世界、15冊。
2019
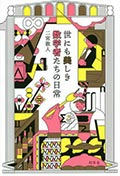
『世にも美しき数学者たちの日常』
- 二宮 敦人(著)
- 幻冬舎 2019年
数学者ってどんなヒト?天才たちの見ている景色
数学者のアタマの中ってどうなっているんだろう?数学者と数学マニア11人にインタビュー。「数学の問題を解くことは、人生を考えること」、「芸術に近いかもしれない」。聞けば聞くほど謎が増える。想像以上に天才だった。
2019

『「数」の日本史─われわれは数とどう付き合ってきたか』
- 伊達 宗行(著)
- 日本経済新聞出版社 2007年
「ひい、ふう、みぃ」に始まる日本列島5000年の数の文化史
20歳はなぜ「はたち」?九九はいつからあった?平城京はピタゴラスの定理でできている?縄文時代から明治、昭和まで、日本人と数とのかかわりをたどる1冊。平安から室町に芽吹き、江戸に花咲く日本の数文化を、再発見してほしい。
2019
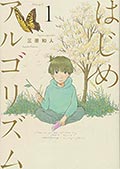
『はじめアルゴリズム(1)~(10)』
- 三原 和人(著)
- 講談社 2017年
数学から見る世界は鮮やかだ。天才少年ハジメの成長物語
雲の流れ、枝の分岐。世の中はなんだって数式で表せるー。小5の天才数学少年ハジメの成長をみずみずしく描くジュブナイル漫画。老数学者の導きと、友人、ライバルとの出会いで、数の世界はどこまでも広がっていく。数学って、こんなに面白かったんだ!
2019

『フラットランド─たくさんの次元のものがたり』
- エドウィン・アボット・アボット(著)竹内 薫(訳)アイドゥン・ブユクタシ(写真)
- 講談社 2017年
二次元?四次元?異なる次元はいかにして捉えられるのか
さまざまな図形が平面の中で生活する二次元の国フラットランド。ある日、正方形の「私」のもとに「球」が訪れ三次元の国の存在を告げる―。アインシュタインが四次元を語る30年以上前の1884年に刊行された、次元の本質を捉えた名作物語。
2019

『黄金比─自然と芸術にひそむもっとも不思議な数の話』
- スコット・オルセン(著)藤田 優里子(訳)
- 創元社 2009年
人類を魅了してきた美しい秩序 神秘に満ちた黄金比のカギ
美しき数学は自然の中に現れる。貝殻の形や葉っぱの付き方、古代の遺跡や人体のデザインにいたるまで、偉大なる自然の秩序が隠れている。プラトンをも魅了した物事をもっとも美しく見せる黄金比。たくさんの図版で堪能あれ。
2019

『ぼくと数学の旅に出よう─真理を追い求めた1万年の物語』
- ミカエル・ロネー(著)山本 知子、川口 明百美(訳)
- NHK出版 2019年
数学YouTuberとたどる1万年 世界一受けたい数学講義
0(ゼロ)、負の数、円周率、虚数……どれも当たり前に使ってるけど、もとは誰かが考え出したもの。だったら、そのルーツを探す時間旅行に出かけよう!旧石器時代を皮切りに、ギリシャ、インド、アラビアへ。ガイドは人気数学YouTuber。ゴールした頃には、数学が一挙に身近に!
2019

『素数の音楽』
- マーカス・デュ・ソートイ(著)冨永 星(訳)
- 新潮社 2013年
数学者が描くノンフィクション「リーマン予想」に挑む天才たち
2,3,5,7,11,13,17・・・・・。一見不規則な数の並びの奥に、妙なる響きを聴こうとした人々がいた。それは素数という、数学究極の謎。世紀の難問「リーマン予想」に挑み、素数の秘密に迫った学者たちの、苦しくも情熱的な生きざまを描く。
2019

『「無限」に魅入られた天才数学者たち』
- アミール・D・アクゼル(著)青木 薫(訳)
- 早川書房 2015年
「無限」とは何なのか?神に挑んだ数学者の物語
近代以前の西洋において「無限」という概念は、神の領域だった。19世紀の数学者ゲオルク・カントールは、無限を数学的に扱うすべを発見し、大転換をもたらした。しかし、難問と向き合うなかで精神を病んでしまうー。ゲーデル、デデキントなど同時代のスターたちも交えた群像劇。
2019
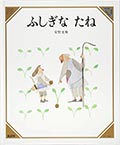
『ふしぎな たね』
- 安野 光雅(著)
- 童話屋 2017年
1コが2コ、2コが4コ……倍々ゲームで学ぶ、数の愉快。
怠け者の男が仙人からもらった不思議な種。1コ埋めれば次の年には必ず2コ実るという。1コが2コ、2コが4コ……。それを10年続けたらどれだけ増える?でも嵐が来たら作物はどうなる?単純な倍々ゲームで学ぶ、数のマジック。親子で楽しみたい数学絵本。4、5歳から。
2019
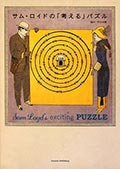
『サム・ロイドの「考える」パズル』
- 伴田 良輔(編訳)
- 青山出版 2008年
数学が娯楽として楽しめる 極上パズルに挑戦しよう!
約100年前に一世を風靡した、パズルづくりの天才、サム・ロイド。生涯で1万もの問題をつくり、数学や計算を庶民の娯楽に仕立てあげた。ひらめき系問題とじっくり思考系問題の計45問に挑戦してみよう!レトロなイラストも魅力的。
2019

『数学ガール シリーズ1』
- 結城 浩(著)
- SBクリエイティブ 2007年
ライトノベルだけど本格派。数式と少女たちへのときめき
高校生、趣味は数式の展開。そんな僕の前に、2人の女の子が現れた。エレガントに問題を解くミルカさんと、元気なテトラちゃんの間で、僕の心は揺れ動く。ライトノベル×数学という異色の組み合わせで大ヒットしたシリーズの第1作。素数、絶対値、無限級数、テイラー展開、母関数など。
2019
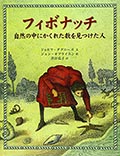
『フィボナッチ─自然の中にかくれた数を見つけた人』
- ジョセフ・ダグニーズ(文)ジョン・オブライエン(絵)渋谷 弘子(訳)
- さ・え・ら書房 2010年
花びらの数、オウム貝のうずまき「フィボナッチ数」発見の物語
朝から晩まで数字のことばかり考えてるから、みんな僕のことを「のうなし」と呼ぶ。でも、好きなことに熱中して何が悪い?世界を旅しながら数学に打ち込み、ついに自然界に潜む数の規則「フィボナッチ数」を発見。中世イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチの思索を体験できる絵本。
2019

『定理が生まれる─天才数学者の思索と生活』
- セドリック・ヴィラーニ(著)池田 思朗、松永 りえ(訳)
- 早川書房 2014年
天才の日常を覗いていたら数学の創作過程が見えてくる
数学者はどんな日常を過ごし、思索を進めているのか?2010年「フィールズ賞」を受賞した天才ヴィラーニが、新定理を生み出すまでの2年を描いた日記。解けない難題に朝まで悩み、仲間との会話でヒントを掴む。時には子どもに絵本を読んだり、日本のアニメに没頭したり。数学者のリアルを覗き見る。
2019

『若き数学者への手紙』
- イアン・スチュアート(著)冨永 星(訳)
- 筑摩書房 2015年
数学者になりたい君へ ヒント満載の21通の手紙
数学を志す少女メグに向けて、大先輩から届いた21通の手紙。数学を職業にするとはどういうことなのか?どうやったらひらめくのか?数学は孤独な作業か、チームでやるものなのか?名手イアン・スチュアートが数学者として生きるためのヒントを詰め込んだ1冊。
2019

『数学する身体』
- 森田 真生(著)
- 新潮社 2018年
数学ギライの認識を変える私たちの心体と共にある数学
人工知能の時代。高度に進化する数学は、私たちの日常とは別世界のように感じられる。しかし、もとはと言えば、指を使って数えるところから数学は始まった。若き独立研究家が「身体とともにある数学」を思索した名エッセイ。アラン・チューリングと岡 潔に数学のありようを学ぶ。
