つながる地球
自然や社会の中で人間のエコロジー(生態系)を問い直す17冊。
2021

『ウォールデン 森の生活(上)(下)』
- ヘンリー・D・ソロー(著)今泉 吉晴(訳)
- 小学館 2016年
森で暮らして見えてきた社会と人間のあるべきすがた
モノにあふれた現代社会で、人間らしい生き方がわからなくなったら、ソローを読んでみるといい。28歳からの2年2カ月、ひとり文明社会に背を向けて、森に囲まれた小屋で思索を紡いだ。トルストイやガンジーにも影響を与えた異色の思想家が、自然への愛や社会と人間の本質を説く。
2021

『世界からバナナがなくなるまえに─食糧危機に立ち向かう科学者たち』
- ロブ・ダン(著)高橋 洋(訳)
- 青土社 2017年
バナナ、米、小麦、砂糖…農作物をめぐる危険な事情
効率的に作物を収穫するには、画一化するのがいい。みんな大好きなバナナやチョコレートでも、小麦やトウモロコシでも同じこと。でもそれは、病原菌や虫の被害で全滅するリスクを増やすことになる。行きすぎたアグリビジネス(農業に関連する経済活動)がもたらす危機と、そこに立ち向かう科学者たちを追う。

推薦コメント
私は、乾燥・高温などの環境ストレス下でも安定的に生産できる植物の開発を目指して、研究を進めています。この本では、米や小麦などの主要作物が、病原菌・害虫や気候変動によって、なくなってしまう可能性を伝えています。食料危機に備えるために、私たちは何をすべきかを考えさせてくれる良書です。
関 原明(環境資源科学研究センター 植物ゲノム発現研究チーム チームリーダー)
2021

『FOOTPRINTS─未来から見た私たちの痕跡』
- デイビッド・ファリアー(著)東郷 えりか(訳)
- 東洋経済新報社 2021年
「人新世」が地球に遺すもの 未来へのツケは大きい
産業革命以降、地球の環境が大きく変化した今の時代を「人新世」と言う。毎年海に流れ出す何百トンものプラスチックは、恒久的に海底に堆積する。人間が放出した炭素の痕跡は10万年後まで残る。私たちは未来にどんな足跡を遺そうとしているのか?遠い未来の視点から書かれた、人類への警告の書。
2021

『風の谷のナウシカ 全7巻箱入りセット』
- 宮崎 駿(著)
- 徳間書店 2003年
人類は滅びるべきなのか?宮崎 駿が描く科学文明のその後
映画は序章にすぎなかった!現在の科学文明が戦争で滅びた1000年後。死の森・腐海に覆われた大地で、人と自然の歩むべき道を求めて孤軍奮闘するナウシカは、驚くべき真実にたどりつく。宮崎 駿が10年以上書き紡いだ大作漫画。環境問題への強烈なメッセージ。

推薦コメント
子どもの頃から夏休みごとに10回は映画を見返すくらいナウシカが好きでした。漫画は映画の後の物語も描いているので、ぜひ読んでもらいたいです。研究者にもよく読まれていて、ナウシカを起点に議論をすると、止まらなくなりそうです。私も読み返す度、「腐海はどうしてできたのか?」と考えます。さまざまな視点で読める名作です。
蒔田 由布子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 上級研究員)

推薦コメント
私は1968年生まれなので、今よりは社会に残る戦争の記憶が近かった世代です。ナウシカを読むと、宮崎 駿さんの反戦の思いを強く感じます。人類と文明のあり方について考えさせられる名作だと思います。映画版よりもはるかに奥深いです。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
2021
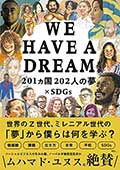
『WE HAVE A DREAM─201カ国202人の夢×SDGs』
- WORLD DREAM PROJECT(編)
- いろは出版 2021年
夢でつながる202人の若者 SDGsが目指す世界
「What is your dream?」そこに寄せられた201カ国、202人の熱い答え。ルワンダで教育改革に取り組むジョセフ、ウクライナで都市緑化活動を始めたオレクサ、北朝鮮の人権保護を訴えるヨンミ。Z世代のSDGs目標達成の希望が地球をつなぐ。

推薦コメント
世界の若者からのメッセージをこんなに多く聞くチャンスはないでしょう。歴史、環境や文化、自由度も異なる次の世代の人々が何を考え、悩み、希望を持って生きていくのか。自分は何ができるか深く考えさせられる1冊です。
松井 南(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ グループディレクター)
2021

『ちきゅうがウンチだらけにならないわけ』
- 松岡 たつひで(作)
- 福音館書店 2013年
食べる、隠れる、運ぶ、住む ウンチがつなぐ生物の環
ヒトもイヌもゾウも鳥も魚も、みんなウンチをする。なのにどうして地球はウンチだらけにならないの?そんなシンプルな疑問を出発点に、絵本作家の松岡 たつひで氏が案内してくれるのは、食物連鎖や生物多様性にまでつながる、地球のエコロジー。自然はこんなに上手く循環している。

推薦コメント
松岡 たつひでさんの絵がとても素敵です。特に良いのは最後に問題提起をしているところ。他の生き物のウンチは自然の中で循環しているのに、人間やペットのウンチは、トイレやゴミ箱に捨てられてしまいます。では捨てた後はどうなるでしょう?人間は衛生面ばかりを気にして、広い視点で見ると利己的な行動をしています。「私たちは自然に対して何ができるだろう」と考えるきっかけになる1冊です。
栗原 恵美子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 研究員)
2021

『土と内臓─微生物がつくる世界』
- デイビッド・モントゴメリー、アン・ビクレー(著)片岡 夏実(訳)
- 築地書館 2016年
嫌われ者?それとも味方?土と人体をつなぐ微生物
著者は、地質学者の夫と生物学者の妻。2人は荒野だった新居の庭に有機物を与えて、生命溢れる庭に変えた。しかし、妻がある日がんになる。これらの経験から、土壌の中と腸の中に棲む微生物に注目し、研究にどっぷりハマった。微生物の重要な働きを知り、食物や人体への見方も変わる。

推薦コメント
土と内臓。一見関係なさそうに思えますが、実は人間の「内側」の腸の中と、植物の「外側」の根の周りが非常に類似した環境にあるということが書かれています。環境やからだへの見方が変わる一冊です。
中村 泰信(量子コンピュータ研究センター センター長)
2021

『家は生態系─あなたは20万種の生き物と暮らしている』
- ロブ ・ダン(著)今西 康子(訳)
- 白揚社 2021年
20万種と同居中!?家は生命の宝庫だった
調べたら、家の中は生き物だらけだった!クモ、ハエ、ゴキブリにダニやカビ……。なんと20万種以上の生き物が、戦ったり助け合ったりしながら一緒に暮らしているのだ。部屋の隅のホコリも、浴室のシャワーヘッドも、生命の宝庫。最も身近な「家」を通して、人間と多様な生物との共生関係を知る。

推薦コメント
家の中の生態系に注目した本。草原、ツンドラ、間欠泉(かんけつせん)の熱湯にさえ生き物が生息するように、冷蔵庫、玄関、シャワーなど家のあらゆるところに生物が棲みついている。身近な生物多様性を活かすも壊すもあなた次第!?「壮大な世界は全てつながっているんだ」と実感できます。
栗原 恵美子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 研究員)
2021
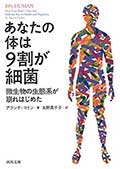
『あなたの体は9割が細菌─微生物の生態系が崩れはじめた』
- アランナ・コリン(著)矢野 真千子(訳)
- 河出書房新社 2020年
腸内の微生物は100兆個 人体という生態系
体には、人間の細胞の9倍もの数の微生物が一緒に住んでいる。人体は多くの生物が共生する惑星だ。なかでも重要なのは腸。腸内細菌のバランスの崩れは、肥満やアレルギー、さらにはうつ病にも関連している。出産時の微生物のやりとりや、食事の大切さ、抗生物質のリスクなど、家族の健康を見直す書。

推薦コメント
腸内細菌の人への影響の大きさに驚かされました。私たちの体型(肥満になりやすさなど)や性格、そしてなんと精神疾患にまで影響があるそうで、今後さらに原因が特定されていくことへの期待が膨らみました。一見関係のなさそうなものにも繋がりがあり、お互いに大きく影響しているということに目が開かされます。
蒔田 由布子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 上級研究員)
2021

『ビジュアル パンデミック・マップ─伝染病の起源・拡大・根絶の歴史』
- サンドラ・ヘンペル(著)関谷 冬華(訳)竹田 誠、竹田 美文(日本語監修)
- 日経ナショナルジオグラフィック社 2020年
目で見て感じるその脅威 感染症と人類の歴史
人類の歴史は感染症との戦いの連続だった!ペストにコレラ、エイズにエボラ出血熱。人類を悩ませてきた20の感染症の発生・流行・終息を、地図上でわかりやすく解説。当時の写真やポスターで、病気への恐怖や偏見もリアルに伝わる。コロナを経験した今こそ手元に置きたい1冊。
2021

『セレンゲティ・ルール─生命はいかに調節されるか』
- ショーン・B. キャロル(著)高橋 洋(訳)
- 紀伊國屋書店 2017年
生態系が健康であるために自然が作ったルールがある
この50年間で、世界のライオンの総数は45万頭から3万頭に減った。分子生物学者の著者は「ある区域における、生息可能な動植物の種類や個体数を調整する自然の摂理」をセレンゲティ・ルールと名づけ、その絶妙なバランスを紐解いていく。壊れた生態系の再生プロジェクトに希望をもらう。

推薦コメント
生物の数はピラミッド型に調整されています。この本では、通常は調整されている生態系が崩れる時に、何が起きているのかを「多すぎ」「少なすぎ」「やりすぎ」というカテゴリーに分類して分析します。すると、ほとんどが人間の「やりすぎ」に起因することが分かるんです。人間の活動がどう生態系のバランスに影響してしまうかを教えてくれます。
栗原 恵美子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 研究員)

推薦コメント
ヌーなどの大型哺乳類が多数生息する「セレンゲティ国立公園」における生態系の調節について論じた良書です。生命がいかに調節されているかを、生物学や医学の発展に多大な貢献をした人物の科学的発見に至るエピソードを紹介しながら、わかりやすく解説しています。
関 原明(環境資源科学研究センター 植物ゲノム発現研究チーム チームリーダー)
2021

『地球の論点─現実的な環境主義者のマニフェスト』
- スチュアート・ブランド(著)仙名 紀(訳)
- 英治出版 2011年
地球への処方箋は!?環境保護のカリスマの主張
70年代のカウンター・カルチャーを牽引した伝説の雑誌「ホールアース・カタログ」。同誌の発行人であり環境保護運動のカリスマであるスチュアート・ブランドが、40年の時を経て「地球のグランドデザイン」を描く。バイオテクノロジーや環境操作、エネルギー問題から経済格差まで、地球と人類の未来を展望する。
2021

『グローバル・グリーン・ニューディール─2028年までに化石燃料文明は崩壊、大胆な経済プランが地球上の生命を救う』
- ジェレミー・リフキン(著)幾島 幸子(訳)
- NHK出版 2020年
教えて、リフキン先生!脱炭素で世界はどうなるの?
化石燃料文明は2028年頃崩壊し、世界中の国も経済もガラリと変わる。新しい時代の主役は、脱炭素、スマートインフラ、そしてグリーン・ニューディールだ。西洋各国の首脳・政府高官アドバイザーとして影響を与え続ける文明評論家リフキンが、次世代を生き抜く大胆なロードマップを示す。

推薦コメント
今まさにG20で議論されている温暖化対策。タイトルは、アメリカの世界恐慌対策のニューディール政策に因んだものです。現在の環境変動は、恐慌前夜なのかもしれません。炭素社会の終焉での再生可能エネルギー、IT等、中国、EUにアメリカを含む全国が加わって進むべき方向性について多くの引用文献をもとに読みやすく書かれています。
松井 南(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ グループディレクター)
2021

『未来を変える目標─SDGsアイデアブック』
- 一般社団法人Think the Earth(編著)蟹江 憲史(監修)ロビン西(マンガ)
- 紀伊國屋書店 2018年
SDGsはむずかしくない!未来への一歩を始めてみよう
SDGsって言われても、いったい何をすればいいのかわからない?だったら、すでに動き出している世界の人たちを知るところからはじめよう!環境問題やジェンダー、貧困などの分野で踏み出しているたくさんの小さな一歩を、イラストや写真、マンガやクイズで紹介。未来の第一歩はここにある!

推薦コメント
私たちの研究センターは、持続的な社会の実現を目指し、植物の研究をしています。SDGsは世界のさまざまな問題について自分で考え始める、良い入り口だと思います。この本は17の目標ごとにデータが充実。クイズもあって楽しく学べます!
蒔田 由布子(環境資源科学研究センター 合成ゲノミクス研究グループ 上級研究員)
2021
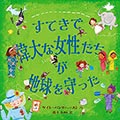
『すてきで偉大な女性たちが地球を守った』
- ケイト・パンクハースト(作)橋本 あゆみ(訳)
- 化学同人 2021年
私がやらなきゃ誰がやる?地球のため戦った女性たち
自分を信じ、勇気をもって行動すれば社会は変わる!森林破壊と戦いノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイや、リサイクル活動で政府を動かしポリ袋禁止を実現したアイサト・シーセイなど、環境保護に取り組んだ女性たちの功績を、カラフルなイラストで紹介。
2021

『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』
- 奥野 克巳(著)
- 亜紀書房 2018年
プナンという生き方が文明社会の常識を問う
ものを借りても返さない。感謝もしない。そもそも悪いと思ってない。非常識?いや、彼らには個人所有という感覚がないのだ。異色の人類学者が、ボルネオ奥地に暮らす狩猟採集民プナンの生活を取材。そこには私たちとは全く異なる他者や自然との繋がり方があった。現代文明の「当たり前」を問いなおす1冊。
2021

『「利他」とは何か』
- 伊藤 亜紗、中島 岳志、若松 英輔、國分 功一郎、磯崎 憲一郎(著)
- 集英社 2021年
コロナで変わったつながり方 キーワードは「利他」
新型コロナウイルスの流行で、人との関わり方が変わりつつある中、「利他」が静かに注目されている。ケア・贈与・民藝・責任・創作という5つの切り口から浮上するのは「他者のためのうつわになる」ことの大切さ。気鋭の論客5人が、コロナ後の社会のあり方を考える。

推薦コメント
異分野の著者5人が利他に関して多角的に論じており、利他に関して一通り知りたければまず読んでおくと良い本だと思います。
橋田 浩一(革新知能統合研究センター 社会における人工知能研究グループ グループディレクター)
