光を追いかけて
波であり粒子である光。掴みづらいその正体に迫る16冊。
2022

『写真科学絵本 ひとすじの光』
- ウォルター・ウィック(著)千葉 茂樹(訳)佐藤 勝昭(監)
- 小学館 2019年
世界的写真家が撮る光の複雑な性質
光ってなあに?虹はなぜ虹色なの?光の波長から、屈折、三原色、色素、分光スペクトル、顕微鏡や望遠鏡まで。数々の実験を通して、光の不思議な性質を解き明かしていく。さがしっこ絵本『ミッケ!』で人気の写真家が20年かけて実現。大人も子どもも感動する、洗練された写真絵本。
2022

『わたしのひかり』
- モリー・バング(著)さくま ゆみこ(訳)
- 評論社 2011年
きらめく町の明かり、もとは太陽から来たエネルギー
部屋を照らす明かりはどこから来るの?太陽光発電はもちろん、水力発電も、風力発電も、石炭を使った火力発電もすべて、太陽のから送られてくるエネルギーを使っているのだ。太陽エネルギーが、さまざまに姿を変えながら、私たちに届くまでを描いた絵本。太陽の貴重さに改めて気づく。
2022
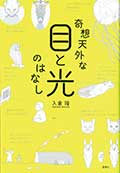
『奇想天外な目と光のはなし』
- 入倉 隆(著)安賀 裕子(画)
- 雷鳥社 2022年
生物の種類によって見える世界はこんなにも違う
視覚心理学の研究者による、目と光の話。白目が見えるようになっているのはヒトの生存戦略、シャコは人間の4倍の色覚を持つ、トンボの目は約2万個あるなど、思わず人に言いたくなるネタが盛りだくさん。生物進化論、視覚心理学、光学をまたいだユニークな1冊。

推薦コメント
人にとって一番身近な光センサーは目。どうして光を捉えると「明るい」と感じるのか、改めて考えるとそれって不思議なことです。この本は、さまざまな生物種の視覚についてイラストつきで解説していて、とてもわかりやすい。私も夢中になって読んでしまいました。
南後 恵理子(放射光科学研究センター 利用技術開拓研究部門 SACLA利用技術開拓グループ 分子動画研究チーム チームリーダー)
2022

『鏡の中の物理学』
- 朝永 振一郎(著)
- 講談社 1976年
量子の世界のロジックとは?朝永 振一郎による物理学入門
鏡の中の世界と現実世界はどう違う?ノーベル物理学賞受賞者・朝永 振一郎による物理の名篇3本を収録。「光子の裁判」は、光子(光の粒子)を被告人に見立てた法廷劇を通じて、量子力学の二重スリット実験の不思議を描いた名作。
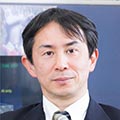
推薦コメント
光の量子的側面、すなわち「光子」の振る舞いを、ノーベル物理学賞を受賞した研究者が平易な語り口調の文章で、わかりやすく解説した名著。第3章「光子の裁判」だけでも読む価値ありです。
田中 拓男(開拓研究本部 田中メタマテリアル研究室 主任研究員)
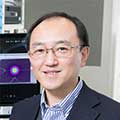
推薦コメント
ノーベル物理学賞を受賞した著者が、身近な「鏡」に映り込むさまざまな物理現象から真理に迫ります。マクロからミクロまで幅広いスケールの物理について、平易な表現で語られているので、結果を予想しながら楽しんで読んでほしいです。また、裁判劇風に語られる「光子の裁判」は有名で、光の波と粒子の二重性を理解する入門書としておすすめです。
南出 泰亜(光量子工学研究センター テラヘルツ光源研究チーム チームリーダー)
2022

『光の量子コンピューター』
- 古澤 明(著)
- 集英社インターナショナル 2019年
量子コンピューター開発の鍵を握る「光」の技術
激化する量子コンピューターの開発競争。さまざまな方式が模索されているが、著者は日本発である「光を使う量子コンピューター」の実現を目指している。量子力学の基本から、光の可能性、実現に向けたカウントダウンまで、研究の最前線に胸が高鳴る。

推薦コメント
光の持つ特徴をフルに使った量子コンピューターの解説。文章から垣間見える著者の情熱も見どころです。ノーベル物理学賞が「量子もつれ」や「ベルの不等式」に授与された2022年、ぜひ手に取ってみてください。
石坂 香子(創発物性科学研究センター 電子状態スペクトロスコピー研究チーム チームリーダー)
2022

『「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる』
- 井上 伸雄(著)
- ベレ出版 2018年
電波と光は電磁波ファミリー基礎から最先端まで一挙に紹介
電波も光も、電磁波の一種だ。テレビ、Wi-Fi、気象レーダーなど、我々の生活を支える「電波」から、光通信、半導体レーザー、量子コンピュータなど、「光」の最新技術まで。電磁波の基礎から、来る光工学の時代まで、一挙に駆け抜ける入門書。

推薦コメント
レーザーを使った技術は多くのノーベル賞の受賞対象となっているだけでなく、いまや身の回りのあらゆる所に使われています。本書籍は電磁波の基本説明から、社会に役立つテクノロジーとしての光まで見渡した、貴重な1冊です。
石坂 香子(創発物性科学研究センター 電子状態スペクトロスコピー研究チーム チームリーダー)
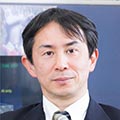
推薦コメント
テレビ・ラジオ・携帯電話の電波も、目に見える光も、レントゲンのX線も、すべて同じ電磁波だと知ってますか?空が青くて夕焼けが赤い訳を知ってますか?電波や光の正体と、それらが関係するさまざまな現象の仕組みが1冊にまとまっています。書名に偽りなしです。
田中 拓男(開拓研究本部 田中メタマテリアル研究室 主任研究員)
2022
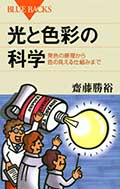
『光と色彩の科学─発色の原理から色の見える仕組みまで』
- 齋藤 勝裕(著)
- 講談社 2010年
色は脳が見るフィクション?分子レベルで知る色の正体
空はなぜ青いのか?緑に安らぎを感じる理由とは?バラの赤とネオンの赤は同じ赤なのか?アリストテレス、ニュートン、ゲーテなど、多くの科学者が探求してきた光と色彩の不思議。視細胞の構造に始まり、色の化学、色と心の関係、未来の色彩まで、色のスペクタクルを多角的に紹介する。
2022

『虹の図鑑─しくみ、種類、観察方法─』
- 武田 康男(著)
- 緑書房 2018年
虹は実体を持たない?変幻自在な絶景を科学する
古来より人々を惹きつけてきた虹。科学的に見ると、光・水滴・観測者の位置関係によって浮かび上がる、光の現象だ。ハワイの満月の夜に出た月虹、アラスカの池に反射する虹など、40年以上虹を追いかける著者が厳選したレアな虹写真が充実。虹のしくみ、観察方法、つくり方などの解説も。
2022
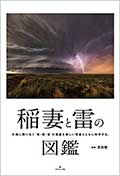
『稲妻と雷の図鑑』
- 吉田 智(編著)
- グラフィック社 2022年
恐ろしくも美しい稲妻 身近な雷の残された謎とは?
東京タワーで発生した上向き雷放電、アリゾナ砂漠を突き刺す閃光、香港の夜景を破る雲放電。雷は積乱雲がもたらす放電現象だが、その発生メカニズムには多くの謎が残されている。雷に魅了された研究者が、写真と共に雷物理を解説する貴重なビジュアル図鑑。ページをめくるたび閃光が走る。
2022
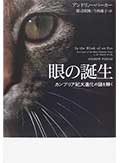
『眼の誕生─カンブリア紀大進化の謎を解く』
- アンドリュー・パーカー(著)渡辺 政隆、今西 康子(訳)
- 草思社 2006年
カンブリア紀の進化の大爆発 その謎を徹底的に追跡する
5億4300万年前から500万年間のカンブリア紀に、わずか4つだった動物門が突如として38もの動物門に進化した。この進化のビッグバンはなぜ起きたのか?古生物の生態と太陽光線との関係を明らかにしつつ、「眼」の誕生こそが、カンブリア紀の進化の鍵であることを解き明かす。
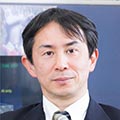
推薦コメント
「眼」という生物が持つ超高性能光学パーツがどうやって生まれたのか。そして眼の誕生が生物の進化にどういう影響を与えたか。生物の急激な進化が起きた「カンブリア爆発」の謎を解明する一説として、興味深い内容です。
田中 拓男(開拓研究本部 田中メタマテリアル研究室 主任研究員)
2022

『ふしぎ!光る生きもの大図鑑』
- 近江谷 克裕、小江 克典(著)
- 国土社 2021年
なぜ光る?どうやって光る?暗闇の中の宝石たち
海をプラネタリウムのように照らし出すウミホタル、点滅するサーチライトの使い手ヒカリキンメダイ、日本人にはなじみの深いゲンジボタル、世界で唯一川の中で光る巻貝カサガイ…。威嚇したり、目くらましにしたり、求愛したり。さまざまな目的とメカニズムで光るふしぎな生き物たちの秘密にせまる。

推薦コメント
光る生物ってこんなにたくさんあったのかと、新しい発見があります。写真の美しさに加えて、説明もわかりやすく、小学生でも多くの学びが得られる本です。最後に実験コーナーがあるのも良いところ。イカに付着した微生物を使った発光実験は、私もやってみたいです。
南後 恵理子(放射光科学研究センター 利用技術開拓研究部門 SACLA利用技術開拓グループ 分子動画研究チーム チームリーダー)
2022

『絵でさぐる 音・光・宇宙─物理学の世界への旅』
- コリン・スチュアート(著)シモ・アバディア(画)片神 貴子(訳)
- 岩崎書店 2020年
カラフルなグラフィックで楽しむマクロとミクロの物理学
イギリスの科学ライターとスペインのアーティストがタッグを組んだ、デザインが魅力の大型絵本。地球の重量、電気と磁気、音の秘密、目に見えない光、光のスピードなど、「音・光・宇宙」に関するトピックを、グラフィックで直感的に伝える。プレゼントにも最適な1冊。
2022

『はじめまして量子力学─ふしぎがいっぱいミクロの世界』
- シェダード・カイド=サラーフ・フェロン、エドゥアール・アルタリーバ(著)橋本 幸士(監)鈴木 真奈美(訳)
- 化学同人 2020年
理解が難しい量子力学をキーワードとイラストで読み解く
粒子でもなく、波でもない。すべての大元でありながら、想像が難しい「量子」の世界をイラストとともに伝える科学絵本。光の謎にはじまり、アインシュタインが考えた光電効果、シュレディンガーのねこ、量子のもつれ、素粒子など、28のキーワードを見開きごとに解説する。
2022

『光と物質のふしぎな理論─私の量子電磁力学』
- R.P.ファインマン(著)釜江 常好、大貫 昌子(訳)
- 岩波書店 2007年
ファインマンさんが挑戦!量子電磁力学を平易に語る
「あなたは何を研究しているの?」。聞かれて説明に困ったノーベル賞物理学者ファインマンが、自身の研究内容である量子電磁力学について分かりやすく伝えることに本気でチャレンジした。光と電子の相互作用についてユーモアを交えて語った、連続講義の書籍化。

推薦コメント
笑いながら読める物理の本は、ファインマンさんが書いたもの以外はないんじゃないでしょうか。私も授業で量子科学を教えているので、数式を使わず一般向けにこの分野の話をすることがどれほど難しいか、身に染みてわかります。物理学への敷居を下げてくれる本当に楽しい本です。
南後 恵理子(放射光科学研究センター 利用技術開拓研究部門 SACLA利用技術開拓グループ 分子動画研究チーム チームリーダー)
2022

『第一人者が明かす光触媒のすべて─基本から最新事例まで完全図解』
- 藤嶋 昭(著)
- ダイヤモンド社 2017年
日本人が発見した光触媒反応。世界中で使われる夢の燃料
日光東照宮やルーブル美術館、クフ王のピラミッド、国際宇宙ステーションまで、世界中で使われる光触媒。抗菌、抗ウイルス、防カビ、防汚、防曇などの効果があり、人工光合成にも使える、夢の燃料だ。1967年に酸化チタンの光触媒反応を発見した第一人者が、活用事例や今後の可能性を紹介する。
2022

『カメラとレンズのしくみがわかる光学入門』
- 安藤 幸司(著)
- インプレス 2019年
「光」が分からなければカメラは使いこなせません
デジタルカメラのボタンを押すと写真が撮れる。当たり前のことだけど、これってどうやっていう仕組みなの?映像計測技術のエンジニアが、光学の基礎やレンズの歴史とともに、カメラのメカニズムを詳しく説明。レーザー光での光記録、デジタル画像処理の話まで。

推薦コメント
私たちにとって身近なスマートフォンのカメラ、これも「光学」です。この本では、光の話を中心に、カメラの仕組みを解説しています。波動性・粒子性といった光の性質から、カメラの歴史、光学ガラス、画像処理まで。専門的ですが、理解しやすいようにイラスト付きで丁寧に書かれているところがとても良いです。
南後 恵理子(放射光科学研究センター 利用技術開拓研究部門 SACLA利用技術開拓グループ 分子動画研究チーム チームリーダー)
