科学道クラシックス 26から50
時代を経ても古びない良書として選んだ「オールタイム・ベスト50」。2019年に選出し、2022年まで引き続き、同じ本をお薦めしました。
クラシックス

『利己的な遺伝子 40周年記念版』
- リチャード・ドーキンス(著)日高 敏隆、岸 由二、羽田 節子、垂水 雄二(訳)
- 紀伊國屋書店 2018年
恋をするのも、争うのもすべては遺伝子の思惑通り?
生物は、遺伝子に利用される「乗り物」に過ぎない-。進化生物学者ドーキンスが「ダーウィンの進化論」を、遺伝子を主語に捉え直した。自らのコピーを増やそうとする遺伝子は、いかに生物を操るのか?親子間の愛や、縄張り闘争も遺伝子のせい?新たな生命観を提示し、大論争を巻き起こした書。

推薦コメント
遺伝子を擬人化して、遺伝子の視点から語っています。この本を機に新しいゲノム観が続々と生まれました。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
クラシックス
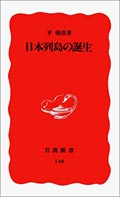
『日本列島の誕生』
- 平 朝彦(著)
- 岩波書店 1990年
深海で発見された日本列島誕生の秘密!
世界地図の中でも、独特な形をしている日本列島。弓状の地形や多数の火山、大陸との間を隔てる日本海。それらの誕生の秘密は深海にあった!?深海の化石の調査や、プレートの水平運動を踏まえ、日本列島が今の形になったプロセスを明らかにする。
クラシックス

『川はどうしてできるのか』
- 藤岡 換太郎(著)
- 講談社 2014年
地形探偵と解き明かす川をめぐる13の謎
ヒマラヤ山脈を乗り越える川がある?タクラマカン砂漠で洪水が発生?海底にも川が流れている?天竜川の源流はロシアにあった?日本人にとってなじみの深い川にも、知られていないたくさんの謎があった。名探偵と一緒に、地形の謎解きミステリーツアーに出かけよう。

推薦コメント
ヒマラヤ山脈を越える川があるなんて、不思議じゃないですか?おもしろいので、とにかく読んでみてください。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
クラシックス

『フンボルトの冒険─自然という〈生命の網〉の発明』
- アンドレア・ウルフ(著)鍛原 多惠子(訳)
- NHK出版 2017年
今こそ見返したいフンボルトの統合的自然観
当時ナポレオンと並ぶ影響力を持っていた大科学者・フンボルト。中南米やロシアを冒険し、環境と動植物の関係を調査。その経験から「生命の網(自然は巨大な一個の生き物で、全てが互いに繋がっている)」という自然観を生み出した。ダーウィンやソローにも影響を与えたその思想と生涯を追う。

推薦コメント
ゲーテと親交の深かったフンボルトは世界中を冒険した大科学者です。500ページ近い本ですがスラスラ読めます。
倉谷 滋(開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員)
クラシックス

『COSMOS(上)(下)』
- カール・セーガン(著)木村 繁(訳)
- 朝日新聞出版 2013年
セーガン博士が語る人類の故郷・コスモス
宇宙という広大な海の浜辺にある地球。探査衛星で明らかになりつつある太陽系の惑星。はるか彼方で輝く星々や銀河。どこかにいるかもしれない宇宙人。カール・セーガン博士が縦横に語るベストセラー。奇跡のように誕生した地球が、核兵器の危機にさらされる現実に警鐘を鳴らす。
推薦コメント
「秩序ある全体としての宇宙」をこれほどおもしろく語る本はありません。高校時代に読んで以来ずっと宇宙や人生と向き合う時の精神的な拠り所になっています。
山崎 展樹(開拓研究本部 上野核分光研究室 専任研究員)
クラシックス

『ホーキング、宇宙を語る─ビッグバンからブラックホールまで』
- スティーヴン・W・ホーキング(著)林 一(訳)
- 早川書房 1995年
宇宙の謎を明かす統一理論へホーキング 博士の思考の軌跡
宇宙はどのように始まり、どう終わるのだろうか?車椅子の物理学者・ホーキング 博士が、数式を使わずに宇宙理論を紐解く。宇宙の膨張、素粒子の力、ブラックホールの構造、時間の本性などを語り、一般相対性理論と量子力学を統合する統一理論を探究する。天才の思考の軌跡を体感できる1冊。

推薦コメント
大学時代、進路を模索し、読み漁った中で出会った一冊です。ホーキング 博士は、宇宙の始まりやブラックホールの謎は、数学と物理を使えばスッキリ理解できるはずと語っています。その明快さと壮大さにロマンを感じ、宇宙物理学専攻を決めました。今でもたまに読み返し、真理を追求し続ける気持ちを再認識します。
長瀧 重博(開拓研究本部 長瀧天体ビッグバン研究室 主任研究員)
クラシックス

『普及版 数の悪魔─算数・数学が楽しくなる12夜』
- エンツェンスベルガー(著)ベルナー(絵)丘沢 静也(訳)
- 晶文社 2000年
10歳から100歳まで楽しめる数学のワンダーランド
ある夜、数学嫌いの少年・ロバートの夢に小柄な老紳士「数の悪魔」が現れ、12夜のレッスンが始まった。洞窟の中で明かされる素数の秘密、うさぎの数で導かれるフィボナッチ数、サイコロを積み上げて学ぶパスカルの三角形……2人と共に冒険するうちに、数学の創造性に魅了される不思議な物語。

推薦コメント
数の悪魔が毎晩夢の中に現れ、少年に数学の魅力を教えるストーリーです。素数やフィボナッチ数、パスカルの三角形、黄金比などをテーマに、小難しくなく、数と遊ぶ楽しさと不思議さを教えてくれます。小学校高学年の頃に読んで、「問題が解けて嬉しい」という以上の数学の奥深さに目覚めました。
杉浦 拓也(数理創造プログラム 特別研究員)
クラシックス
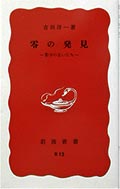
『零の発見─数学の生い立ち』
- 吉田 洋一(著)
- 岩波書店 1979年
もしも「0」がなかったら今の文明は存在しない?
無名のインド人数学者が発見した「0」のおかげで、数学は飛躍的に進歩し、人類の文明にも多大な貢献をもたらした。アラビア数字の誕生から、ピュタゴラスによる三平方の定理、ソロバンやコンピュータなどの計算機の歴史まで。数学嫌いにもなじみの深いトピックに沿って描かれる数学発展史。

推薦コメント
普通は0という数字がイノベーションだと気付きません。それを発見して驚くのが、研究者に必要な力だと思います。
加藤 忠史(脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー)
クラシックス

『フェルマーの最終定理』
- サイモン・シン(著)青木 薫(訳)
- 新潮社 2006年
数学界最大の難問に隠された数学者たちの熱いドラマ
360年間誰も解くことができなかった「フェルマーの最終定理」。町の図書館で数式に出会った少年ワイルズは、人生を数学に捧げ、1995年、ついに完全証明を成し遂げた。サイモン・シンがワイルズへの取材をもとに、3世紀に及ぶ数学者たちの苦闘を描いたノンフィクション。数学はこんなにアツかった。

推薦コメント
360年解けなかった超難問をめぐるノンフィクションです。私のような研究者にも、時に「わかった!」という瞬間が訪れ、幸福感に包まれることがあります。この本では天才数学者ワイルズがフェルマーの最終定理を証明したその瞬間を「言葉にならない美しい瞬間」と振り返ります。そのリアリティは圧巻です。
花栗 哲郎(創発物性科学研究センター 創発物性計測研究チーム チームリーダー)
クラシックス

『新装版 オイラーの贈物─人類の至宝eiπ=-1を学ぶ』
- 吉田 武(著)
- 東海大学出版会 2010年
目的はただ一つ オイラーの公式を理解すること
ファインマンをして「人類の至宝」と言わしめたオイラー公式。その公式を理解することを唯一の目的に、本書はつくられた。パスカルの三角形に始まり、微分積分から三角関数、行列にいたる流れを俯瞰し、数式を解き進める。数学の美の頂点に、ぜひチャレンジしてみて欲しい。

推薦コメント
高校生の頃、大学数学にチャレンジしようと手に取りました。一冊かけてオイラーの公式を理解するために、丁寧に順を追って数式を解説しています。表紙の数式eiπ=-1を初めて見た時、一見関係のない3つの値が並んでシンプルな解になることに驚きました。初めて数学の美しさを学んだ印象的な本です。
磯部 忠明(仁科加速器科学研究センター RI物理研究室 専任研究員)
クラシックス
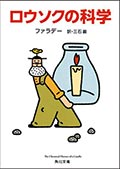
『ロウソクの科学』
- ファラデー(著)三石 巌(訳)
- 角川書店 2012年
1本のロウソクに始まるファラデーの伝説の講演
炎、大気、水、物質。たった一本のロウソクに宇宙の法則がすべてある。19世紀イギリスの大科学者ファラデーが、ロウソクの実験を通して子どもたちに伝える科学と自然と人間との深い関わり。少年少女の心で耳を澄ませたい、クリスマスの夜の特別講演。

推薦コメント
「電磁誘導の法則」を発見した物理学者、マイケル・ファラデー(1791ー1867)が子ども向けのクリスマス・レクチャーで語った内容を本にしたもの。「ロウソクが燃える」ということに関わる深淵な物理現象を説明しています。
仲 真紀子(理化学研究所 理事)
クラシックス

『物理学とは何だろうか(上)(下)』
- 朝永 振一郎(著)
- 岩波書店 1979年
星を見つめることから物理学の歴史は始まった
近代物理学は占星術や錬金術などから生まれた。占星術を天文学に発展させたケプラー、「実験」という方法を導入したガリレオ、錬金術から化学を育てたボイル、万有引力を発見したニュートン……。ノーベル賞受賞者の朝永 振一郎が、物理学の歴史を振り返りながら、科学が進むべき未来を展望する。

推薦コメント
湯川さんの終生のライバルである朝永 振一郎さんが物理学の歴史を解いたのがこの本。名著です。
初田 哲男(数理創造プログラム プログラムディレクター)
クラシックス

『だれが原子をみたか』
- 江沢 洋(著)
- 岩波書店 2013年
古代から想像されてきた「原子」が発見されるまで
「原子」は存在するのか?アリストテレスの時代から、アインシュタインが登場するまで、原子の存在をめぐる論争は長い間続いてきた。科学者たちによる仮説と実験の繰り返しの歴史を辿り、実験を再現。その苦難の道を追体験する。
クラシックス

『不思議の国のトムキンス〈復刻版〉』
- ジョージ・ガモフ(著)伏見 康治(訳)
- 白揚社 2016年
トムキンス氏と旅する相対性理論のヘンテコな世界
銀行員トムキンス氏は、相対性理論の講演を聞きながらウトウト…。すると世界は一変していた。速度を上げると体が平べったくなる「のろい町」、1匹の動物が何十匹にも広がって見える「量子ジャングル」。ロシアの物理学者ガモフが相対性理論と量子論を物語に仕立てた。アインシュタインも読んだ不思議の国のお話。
クラシックス

『ねじとねじ回し─この千年で最高の発明をめぐる物語』
- ヴィトルト・リプチンスキ(著)春日井 晶子(訳)
- 早川書房 2010年
ねじとねじ回しがなかったら科学も経済も遅れていた!?
この1000年で最大の発明はねじであると著者は言う。蛇口から携帯電話、ペットボトルのふたまで、ねじがなければ生まれなかった。古代ギリシアから用いられていた回転と螺旋の工学。日用品を見る目がガラリと変わる物語。
クラシックス

『世界の発明発見歴史百科』
- テリー・ブレヴァートン(著)日暮 雅通(訳)
- 原書房 2015年
先史時代から21世紀まで人類史の重要発見&発明300
260万年前の石のナイフから、原子論、印刷術、蒸気機関、クローン化技術、ウィキペディアまで。生活を一変させ常識を覆した重要な発明・発見300項目を年代順に紹介した事典。ボタンホールや絆創膏、水洗トイレ、鉛筆、歯磨き粉など、身近なものの発明秘話も楽しい。
クラシックス

『新装版 道具と機械の本─てこからコンピューターまで』
- デビッド・マコーレイ(作)歌崎 秀史(訳)
- 岩波書店 2011年
こんな仕組みで動いていた!道具と機械のイラスト図鑑
缶切り、トイレのタンク、人工衛星、コンピュータ。実験助手のマンモスくんが、200種の道具と機械のからくりを案内してくれる大型図鑑。てこの原理やバネの力、浮力の利用など、発明に使われている原理で分類しているから、仕組みが理解しやすい。400ページ1.7kgのヘビー級。一家に1冊欲しい。
クラシックス

『届かなかった手紙─原爆開発「マンハッタン計画」科学者たちの叫び』
- 大平 一枝(著)
- 角川書店 2017年
原爆投下の裏のドラマ開発した科学者たちの苦悩
1945年、原爆投下の直前、大統領宛に送られた70人の署名。反対を訴えたのは開発に携わる科学者だったー。原爆開発の裏で何があったのか?署名を集めた物理学者シラードとは?真実を知るべく、著者は渡米し、署名した科学者たちを取材。90歳を超える彼らの証言から見えてくるマンハッタン計画の本質とは。
クラシックス

『ニコラ・テスラ 秘密の告白─世界システム=私の履歴書 フリーエネルギー=真空中の宇宙』
- ニコラ・テスラ(著)宮本 寿代(訳)
- 成甲書房 2013年
エジソンのライバル天才発明家の自伝的告白
電気の交流誘導モーターを発明し、エジソンのライバルと呼ばれたニコラ・テスラ。天才を形成したのは、幼少期の奇妙な体験や病との戦いだった。やがて探究は地球や人類自体のエネルギー利用へと発展する。彼はどのように発想し、未来を予想したのか。本人の回顧録から脳内を覗き見る。
クラシックス
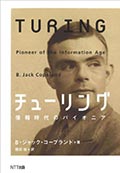
『チューリング─情報時代のパイオニア』
- B・ジャック・コープランド(著)服部 桂(訳)
- NTT出版 2013年
コンピュータの父でAI創設者チューリングの生涯を追う
コンピュータの基本モデル「チューリング・マシン」を考案し、人工知能の先駆研究も行なった英国の天才数学者、アラン・チューリング。第二次世界大戦では、ナチスの暗号を解読して勝利に貢献。しかし41歳で謎の死を遂げる。生い立ちから、ゲイとしての私生活、理論の詳細まで、逸話に溢れる人生を描く。
クラシックス

『ウィーナー サイバネティックス─動物と機械における制御と通信』
- ノーバート・ウィーナー(著)池原 止戈夫、彌永 昌吉、室賀 三郎、戸田 巌(訳)
- 岩波書店 2011年
サイバネティックスという新しい学問領域を生み出した書
足を動かす、コップに手を伸ばして水を飲む。数学者ウィーナーは、こんな単純な動作にも、複雑な制御の仕組みが働いているのだと考えた。心の動きや、社会までをダイナミックな制御システムとして捉え、20世紀後半の科学技術に多大な影響を与えた書。人工知能や認知科学、非線形科学の研究の基礎になった。1948年初版刊行。
クラシックス

『システムの科学 第3版』
- ハーバート・A・サイモン(著)稲葉 元吉、吉原 英樹(訳)
- パーソナルメディア 1999年
ノーベル経済学賞受賞者が探る人工物の本質と可能性
自然や社会といった複雑な外部環境のなかで、自らの目的を達成するために、人間はさまざまな人工物をつくってきた。本書では、飛行機やコンピュータのようなモノから、経済や企業のような社会組織までを、人間が設計した「人工システム」として捉え、その本質を探る。
クラシックス

『サイエンス・インポッシブル─SF世界は実現可能か』
- ミチオ・カク(著)斉藤 隆央(訳)
- NHK出版 2008年
タイムマシンやテレパシーSFの技術は実現するのか?
理論物理学者ミチオ・カクが「SFで描かれるテクノロジーは実現可能か?」について、不可能を3つのレベルに分けて論じる。テレポーテーションは不可能レベル1で今世紀~来世紀中には実現するかも。予知能力はレベル3でまず不可能。では透明人間は?好奇心のままに読むうちに、物理の知識もグンと増える。
推薦コメント
サイエンスをエンターテインメントに乗せて発信していくことは非常に大事です。僕は昔、子ども向けの講演によくこの本を使っていました。本書では「不可能」を3つのレベルに分けていますが、「なにが可能で不可能か」にはバラエティがある。夢のようなSFの世界も、現在にすでに萌芽があるのです。
十倉 好紀(創発物性科学研究センター センター長)
クラシックス

『ほしのはじまり─決定版 星 新一ショートショート』
- 星 新一(著)新井 素子(編)
- 角川書店 2007年
星 新一の描く未来は50年以上経っても古びない
科学者の幼い頃の愛読書としてよく名が挙がる星 新一。SFを中心に1000編を超える作品を執筆した、ショートショートの神様だ。バーで働く美人ロボットを描いた「ボッコちゃん」、平和な休日に突然恐竜が出現する「午後の恐竜」など、星チルドレンの作家・新井 素子が選び抜いた54篇を収録した保存版。

推薦コメント
小学生の頃、星 新一のショートショートに夢中になりました。今読んでも古くならないおもしろさがありますね。
鈴木 千歳(バトンゾーン研究推進プログラム 人工ワクチン研究チーム テクニカルスタッフ)
クラシックス

『星を継ぐもの』
- ジェイムズ・P・ホーガン(著)池 央耿(訳)
- 東京創元社 1980年
5万年前の月面に人が?宇宙と人類の謎に迫るSF
月面で宇宙服を着た死体が発見された。調査の結果、彼は5万年前に死亡していたことが分かる。地球が旧石器時代だった頃、月面を闊歩していた人間とは一体何者か?月や地球との関係は?突如現れた巨大な謎に、研究者たちが果敢に挑む。宇宙スケールで人類の起源を冒険する、ハードSF。

推薦コメント
月で5万年前の人の遺体が発見されたという所から始まるSFです。大胆な謎解きに引き込まれました。
杉浦 拓也(数理創造プログラム 特別研究員)
