2024年12月27日、理化学研究所計算科学研究センター(R-CCS)は、神戸大学大学院理学研究科附属惑星科学研究センター、および慶應義塾大学理工学部情報工学科、東京大学情報基盤センターと共同で「次世代計算機盤に係る調査研究」事業に関する合同ワークショップ〜フィージビリティスタディ結果報告〜を開催しました。当日は会場とオンライン合わせて500名ほどの方に参加いただきました。
本事業は、2022 年8月に文部科学省「次世代計算基盤に係る調査研究」事業として、システム研究調査チーム 2件、新計算原理調査研究チーム1件、運用技術調査研究チーム1件が採択され、次世代計算基盤のシステムの方向性や運用の在り方について調査研究(FS:フィージビリティスタディ)を実施しています。2024年度は本事業の最終年度となるため、今回のワークショップではこれまで実施してきた調査研究の結果について、さまざまな分野の研究者を中心とした参加者に広く報告することを目的として開催されました。
 会場の様子
会場の様子本ワークショップ第一部では、まず「次世代計算基盤に係る調査研究」の田浦 健次朗プログラムディレクターより、本事業の紹介を兼ねた開会挨拶がありました。その後、システム調査研究チームの近藤 正章 チームリーダー(理化学研究所)、牧野 淳一郎 特命教授(神戸大学)、新計算原理調査研究チームの天野 英晴 上席研究員(東京大学)、運用技術調査研究チームの塙 敏博 教授(東京大学)が、それぞれのチームで実施してきた調査研究の結果を報告しました。
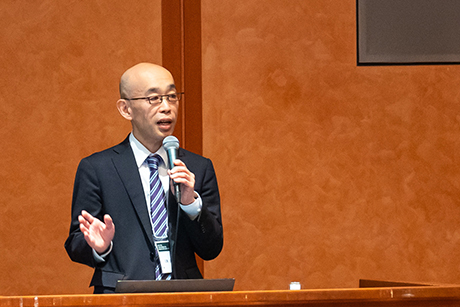
近藤 正章 チームリーダー

栗原 潔 文部科学省 計算科学技術推進室長
第二部では、文部科学省の栗原 潔 計算科学技術推進室長より「ポスト富岳時代を見据えた、新たな政府のスパコン戦略の展望」と題して講演いただきました。続いて本事業の小林 広明プログラムディレクターをモデレーターとして「今後の次世代計算基盤開発・整備の在り方」をテーマにパネルディスカッションを行いました。パネリストとして市村 強 教授(東京大学)、栗原 潔 計算科学技術推進室長、小島 熙之 氏(Kotoba Technologies, Inc CEO)、高木 亮治 准教授(宇宙航空研究開発機構)、焼野 藍子 准教授(東北大学)に登壇いただき、各チームの報告者やプログラムディレクター、会場での参加者も巻き込みながら、活発な意見交換が行われました。
最後に、朴 泰祐プログラムディレクターより閉会の挨拶を行いました。
 パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションの様子会全体を通して、さまざまな立場の方が率直な意見を述べられ、非常に実りのある会となりました。また登壇者からは、本調査研究で得られた知見は非常に有用で、次世代の計算基盤開発だけでなく今後のHPCI※業界全体にとって重要であること、今回築かれた協力体制を、本事業終了後も維持していくことが大事だというコメントがありました。
※HPCI(革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ):「富岳」をはじめ、国内の大学や研究機関の計算機システムやストレージを高速ネットワークで結んだ共用計算環境基盤のこと。
なお、当日の発表資料を以下のページにて公開しております。ぜひご覧ください。
次世代計算基盤に係る調査研究に関する合同ワークショップ ~フィージビリティスタディ結果報告~(2024年12月27日・東京/オンライン)
関連リンク
- 2024年12月27日シンポジウム「2024年度 次世代計算基盤に係る調査研究に関する合同ワークショップ ~フィージビリティスタディ結果報告~」
