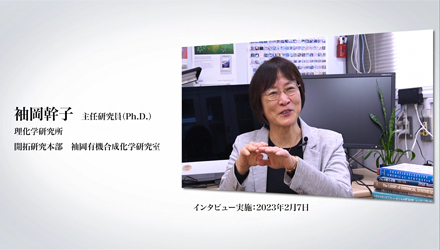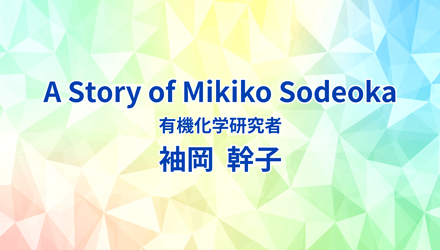若手に権限委譲するラボ・マネジメント
袖岡 幹子 主任研究員(Ph.D.)
理化学研究所 開拓研究本部 袖岡有機合成化学研究室
(インタビュー当時)
略歴
| 1981年 | 千葉大学 薬学部 薬学科卒業 |
| 1983年 | 千葉大学 大学院薬学研究科 博士前期課程修了 |
| 1983年 | 公益財団法人相模中央化学研究所 勤務 |
| 1986年-1992年 | 北海道大学 薬学部 教務職員 / 助手 |
| 1989年 | 薬学博士号取得(千葉大学より) |
| 1990年-1992年 | 米国ハーバード大学 化学科 博士研究員 |
| 1992年 | 東京大学 薬学部 助手 |
| 1996年 | 公益財団法人相模中央化学研究所 副主任研究員 / 主任研究員 |
| 1999年 | 東京大学 分子細胞生物学研究所 助教授 |
| 2000年 | 東北大学 教授(反応化学研究所 / 多元物質科学研究所) |
| 2006年-2024年 | 理化学研究所 主任研究員 |
| 2013年-現在 | 理化学研究所 環境資源科学研究センター グループディレクター 兼務 |
| 2022年-現在 | 理化学研究所 環境資源科学研究センター 副センター長 |
| 2024年-現在 | 理化学研究所 理事長補佐 |
プロジェクト説明
足立:このプロジェクトは前理事の原山先生がELSEVIER FOUNDATIONのボードメンバーでいらっしゃったことから、「理研で、女性研究者とか若手研究者向けの何かをやってみませんか」とお話しをいただいて、我々がスタートしたものです。本日はサイエンティフィックなお話しではなく、ラボのマネジメントやリーダーシップなど若手の研究者がこれからPIになる時に、何か参考になるようなお話しが伺えたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。
袖岡:よろしくお願いします。
修士号を取得後、研究職で就職
足立:袖岡先生の略歴を拝見いたしました。1983年に千葉大の博士前期課程を修了されてマスターを取られたら、財団法人相模中央化学研究所に就職されたということですが、博士後期課程には進まずに民間財団法人の研究所に勤務されたきっかけは何かありますか。
袖岡:私は生物と化学が好きで、何より薬剤師の免許が取れるので、将来困らないかなと考えて薬学部に行きました。4年生で研究室に配属になったら、とっても実験が面白かったです。当時、薬学部はかなり女性が多かったのですが、それでも大学院に行く女性は非常に少なかったです。私は、実験が面白いからもう少し勉強したい、修士に行こうと思いました。その時に結構周りの人から、「修士課程、大学院なんかに行ったら、就職先がなくなりますよ」と言われました。当時はまだ男女雇用機会均等法の前だったので、みんなにそう言われました。でも、その時に直接実験の指導をしてくださっていた先生が女性で、非常にバリバリ研究されていたので、まあ何とかなるかな、とにかく修士に行こう、と思って進学しました。研究を始めると、本当に面白かったです。その頃に、研究者としてやっていきたいなと思い始めました。ただ修士を終える頃になって就職を考えた時に、大学のポジションがなかなかなかったです。それならば企業の研究所で研究をしたいなと思ったのですが、当時はまだ企業の方も「うちは女性の研究職は取りません」と堂々と言える時代で、どこも試験さえも受けさせてくれませんでした。そういう状況だと、なかなかそのまま博士課程に行くという決心もできませんでした。本当にどうしようかな、ぎりぎりまで困ったなと思っていたところに、相模中研から声をかけていただいて、研究補助員という形で拾っていただきました。何とか相模中研に、研究職というか研究補助員で就職ができました。
足立:相模中央研究所には、お知り合いはいたのですか。
袖岡:ちょうど、修士の時の先生であった日野先生と同じ研究室出身である柴﨑先生が、相模中研でPIになって、新しくグループを始めるというタイミングでした。その時に、「誰か(研究職を探している)そういう方はいませんか」と、ちょうど声をかけていただいて、採用していただきました。
足立:相模中央化学研究所というのは、私もホームページを拝見して、非常にユニークな研究所なんだろうと思ったのですが。
袖岡:そうですね。はい。
足立:アカデミア、大学や理研とは少し違う形なのでしょうか。
袖岡:当時の相模中研は、今はバブルがはじけてなくなってしまった日本興業銀行がスポンサーで、興銀系の化学会社がついていました。かなりアカデミックな研究もできるけれども、企業ともいっぱい繋がっていて、社会に近い研究をしている、アカデミア・大学と企業の真ん中くらいに位置するような研究所で、当時は本当にアクティブでした。当時、日本の大学もコンサバティブで、大学のアカデミックなポジションは、上の人が誰か辞めない限り空かない、公募もほとんどない、という時代でした。アカデミアには行きたいけれども、ポジションがすぐにはないような、すごくアグレッシブな研究者が、ポスドクあるいは私みたいに修士を出ている人も含めて、全国のいろいろな大学のいろいろな学部から集まっていて、ものすごく活気のある所でした。だから研究をすごく一生懸命やりました。また、割と研究室間の垣根が低い組織だったので、自分のラボだけではなく、いろいろなラボの人達とよく飲みよく遊び、という感じで、ものすごく楽しい研究所でしたね。
足立:研究環境としても非常に恵まれていたのですか。
袖岡:そうでしたね、当時としては。当時の理研を知らないですが、少なくとも大学と比べたらはるかに恵まれた場所でした。
足立:3年間、研究補助員として、自分の研究ではなくてPIのサポートをされたという形でしたか。
袖岡:ちょうど、柴﨑先生が36歳ぐらいで、初めてPIになられて、「さぁやるぞ」とやる気満々でラボを立ち上げられたタイミングでしたので、基本的には、先生がやろうとする研究を一緒にやる感じで、研究を始めました。私にとってはそれまで大学院でやっていた研究とは全然違う研究だったので、非常に勉強になりました。当時、柴﨑先生が新しくラボを構えられて、とにかく早く良い研究成果を出したいというタイミングだったので、非常にたくさん「あの実験、この実験、これをやってみましょう」と、いろいろなことを求められました。その時は、「そんなに言われてもできない」と思ったりもしたのですが、でもこちらも意地になってやっているうちに、気がついたら自分ができるキャパが広がっていたな、ということを結構経験しました。また、非常に熱く研究を語る先生だったので、ますます研究が面白くなりました。そういう状況もあり、もっと研究者としてやっていきたいな、博士号も取りたいな、とすごく強く思いました。
働きながら博士号取得へ
足立:3年間がんばって、相模中央(化学)研究所で勤められた後に、北大に教務職員助手として転出をされたきっかけは何でしょうか。
袖岡:ボスであった先生が北大の教授になられて、一緒について行ったという流れになります。
足立:なるほど。それと並行して、1989年に千葉大で薬学博士を取得されていらっしゃいますが、それは論文博士という形なのでしょうか。
袖岡:そうですね。相模中研でやった研究をそのまま北大でも続けました。当時、昼間は学生さんの面倒を見ながら自分の実験をして、夜中に学位論文を書くという生活をしばらくしていました。結構大変だったのですが、それで無事、論文博士を取ることができたという感じです。
足立:マスターまでの母校である千葉大で論文博士を出されたのですね。その時は、自分のお仕事と、それに加えて自分の論文のための研究ということで、かなりハードに働かれたのですか。
袖岡:そうですね。ドクター論文を書いてる間は結構大変でした。
海外での研究に挑戦
足立:そして北大の身分を維持しながら、アメリカのハーバード大学に派遣されたのですか。
袖岡:ポスドクという感じでしたが、当時は助手の身分を休職して海外に留学することができた時代だったんです。学位を取って、留学の機会をいただいて、留学をさせてもらいました。
足立:海外でやってみたいなというのは、かなり早い段階から考えられていたのですか。
袖岡:学位を取った後ぐらいから、自分もゆくゆくはPIになりたいなと考えるようになりました。ボスの先生が、「袖岡さん、PIになるっていうのは、真っ白なキャンパスにゼロから絵が描けるかどうかですよ」と言ってくださいました。確かに一生懸命研究していて、自分なりに考えて展開したりしていたつもりだったんですけど、確かにボスの研究の範疇を全然出ていない。自分があと何年か経った時にゼロから描くとしたら、どんな研究がしたいかなと、留学をさせていただけることになった時に、考え始めました。当時その頃までは有機合成化学や触媒化学をやっていたのですが、ケミストリーとバイオロジーの境界領域みたいな研究をしたいと思いました。そこで、留学を機会にいったんそれまでやっていた研究を離れて、バイオロジーの勉強をしたいなとすごく強く思いました。それで、バイオロジーの研究室に留学しようと思ったんですが、当時の私の英語力がなく、ボスの先生に、「袖岡さん、研究の内容も分からなくて、英語も分からなかったらどうにもならない。2年行かせてあげるから、1年目は英語が聞き取れなくても実験ができる有機合成化学の所に行って、そこで英語がちゃんとできるようになったら、2年目に好きな所に移ったらどうですか」とアドバイスしていただいて、確かにそうだなと思いました。そこで、1年目は私のボスである柴﨑先生が、昔留学していたE. J. Corey先生というハーバードの先生にお願いしてくださいました。そこに留学をして、1年後にようやく英語が分かるようになったので、同じDepartmentの中のMolecular BiologyをやっていたGreg Verdine先生という若い先生の所に移って、バイオロジーの勉強をさせてもらったというのが2年間の留学ですね。
足立:そして1992年に、東大の助手で戻られたきっかけは何でしょうか。
袖岡:柴﨑先生が、私が留学している間に東大の教授に移られ、「袖岡さん、もう1回戻ってきますか」と東大に呼んでいただきました。なので、そこまではずっと、柴﨑先生について行ったという感じですね。
PIとして研究室を構えて
足立:そして1996年に相模中央化学研究所に戻られたということなのですか。
袖岡:はい。
足立:どのようなきっかけだったのですか。
袖岡:留学から帰ってきて、新しいことを少し柴﨑先生にやらせていただきました。自分のグループを持ちたいなとすごく思い始めた時期で、ちょうどタイミング良く、相模中研から「グループリーダーで戻ってきませんか」と声をかけていただいて、相模中研に移ったという形になります。
足立:では、ここで初めて研究室を持たれたのですね。
袖岡:そうですね。
足立:実際に自分の研究室を構えて、どうでしたか。
袖岡:相模の研究室は、ポスドクさん2人と、技術補助員のような方が2~3人、あとは、卒研生が1人ぐらいの、割と小さなグループでした。まさに昔、柴﨑先生が始められたのと同じような形で、実際に私は一回そこで見ていたので、大体様子も分かっていました。その時は本当に、「さあやるぞ」と、自分がやりたいことをそこで始めた感じでした。
足立:実際に研究室を持たれて、戸惑ったことや、こういうことを知らなかったなぁ、ということはありますか。
袖岡:相模中研は元々いた所で、以前いた時と同じようなグループを立ち上げた形でしたので、すごく困ったことはなかったです。良いポスドクさんを探しリクルートする、その方に来ていただくために、一生懸命動く、ということは初めて経験しました。
足立:ポスドクさんを雇う時に、袖岡先生なりに気をつけたことや、工夫されたことがありますか。
袖岡:やっぱり自分の知っている人が、その人(ポスドク)を知っているというのは、とても安心できますよね。理研に来てからは、たくさんのポスドクの方と一緒に仕事をするようになり、普通にアプリケーション(応募書類)が来てという方も多いですが、最初の頃は、知り合いのつてで「誰かいい人いませんか」と言って、「ここにこんな人がいますよ」と教えてもらうやり方をしていました。
足立:そこを3年で辞められて、次に東大の助教授に移られたきっかけは何でしょうか。
袖岡:ちょうどバブルがはじけて、日本中の銀行がバタバタとつぶれていく時代になって、日本興業銀行自体が危ない、もうそういう所(研究所)にお金を出している場合じゃないぞっていう状況になったのです。相模も辞めざるを得ないというか、相模にそのままいても、未来はないなという状況に陥ったので、とにかくどこか探さなきゃと思いました。いくつかの大学教授ポジションにアプライしていたのですが、なかなか決まらなかったです。どうしようかなと思っていたところに、東大の当時の分子細胞生物学研究所の橋本先生が声をかけてくださいました。結果的には割とすぐ東北大の教授に決まってしまったので、橋本先生の研究室にいた時間は非常に短いですが、その研究室は、1つの研究室の中で有機合成化学と生物の実験と両方やっていらして、1つのラボの中で、2つの違う研究をどうやって進めていくかということを見させていただいたのは、非常に良い経験になりました。その後も橋本先生には大変お世話になって、今でも頭があがらない先生です。
足立:結果としては1年間、東大で過ごされて、その時は講座制の助教授でしたか。
袖岡:PIではなくて、一回、その先生のラボの助教授という立場になりました。でもその先生は非常に理解があって、彼の研究に協力しながら、自分でやりたい研究もやっても良いですよとおっしゃってくださいました。
足立:引き続き、やっぱり自分の研究室を持ちたいということで、アプライをあちこち出されていた感じでしょうか。
袖岡:実はすでにアプライを出していました。でも音沙汰がないので、だめかなと思っていたのです。橋本先生の研究室に移った途端にヒアリング(面接審査)に呼んでいただいて、そのまま決まったという感じのタイミングでした。
足立:そうすると、東北大で教授として研究室を構えて、頑張っていこうという感じになったのでしょうか。
袖岡:はい。
足立:東北大では6年間過ごされていますけれども、先生のキャリアの中でどのような時代でしたか。
袖岡:東北大は、元気な学生さんが来て、学生さん中心の研究室を立ち上げるという感じでした。私が教授で行った時点では、前の先生と一緒にやられていた助教授の先生がまだ残っていらした。その(助教授の)学生さんもいる所に自分が赴任して行く形でした。でも実は(以前)柴﨑先生が北大に行かれた時も、そういう状況で、そういう所を見ていたので、いかに元からいらっしゃる方と仲良くやるかということに最初は気を使いました。でも結果的には非常にうまく行き、その(助教授の)先生も栄転されました。
足立:そうすると、東北大にもテニュアでいらっしゃったのですね。
袖岡:はい。
理研へ
足立:そこで2006年に理研に来られようと思ったきっかけは何でしょうか。
袖岡:最初私が(東北大に)赴任した時には、反応化学研究所という小さな化学中心の研究所でした。少し生物がかったことをやっている先生もいらっしゃる研究所だったのですが、翌年改組になりました。科学計測研究所、素材工学研究所、と3つの研究所が一緒になって、多元物質科学研究所という大きな研究所になりました。材料開発にフォーカスをする研究所になったので、ここでバイオロジーとの境界領域を広げていくのは少し難しいかなと感じました。一応、少しそういう実験ができるラボを作り始めてはいたんですが、大きく展開するのはなかなか難しいかなと思いました。それで、理研に移ることになったという経緯です。理研は吉田稔さんとか長田裕之さんとか、ケミカルバイオロジーをやってらっしゃる方がいて、非常にそういうことがやりやすそうな場所だなと思って、理研に動く決心をしました。
足立:そうすると、理研側から声がかかったという感じだったのか、袖岡先生が公募に応募されたのか、どんな感じだったのですか。
袖岡:ちょっと声をかけていただいたのですが、最終的には公募に応募して選んでいただいたという形です。
足立:自分自身のラボを立ち上げる経験を何回か重ねてこられていますが、理研ではどんなラボを作りたいと思って来られましたか。
袖岡:理研ではケミカルバイオロジー、ケミストリーとバイオロジーを両方できるようなラボを作りたいと思いました。理研に移ってきてから、段々とバイオロジーのファシリティも作っていったという感じです。理研の素晴らしいところは、本当に研究室の垣根が低いし、皆さん本当に新しく来た人を助けようとするメンタリティーが強いです。私がここに初めて来た時は、(前任の)中田先生が作られた完全に有機合成化学研究用のラボでした。そして、反対側に伊藤幸成さんのラボがありました。ちょうどその時、伊藤さんもバイオロジーのファシリティを作ろうとされていました。彼が作った実験室を半分使わせてもらって、バイオロジーの実験を少しずつ始めました。装置とかもないので、長田研、吉田研に借りに行って、実験をやらせてもらうという感じで、とてもやりやすかったですね。
留学していた時に、1年目は完全に有機合成化学のラボで、Corey先生は大変偉い先生で、私が行ってすぐノーベル賞を取られました。非常に厳しくて、Corey先生が毎日紙と鉛筆を持ってきて、一人一人とディスカッションして回り、次にやることを書いて置いていく。また次に先生が来るまでにやってないと大変というので、皆さんすごいピリピリしているようなラボで、セミナーもなかったです。もうとにかくハードワーキングが大事だというラボだったんですね。2つ目のラボは全然違って、当時私と同い年のアシスタントプロフェッサーの人が立ち上げたばかりでした。大学院生もみんなで助け合って研究しようねという感じでした。装置とかもまだないので、お隣のこれまたすごい大先生、Schreiber先生のラボに装置とかをみんなで借りに行きました。下の人同士ですごく仲良くなれるみたいな感じのラボでした。180度違うラボを2つ経験しましたが、理研に来てラボを立ち上げた時は、まさにその2番目のラボの雰囲気だったかなという気がします。
足立:そうすると、バイオロジーのほうにも手を広げられていく時に、ポスドクさんもちょっと土地勘のないところで募集をされたと思うのですが、その時に工夫された点とかありますか。
袖岡:やはり知ってる先生に「誰かいませんか」と推薦してもらって、という感じでしたね。やっぱりなかなかバイオロジーの方は来てくださらないんです。最初にうちのラボでちゃんとバイオロジーができるようになったのは、今神戸の理研にいる土屋 綾子さんという方が来てから。あの時は何で(どの予算で)来てたのかな。CRESTか何かの博士研究者、ポスドクさんという感じで、知っている先生の紹介で、その先生のラボの方が来てくださった。普通の完全にバイオロジーのラボ(出身の方)だと、なかなかケミストリーの人とうまくコミュニケーションがいかなかったりもするのですが、彼女は元々天然物みたいなことをやっていたラボの出身で、非常に人柄も良くてパワフルな方でした。彼女のおかげでできることが広がったかなという気がしますね。
もう1人(のキーパーソン)は闐闐(どど)さんで、彼は東北大からです。元々は先ほどの橋本先生の修士の学生で、私が東大の時に一緒だった人です。博士課程から東北大に来てくれました。当時は(私自身が)まさか後々理研に行くことになるとは思ってもいなかったんですが、バイオロジーの細胞培養とかいろいろなことを学ぶために、理研の長田研に闐闐さんを派遣して、そこでいろいろなことを勉強してもらいました。それで東北大でも、少し生物系の実験を立ち上げることができました。理研に来てからは、彼がバイオロジカルな研究の中心になって、いろいろなことを今やってくれているという感じです。
足立:そうすると、バイオロジーとケミストリーいう異分野を融合させる時に、それぞれキーになる人の助けを借りながらラボ全体のマネジメントをされたのですか。
袖岡:そうですね。
研究者キャリアでの転換点
足立:袖岡先生の研究者のキャリアを振り返って、一番のジャンプといいますか、ここはかなりPIとして変わったなとか、研究者としても完全にキャリアのステージが変わった時はどんな時でしたか。
袖岡:やっぱり理研に来た時かなとは思いますね。やれる研究の幅が広がったというか。ちょうど大きな研究費が採択されたというのもありますが、理研はフレキシブルにそういう時に場所を使わせてくれて、一時は非常にたくさんコワーカーがいる状況になりました。できることが広がって、(化学と生物学の)境界領域の研究をちゃんと本格的にできるようになったという意味では、やっぱり理研に来たというのが転換点かなと思います。
足立:コワーカーが増えたりとか、大きな予算をいただいた時に、結構慣れないことや自分自身でもいろいろ改善をしながらというところがあったと思いますが、どんな工夫をされて、忙しい状況を乗り越えられましたか。
袖岡:ラボのマネジメントの仕方を少し変えた、というのはあるかなと思います。東北大にいる頃から、助手の方に何人かの学生さんと一緒にやってもらい、それぞれ違うテーマで走る体制にはしていました。そのプロジェクトをやるくらいになると、東北大から一緒に来てくれた(スタッフ研究員の)闐闐さんとか平井さんとか、濱島さんとかが30半ばくらいになり、そろそろ彼ら自身がPIになる準備期間というか、そういう年代になってきたこともありました。かなり彼らに任せる、彼らの裁量と責任の範囲を広げてやる形に、少しずつシフトをしました。自分自身があまりにも忙しくなって、手が回らなくなったっていうのもあるんですけれども。そのように、ラボのマネジメントという意味では、サブグループ体制みたいな形にシフトしました。
ラボ・マネジメントのコツ
足立:若い方に任せる時に、これだけはぜひ守ってほしいみたいな、袖岡先生から伝えたこととかありますか。
袖岡:サイエンスという意味では、やっぱり何か面白いことをしようよっていうのがあります。あとは「下の人のことをちゃんと考えようよ」というのは、かなり伝えたつもりですね。分業制と言ったら変ですけど、中には変なことをする人とか、お説教しなきゃいけない学生さんとか、そういう人もいた時に、あらかじめ状況をシェアしていました。彼らがその人を怒る時には、私はちょっと引いて眺めるし、私が怒る時には彼らがちょっと眺めるというような形でやるようにはしていました。
足立:怒る時に、どのようなことに気をつけて伝えますか。
袖岡:今の学生さんは叱ると(委縮して)クシュっとなってしまうか、すごい反発しちゃうか、ということがあるので、非常に難しいです。さっきの分業じゃないですけど、1人は叱る側に回って、もう1人がちょっとフォローする側に回る形でやることが多かったですね。
それはやっぱり、コワーカーを信頼できているからできているという感じですね。あうんの呼吸というか。
足立:信頼できるコワーカーに成長していただくこつは何かありますか。
袖岡:彼らの力ですかね。(笑い)
足立:袖岡先生としては、見守りつつですか。
袖岡:そうですね。自分も振り返って、やっぱりオン・ザ・ジョブ・トレーニングじゃないですが、元のボスがラボの中で何か問題があった時に、どういうふうに対処するのかを見ていたり、そういうことが役立っています。彼らがどう思っているか分からないですが、いろいろ見て経験したことが、今後彼らがPIになった時に役立つのかなとは思います。
転籍を繰り返したキャリアを振り返って
足立:袖岡先生が、PIとして一番嬉しかったこととか、具体的なエピソードがあれば教えていただけますか。
袖岡:やっぱり研究が、とてもうまくいった時っていうのが一番嬉しくて、それを実際に一緒にやっている人と一緒に喜べる時が一番嬉しいですね。
足立:反対に一番嬉しくなかったことはありますか。
袖岡:最近はサブグループ体制なので、なかなか、いい結果が出た瞬間に出会えないので、それを一緒にその場で感動できないというのは、ちょっとつまらないなと思います。
足立:袖岡先生が最初にPIとして独立した時の自分に、今だったらかけられる言葉とかありますか。
袖岡:難しいね。・・・そうですね。・・・何とかなるかなっていう。(笑い)自分の経歴を振り返っても、多分こんなに転職している人はあまり多くないと思います。あまり自分の意思と関係なく転職したことが結構多いです。それでも、何か思いを持って発信していると、誰かが助けてくれる。私の場合は本当に、いろいろな所に行って大変でしたけど、その分いろいろな人に出会えて、結構それが財産になっています。後々、いろいろな所で繋がりました。ピンチの時、助けていただいた場面もたくさんあります。そういう意味では、多分イレギュラーな経歴ですけど、それも悪くなかったかな、と思います。
足立:ありがとうございます。そうしたら、ひとまず私からは以上です。
二つの分野の境界領域を進む
松尾:袖岡先生が、最初に相模中央研究所で、新しいPIとして立ち上げられたラボに所属をされて、そこで様々な研究をして、自分のやりたい研究としてバイオロジーにたどり着いたと伺ったのですが、どういう過程を経て、自分のやりたい研究を見つけていくと良いか、アドバイスをいただけるようなことはありますか。
袖岡:私の場合は、今でも触媒化学とケミカルバイオロジーを両方やっているのですけれど、触媒化学の方はずっとやっているので、その流れの中からいろいろな蓄積があって、それを違う方向に発展、こっちの方向に行ってみようとかいう形で発展させてきたので、これ(触媒化学に近いところ)は割とスムーズな形だと思います。バイオロジーとの境界は、薬学部だったので生物の講義ぐらいは受けていたのですが、全く研究の経験はないところから(始めました)。先ほどの柴﨑先生のお言葉で、ちょっと何か違うことをやらなきゃ、というふうに思って、自分が何に興味があるかなと考えた時がありました。研究の話になってしまいますが、私が相模中研でやっていたのは、プロスタグランジン、プロスタサイクリンという末梢血管を広げる作用のある化合物の誘導体を効率良く作る研究でした。ものすごくよく効く化合物ができた時に、ものすごくちゃんとプロテクトしてケアフルにやってるのに、自分の手が真っ赤になりました。それで、この化合物はすごいなと思ったのです。これはどうやって効くんだろう、そのメカニズムを知りたいなと強烈に思ったんです。当時はまだ、プロスタグランジン、プロスタサイクリンのレセプターも分からなかった時代で、手も足も出なかったのですが、ちょうど何をやろうかなと考えてきた頃に、モレキュラーバイオロジーがすごく進展して、どんどんクローニングもできて、タンパク質も作れて、という時代になってきていました。それだったら何かケミストリーの側からできることがあるんじゃないかなと思ったのです。
多様な環境に向けた地道な取組
松尾:進路を考える時に、薬剤師の免許を持っていて将来困らないというお話とか、周りには「就職先がなくなる」と言われたりとか、女性の先生でロールモデルになる方がいらっしゃったというお話でしたが、そういった女性ならではのご経験をされたその頃の環境からすると、今はだいぶ変わっていると思われますか。
袖岡:今はだいぶ風が変わっている感じはするので、もっともっと女性研究者が増えてほしいなと思っています。
松尾:今、ラボは非常に大所帯で、国籍も年代も性別も多様な方達がいらっしゃると思うんですけど、その多様なラボをマネジメントする、PIとしてマネジメントすることならではの喜びとかご苦労があれば教えてください。
袖岡:あんまりそれは考えたことがないかもしれないですね。一応、セミナーは英語でやれる人はやる形にしていますが。日本語の分からない人が困らないようにというか、寂しい思いをしないようにというのは心がけています。
松尾:ありがとうございます。
キャリアの岐路を振り返って
足立:海外で自分のラボを構えようと思ったことはありますか。
袖岡:留学の2年間が終わる時に、一応休職で行っていたのですが、柴﨑先生が東大に移られました。帰る所が一時はないかなという状況になり、もう少し海外にいてもいいかなとちょっと思いました。もう一度東大に声をかけていただいたので、そのまま日本に戻ってきたという感じです。
足立:理研に移籍せず、東北大にずっとい続ける選択肢はなかったですか。
袖岡:東北大にそのままいる選択肢も、あったとは思います。そしたらそれなりにやってたとは思うんですけど、ケミカルバイオロジーを今くらいできたかは分からないですね。有機化学の研究室としては東北大の方が十分やれていました。
足立:特に論文博士を取ろうと目指されていた北大時代が、非常にハードに働かれていた印象があるのですが、先生のワークライフバランスの変化といいますか、研究者のキャリアを過ごす間に変わってきたりとかありますか。
袖岡:あまり変わってないかもしれません。
足立:今もかなり長く(働いていますか)?
袖岡:今もかなり長く(職場に)いるかもしれない。でもおいしい物を食べたりとか、楽しむところは楽しんでますけれども。(笑い)
PIを目指す醍醐味
足立:若手の研究者でPIを目指す人へ何かメッセージをいただけたらありがたいです。
袖岡:研究が楽しくて、自分がやりたい研究が見つかるのだったら、やっぱりPIになって、それを実現するのが大事だなと思いますね。
足立:PIにならずに、ずっと手を動かし続ける研究職でいるという選択も多分あると思うのですが、その中でPIを目指す醍醐味といいますか。
袖岡:やっぱり自分のやりたいことがやれるということに尽きると思うんですよね。私自身も最初はとにかく実験が面白いから、実験を続けられるような職業に就きたいなっていうところから始まりました。そして、研究が面白いなとなって、自分なりのアイデアで研究ができるような職に就きたいとなった。段々やっぱり、ボスの範疇の研究じゃなくて、もっと違うこんなことがやりたいなと考え始めた。だから多分これを考え始める時が、PIを目指す時なのかなというふうに思っていました。
足立:それを考え始めた時期が、袖岡先生の研究キャリアの中ではどこらへんですか。
袖岡:多分留学に行く前後だと思います。留学先でいろんな人に出会ったというのも大きいかもしれませんね。向こうの大学院生達は、大学院を出て博士を取ってポスドクをしたら、すぐPIになります。アメリカはそういうキャリアパスなので、みんな「PIになったらどうしよう、何をしよう」ということを、すでに大学院生とかポスドクの頃からすごく考えているのを、聞いていました。私は普通の人よりも3年ぐらい遅れて学位を取っているので、それよりも遅れていました。でも、彼らが若い時からこんなことを考えているんだと聞いていたことは、それなりに影響があったような気がします。
足立:あちこち転職をされてきたということで、それぞれの転機のお話しを伺ってきたんですけれども、あの時こうしておけば良かったなとか、ああいう可能性があったかもしれないみたいなことを思うことはありますか。
袖岡:結構、転機が多かったので、いろいろその時々考えるんですけど、ある時から、2つ選択肢があっても両方生きてみることはできないので、やっぱりこっちを選んだら、こっちを選んで良かったと思えるようにしようと、ちょっとマインドを変えました。ずっと悩んでいて、やっぱりあっちにすれば良かったかなと後悔するのだけは嫌だなと思うので。だからこっちを選んだからにはこっちが良かったって思えるように頑張ろう、そんなふうに思ってきました。
チャンスは掴む
足立:あと最後に1点だけ。女性の就職先がなかったとか、いろいろな時代の状況もあったと思うのですが、相模中央化学研究所に社会人として初めて勤務して、その環境の中では、あまりそういうことは起きなかったですか。もう男女関係なく。
袖岡:採用された時がまず、同じ年に同期で入った修士卒の男性よりも1つ低い身分でしか採用してもらえなかったです。
足立:修士卒でもですか。
袖岡:同じ修士卒なのに。研究員補という身分があって、これは裁量労働制だったんですね、今で言う。で、こちらは研究補助員(非裁量労働制)。入った時は差をつけられていました。すごい腹が立って、結構夜遅くまで実験したりしていたんで、それを全部残業つけてました。そうしたらある時に所長さんから呼ばれて、「これ以上残業をつけると、同期の人よりも給料多くなっちゃうから」と言われて、次の年に(ポジションを)上げてもらいました。
足立:仕事の内容とかはまったく男女関係なかったですか。
袖岡:柴﨑先生が結果的には素晴らしかったなと思うのは、すごいプレッシャーをかけられていろいろ大変だったんですけど、女性だから何か手加減をして、この仕事はやらせないとか、そういうことは全くなかったです。男女にかかわらず、プレッシャーをかけるタイプ。また柴﨑先生は、結果が出たらちゃんとそれを発表したりとか、いろいろなチャンスもくれました。あとは、いろいろな人に紹介してくれるとか、そういうこともすごくしてくださいました。当時、女性がなかなか上に上がれないというのは、妙に気を遣われて、危ない実験はさせないようにしようとか、何かそういうので、結果的には思うような研究がやらせてもらえないような、そういうファクターが多分あったと思います。重いものを持ってはいけないんじゃないかとか。多分柴﨑先生も必死な時代だったと思うんですけれども、そういう意味では男女の区別なく、研究は思う存分やらせてもらったおかげで、いろいろな結果も出せました。また北大に先生が移る時も、連れて行っていただきました。そういう意味では、柴﨑先生の厳しい指導のおかげで今日があります。
足立:最初の入る時の差以外では、もう研究者の人生を振り返ってみて、男女で何か差をつけられることに遭遇されたことはないですか。
袖岡:ほとんどないですね。大学で直接指導してくださった助教授の先生が、中川先生という女性で、バリバリ(研究を)やられていました。相模中研に行った時も、女性のシニア研究者の方がいらっしゃいました。北大に行った時も、同じ研究室の中にやっぱりバリバリ(研究を)やられている女性の研究者の方がいらっしゃいました。よくロールモデルがいないという話しを聞くんですが、結構周りに、普通に女性研究者がいたので、あんまり女性だからだめかなとか、そんなことは思ったことなく、頑張っていれば何とかなるかなと思ってやってきた気がします。
足立:長い時間どうもありがとうございました。
インタビュー実施:2023年2月7日
インタビュー場所:物質科学研究棟6階 S601室
RIKEN Elsevier Foundation Partnership Project
撮影・編集 西山 朋子・小野田 愛子(脳神経科学研究センター)
撮影支援・編集支援 雀部 正毅(国際部)
インタビュアー・製作支援 松尾 寛子(ダイバーシティ推進室)
インタビュアー・製作 足立 枝実子(ダイバーシティ推進室)