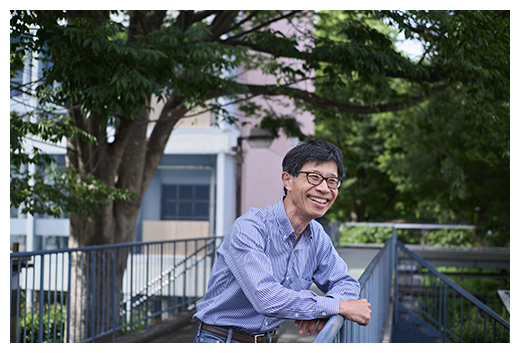物に囲まれた私たちの世界。物質とは何かという素朴な疑問を端緒に、人類が直面する地球環境問題など社会課題の解決に挑む研究者がいます。物質科学を専門とする創発物性科学研究センターの有馬 孝尚 センター長です。理研が世界に誇る大型放射光施設「SPring-8(スプリングエイト)」などを駆使し、物質を構成する原子や電子の実像に迫り、持続可能な社会の実現に欠かせない材料開発に注力しています。
好きなことを楽しんでこそ
世界がライバルとなる競争の激しい分野だが、約40年に及ぶ研究者人生で一貫しているのは「好きなことを楽しむ」という思いだ。その源泉は幼少期にある。少年時代を過ごした兵庫県西宮市には当時、農地が広がり、田んぼでカブトエビ捕りに夢中になった。また、部品を買い集めてラジオを製作したり、毎日、ラジオで流れる気象通報を聞き、天気図を描いたりした。
エンジニアを目指す一方で、自然界に物理法則が働いていることに魅了され、東京大学 工学部 物理工学科に進学し、光物性や磁性などを学んだ。1988年の修士課程修了後、いったん東レ株式会社に就職したものの、材料科学の最先端を知りたいと2年後に大学に戻った。東京大学 理学部 助手、筑波大学 物質工学系 助教授、東北大学 多元物質科学研究所 教授などを経て2011年、東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授に就任した。2007年以降、理研での研究活動もスタートさせた。
数々の成果で新材料開発を加速
物質の新しい機能を引き出すための鍵を握るのが、原子核の周りを回る電子だ。電流の正体であり、スピンという自転に似た性質を持って小さな磁石として働くからだ。複数の電子の自転の向きをそろえたものが磁石である。さらに、配置を工夫すれば、回転ドアを通る人の流れのように、電流や光が一方向に流れやすくすることもできる。
そのためには電子の振る舞いやスピンの配列を精密に観測する必要があり、2007年にSPring-8を有する放射光科学総合研究センター(現 放射光科学研究センター)にスピン秩序研究チームを立ち上げ、通常中性子で見ることの多いスピンをあえてX線で調べて、中性子では得られない情報を得ることを本格化させた。
2013年には創発物性科学研究センターの強相関量子構造研究チームリーダー、2024年には同センター長に就任。2021年には、物理学で優れた業績をあげた研究者に贈られる仁科記念賞を木村 剛 教授(東京大学 大学院新領域創成科学研究科)と共に受賞した。光の一方通行を示す銅のホウ酸化物の発見、イリジウムの周りの電子が公転とともに自転方向を変える現象の観測など、400本を超える論文を世に送り出した。これまで予想されていなかった物質特性は世界の研究者を刺激し、新材料開発を加速させている。
大局観で臨む
物質の性質を追究することは人類が抱える問題の解決にも不可欠だ。産業革命以降、物質的には豊かになったものの、地球沸騰化の時代を迎え、食料やエネルギーの確保も厳しさを増す。こうした課題の解決に資する新材料を発見し、エネルギー革命を先導する熱電変換材料、回路やメモリ、太陽電池の実現を目指す。
趣味が将棋で、大局観を大切にする。学部生時代から博士課程まで、異なる指導教官に師事したことも視野を広げた。若手研究者には「たこつぼに陥らず、専門外の分野にも興味を持って臨んでほしい」と指導している。
この記事の評価を5段階でご回答ください