「科学道クラシックス」選書会議―プロジェクトの舞台裏
 科学道クラシックスの選書会議
科学道クラシックスの選書会議
2017年に始まった科学道100冊プロジェクト。2019年から、毎年恒例の企画として再スタートを切りました。2019年からは、100冊の本を「テーマ本」50冊と「科学道クラシックス」50冊の2階層で選出することになりました。今だからこそ読んで欲しい旬の本がある一方で、いつの時代も変わらず、お薦めし続けたい名著があるという思いから、この構成となりました。
- テーマ本(毎年変わる50冊)…毎年注目のトピックを3つ設定して選出する。
- 科学道クラシックス(定番50冊)…時代を経ても古びない良書をして選出する。
科学道100冊の定番としてお薦めし続ける「科学道クラシックス」の本は、どのように選ばれたのでしょうか?今回は「科学道クラシックス」の本の選考過程と、その中で語られた熱い想いをご紹介します。
 選書会議の様子
選書会議の様子
選書のプロセス
- 幅広い観点から科学のおもしろさを伝える
- 科学の視点から必読書といえる良書をお薦めする
という基準を設定し、2つのステップを踏んで選書を行いました。
Step1:理化学研究所内アンケート
理化学研究所内で「大人になる前に出会ってほしい科学道の本」というアンケートを実施。「この本に出会って科学に進むことを決めた」など、研究者を含む職員から、たくさんの声が寄せられました。
Step2:選書会議
アンケートで集計したデータをもとに、50冊の本を選定するための「選書会議」を実施しました。選書会議のメンバーは理化学研究所の松本 紘 理事長をはじめとする同研究所の理事、研究者ら9名と、プロジェクトの企画・制作を担う編集工学研究所の松岡 正剛 所長の計10名。約300冊の候補本を前に、「学生時代にこの一冊に魅了された」「この科学者に注目してほしい」と意見を交わし、50タイトルに絞り込んでいきました。
選書委員からのメッセージ
 理化学研究所 理事長 松本 紘
理化学研究所 理事長 松本 紘
中学生や高校生が、科学に興味を持つきっかけになれば嬉しいです。みんながみんな科学者になるわけではないですが、科学の成果を世に役立てるということについて、より多くの若い人たちに想像力を持ってもらいたいです。理化学研究所には立派な研究者がたくさんいます。幅広いジャンルの本を集めて、彼らの本に対する情熱が伝わるような100冊にできればと思います。
- お薦めの本:『新装版 道具と機械の本』ほか
 編集工学研究所 所長 松岡 正剛
編集工学研究所 所長 松岡 正剛
理化学研究所が「科学道100冊」を進めることは、日本にとって非常に大事なスタートだと感じています。すでに研究者の方々から素晴らしい推薦をいただき、私のような専門外の者でも科学への憧れを抱くような本がズラッと並んでいます。一番大事なのは子どもたちが理科少年、理科少女としてキラキラした夢を持てること。そんな本との出会いを演出したいです。
- お薦めの本:『システムの科学』ほか
 理化学研究所 理事 小谷 元子
理化学研究所 理事 小谷 元子
2017年に始まったこのプロジェクトが好評で嬉しく思っています。私は子どもの時、本を読んで先生に質問に行くのが好きでした。私のヒーローは朝永 振一郎さんです。良書は決して古びないので、読み継がれてほしいです。
- お薦めの本:『物理学とは何だろうか(上)(下)』ほか
 理化学研究所 理事 加藤 重治
理化学研究所 理事 加藤 重治
科学者の生きざまは、一般の人たちにあまり知られていないと感じます。人物伝などで科学者は熱い思いをもって研究をしていることや、科学研究独特の規範を伝えるのは重要だと思います。
- お薦めの本:『日本列島の誕生』ほか
 理化学研究所 開拓研究本部 上野核分光研究室 主任研究員 上野 秀樹
理化学研究所 開拓研究本部 上野核分光研究室 主任研究員 上野 秀樹
私は高校では特に物理が得意というわけではなかったのですが、本やテレビのドキュメンタリーを見て、加速器を用いた実験で粒子の謎が解き明かされることに感動して、今その研究をしています。若い人にそういう出会いをしてほしいですね。
- お薦めの本:『いかにして問題をとくか』ほか
 理化学研究所 開拓研究本部 Kim表面界面科学研究室 主任研究員 金 有洙(Yousoo Kim)
理化学研究所 開拓研究本部 Kim表面界面科学研究室 主任研究員 金 有洙(Yousoo Kim)
私が科学者という職種に興味を持ったきっかけは、中学生の時に偶然手に取ったエッセイ集でした。本は別に最初から最後まで読まなくてもいいんです。まずは中高生が気軽に触れられるものを紹介していきたいです。
- お薦めの本:『ご冗談でしょう、ファインマンさん』ほか
 理化学研究所 開拓研究本部 大森素形材工学研究室 専任研究員 片平 和俊
理化学研究所 開拓研究本部 大森素形材工学研究室 専任研究員 片平 和俊
小さい頃は星 新一の本、中でもロボットが出てくるものが好きでした。私はエンジニアリング分野なので、ものづくりに関する本を薦めたいですね。図工が好きな学生のワクワクする気持ちを刺激したいです。
- お薦めの本:『ねじとねじ回し』ほか
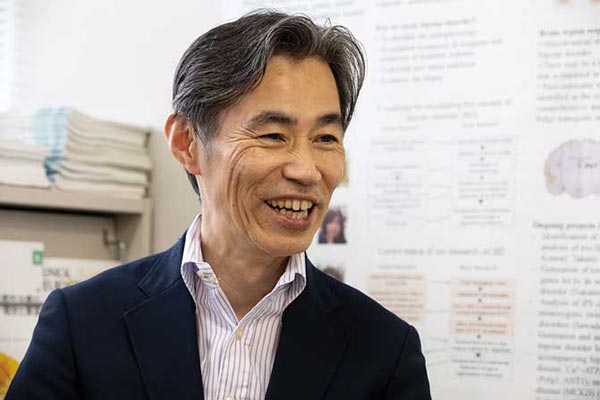 理化学研究所 脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー 加藤 忠史
理化学研究所 脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー 加藤 忠史
読書は自分の知らない世界や他人の人生を知ることです。僕は人と喋らずに本とばかり会話していたけど何とか育ちました。本ばかり読んでいても何とかなります(笑)。たくさん読んで、いろんな人生を経験してねと伝えたいです。
- お薦めの本:『シートン動物記 オオカミ王 ロボ』ほか
 理化学研究所 開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員 倉谷 滋
理化学研究所 開拓研究本部 倉谷形態進化研究室 主任研究員 倉谷 滋
生物に興味のある子どもにはやっぱり図鑑でしょう。自然と分類学や形態学が頭に入ります。本には若いうちに読まなくてはいけないものがあって、そんな本との出会いで、世界の見方が変わる経験もできるはずです。
- お薦めの本:『完訳 ファーブル昆虫記 第1巻』ほか
 理化学研究所 広報室長 生越 満
理化学研究所 広報室長 生越 満
私が学生の時はアイザック・アシモフを愛読していました。読書は本を通して自分と向き合うことだと思います。自分で何を考え、どう成長したかで、同じ本でも印象が変わります。学生のうちに多くの本に触れてほしいですね。
- お薦めの本:『ホーキング、宇宙を語る』ほか
