2011年1月24日
独立行政法人 理化学研究所
財団法人 高輝度光科学研究センター
透明なコバルト添加の二酸化チタン薄膜が磁石となる謎を解明
-薄膜磁性はチタンの電子がコバルトの電子スピンをそろえて発現-
ポイント
- チタンの3d電子が、まばらに存在するコバルトの3d電子のスピンを制御
- 薄膜の表面近傍は半導体、内部は金属としての性質を示す現象を突き止める
- スピントロニクス分野の材料、デバイス設計に指針
要旨
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)と財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI、白川哲久理事長)は、可視光に対してほぼ透明で、スピントロニクス※1材料の有力候補であるコバルト添加の二酸化チタン(Co:TiO2)薄膜では、自由に動きまわるチタン原子の3d電子※2が、まばらに存在するコバルト原子の3d電子スピンをそろえることで、磁石としての性質を発現することを世界で初めて解明しました。これは、理研放射光科学総合研究センター(石川哲也センター長)の量子秩序研究グループ励起秩序研究チームの辛埴チームリーダー(国立大学法人東京大学物性研究所教授兼任)と大槻匠研究員、JASRIの大橋治彦副主席研究員と仙波泰徳研究員らの共同研究による成果です。
私たちの日常生活を支えているエレクトロニクス技術は、電子が持つ「電気を伝える性質」と「磁石としての性質」を別個に利用していますが、近年、その両方の性質を同時に利用したスピントロニクスという分野が注目され、新たな素材や機能の開発が模索されています。
研究グループは、スピントロニクス材料の有力候補で、二酸化チタンにコバルトを少量添加したコバルト添加二酸化チタン(Co:TiO2)薄膜の電子状態を、大型放射光施設SPring-8※3を活用したX線光電子分光法※4で詳細に解析しました。その結果、Co:TiO2薄膜が磁石になる起源は、薄膜内を動きまわるチタン原子の3d電子が、まばらに存在するコバルト原子の3d電子スピンの向きをそろえる点にあることを解明しました。さらに、硬X線(波長約0.16nm)と軟X線(波長約1nm)という2種類のX線光電子分光法を駆使して解析した結果、二酸化チタン薄膜表面では、金属的な性質を表すフェルミ端※5が存在しないため半導体的な性質を示す一方で、薄膜内部では、フェルミ端が存在し金属的な性質を示すということを見いだし、薄膜の表面と内部では電気伝導特性に違いがあることを突き止めました。これらは、Co:TiO2薄膜が真のスピントロニクス材料であることを示すとともに、実用化への指針を示す結果となります。
本研究成果は、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』(1月28日号)に掲載されるに先立ち、オンライン版に近日掲載予定です。
背景
私たちの日常生活に欠かすことができないエレクトロニクス技術は、レーザーやトランジスタのように半導体を材料としているデバイスと、ハードディスクのように磁性体を材料としているデバイスによって支えられています。半導体は電子の電荷(電気を伝える性質)を利用しているのに対し、磁性体は電子のスピン(磁石としての性質)を利用しているため、電子が持つこれら2つの性質は全く別物として研究が進んできました。
近年になると、これら2つの性質を同時に取り入れて、不揮発性磁気メモリ(MRAM)※6やスピントランジスタ※7といった、従来にはない全く新しい素材や機能を持ったスピントロニクス材料による素子の開発が注目されてきています。特に、半導体に磁性体を少量添加した希薄磁性半導体と呼ばれる物質が盛んに研究されていますが、多くの希薄磁性半導体のキュリー温度※8は室温よりも低いため、室温では磁石としての性質を失ってしまい、日常生活の製品へ応用することが困難です。一方、地球上に豊富に存在し、白色顔料や光触媒として知られる二酸化チタン(TiO2)に、磁石としての性質を持つコバルト原子(Co)を数パーセント添加したコバルト添加二酸化チタン(Co:TiO2)の薄膜は、大気中でも極めて安定な物質であり、室温より高い温度でも磁石としての性質を失わないため、スピントロニクス材料として非常に期待されています。またCo:TiO2薄膜は、私たちの目に見える光(可視光)に対してほぼ透明であるため、光通信で用いられる光アイソレータ※9などの光機能素子にも応用することができます(図1)。
今後のスピントロニクス材料の物質設計やデバイス応用にとって、このCo:TiO2薄膜が磁石としての性質を示す起源を知ることは非常に重要ですが、材料発見から10年経った現在でもその詳細は分かっていません。特に、添加したコバルト原子が二酸化チタン中でどのような形で存在しているか、ということさえもはっきり分かっておらず、コバルトは二酸化チタンの中でまばらに存在しているという説と凝集しているという説が存在しています。コバルトが凝集している場合、薄膜の磁石としての性質は凝集したコバルトの塊が担うようになるために、本来の希薄磁性半導体としての性質が得られず、Co:TiO2薄膜は真のスピントロニクス材料として期待できません。これまでに研究グループは、まばらに存在している説を支持するデータを得ていますが、その場合、原子レベルの小さな磁石であるコバルト原子の電子スピンの向きが一定方向にそろわないと、物質全体が磁石としての性質を示すことができません。しかし、どのようにしてコバルト原子の電子スピンの向きがそろうのかは不明のままです。さらに、多くの電子デバイスの材料は薄膜化して使用されており、例えば、結晶構造などの特性が薄膜表面と内部で異なることが知られています。そのため、デバイス応用まで視野に入れると、その材料を薄膜化して表面と内部の特性を調べることは非常に重要です。
研究グループは、物質の表面から1nm程度の情報を提供するエネルギーの低い(波長約1nm:1nmは10億分の1メートル)軟X線(SPring-8の理研物理科学IIIビームラインBL17SU)と、表面から10nm程度の深さの情報を提供するエネルギーの高い(波長約0.16nm)硬X線(理研物理科学IビームラインBL29XU)という2種類のX線を、二酸化チタンに5%のコバルト原子を添加したCo:TiO2薄膜に照射してX線光電子分光法による測定を行い、チタン原子とコバルト原子の電子の性質や、薄膜表面と内部の電気的な特性の違いを調べました。
研究手法と成果
本来、二酸化チタン中のチタン原子は、3d電子を1個も持たない4価の形(Ti4+)で存在しますが、今回測定したCo:TiO2薄膜では、3d電子を1個持つ3価の形(Ti3+)がわずかに含まれていることが判明しました(図2矢印)。また、二酸化チタンは電気を流しにくい幅広なバンドギャップ※10を持つ半導体として知られていますが、Co:TiO2薄膜では、バンドギャップ内(電子のエネルギー3.5eV~0eV)に未知の成分が存在し、特に薄膜内部ではフェルミ端(図3右の黒矢印)を確認することができたため、薄膜内部は金属的であることが分かりました。さらに、薄膜表面ではTi3+が少なく(図2赤線)、またフェルミ端を確認することができないため(図3右の赤線)、薄膜表面は半導体的であることが分かり、表面と内部で電気伝導特性が異なっていることを明らかにすることができました。
次に、バンドギャップ内に存在している未知の成分について詳細に調べるため、ビームラインのBL17SUを使って共鳴光電子分光※11測定を行いました。共鳴光電子分光は、照射するX線のエネルギーを、目的とする原子固有のエネルギーに合わせることで、その原子の成分を増大させた光電子スペクトルを得ることができます。そのためまず、X線のエネルギーをコバルト原子固有のエネルギーに合わせて照射したところ、磁石としての役割を担うコバルト原子の3d電子成分が、フェルミ端(0eV)から少し離れた位置(3eV付近)に存在していることが分かりました(図4左)。次に、チタン原子固有のエネルギーに合わせて照射し調べたところ、電気を伝える役割を担うチタン原子の3d電子成分が、フェルミ端近傍(1eV)に存在していることが分かりました(図4右)。これは、未知の成分の正体が、コバルト原子とチタン原子の3d電子成分であることを示しており、さらに、互いに近い位置に存在し重なり合っていることから(図4中)、これらの電子が相互作用していることを見いだしました。すでに、まばらに存在する磁石としての役割の電子スピンと、薄膜内を動きまわって電気を伝える役割の電子スピンは、互いにスピンの向きをそろえるように相互作用することが知られています。つまり、動きまわるチタン原子の3d電子が、まばらに存在するコバルト原子の3d電子スピンの向きをそろえることが要因となって、Co:TiO2薄膜が磁石としての性質を示すことを突き止めました(図5)。
今後の期待
今回、スピントロニクス材料として有望なCo:TiO2薄膜が磁石の性質を示す起源を解明することができました。この結果は、研究グループが支持する「コバルトは二酸化チタンの中でまばらに存在している」という説に基づいて説明でき、Co:TiO2薄膜が真のスピントロニクス材料であることを示します。さらに、Co:TiO2薄膜の表面と内部とでは、電気伝導特性が異なるという応用上重要な知見も得ることができました。
電気伝導特性と磁石としての性質のうち、片方を変化させることで他方を制御することができるスピントロニクス材料を使った素子では、不揮発性磁気メモリやスピントランジスタ、光アイソレータといった、これまでにない全く新しい機能が期待でき、エレクトロニクス産業を大きく発展させる可能性を秘めています(図1)。今後スピントロニクス分野の実用化に向けて、今回の知見が材料設計やデバイス設計に大きく貢献すると期待できます。
発表者
理化学研究所
放射光科学総合研究センター 励起秩序研究チーム
チームリーダー 辛 埴(しん しぎ)
研究員 大槻 匠(おおつき たくみ)
お問い合わせ先
播磨研究所 研究推進部 企画課
Tel: 0791-58-0900 / Fax: 0791-58-0800
ビームラインに関するお問い合わせ
ビームラインBL17SU
放射光科学総合研究センター 基盤研究部
軟X線分光利用システム開発ユニット
ユニットリーダー 大浦 正樹(おおうら まさき)
Tel: 0791-58-0802(内線3812)
ビームラインBL29XU
放射光科学総合研究センター 基盤研究部
放射光イメージング利用システム開発ユニット
ユニットリーダー 香村 芳樹(こうむら よしき)
Tel: 0791-58-2839
SPring-8に関するお問い合わせ
財団法人高輝度光科学研究センター 広報室
Tel: 0791-58-2785 / Fax: 0791-58-2786
報道担当
理化学研究所 広報室 報道担当
Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715
補足説明
- 1.スピントロニクス
物質を構成している電子が持つ「電荷」と「スピン」という2つの性質を利用しようとする研究分野のこと。「スピン」と「エレクトロニクス」の2つを合わせた造語である。個々の性質では実現できなかった新機能を実現することが目的であり、現在実用化されているものの中に、ハードディスクの読み取りヘッドがある。 - 2.3d電子
3d軌道(原子を構成している電子軌道の一種)にいる電子のこと。原子番号が21から30までの遷移金属では、3d軌道が原子の一番外側に位置し、この3d軌道にどのように電子が配置されるかが個々の物質の物性を決定している。 - 3.大型放射光施設 SPring-8
SPring-8は兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高輝度の放射光を生み出す理研の施設。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8GeVに由来。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のこと。SPring-8では、この放射光を用いて、物理、化学、地学などの基礎研究から、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。 - 4.X線光電子分光法
物質にX線を照射し、試料表面から放出される電子の個数とエネルギーの関係を調べることにより、物質内の電子状態を調べる実験手法。この手法により、物質内の電子のエネルギー分布を直接観測することが可能となる。硬X線光電子分光法、軟X線光電子分光法などがある。 - 5.フェルミ端
結晶中の電子は、結晶の周期性によって生じたエネルギーの束(バンド)をエネルギーの低い順に詰めていく。金属の場合、電子をバンドの底から詰めていくと、最後に電子が詰められたエネルギー準位と、電子が空になっているエネルギー準位の境目をフェルミ準位と呼び、金属のフェルミ準位近傍を光電子分光で測定すると、フェルミ準位で0から不連続にスペクトルの強度が増大する。これをフェルミ端と呼ぶ。 - 6.不揮発性磁気メモリ(MRAM)
Magnetic Random Access Memoryの略で、磁気を利用した記憶素子。現在パソコンに使われている半導体メモリは、電源を切ると記憶が失われてしまうが(これを揮発性という)、MRAMは電源を切っても記憶情報が失われない(これを不揮発性という)。半導体メモリに比べて、不揮発、高速動作、低消費電力、高集積可能といったメリットがあり、次世代のメモリとして期待されている。 - 7.スピントランジスタ
従来の半導体トランジスタとは、電子のスピンによって動作制御を行う点が異なる。LSI(集積回路)を高速かつ低消費電力化することができる。また、スピンの不揮発性を利用して、1つの素子でトランジスタとメモリの機能を合わせ持つこともできる。 - 8.キュリー温度
磁石としての性質を持つ物質が、その温度以上では磁石ではなくなってしまう温度。例えば、磁石として知られている鉄は、770℃以上まで温度を上げると磁石ではなくなってしまう。 - 9.光アイソレータ
光を一方向のみに通す性質を持ったデバイス。光通信に使われている半導体レーザーや光増幅器は、途中の光学部品からの反射光があると動作が不安定化してしまう。光アイソレータはこの反射光を遮断できるので、光通信では不可欠なデバイスである。 - 10.バンドギャップ
結晶のバンド構造において、電子が存在することのできないエネルギー領域。半導体においては、価電子帯(最も高いエネルギー帯)と伝導帯(最も低いエネルギー帯)のエネルギー差を指す。 - 11.共鳴光電子分光
X線光電子分光測定ではさまざまなエネルギーを持ったX線が用いられるが、ある特定の原子固有のエネルギーを持つX線を照射すると、その原子の成分を増大させた光電子スペクトルが得られる。これを共鳴光電子分光と呼ぶ。共鳴下と非共鳴下のスペクトルの差を調べることで、複数の元素から構成される物質であっても、特定の元素の成分を選択的に取り出すことができる。今回の例では、コバルト(またはチタン)固有のエネルギーのX線を照射することで、コバルト添加二酸化チタン(Co:TiO2)薄膜内のコバルト(またはチタン)の3d軌道の成分を選択的に取り出している。
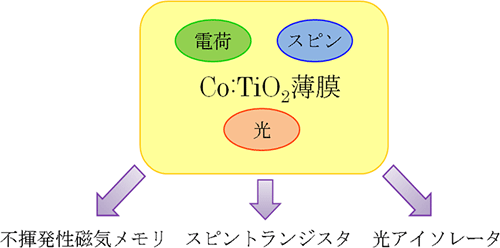
図1 スピントロニクス材料であるCo:TiO2薄膜とその応用例
電気を流す性質と磁石としての性質を併せ持つCo:TiO2薄膜は、それらの性質を同時に利用するスピントロニクス材料として非常に期待されている。また、Co:TiO2薄膜は可視光に対してほぼ透明なため、透明な磁石でもある。不揮発性磁気メモリやスピントランジスタ、光アイソレータといったスピントロニクス素子が実用化されれば、従来のエレクトロニクス産業を大きく発展させることができる。
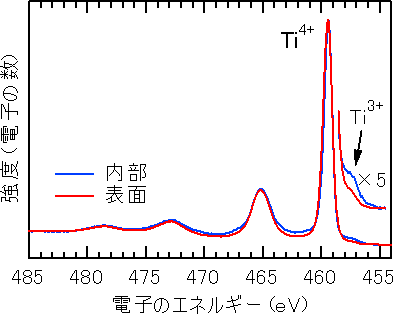
図2 チタンの光電子分光スペクトル
チタン原子の3d軌道に電子を1個持つ3価(Ti3+)成分が存在する(矢印)。薄膜表面よりも内部でTi3+が多く存在することが分かる。
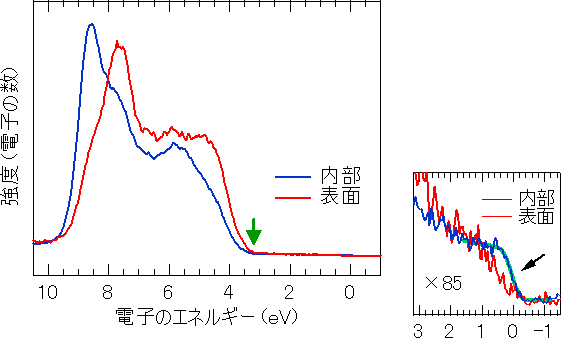
図3 コバルト添加二酸化チタンの光電子スペクトル
本来の二酸化チタンでは、緑色の矢印より右側(電子のエネルギ3.5eV~0eV)はバンドギャップに該当して電子は存在しないため、強度が見られないはずである。しかし、この付近(電子のエネルギーがゼロ)を拡大すると(右図)、Co:TiO2薄膜のバンドギャップ内部には未知の成分が存在することが分かる。また、内部(青線)ではフェルミ端(黒矢印)が存在するため金属的であるのに対し、表面(赤線)ではフェルミ端が存在しないため半導体的であることが分かる。
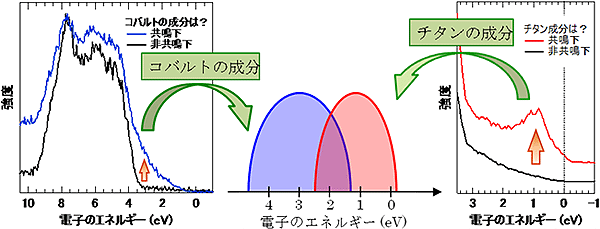
図4 コバルトとチタンの共鳴光電子分光スペクトル
左の図ではコバルト原子の3d成分を、右の図ではチタン原子の3d成分を増大させている(オレンジの矢印)。これらの結果から、磁石としての性質を担うコバルト3d成分と、電気を伝える性質を担うチタン3d成分が重なりあうことが分かる(真ん中の図)。この重なり合いがコバルト3d電子とチタン3d電子の相互作用を表しており、まばらに存在するコバルト3d電子スピンの向きをチタン3d電子がそろえていることを明らかにした。
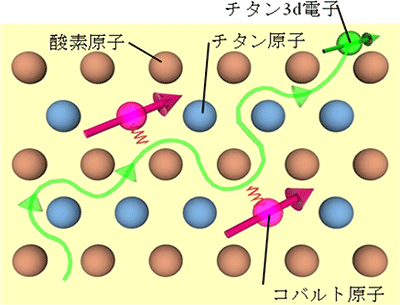
図5 コバルト添加二酸化チタンが磁石になることを示す模式図
チタン原子と酸素原子からなる二酸化チタンにコバルト原子を添加すると、コバルト原子がチタン原子の場所を置換する。二酸化チタン中を動き回るチタン原子の3d電子は、コバルト原子の3d電子スピンに作用してその向き(赤色の矢印)を同じ方向にそろえ、全体として磁石としての性質を発現させる。
