2020年4月以来、理研は新型コロナウイルスに対する特別プロジェクトに、まさしく"オール理研"で取り組んできました。それからおよそ2年。飛沫感染のシミュレーションやPCRに代わる検査法、湿布のように貼るタイプの簡易ワクチンの研究開発など、幅広い分野の成果を次々に発信、現在はポストコロナの時代を見据えた研究も進みつつあります。進捗状況や今後の展望について、小安重夫理事に聞きました。
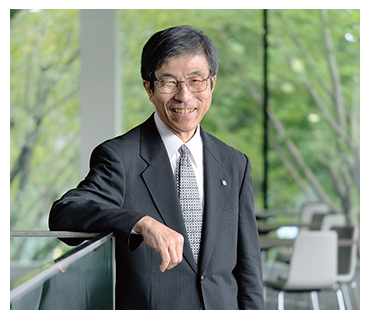
小安 重夫(こやす しげお)
理事
1955年東京都生まれ。東京大学大学院理学系研究科。理学博士。米国ハーバード医科大学病理学助教授、内科学准教授、慶應義塾大学医学部教授などを経て、2014年に理研統合生命医科学研究センターセンター長に就任。2015年から現職。
幅広い研究分野で国難に立ち向かう
新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)を受け、松本紘理事長が先頭に立って理事長裁量経費の投入を采配し、始動した特別プロジェクトの研究課題は総数30を超える。より迅速かつ効率的なウイルス検出法の開発、多角的なシミュレーション、人工知能(AI)、ICTなどを活用した生活や社会を持続させるための研究など、取り組む分野は幅広い。研究成果をいち早く社会に届けるために、研究課題の募集にあたり「早期実用枠」も設けた。
他機関の新型コロナウイルス研究への支援強化にも迅速に取り組んだ。大型放射光施設「SPring-8」、X線自由電子レーザー施設「SACLA」に加え、本格稼働前だったスーパーコンピュータ「富岳」の試用的運用を関係省庁と調整の上、急ぎ開始し、理研内外の研究を強力に後押し。新型コロナウイルスのタンパク質と治療薬候補化合物の相互作用に関するデータベースの公開も行った。
がん免疫細胞療法を応用してワクチン・治療薬開発へ
早期実用枠で採択されたプロジェクトの一つが、「人工アジュバントベクター細胞(aAVC)」を応用したワクチン・治療薬の開発だ。aAVCは、もともとがんの免疫細胞療法として開発された。糖脂質を認識する膜タンパク質やがん抗原のmRNAが組み込まれており、投与すると「自然免疫」と「獲得免疫」の両方を活性化する。自然免疫はがんや病原体といった異物を非特異的に攻撃し、獲得免疫は異物の種類に応じて特異的に攻撃する免疫機能だ。がん抗原の代わりにウイルス抗原のmRNAを組み込むことで、ワクチンや治療薬として使える可能性があり、研究が進められている。
「既存のワクチンの有効性は実証されています。ですが、抗がん剤治療中の患者さんなどでは免疫が抑制され、十分な効果を得られないことがあります。aAVCは自然免疫にも働きかけるので、そのような方々への効果が期待できます。すでに、がんの治療薬として製薬企業とライセンス契約注1)を結び、安全性を確かめる第1/2相の治験が始まっています。新型コロナウイルスに対しても、早期の臨床応用を目指しています」と小安理事は語る。
- 注1)2019年9月2日お知らせ「理化学研究所とアステラス製薬 全世界の独占的ライセンス契約を締結」
ワクチンの効果が30分で分かる検査法
海外では、ワクチン接種完了から時間が経った時のブレークスルー感染が問題になり、ワクチン効果を回復するためのブースター接種が始まった国もある。国内でも2021年12月から3回目の追加接種が始まることが決定した。
ワクチンの効果測定に使われるのが血中の抗体価(抗体の量)だ。理研では、わずか1滴の血液で抗体価を測定できる「ウイルス・マイクロアレイ検出システム」が開発された(動画)。小さな基板(マイクロアレイ)上に新型コロナウイルスの複数のタンパク質を固定し、滴下した血液に抗体があれば結合して発光するように加工する。既存の簡易な抗体検査法より500倍ほど精度が高く、30分で結果が出るため、抗体の定量検査にも有用だ。
動画: プレスリリース解説 vol.7「新型コロナウイルス抗体の種類と量を30分で測定」
伊藤主任研究員ら共同研究チームが開発した「ウイルス・マイクロアレイ検出システム」の仕組みと実際の装置を紹介。(6分01秒)
動画テキストファイル
小安理事は「ワクチンの効果持続期間やブースター接種の効果などは世界的に関心が高い。迅速で高精度の抗体価検査法の原型が完成したので、できるだけ早く実用化に持っていきたい」と話す。
別途、ウイルス感染の有無が5分で分かるウイルス検出法の開発注2)にも成功し、企業との共同開発も始まっている。
- 注2)2021年4月19日プレスリリース「新型コロナウイルスの超高感度・世界最速検出技術を開発」
新型コロナ研究から広がる今後の展望
2021年4月の科学技術・イノベーション基本法の改正に対応し、理研の研究開発の対象は「科学技術(人文科学のみに係るものを除く)」から「科学技術」へ拡充され、社会課題の解決を目指す視点でもさまざまな新型コロナウイルスに関する研究が進められている。その一つが、コロナ禍で増加が懸念されている虐待や子どもの問題行動の予防と解決に向けた行動療法の研究だ。すでに世界で広く実践され効果が実証されている「親子相互交流療法」をリモートで実践し、実施前と後で親の脳の活動に変化があったかどうかを脳機能的核磁気共鳴画像法で調べる。その効果を神経科学的に検証、さらにリモートでの家族支援に役立つノウハウの構築を目指す。
これからの研究のあり方について小安理事は、「今回の経験を、他の感染症や将来のパンデミックに生かす方向で研究を進めるべき」と強調する。例えば、抗体の一つである免疫グロブリンM(IgM)を高めるワクチン。既存のワクチンは免疫グロブリンG(IgG)抗体にアプローチするが、デング熱のように、ワクチンでIgG抗体量が増加した後に感染するとむしろ重症化する「抗体依存性増強」が起きるものがある。IgM抗体を高めるワクチンならこれを回避できる。
さらに、「免疫の持続性に関する研究から、"免疫記憶のメカニズム"という免疫学における未解明の謎を解く研究へ発展させていきたい」と語る。ヒトは、病原体によっては、一度感染したら二度と感染しない「終生免疫」を獲得できる場合がある。一方、インフルエンザのように何度も感染する病原体もある。どうして免疫記憶の差が生じるのか、ヒトの免疫がどう働けば終生免疫が確立するのか、現時点では謎だ。「免疫記憶のメカニズムを解明できれば、免疫記憶を消すメカニズムの解明、さらには消去方法の開発により花粉症などのアレルギーや自己免疫疾患の治療にも応用できるかもしれない。新型コロナウイルス研究を、ぜひこの段階まで発展させたい」と将来の展望を語った。
(取材・構成:大岩ゆり/撮影:相澤正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)
関連リンク
- 2021年7月19日クローズアップ科学道「ビタミンDで高効果の新型コロナウイルスワクチン開発」
- 2021年6月21日クローズアップ科学道「検出法開発からマスクの効果分析まで、新型コロナ研究で成果」
- 2021年9月27日クローズアップ科学道「医療から宇宙まで 研究を支える基盤施設 ―SPring-8とSACLA―」
この記事の評価を5段階でご回答ください
